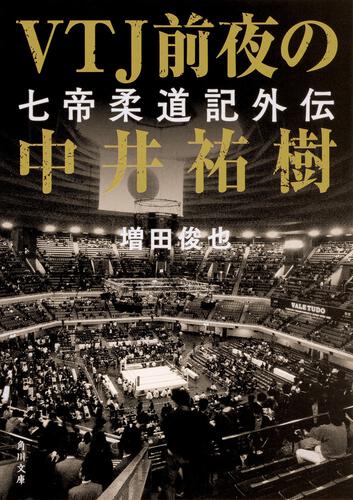5/10(金)配信の「文芸カドカワ」2019年6月号では、増田俊也さんの新連載「眠るソヴィエト」がスタート!
カドブンではこの新連載の試し読みを公開いたします。

29歳の大学生・当麻一郎は賞金50万円に惹かれて謎の生物を探すアルバイトに応募し山奥へと向かう。
1
東京駅八重洲改札口を出たところで公衆電話を見つけた私は、小さく畳んだメモを財布から抜き出し、それを見ながら電話をかけた。面倒くさそうな対応をされむっとしたが、まずは行ってみることにした。なんだってそうだが、始まりはたいていこんなものだ。二十九年生きてきて身に付けた、数少ない私の生活の知恵である。
駅構内を歩き、地下鉄への階段を降りていく。悪臭の湧きあがる雑踏に揉まれながら、福岡になど行かなければよかったと思った。姉貴に会いたかっただけなのに、親父とおふくろの顔を見て不愉快になった。
地下鉄を二度乗り換え、目的駅で降りた。地下鉄車両の車輪が撒き散らす鉄粉に咳きこみながら地上へ出ると、街は自動車の排気ガスで黒く澱んでいた。その澱みが真夏の強い陽光を吸収し、そこここでつむじ風のように渦を巻いている。汗まみれの私は工事現場の轟音が響くなかを何度も行ったり来たりし、巨大なビル群の裏手にようやくその小さなビルを見つけた。
ガラス製の扉を押して中へ入った。内壁は滲みだらけで、古い建物特有の饐えた臭いが漂っていた。リノリウムの床に吐き捨てられているガムを避けてエレベーターに乗った。
三階のドアが開くと、すぐ目の前が山岳ジャーナル社になっていた。入口上の黄ばんだプラスチックプレートに《山岳ジャーナル編集部》とマジックの手書きで書いてある。
開けっ放しのドアから中を覗いた。いかにも雑誌編集部という雑然とした部屋にスチールデスクが二十個ほど向かい合わせになっている。
「すみません――」
声をかけながら一歩入った。
手前の中年男性が眠たげな顔を上げた。
「アルバイトの件で来ました。当麻といいます」
「アルバイト?」
「はい。当麻一郎といいます。先ほどビッグフットの件で電話で話したんですが」
「ああ、じゃあ遠藤だ」
男は首を伸ばし「おおい、遠藤。バイト云々の人が来てるぞ。当麻さんていう人だ」と呼んだ。
「え? もう来たの?」
奥で四十年輩の男が立ち上がった。
そして「ちょっと待って、いま行くから」と机の上をガサガサやって何枚かの紙を手にし、机の間を縫ってくる。
近づきながら右掌でソファを示した。
「どうぞそこへ座って」
「ありがとうございます」
「さっき話した人だね」
手にしていた書類を机の上に放り投げながら言った。
向き合うと小柄な男だった。
「ええ。そうです。先ほど電話でお話しさせていただきました。募集を見て興味を持ちまして」
「どうぞ、座って」
男はまた掌でソファをすすめ、先に座った。
私は改めて頭を下げ、対面に腰をおろした。
男が財布を尻ポケットから出し、名刺を抜いて差しだした。
「昨日今日でもう九人目でね。思ったより応募が多くて」
名刺には《編集部デスク 遠藤康幸》とあった。前頭部が後退しつつあるので中年に見えたが、こうして向かい合うと肌の色艶から三十代前半だと思われた。
「すみません、名刺持ってないんで」
「ああ、いいよ。それよりどうしたの、大きな荷物持って」
床に置いてある大きなスポーツバッグに眼を遣った。
「実家に帰ってて、東京駅からそのまま来たんです」
「御実家は東北方面?」
「いや、反対方向です。福岡です」
言いながら私は鞄から履歴書を出し、机に置いた。
「ありがとう。ちょっと拝見――」
遠藤が手にした。見ながらぶつぶつと何度か口を動かし「慶應の学生なのね。国文学専攻か」と言った。
「それにしては少し――」
眼だけを上げて私を見た。
「二十九歳です。そこに書いてありますが、一度大学を出てからの再入学なんで」
遠藤はまた履歴書に眼を落とした。
「なるほど……。えっ、医学部出てるの?」
驚いたように言って今度は眼だけではなく顔を上げた。
私は黙って頭を下げた。
こういうときに喋ると嫌われることがある。それで何度か痛い目にあっていた。具体的に聞かれるまでは何も言わないほうがいい。遠藤はまた履歴書に眼を落として眉根を寄せた。
「どうして医学部出てから文学部に入ったの? 他の学部出てから医学部に入り直す人間はときどき聞くけど、医学部出てから他の学部に入る人は初めてだ」
「すみません」
頭を下げた。
「いや、謝ることはないよ。謝ることはないけど、どうしてかなと思っただけで」
「実家が開業医なんで、無理やり医学部に入らされたようなもので」
「でも信州大学っていったら国立でしょ。無理やりお金積んでなんて入れないでしょ」
「だからちょっとだけ勉強して……」
言ったあと、しまったと思った。しかしもう遅かった。遠藤が体を起こし、背もたれに体をあずけた。
「ちょっとだけ?」
「すみません」
私は目線を下げ、頭を下げた。
「いや、謝ることはないよ。俺は勉強できなかったから驚いただけで」
遠藤は嬉しそうに笑っていた。その笑顔に私は好感を持った。悪い人物ではなさそうだ。
「医師免許は持ってるの?」
「ええ。まあ一応は」
「出てからすぐに慶應に?」
「いえ。一年間勉強してから」
「そうだよね。入試から六年ブランクがあったわけだからね」
言って、また履歴書に眼を落とした。
「で、今回は、またどうしてうちみたいなところに応募してきたの。慶應の学生なら割のいい家庭教師とかあるだろうに」
「それは――」
「やっぱり五十万円に惹かれて?」
「ええ。はい。そうです」
「だめでしょ。医学部出てる人がそんなの信じては」
そんなのと言っても、それをダシにしているのは、この会社のほうである。
「あれは冗談だからさ」
「はあ……」
「盛り上げるために言ってるだけ。わかる?」
「ええ。でも、もし撮影できたら本当に貰えるんですよね」
遠藤がにやつきながら首を振った。
(このつづきは「文芸カドカワ」2019年6月号でお楽しみください)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。