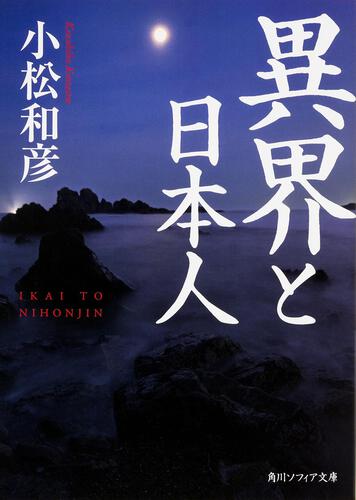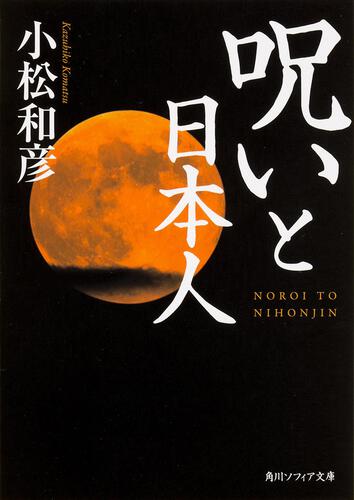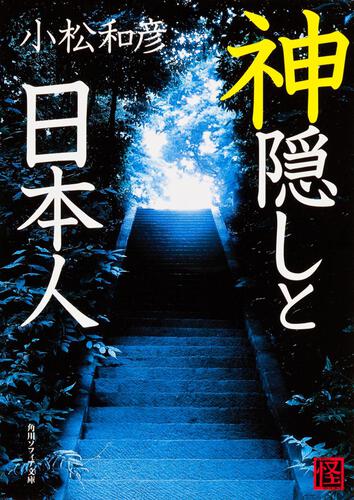俗世の向こう側にある極楽・地獄。日本列島に見出された聖地とはどんな場所か? 小松和彦『聖地と日本人』(角川ソフィア文庫)から、能の《融》の舞台ともなった「河原院――化け物屋敷に棲む吸血鬼」の一部を特別公開します!
河原院 ── 化け物屋敷に棲む吸血鬼
「化け物屋敷」の正体
能の《融》は、平安時代初期の嵯峨天皇の皇子で、源氏の姓を賜って臣下となった源融の旧宅、すなわち「河原院」が舞台になっている。
作られた当時の河原院は、鴨川の西、五条から六条にかけての八町を占めるという広大な敷地の邸宅であったらしい。《融》のあらすじは、次の通りである。
東国の僧が、河原院で休憩する。するとそこに田子(水を入れて担う桶)をかついだ老翁がやってきて「自分はこの所の汐汲みだ」と言う。僧が「このようなところに汐汲みがいるはずがない」と疑うと、老翁は「ここは融の大臣が塩釜に模した庭をもつ邸宅なので、汐汲みがいるのは当然ではないか」と答える。不思議に思った僧が一夜を明かすと、夢に融が出てきて、舞を舞って去っていく、という話である。
この河原院は、私たち異界に興味を持っている者たちにとっては、「化け物屋敷」とほとんど同義語である。河原院というと思い出すことがある。もうかれこれ二十年も昔のことになるだろうか、ある学会の懇親会が東本願寺(京都市下京区烏丸通七条上る)の渉成園(枳殻邸)を借りて行われた。スピーチを求められたある高名な研究者が、この庭園が源融の邸宅・庭園の遺蹟であると説明し、「もし今晩ここに泊まったら、河原院の幽霊の訪問を受けるかもしれないですなあ」と付け加えて、参加者の笑いを誘った。
妖怪・幽霊伝承にはことのほか興味を抱いていたので、河原院源融の幽霊の話はすぐに思い至ったが、渉成園が河原院の遺蹟であるということは初耳であった。融の邸宅がそのまま残っているわけでもないのに、ここが融の邸宅跡と思ったとき、私は宴会場のふすまの陰に、衣冠束帯姿の融が静かに着座して控えているような気分に襲われ、背筋が寒くなったのであった。
融の幽霊がその旧宅に出たという話は、いくつかの説話集に載っている。たとえば、『今昔物語集』の話は、次のようなものである。
今は昔、河原院は融の左大臣が作って住まわれた家である。庭園は陸奥の国の塩釜の景色を模して作り、池には海水を汲み入れてたたえた。このように素晴らしい風流な邸宅であったが、大臣が亡くなった後は、子孫にあたる方が宇多院(史上初の法皇)に献上したので、宇多院がお住まいになっていた。その当時、醍醐天皇(宇多院の第一皇子)がたびたびそこに行幸され、まことにめでたいことであった。
さて、宇多院がおられた時の夜半のことである。西の対屋の塗籠(寝室もしくは納戸用の部屋)の戸を開けて誰かが衣擦れの音をさせながらやってくる気配がした。院がそちらの方に目をやると、きちんとした束帯姿の人がかしこまっていた。院が「そこにいるのは誰か」と尋ねると、「この家の主の翁でございます」という答えが返ってきた。
「融の大臣か」
「さようでございます」
「どのような用か」
「私の家ですので、ここに住んでおりますが、院がこのようにおいでになりますので、恐れ多く気詰まりに思います。いかがなものでしょうか」
「それはまことにおかしなことを申す。私は人の家を奪い取った覚えはないぞ。お前の子孫がこの家を献上したから住んでいるのだ。たとえものの霊ではあっても理不尽なことは申すな」
このようなやりとりの末に、院が一喝すると、霊の姿はかき消すように見えなくなり、以後、二度と現れなかった。この話を聞いた当時の人びとは、旧主の大臣の亡霊を恐れることなく説き伏せ、退散させた院の剛胆さを賞賛したという。
この話からうかがわれるように、融は贅を尽くして作った河原院を、たいへん気に入っていたようである。『顕註密勘』という『古今和歌集』の注釈書にも、「陸奥の塩釜の浦の景観をうつして塩屋を設け、塩を焼かせ、その煙が立ち上り、また池を掘って毎月海水を三十石も運び入れ、そこには海の魚貝も棲まわせた」とある。この海水は難波から運んだという。
『伊勢物語』にも、融が神無月(陰暦十月)の晦日の頃、菊の花が咲き誇り、紅葉が千草に見える頃合いの邸宅で、夜が明けるまで宴を開いた様子が描かれている。これを読めばその豪華さが偲ばれ、融が気に入るのも当然であった。
しかしながら、邸宅が豪華であればあるほど、主人がそれを愛すれば愛するほど、主人亡き後にその邸宅が荒れ果てたときは、物寂しいものである。実際、融が亡くなった後、融の子孫にはこの邸宅を維持することができなかったらしく、宇多院に献上し、さらにその子である醍醐天皇が伝領し、その後は融の三男の仁康上人が預かる寺になったが、やがて荒れるに任せられたらしい。
たとえば、『古今和歌集』のなかに、紀貫之がこの河原院の旧宅を訪ねて、素晴らしい邸宅も融がいなくなって荒れ果ててしまった様子を、次のように詠んでいる。
「君まさで煙絶えにし塩がまの うらさびしくも見えわたるかな」
能の《融》は、このあたりのことをふまえて作られた作品なのである。
融は寛平七年(八九五)、七十三歳で亡くなった。この年齢は今日でさえも長生きした部類にはいる。つまり天寿を全うしたのだ。人生半ばにして病気や殺害によって亡くなったわけではないのだから、怨念が残ってこの世に融の亡霊がさまよい出る理由はなかった。
では、どうして幽霊になって出没したのだろうか。その理由は、深く深く過剰なまでにこの邸宅を愛していたことにあるのだろう。邸宅への執着が融の霊魂をこの旧宅に留まらせることになったのである。そしてその融の亡霊が、人の前に出てきては「この家は自分の家である。あなたは出て行って欲しい」と告げたのであった。おそらく、宇多院がこの邸宅に移り住んだころから、誰が言い出したわけでもなく、融のこの邸宅への執着ぶりを知る者たちのあいだで、この家には融の幽霊が出る、という噂が流れて語り伝えられていたのであろう。そんな噂話の一つが、前述の『今昔物語集』に収められた話であったのではなかろうか。
(このつづきは本書でお楽しみください)
▼小松和彦『聖地と日本人』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322007000735/