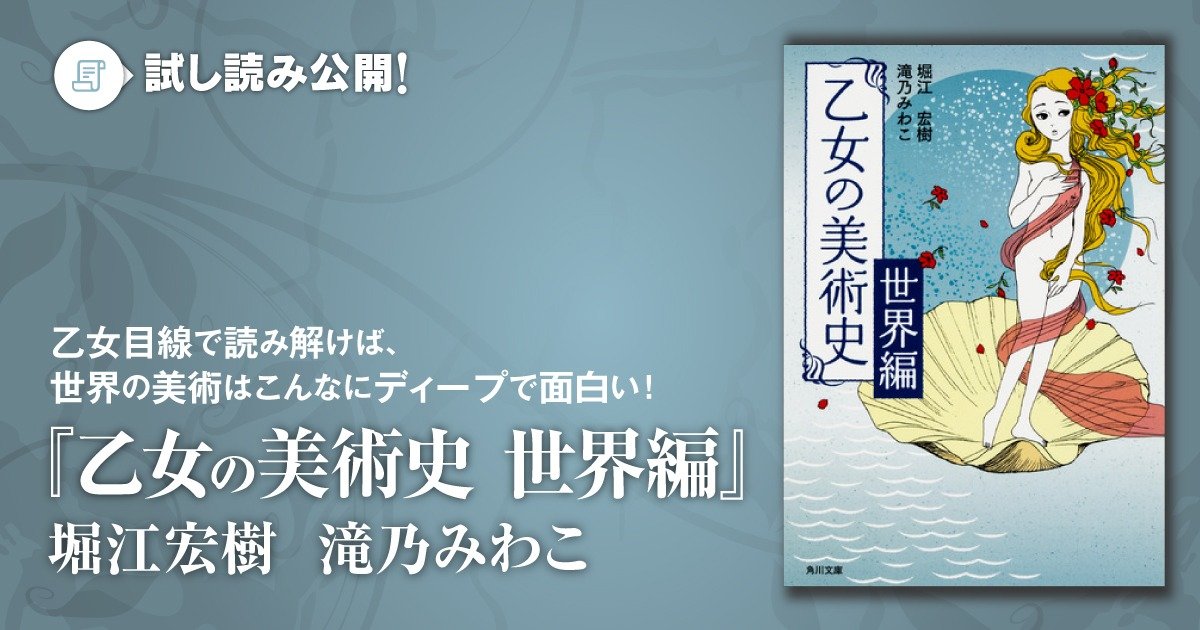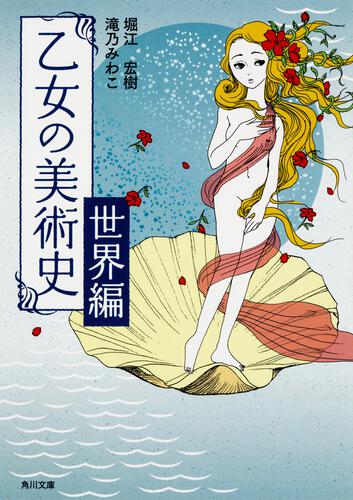歴女のバイブル「乙女」シリーズ最終巻『乙女の美術史 世界編』(著:堀江宏樹 滝乃みわこ)が角川文庫より7月25日に文庫化されます。文庫化に先駆けて、本作の試し読みを「カドブン」にて公開いたします。
はじめに
日本は「世界一美術展に行く人が多い国」です。しかし、そこで人々が熱心に見ているのは、作品ではなく「説明文」……。これはとても残念なことです。
この本は一度読んだだけで頭に残り、すぐに美術館に行きたくなる本を目指しました。
「美術」とよばれるものは古代から脈々と続いていましたが、現代に通じるアート、そしてアーティストという概念が生まれたのは、近代のヨーロッパでした。
この本では、ヨーロッパ美術を中心とした世界中の名作アート、そしてそれを創りだしたアーティストの人生とはどんなものだったのかをお話ししています。
すばらしい作品に触れたとき、このすばらしいものを創り上げた人は、どんな人生を送ったのだろう、どうしてこの作品を創るに到ったのだろうという疑問が自然と湧いてきますよね。しかし、教科書や資料集には、ほとんどそのことについては書かれていません。それは20世紀後半からの美術史において、「作者の人生とその芸術作品は別物として、分けて考えよう」という傾向があったからです。
この本が、みなさんと世界のアート、そして愛すべき個性的なアーティストたちとの出会いの扉となってくれることを心から願っています。美しいものを知り、愛することができる人生を送るほどの幸福はありませんから。
堀江宏樹
滝乃みわこ

『真珠の耳飾りの少女』 ヨハネス・フェルメール 1665年 オランダ マウリッツハイス美術館所蔵

『地理学者』ヨハネス・フェルメール 1669年ごろ ドイツ シュテーデル美術館所蔵
「恋多き妻」に萌えていたマスオさん─フェルメール
謎めいた『真珠の耳飾りの少女』の絵画で有名なヨハネス・フェルメール(1632—1675)。2011年に日本初公開された『地理学者』は、彼が男性をメインモデルとして描いた数少ない作品です。
彼が暮らしたオランダは、17世紀になってできたばかりの新しい国でした。なぜオランダが生まれたかといえば、民衆にだけは「清貧」な生活を送ることを強いる当時のカトリックの考えでは、お金をたくさん稼ぐために商売することは誇れる行為ではないとされたのです。
そこで、もともとネーデルラントと呼ばれていた地域で、商業が特に発展しつつあった南部がオランダ(プロテスタントが主流)になり、北部はベルギー(カトリックが主流)になったのでした。
フェルメールが生まれたのは、そんなオランダの西部にあるデルフトという運河の街でした。父親は実業家で、「空飛ぶ狐」という宿屋兼居酒屋を経営していました。さらに織物産業もやっていたようです。
そもそもフェルメールが画家の修業を始められたのも、実家が裕福だったから。師匠について、画家を目指すための年間の授業料は「普通の単純労働者の年収並(『芸術新潮』2000年5月号「フェルメール あるオランダ画家の真実」特集)だったそうです。現代日本なら毎年、数百万円以上が学費としてかかった計算になりますから、かなりのボンボンだったのでしょう……というところまで、現在は彼の研究が進んでいます。「ナゾの画家」といわれつづけるフェルメールですが、このあたりまで分かってきてるんですよ。
それにしても全作品がわずか35枚というのは、かなり少ない数字ですね。もともと画家としてのフェルメールには、商売っ気がほとんどなかったようです。フランスからわざわざ旅をしてフェルメールのもとを訪ねた美術評論家バルタザール・ド・モンコニーに「絵を見たい」といわれても、「手元には一枚もない!」といって驚かれたりしたそうです。
当時、職業画家は自宅の一部をショールームがわりとして、こういうファン(顧客)の訪問を待ちわびていたものですが……(たとえば、ルーベンスはそれは立派なショールームを、アムステルダムの一等地にある自宅内に持っていました)。
このようにフェルメールが相当マイペースで製作できた背景には、必ず彼の作品を高値で買いとってくれる、デルフトの醸造業者のライフェンというパトロンがいたからのようですね。フェルメールが25歳ころから付き合いがあった、馴染みのお客さんです。そして彼自身が、父親から受け継いだ宿屋の事業などで忙しかった……ということもあるでしょう。
ただ、彼はつねに「日曜画家」だったわけではなく、「職業画家」として一定以上の評価を受けてもいました。たとえばデルフトの画家組合「聖ルカ協会」の組合長を史上最年少で何度かこなしています。気に入らなければ仕事をしない江戸っ子みたいな職人気質と、ビジネスマンとしての顔を合わせもっていたのがフェルメールという画家です。
後にフェルメールはいわば「マスオさん」として、妻・カタリーナと義母・マリアと共に暮らすようになったのですが、妻より義母(しかも最初は結婚に大反対だった)に気に入られるという、珍しい「良夫」ぶりも見せたようですね(※)。
「肝っ玉母さん」の義母マリアに世話になっていたフェルメールですが、実は妻のカタリーナはフェルメールの作品にしょっちゅう描かれているように「恋多き女」で、マリアは娘のご乱交をあまりよく思っていなかった……という説もあります。
フェルメールの作品の大半が、地味なようでいて、実はセクシーなのはご存じでしょうか? 同じ衣裳(たとえばテンの毛皮のついたイエローの服など)が何度も使われているため、妻・カタリーナが頻繁にモデルを勤めていたと考えられています。絵のテーマにも、謎めいた微笑みを浮かべた女たちの「手紙のやりとり」といった題材が散見されますね。

『婦人と召使い』ヨハネス・フェルメール 1667年ごろ アメリカ フリック・コレクション所蔵
『婦人と召使い』は「奥様もすみにはおけませんわ!」とささやくような召使いの手から、夫以外から来たラブレターを受け取り、はじらっている(ように見える)女性の姿だったり、『音楽の稽古』ではハンサムな音楽教師から、マンツーマンでレッスンを受ける女性を、部屋の入り口から覗くかのように描いたり……ときには娼婦たちの姿がダイレクトに描かれもしました。
20世紀のシュールレアリズムの画家、サルヴァドール・ダリの採点によると、歴史上の画家でもっとも上手いのはフェルメールだそうですが、彼の絵の思わせぶりなセクシーさや、悪女な奥さんが描かれていることもダリの評価に貢献していたのかもしれません。ダリも、妻・ガラの尻に敷かれ続けた夫でしたから。
しかし、フェルメールは死後しばらくしてから19世紀半ばまで、ほとんど「忘れられた画家」でした。その理由は、次第に絵画が「民衆を教育する手段」となっていたことと密接な関係があります。
たとえば、17世紀以降、ヨーロッパの美術界のトレンドをリードするようになるフランスでは、ルイ14世の治世中にアカデミーという組織による、通称「サロン(官展)」が開催されはじめています。
20世紀初頭ごろまで圧倒的な影響力をもった組織ですが、この「サロン」に入選するには歴史や神話を題材に描いた作品でなければいけませんでした。しかし、フェルメールに再評価が集まりはじめる19世紀半ばのフランスの美術界といえば、印象派なども登場しはじめ、旧来の名画のルールが次第に崩れはじめた時代だったのです。
フェルメールが忘れられたのは、彼が生きた時代以降の絵画ニーズと、彼自身の生きた時代のニーズがかなり違ってしまったからなのですね。絵自体の芸術性とは絶対的なものではないのです。現代と同じく、お客さんのニーズがすべて、という事情はこのころから同じなんです。
フェルメールといえば、静謐な風景画とか静物画、そして思わせぶりな男女の絵が有名ですね。しかし、それにもお客さんのニーズがらみの理由がありました。当時のオランダのニーズでは、商売でお金を得たニューリッチたちが自宅を飾るために、気の利いた、しかもあまり大きくない絵画を求めるのが主流でした。大邸宅を持つ貴族とは違い、彼らの家はこぢんまりとしていたためスペース的な問題があったという、せちがらい理由です……。
(このつづきは、本編でお楽しみ下さい)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。