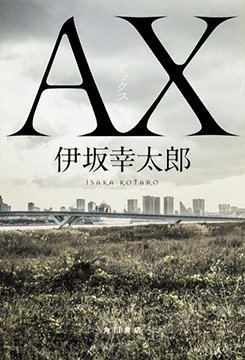試し読み

【試し読み】伊坂幸太郎『AX』
伊坂幸太郎さんの〈殺し屋シリーズ〉最新作『AX(アックス)』が2017年7月28日に発売されます。
発売に先駆けまして、カドブンでは本年度最大の注目作『AX』の冒頭の試し読みを公開いたします。
この機会に『AX』の世界観をぜひお楽しみください。

玄関ドアに鍵を差し込む。ゆっくりと入れたにもかかわらず、がちゃりと響くのが、兜には忌々しくてならない。音が鳴らない鍵が発明される日は来ないのか。神経を尖らせ、手を慎重に回転させる。錠の外れる音に、胃が痛む。扉を開く。照明の消えた家の中は、しんとしている。
靴を静かに脱ぐ。すり足で、廊下を進んだ。リビングは暗い。家の人間は全員、と言っても二人だが、すでに寝入っているのだろう。
息を潜ませ、自分の動作に気を配りながら、二階へと上がる。昇って、右手の部屋に入る。電気を点け、聞き耳を立てた。ゆっくりと息を吐く。ほっとする瞬間だ。
「なあ、兜、おまえは所帯持ちだから、これから家に帰って、こっそりカップラーメンでも食べるんだろ」
以前、同業者の男に言われたことがある。子供向けのテレビ番組、機関車トーマスを溺愛する、奇妙な男で、檸檬という名で知られていた。乱暴で、軽薄な言動が多いものの腕は立つ。その時は、別の依頼人から同じ標的の殺害を依頼され、共同で仕事をこなした後だった。一息ついた兜たちに、檸檬は得意げに、「ソドー島建設の責任者の名前は何だ?」と機関車トーマスにまつわるクイズを出していたが、誰も答えようとせず、仕方がないからか、兜のことを話題にしてきたのだ。
「兜、家族は、おまえの仕事を知っているのか」と訊ねてきたのは、檸檬の仕事仲間、蜜柑だ。二人は背恰好が似ているものの、性格については反対で、だからこそ二人で仕事をこなすことができるのかもしれない。彼らは、妻子持ちの同業者が珍しいからか、兜にずけずけと質問をぶつけた。
「家族はもちろん知らない」兜は即座に言った。「一家の大黒柱が、こんな物騒で恐ろしい仕事をしていると知ったら、家族は絶望するだろう。普段は、文房具メーカーの営業社員だ」
「家族にはそう偽っているのか」
「まあな」正直なことを言えば、兜は実際に、文房具メーカーに勤めていた。息子が生まれた頃、二十代の半ばに中途入社し、そこからずっと正社員だ。四十代半ばとなった今は、営業部でもベテランの一人だった。
「だけど、一家の大黒柱が命がけの仕事をして、帰ってから夜食でカップラーメンとは、何とも情けねえな」檸檬がからかってくる。
「馬鹿を言うな」と兜は怒った。「カップラーメンなんかを食べるわけがない」
その語調が強かったからか、檸檬は反射的に後ろに体を反らし、身構える。「怒るなよ」
「そうじゃない」兜は声を落ち着かせ、続ける。「カップラーメンはな、意外にうるさいんだよ」
「何だ、それは」
「包装しているビニールを破る音、蓋を開ける音、お湯を入れる音、深夜に食べるにはあまりにうるさい」
「誰も気づきゃしねえだろうに」
「うちの妻は気づく」兜は答える。「その音がうるさくて、起きたことがあるんだよ。彼女はな、真面目な会社員で朝も早い。通勤にも時間がかかるからな。だから、深夜にそんな音で起きてみろ、大変なことになる」
「大変? 何が大変なんだ」
「翌朝、起きて、会った時の重苦しさと言ったら、ないぞ。彼女の吐いた溜め息が積もって、床が見えなくなる。比喩ではなくて、本当に息が苦しいんだ。『うるさくて、まるで眠れなかった』と指摘された時の、胃の締め付けられる感じは、分からないだろうな」
「兜、冗談言うな。おまえが緊張しているところなんて、想像できない」
「そりゃそうだ。仕事は緊張しない。やるべきことをやるだけだ」
「かみさんに対してはそうじゃないのか」
当たり前だ、と兜はうなずく。
「でも、じゃあ、どうするんだ。カップラーメンが無理なら。スナック菓子にしても音はするぞ」蜜柑がその、愁いを含むような二重瞼の眼差しを向けた。「腹が減ったら、どうする」
「バナナか、おにぎり」兜は真剣な面持ちで、言う。
なるほど、と同業者の二人が感心しかけた。「鋭いな」と。が、兜はすぐに、「と考える奴はまだ、甘い」とぴしゃりと言い切る。
「甘いのか」「バナナもおにぎりも音がしないけどな」
「いいか、深夜とはいえ、時には、妻が起きて、待ってくれていることもあるんだ。夕食、もしくは夜食を作ってくれていることもある」
「あるのか」
「平均すれば、年に三回くらいはあるだろう」
「ずいぶん多いな」蜜柑はこれは明らかに、皮肉で口にした。
「そうなった場合、彼女の手料理を食べることになる。意外に量が多かったりする。もちろん、おにぎりもバナナも食べようとは思えない」
「そういうこともあるだろうな」
「いいか、コンビニエンスストアのおにぎりは消費期限が短い。翌朝にはもう駄目だ。バナナも意外に日持ちしない」
「つまり?」
「最終的に行き着くのは」
「行き着くのは?」蜜柑が聞き返した。
「ソーセージなんだ。魚肉ソーセージ。あれは、音も鳴らなければ、日持ちもする。腹にもたまる。ベストな選択だ」
檸檬と蜜柑が一瞬黙る。
「時々、深夜のコンビニで、いかにも俺と同じような、仕事帰りの父親が、おにぎりやらバナナを買っていこうとするけれどな、それを見るといつも、まだまだだな、と感じずにはいられないんだ」兜は続ける。「最後に行き着くのは、魚肉ソーセージだ」
言い切る兜を、ぽかんと眺めていた檸檬はやがて、ゆっくりと手を叩きはじめる。はじめは間を空けていたのが、だんだんと早く。スタンディングオベーションを座りながらにやるかのような雰囲気で、顔は至って、真面目だった。「兜、おまえは今、非常に情けない話を、これ以上ないくらいに恰好良く語ってるぞ。感動だ」と拍手を小刻みにしていく。隣の蜜柑が、馬鹿馬鹿しい、と苦虫を潰していた。「業界内で兜と言ったら、一目置かれている。一目どころか二目も。それがこんな恐妻家だと知ったら、がっかりするやつもいるだろうな」
あの二人には最近、あまり会わないな、と兜は思う。「ソドー島建設の責任者は、ジェニー・パッカードさんでした!」と誇らしげに言う檸檬の顔が思い出された。
背広のポケットに突っこんでいた魚肉ソーセージを取り出す。静かにビニールを剝がし、一口を齧る。空腹をソーセージが慰める。椅子が軋むため、まずいまずい、と焦る。妻が起きてこないか、耳を澄ました。
(このつづきは、本編でお楽しみ下さい)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。