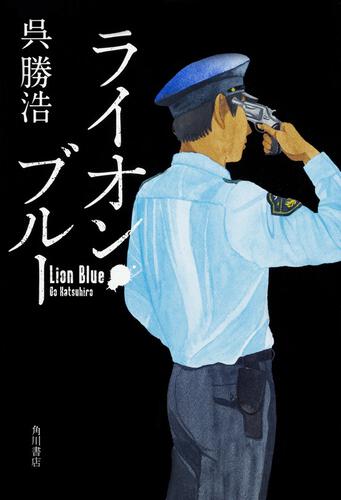無差別銃殺事件を生き延びた5人。彼らは、何を隠しているのか。呉勝浩「スワン」#13
呉勝浩「スワン」

十月――
1
白い砂の上にニョキニョキと、赤茶けた突起物が生えていた。こんもりとした緑色の塊に、ごつごつした小さな岩。岩の表面には引っくり返ったシイタケのような生物が張りついている。暗がりに横たわる長方形の空間はブルーライトに照らされ、まるで音の届かない海の底──、もしくは台詞を失くしたステージを思わせた。
「リュウキュウスガモを入れてみたんだ」
おだやかな声だった。呼びかけ未満の口ぶりだった。楽しい会話のためでなく、ご機嫌をうかがうわけでもなく、得意げな響きともぜんぜんちがう。苛立ちすら、そこにはない。あえていうなら「あきらめ」が、彼とわたしのあいだに満ちているのだと、片岡いずみは感じた。
水槽の奥のほう、細かな突起にまみれたカリフラワーみたいなサンゴの背後で、前回見かけなかった丈の高い海草がたゆたっていた。黄緑色のすっきりのびた形は、草原でゆれていても不思議ではなかった。青白い光を透過させながら水中をなでる様は、薄いヴェールを連想させた。
育てるのがむずかしい品種でね──と、北代周吾がつづけた。水質の維持に骨が折れる。かといってずっとかまってはいられない。いつもここで診察をするわけにもいかないからね──。
「もっと高価なろ過器を購入すれば安心なんだが、家内を説得する手間を想像すると徒労感が勝ってしまう」
北代が口を閉ざし、ぶううん、というかすかな機械の作動音だけが残った。
デスクチェアに腰をうずめたいずみは、壁ぎわの水槽と向き合っていた。デスクを挟んだ北代もおなじようにしていた。明かりを消し、カーテンも閉めきっているから、水槽のライトと開けっぱなしのドアから差し込む廊下の光だけが視界の助けだった。ドアの開放はいずみの希望だ。変な誤解をされたくないと理由をつけたが、孫と祖父ほど歳の離れた北代からよこしまな視線を感じたためしはなかった。ただ、密室が嫌だったのだ。
水槽の中は時が止まったみたいにじっとしていた。いずみと北代も似たようなものだった。
このアクアリウムには魚やエビがほとんどいない。動く生きものは疲れる、と北代はいう。ならば自分も許されるといずみは思う。活発さとかけ離れたヒト型オブジェ。でも北代は、うんざりしているにちがいない。オブジェにカウンセリングをほどこすなんて、どう考えたって気が滅入るから。
「学校は──」
その問いかけは水槽を向いていた。
「どうかね」
いずみは返事をしなかった。期待されているとも思わなかった。
「バレエ教室のほうだけでもと、お母さんはおっしゃってるが」
いつもどおりの台詞を、いつもどおりにやり過ごす。ずっと保ってきた一方通行のコミュニケーション。
いずみはぼんやり、水槽に映る少女を見つめた。我ながら生気のない顔つきだった。さえないトレーナーとデニムパンツ。むさくるしくのびた黒髪は、まるで腐った海藻だ。
「少しずつでいい。少しずつで」
北代がつぶやいた。独白のように。それはこの気だるい時間の終わりの合図。
北代メンタルクリニックを出ると曇り空が広がっていた。間もなく帰宅ラッシュという時刻だった。十分ほど歩けば三郷駅南口に着く。いずみが母と住むハイツは駅を北口へ抜けて進んだ早稲田公園の手前にある。初め、母は近場のクリニックに反対していた。男性医師という点にも抵抗があったようだ。歩いて通えるところがいいと押しきったのはいずみだ。正解だったと思っている。でないとあの心配性な母は、いまでもきっと車で送り迎えするといって聞かなかっただろうから。
駅へ急いだ。三郷一丁目の交差点からのびる二車線道路の道沿いには銀行やコンビニがほどほどの間隔でならんでいる。交通量に比べ通行人は多くない。
バスロータリーの先に高架が見えた。その下に改札がある。そこを通り過ぎて高架をくぐるのがいつもの帰宅ルートだ。
いずみはICカードを入れたパスケースをかざし、改札の中へ進む。
西船橋方面ホームの階段を上がる。タイミングよくやってきた電車に、数人の待ち人とともに乗り込む。
車内もガラガラだった。楽に座れた。電車が動く。十秒もせず川の上を走りだす。三郷市と流山市をわける江戸川を越えるあいだ、いずみは窓に背を向け、ぎゅっと目をつむった。
冷や汗が流れた。心臓をにぎりつぶされる感覚だ。
四月の事件以来、川を越えることに忍耐が必要となった。三郷は江戸川と中川に挟まれた土地で、武蔵野もつくばエクスプレスも、陸地だけのルートはない。いや、たとえ三郷でなくとも、生きている限り、それを永遠に避けつづけることは不可能だ。川だけでなくショッピングモールやカフェ、閉ざされた空間。
ゆっくり慣れていくしかない。黒から白へ、魔法のような回復はあり得ないから──。
北代のアドバイスは正しいのだろう。事実いずみはこの数ヵ月で徐々に外へ出られるようになった。突発的なパニック症状も影をひそめ、背を丸めながらではあるけれど、こうして電車にも乗れている。週に一度のカウンセリングを隔週に変えたのは、それなりの手応えがあったからだ。
けれど学校となると、話がちがう。
まして、バレエ教室なんて。
南流山駅に停まったのち、電車は新松戸駅に到着した。都内へ通じる常磐線が連絡しているため利用客は多い。いずみは腰を上げ、足早に電車を降りた。
にぎわいのある駅前に立ち、パンツの後ろポケットから紙を取りだす。A4用紙に地図が印刷されている。それを頼りに、まずは消費者金融の看板を目指した。陽は暮れかけ、辺りには仕事帰りの会社員や買い物袋を提げた女性などが行き交っていた。
消費者金融のビルを過ぎると、にぎやかさがくすんでいった。建物が混み合っているせいか、おなじ二車線道路なのに三郷よりも窮屈な気がした。パチンコ店を越え、ほどなく指定の店にたどり着く。通り沿いにある、半地下になった中華料理店だ。営業している様子はない。それは事前に知らされていた。
約束の六時半を少し過ぎている。
あらためて、いずみは自分がここを訪れた理由を自問した。
決心をつけるように息を吐き、階段をおりてゆく。
動く気配のない片開きの自動ドアを両手でこじ開けようとしたとき、
「ああ、すみません」
ガラスの向こうから声がして、いずみは彼の存在に気づいた。
レジカウンターのそばからぬっと現れた男性が、中からドアを開いてくれた。
店内は暗かった。空気がひんやりとしている。左右にならぶテーブルは空っぽで、厨房には人影どころか食器のたぐいも見当たらない。
「えーっと」ドアを開けてくれた彼はウェイターやシェフに似つかわしくない灰色の背広を着込んでいた。「片岡いずみさま、でしょうか」
どこかとぼけたしゃべり方だった。丸い顔に丸い眼鏡をかけていた。眼鏡の奥の瞳も丸かった。永遠にびっくりしつづけているような顔つきだと、いずみは思う。
彼は手もとのバインダーといずみを見比べ、かすかに首をかしげた。
「失礼ですが、お母さまは」
「仕事です。わたしだけでは駄目ですか」
表情を変えないまま、彼はこちらをのぞき込んできた。
「そもそも母は関係ありません。関係あるのはわたしだけです」
「しかしいずみさんは──」
「十六歳です。もうすぐ十七になります」
ふたたび沈黙があって、それから彼はペンをにぎった手でおでこをかいた。
「べつにお酒を飲むわけじゃないですよね」
「それは、はい、もちろん」
「なら、子どもあつかいはやめてください」
ふうん、と彼は鼻を鳴らした。すっとぼけた調子で。
「あの、まずは名乗ってもらっていいですか」
「これは失礼しました。わたくし、徳下宗平と申します」
馬鹿丁寧に名刺を差しだされ、いずみは慣れない手つきでそれを受け取った。
『浅羽法律事務所 弁護士 徳下宗平』
「お送りした招待状をお見せいただきたいのですが」
名刺をポケットにねじ込み、ショルダーポーチから封筒ごと徳下に渡す。これが自宅に届いたのは先々週のことだ。
中を確認した徳下は「たしかに」とうなずき、封筒を背広の内ポケットにしまった。
「できましたら身分証もお見せいただけますか」
「……学校のやつしかないですけど」
「写真付きのものでしたらけっこうです」
「見せたら参加させてくれますか?」
呆けた、という表現がぴったりな顔が返ってくる。
「参加させてもらえないなら見せる必要はないと思います。個人情報だし」
「たしかに」
徳下がおおげさにうなずく。
「今日の集まりについてお母さまはなんと?」
「行きたかったら行けばって」
「わたくしから直接ご連絡をしても?」
「仕事中だと伝えたはずです」
ふうん、とうなる彼の目前に、いずみは学生証を突きだした。
徳下の丸い目が大きくなった。
「文句でも?」
「まさか。とんでもございません」
ポニーテールだったころの写真が付いた学生証をしまい、徳下をにらむ。
「いいんですか? 時間、過ぎてますけど」
「ああ、たしかに。まずいです。みなさまに怒られてしまいます」
焦ったそぶりもなく、
「わかりました。では片岡さま、どうぞこちらへ」
徳下は店の奥へ歩きだした。
明かりの落ちた店内で、彼が向かう引き戸からは光がもれている。
招かれた個室の狭さに、神経がぴりっと尖った。
天井から吊るされたランタンのような照明が、中央の円卓をあたたかく照らしていた。回転台のある中華テーブルを直に見るのは初めてだ。
「みなさま、お待たせいたしました」
徳下の呼びかけに、先客たちが視線を投げてくるのがわかった。いずみはうつむきかげんにそれを受けとめた。赤く塗られた中華テーブルを見据え、目を合わせないように彼らをうかがう。
テーブルには、四人の男女がついていた。年齢はまちまちだが、いずみより若そうな者はいない。
「空いてる席に──」
「ドアを、開けたままでお願いします」
徳下が間抜けに目を大きくする。
「少しだけでいいから、お願いです」
返事を待たず、いずみは手近な椅子に座った。
徳下は戸を閉めきらないところまで引き、「では──」とテーブルの面々を見下ろした。
「本日はお集まりいただきありがとうございます。あらためまして、この会合の進行役をつとめさせていただく徳下宗平と申します」
東京都の弁護士会に所属していることと、自分の登録番号を淡々とつづけた。
「お渡しした名刺の肩書について一点お断りがございます。わたくしが浅羽法律事務所にお世話になっていることは事実ですが、本件と浅羽の事務所は直接の関係がありません。問い合わせ等ございましたらわたくし自身にしていただければと思います」
「上司にクレームは困るというのか」
一番奥に座るポロシャツの男性が声をあげた。盛り上がった白髪の下の鋭い目つきが、じっと徳下を刺していた。胸もとで組んだ細い腕に血管が浮いているのを、いずみは視界の端で見てとった。北代と同年代に見えるが、体型も話し方の印象もまったくちがう。
「お叱りでしたら事務所にご連絡くださってかまいません」徳下がとぼけた口調のまま返す。「しかしながらこの会合は浅羽を通じわたくし個人が請け負っているものなのです。仔細な事情は省きますが、わたくしにここでの成果を浅羽へ報告する義務はありませんし、するつもりもございません。よって問い合わせは二度手間となる可能性が高いのです」
「公認のアルバイトか。充分うさんくさいな」
白髪の老人に向かって徳下が目を大きくした。その沈黙にバツが悪くなったのか、老人が先に目をそらす。
「ややこしい話はいいのだけど」
老人の横の、席をひとつ空けた左隣に座る女性がふくよかな頬に手を当てぼやいた。「そこの飲みものをもらえません? なんだか喉が渇いちゃって」
「これはたいへん失礼しました」
恐縮したそぶりで頭を下げる徳下の背後に、緑茶のペットボトルがならぶワゴンと、そして場ちがいなホワイトボードがあった。
「コーヒーと紅茶もありますが」
「紅茶は無糖?」
「ええ、そのようになっております」
ならそれをちょうだい、と女性がいう。薄手のセーター越しにも豊かな身体つきが見てとれた。いずみの母よりも少し上の年齢だろう。パーマをあてた短めのヘアスタイルが、いずみの目には少しやぼったく映った。
徳下に訊かれ、いずみは緑茶を求めた。彼は円卓をめぐって参加者ひとりひとりにペットボトルと紙コップを配ってゆく。
「飯もって期待してたんだけどなあ」
いずみの右手からだった。
「ビールとかさ」
青みがかったワイシャツの男性がペットボトルをふりながら、こちらを見てニコリと笑う。「ね?」
いずみは手もとの緑茶に視線をもどした。男性はパーマの女性よりずっと若く、すっきりした短髪をさらっと茶色に染めていた。会社員のようだが、ちょっと軽薄な印象だ。
「だって集合場所が中華料理屋なんだもん。仕事帰りにわざわざ出向いたわけだし、それくらいって思っちゃうでしょ」
「申しわけございません。交通の便がよく、落ち着いて話し合える場所というのがここくらいしか見つかりませんで」
「まあ、いいですけど。でも、こんなつぶれた店舗を借りるって意外とむずかしくないですか? 仕事柄わかるんですよ、そういうの。もしかして依頼人の方って、けっこうな身分の人だったりして」
「コナガワ物流の社長だ」白髪の老人が不機嫌そうに答えた。「手紙に名前があった。検索くらいしてないのか」
「へえ、やっぱお金持ちかあ。いや、すんません。これでもわりと忙しい身なもんで」
照れたように頭をかくワイシャツの男に、老人が顔をしかめた。
徳下が最後に飲み物を配った相手はパーマの女性の左隣、いずみの正面に座るスタジアムジャンパーの男性だった。彼はコーヒーのミニボトルに手をつけるでもなく、礼をいうでもなく、縮こまってうつむいている。
「では、お飲みものも行きわたったようですし──」
「その前にいいかしら」
徳下の進行をパーマの女性が遮った。
「いちおう確認したいのだけど」
戸惑いと警戒がまじった口ぶりだった。
「手紙にあったとおり、ここでの会話はここだけのものなのね?」
「そうです」と徳下が即答する。
「じゃあ、名乗り合わなくていいという約束は守ってもらえるのかしら」
「もちろんです。お名前をはじめとするみなさまの個人情報を、わたくしがほかの方に明かすことはいたしません」
「おれはべつにいいですけどね。隠すほどたいした人間でもないし」ワイシャツの男性が割り込んだ。「ま、みなさんに合わせますよ。でも、君やあんたやAさんBさんじゃ話しにくいし、せめてニックネームがほしいと思いません?」
ワイシャツの男性といっしょに徳下が、ほとんど同時にほかの面々を見渡した。
「あんたはどう? ずっと黙ってるけど」
ワイシャツの男性に手のひらで指され、スタジアムジャンパーの男性がおどろいたように顔を上げた。
「お、おれは……」
「あ、ごめんごめん。無理にしゃべらそうってつもりじゃないんだ」
勝手に切り上げ、ワイシャツの男性は座り直す。
「おれから自己紹介させてください。呼び名はハタノで。波に多いに野原のノで波多野。三十一歳、仕事は賃貸マンションの営業っす。嘘か真かは、ご想像にお任せします」
これでいい? と徳下を向く。
「けっこうです。仮に嘘でもわたくしは指摘いたしません」
満足げに笑みを浮かべた波多野が、白髪の老人を見やった。
「保坂伸継。本名だ」
老人は、そういってむすっと口を結ぶ。
「わたしは──」と、ためらいがちにパーマの女性。「こういうのは苦手なのよ。AとかBでもいいのだけど……」
「好きな芸能人とかでいいんじゃないですか」
「じゃあ……イクタにしようかしら。生田斗真くんの」
波多野が「似合ってますよ」と適当な合いの手を入れた。
「あんたはおれがつけてもいい? あんた強そうだからドウザン。力道山の道山ね」
ジャンパーの彼はうつむいて答えず、そのまま道山が採用となった。
「君はどうする? ご希望なら考えてあげるけど」
「──片岡いずみ」
がたっと椅子の音がした。道山がこちらを見て口をパクパクさせていた。しん、と空気が固まった。波多野の合いの手もなく、保坂は目を吊り上げ、生田は手で口を押さえおどろきを表している。
「みなさま」徳下の、緊張感のない声が呼びかけた。「無用な詮索や邪推はおひかえいただくよう願います。疑心暗鬼や不和は、有意義な議論のさまたげになりかねません」
同意を得るように面々を見回す。
「繰り返しになりますが、ここでの会話はここだけのものです。みなさまの発言が週刊誌やワイドショウに流れることも、たとえば捜査関係者の耳に入るようなこともありません。ぜひとも自由闊達に意見を交わし合っていただければと思います」
「徳下さん」
いずみが尋ねる。
「お礼についても、ちゃんと説明してください」
「もちろんです」
徳下が大きくうなずいた。
「しかし、いましばらくお待ちください。まずはこの会合の趣旨をご説明しなくてはなりません」
手紙との重複もありますが、と断ってからつづける。
「依頼主は吉村秀樹氏。さきほど保坂さまがおっしゃってくださったとおり、株式会社コナガワ物流の代表取締役社長であらせられます。ご記憶の方もおられるかもしれませんが、秀樹氏は四月に湖名川シティガーデン・スワンで起こった無差別銃撃事件において、お母さまである吉村菊乃さんを亡くしておられます」
湖名川シティガーデン・スワンで起こった無差別銃撃事件──。その文言が発せられた瞬間、部屋の空気は張りつめ、いずみはみぞおちのあたりに痛みを感じた。
「日曜日にスワンへ出向きスカイラウンジでゆっくりランチを楽しむ。それが彼女の習慣だったそうです。犯人の男たちが最初の銃弾を放ったときも、菊乃さんはスカイラウンジのテーブルについてらっしゃった……。今夜ここにお集まりいただいたのは、あの日菊乃さんとおなじように事件に巻き込まれ、そして無事生き残った方々なのです」
互いが互いを、かすかに探る気配があった。
「どうかみなさまの貴重なお話を、わたくしどもにお聞かせいただきたいのです」
「なんで?」波多野が訊く。「ご指名の理由は当然そうだろうって思ってたけど、手紙には具体的な目的が書かれてなかったよね」
スワン事件について情報提供をしてほしい──要約するとそのような文面だった。
「犯人は死んでる。ふたりとも自殺した。それは警察も認めてるんでしょ?」
「はい。大竹は白鳥広場で、丹羽はスカイラウンジで」
大竹は自らを日本刀で突き刺し、丹羽はこめかみを模造拳銃で撃ちぬいた。
呼吸を、いずみは整える。
「だったらいまさら、何が知りたいわけ?」
「もっともなご質問です」
すべて想定内とでもいうように、徳下はよどみない。
「本題はここからです。まず第一に、依頼主である秀樹氏にとってお母さまはとても大切な存在だった点にご留意ください。愛する母親のとつぜんの、そして理不尽な死に対する怒りと哀しみが、この依頼の動機であるとご理解いただきたいのです」
「金銭が目的じゃないというんだな」
「そのとおりです」保坂の確認に徳下が応じる。「わたくしが知るかぎり、菊乃さんの死は制度上なんら問題なく対応されています。その点に異議を差し挟む余地はごくわずかしかございません」
生命保険金絡みのようなもめ事はないということだろう。事件から半年が過ぎているうえ、秀樹の社会的地位を考えれば説得力があるといずみは思った。反面、ごくわずか、というまどろっこしい言い回しが引っかかる。
「第二に、警察の捜査は被疑者死亡をもって完了しています。犯人の男たちが模造拳銃を製造した過程だとかの周辺捜査はつづいているようですが、あくまで補足的なものでしょう。そもそも警察が犯行の認定以外に興味をもっていたかも疑問です」
「どういう意味?」
生田が、こわごわと手を挙げた。
「犯行の認定って……、あいつらが、みんなを殺したってことよね?」
「はい。正確には殺害にいたらなかったぶんも含め、犯人がいつどこで誰をどのように傷つけたかです。あの混乱のなかで転倒や不慮の接触によって怪我をされた来場者もいらっしゃいましたから、警察はスワンに設置された防犯カメラを検証し、じっさい犯人が手にかけた被害者を特定していったと思われます」
生田が、挙げた手を頬に移した。
「えっと……それで充分じゃないかしら? だって殺してまわったのは犯人の奴らなんでしょ? それ以外はべつに……」
「ごもっともです」
徳下は玩具の人形みたいにうなずく。「犯人の動きを特定するのが最優先なのは当然です。しかし逆にいうと、それ以外を念入りに調べる必要性は低い。本館は相当な面積がありますし、来場者も数万人規模だったと聞きます。何もかも把握するのはむずかしく、さほど重要でもない。警察がそう判断するのは妥当です。見逃しの余地はあるのです。たとえば犯人たちの銃撃の外側で、何か犯罪行為があったとしても」
え……。声にならない声が、生田の口もとからもれた。
「馬鹿な」保坂が苛立ったように吐く。「火事場泥棒くらいあっても不思議じゃないが、ならば被害届が出ているだろ」
「被害者が死亡していたらどうでしょう」
保坂が絶句した。
「事件のさなか、スワンのどこかで犯罪行為があった。その被害者は、犯人によって命を絶たれてしまった。この場合、最初の犯罪行為を訴えるすべがありません」
生田が口もとを手のひらで覆う。
「失礼しました。あくまで仮定の話ですのでお気になさらず」
「いやいや」波多野がテーブルへ身を乗りだした。「でもつまり、そういうことですよね? 犯罪行為かどうかはともかく、吉村社長はお母さまの死に何か不審を抱いてらっしゃって、隠された真実をあきらかにすべくあなたを雇ってこのお茶会を開いたと」
「否定はいたしません。真実をあきらかにしたいという意味では」
「だったらその娘を質せばいい」
保坂の尖った口調が耳を叩いた。
「菊乃さんは事件が起こったときスカイラウンジにいたのだろう? 何か隠しているとすればその娘以外にいないじゃないか」
「まあまあ、保坂さん」波多野が苦笑まじりにいさめる。「そんなふうにトゲトゲしたらかわいそうでしょ。この子だって被害者に変わりないんだから」
乱暴に鼻を鳴らす保坂の様子が目の端に映った。
徳下がなだめるようにいう。「秀樹氏の希望は誰かを吊るし上げることではありません。犯行時のスワンで何があったのか。目的はそれを知ることで──」
「お礼の話を」
いずみの発言に、徳下の声がやんだ。
「わたしの目的はお金です。それ以外は興味ありません」
つるつるのテーブルを見つめ返事を待った。保坂のほうは見なかった。波多野や生田から、ぎょっとしたような視線を感じる。
「──かしこまりました。では、みなさまへのお礼について説明します。この会は毎週金曜日、計四回を予定しております。一回につき二時間以内。出席の時点で交通費を三千円、一時間以上の参加で一万円をお支払いいたします」
ひゅう、と波多野が口笛を吹いた。
「参加不参加はその都度自由ですが、皆勤の方には別途二万円の皆勤賞をご用意します。以上は出席のみを条件とした基本給のようなものです。加えて毎回、上限三万円のボーナスを設定しております」
「役に立ったらもらえるということかしら」
当然そうだろうと思われた生田の確認に、徳下はうなずかなかった。
「便宜上ボーナスと申しましたが、基本的には報酬の一部とお考えください。いわば『真実を話していただくこと』への対価です。言い換えると、『偽りを述べた場合』は減額の対象とさせていただきます」
ぴりっと空気が尖るのを感じた。
「現時点で嘘の氏名を名乗ってる可能性があるけど?」と波多野。
「この会の目的は菊乃さん殺害の真実をあきらかにすることです。あるいは悲劇の総括」
その言葉に、いずみは思わず顔を上げた。
徳下と目が合った。反射的にそらしてしまう。喉の渇きを覚えた。
「ともかく」と、徳下がつづける。「この目的に関わらない嘘は不問といたします。そうでない嘘──我々を真実から遠ざけるような嘘があった場合は、内容を考慮したうえで減ずる額を決めさせていただきます。最悪の場合、たったひとつの嘘で三万円が消える可能性もあるとご理解ください。真偽の判定と減ずる金額の決定は、僭越ながらわたくしが独断でさせていただきます」
「真実かどうか、君が見抜ける根拠はなんだ」
「NO動画をご存じでしょうか」
保坂の質問に、徳下が問いで返した。
「犯人たちがみずからの犯行をリアルタイムで録画した映像です」
大竹のものがO動画、丹羽のものがN動画と呼ばれているのだと補足を入れ、
「一時間の動画が六つのファイルに分割され、アップロードされています。規制がかかっている現在、閲覧はむずかしくなっていますが、わたくしは計十二個のファイルをすべてもち、そして穴が空くほど繰り返し観ているのです」
犯行の全容をほとんど把握するほどに──、と加える。
「秀樹氏が警察から得ている情報もあります。証言の真偽判定はこれらを参照のうえ行います。誤りなきよう細心の注意を払うつもりですが、減額を理不尽に感じることもあろうかと思います。よってこのお金は、あくまでボーナスとお考えいただければと思うのです」
「減らしたぶんを懐に入れる気じゃないのか」
「ならばここでわざわざお伝えしません」
徳下が即答し、文句はなくなった。
「報酬について最後にひとつ。四回のうちに秀樹氏が求める疑問を解決できた場合、ひとりあたり五万円をお支払いいたします。これは出席回数にかかわらず、ここにおられる全員が対象となります。また、たとえば二回目で解決となったさいは三回目、四回目の報酬も含めて全額お支払いさせていただきます」
「皆勤と正直と解決でMAX二十三万か。えらく太っ腹ですねえ」
波多野の口ぶりに皮肉めいた響きがあった。
「ま、もらえるもんはありがたくもらいますけど。で? その疑問ってのはなんなんです?」
「なぜ、吉村菊乃さんが殺されたのか」
不意打ちをくらったような気配が満ちた。
変わらぬ調子で徳下がつづける。
「午前十一時ちょうど、丹羽佑月が白鳥広場で、大竹安和が黒鳥広場で、それぞれ犯行を開始します」
その後、丹羽は二階フロアを黒鳥広場へ、大竹は一階フロアを白鳥広場へ。ふたりは向かい合う恰好で進みながら犯行をつづけた。
「犯行開始時刻、菊乃さんはまだスカイラウンジにいらっしゃった。なのになぜか、一階のエレベーター乗り場で被害に遭うのです」
本館一階のいちばん奥、黒鳥の泉がある噴水広場で。
「スカイラウンジへつながるエレベーターのそばで倒れ、二発の銃弾を浴びています」
「騒ぎに気づいて逃げようとしたんでしょ? そこを撃たれた」
「ちがいます」波多野の意見を、徳下ははっきりと否定した。「ちがうんです」
その声に、かすかな力みを感じる。
「先入観を与えたくありませんので、お伝えする事実は最小限とさせていただきます。まず、菊乃さんが撃たれたさいの状況です。これはスワンの防犯カメラによって確認できたのですが、犯人はフロアとエレベーターにまたがってうつ伏せに倒れていた菊乃さんを撃ち殺しています。彼女の身体は上半身がエレベーターの中、下半身がフロアのほうにはみ出しており、そして撃たれたのは後頭部と背中です」
謎かけに戸惑うような沈黙を、「あら?」と生田が破った。
「はい、お気づきのとおりです。状況は、彼女がエレベーターを降りたときに倒れたのではなく、エレベーターに乗ろうとして倒れたことを示しています」
空気が重さを増す。保坂のほうからうなるような息づかいが聞こえた。
「次に死亡推定時刻です。菊乃さんが亡くなったのは午前十一時よりももっとあと──正午前後とみられています」
椅子が鳴る。目を見開いた道山が、後ずさるように身体を起こしていた。
さて──。何事もなかったように徳下が告げる。
「まずは事件発生時刻に、みなさまがどこにいらしたか。そこからはじめましょう」