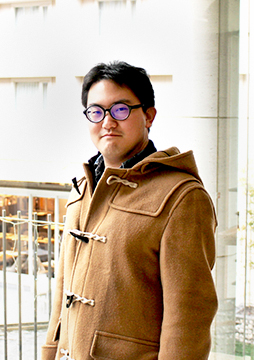人命の価値が極めて低い時代ならではのミステリー――『雨と短銃』杉江松恋の新鋭作家ハンティング
杉江松恋の新鋭作家ハンティング
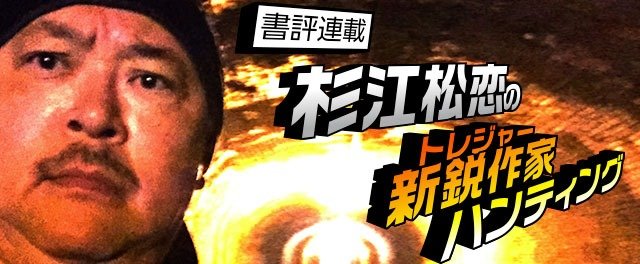
書評家・杉江松恋が新鋭作家の注目作をピックアップ。
今回は、注目を集める伊吹亜門の新作。
抜群の状況設定が読者にとっては最大の説得材料である。
伊吹亜門『雨と短銃』(東京創元社)を読んで感心するところ大だったので、ぜひともこの感覚をみなさんと共有したいと思った次第である。この作者、思っていた以上に勘が良い。勘、というと漠然としているが、おもしろくなりそうだな、という期待感を膨らませる技巧と言い換えてもいい。娯楽小説の書き手として、羨ましい才能だ。
幕末期を舞台とした時代ミステリーである。中心に置かれているのは、人間消失の謎だ。一八六五(慶応元)年、京都のとある料理屋で尾張藩公用人の鹿野師光は、土佐藩浪人の坂本龍馬と密会し、人捜しを頼まれる。捜す相手は、薩摩藩士の菊水簾吾郎という人物である。この世から姿を消したかのような不可解な形で簾吾郎はいなくなってしまったのだ。
簾吾郎が最後に目撃されたのは西陣にある村雲稲荷と呼ばれる神社の境内だ。訳あって龍馬がそこに踏み込むと、斬撃によって瀕死の重傷を受けた長州藩士・小此木鶴羽が倒れていた。傍らに立っていたのが簾吾郎である。逃げる簾吾郎を追って龍馬は境内の奥へ走ったが、そこには神社に仕える下働きの父子がいたのみであった。父子は簾吾郎の姿を見ていないという。身を隠せるような物陰があったわけでもなく、くだんの薩摩藩士は文字通り姿を消してしまったのである。
密閉空間からの人間消失を扱ったミステリーは数多いが、目撃者に実在の有名人である坂本龍馬を配した点が、まずいい。またこの謎は、解かれなければすべてがご破算になるという切羽詰まった事態と共に呈示されるのである。師光が簾吾郎の行方を捜すように頼まれるのは、それゆえなのだ。謎が状況設定に支えられ、主人公がいかなる目的を持って行動しているのかも事件の構図を見れば一目で理解できるように書かれている。
龍馬と師光が会う第一章に先立って、四つの寸景を描いた序章が置かれている。日本史にあまり詳しくない読者でもここに目を通せば幕末当時の状況がすぐに理解できるはずだ。最初に書かれているのは長州藩の要人・桂小五郎と、土佐を脱藩した龍馬、中岡慎太郎の三名による密談の場面だ。おおざっぱに言えばこのとき、長州藩は徳川幕府によって追い詰められていた。その先兵となったのが薩摩藩だったのだが、龍馬は犬猿の仲である長州と薩摩の手を結ばせることで討幕を成し遂げるという奇策を小五郎に呈示する。いわゆる薩長同盟立案の瞬間だ。司馬遼?太郎『竜馬がゆく』をはじめ、数々の作品で描かれた名場面である。続いて、事件の主要な登場人物の一人である鶴羽が小五郎から京に行って龍馬らに協力するよう命じられる場面が描かれる。これが二つ目。
三つ目は京の二本松薩摩藩邸における場面で、西郷吉之助、のちの隆盛と龍馬の談判である。これまた『竜馬がゆく』をなぞるような形にはなるが、要するに薩長同盟が政治的な曲芸の上で成し遂げられようとしていることを強調するために置かれているのである。一つでも間違いがあれば計画は崩壊するだろうということが並々ならぬ会見の様子によって読者に印象づけられる。最後に鶴羽が何者かによって斬られる衝撃的な場面が置かれ、物語の幕開けに必要なすべての道具立てが揃う。
伊吹のデビュー作は短篇「監獄舎の殺人」であった。二〇一五年に第十二回ミステリーズ!新人賞に輝いた作品で、伊吹はこれを連作化、二〇一八年に短篇集『刀と傘 明治京洛推理帖』として上梓した。新人の初単行本としては異例なほどの話題となり、結果として第十九回本格ミステリ大賞も射止めている。続篇となる本書は、初の長篇作品というわけだ。
短篇もいいが、長篇という形式がこの作者の資質をさらに引き出している。謎という素材を物語の文脈の中で活かすことに成功しているからだろう。前述したように、最初に呈示される状況は申し分ないほどに読者の興味を惹きつける。伊吹はさらに、危機の予兆を随時織り交ぜながら緊張を維持して叙述を進めていく。これは鹿野師光という探偵役の功績だろう。龍馬と会ったあとで師光は事件の関係者に話を聞いていく。ここが単なる情報の羅列ではなく、利害関係が複雑な相手との肚の探り合いとして描かれるのである。西郷隆盛は外見からは想像できないほどに繊細な配慮をする計略家だったそうで、薩摩邸で彼と話した師光も、一度は門前払いに近いようなあしらいを受ける。読んでいるほうの苛立ちが高まるような書きぶりだ。さらに幕府の公安警察である新撰組副長・土方歳三まで接近してくる。油断を見せたら襲い掛かってくる野獣に身の周りをうろつかれるようなもので、まったく気が抜けないわけである。これで一気にページをめくらされる。
魅力的な謎に加えて先行きが読めないというサスペンス、命の危険さえちらつくスリル。ミステリーの必要条件がすべて備わっている。幕末が物語の舞台となっている点にも意味がある。イデオロギー闘争の中で多くの志士たちが死んでいった。人命の価値が極めて低い時代であることが背景にある物語でもあるのだ。現代の小説なら、ここまでの緊迫感は出なかっただろう。むだが一切なく、娯楽小説として申し分なし。伊吹亜門、ついに本領発揮。