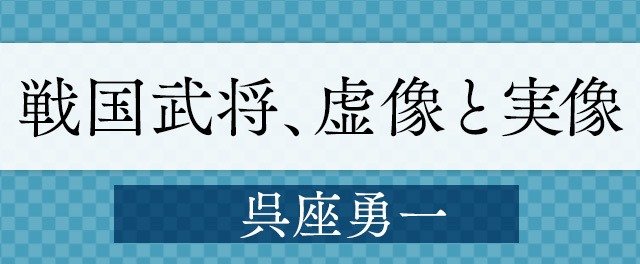呉座勇一「戦国武将、虚像と実像」
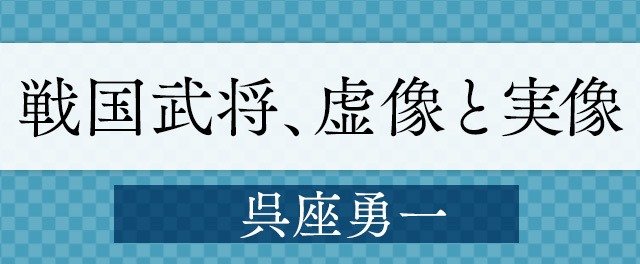
はじめに
織田信長や豊臣秀吉や徳川家康といった戦国武将に関しては、だいたいこういう人物だろうというイメージを皆が持っている。その人物像は小説やドラマ、映画などに淵源していることが多いので、人それぞれ違う、ということはあまりない。秀吉は人たらし、家康は狸親父といったイメージが世間一般に広く流通している。
だが、そうした人物像は必ずしも固定的なものではない。昔からずっと同じイメージで語られてきたわけではなくて、時代ごとにイメージは変わっている。我々が抱いている信長像や秀吉像は何百年も前に作られたものではなく、意外と最近、たとえば司馬遼太郎が作ったイメージに左右されている、ということが結構ある。そこでこの連載では、信長像や秀吉像が時代によってどう変遷したかということと、実際はどういう人だったのかということを、述べたいと思う。それによって、時代ごとの価値観も浮かび上がってくるだろう。
第一章 明智光秀――常識人だったのか?
第一節 近世の明智光秀像
同時代人の明智光秀像
明智光秀というと、古典的教養を備えた常識人で、朝廷や幕府といった既存の権威・秩序を尊重する保守派の印象が強いだろう。しかし以前、拙稿「明智光秀と本能寺の変」(『明智光秀と細川ガラシャ』筑摩選書)で論じたように、光秀が古典に通じていたのは事実だが、伝統や権威を尊重し、改革に否定的な人物であることを明確に示す一次史料は存在しない。
上の光秀像は、本能寺の変の動機を考える中で生み出されていった。織田信長の改革路線に光秀が反発して、本能寺の変が起きた、と想定したのである。
けれども、このような理解は昔から存在したわけではない。光秀敗死直後、人びとは光秀を一様に非難した。光秀が山崎の戦いに敗れ、敗走中に死んだのは天正十年(一五八二)六月十三日だが、興福寺僧の英俊の日記『多聞院日記』天正十年六月十七日条には「(光秀は)細川の兵部太夫が中間にてありしを引き立て、中国の名誉に信長厚恩にて之を召し遣わされ、大恩を忘れ曲事を致す。天命かくのごとし」(読者の便宜を考え、漢文を書き下し文に改め、現代仮名遣いに改めると共に、漢字・かな表記を一部改め、また送り仮名なども補った。以下同じ)と記されている。英俊は光秀に対し、自分を抜擢してくれた主君織田信長を裏切った恩知らず、と批判を加えているのだ。
また同年十月に京都大徳寺で行われた織田信長の葬儀を契機に制作された、大村由己『惟任退治記』も「当座の存念に非ず。年来の逆意、識察するところなり」と記し、計画的犯行であると主張している。慶長十四年(一六〇九)以前に成立した太田牛一の『別本御代々軍記』も「明智日向守光秀、越前国へ罷り越し、奉公致し候ても、別条無く一僕の身上にて、信長公を憑み奉り、一万の人持に成され候ところ、たちまちその御恩を忘れ、不似相の天下の望みを含み、謀反を企つ」と、光秀の天下取りの野望と忘恩を指摘している。
このように、同時代人は基本的に光秀謀反の動機を野心に求めており、いわゆる怨恨説を採用していない。唯一、イエズス会士ルイス・フロイスが記した日本布教史である『日本史』は、信長が光秀を足蹴にした事件に言及している。だが、そのフロイスにしても、怨恨よりも「過度の利欲と野心が募りに募り、ついにはそれが天下の主になることを彼に望ませるまでになった」蓋然性の方が高いと説いている。
要するに同時代人は、光秀を冷酷で恩知らずな策略家とみなしており、彼に同情を示すことはなかった。むろん、彼らは中立的な立場ではなく、その光秀評は客観的で公正とは言えない。大村由己は秀吉に、太田牛一は信長に近侍していたので、当然光秀のことを悪し様に言う。フロイスも、キリスト教に好意的だった信長に感謝していた。
だが、英俊は信長から特に恩義を受けておらず、その彼が光秀を非難していることの意味は小さくない。敗者に冷淡なだけともとれるが、中世社会において源義経を非難する声がなかったことを考えると、やはり光秀の謀反は同時代人から見て正当化できるものではなかったと考えられる。
怨恨説の登場
ところが江戸時代になると、実は光秀は横暴な信長に翻弄された気の毒な人だったという話が段々出てくる。怨恨説の嚆矢は寛永三年(一六二六)に成立した小瀬甫庵の『太閤記』(以下、『甫庵太閤記』と表記する)、『甫庵太閤記』より数年早く成立したとされる川角三郎右衛門の『川角太閤記』あたりだろう。『甫庵太閤記』は、光秀が徳川家康の饗応を信長に命じられて、食事などの準備を念入りに行ったのに、信長から急遽毛利攻めを指示されて無駄になったため恨んだと記す。ただ、これは〝いじめ〟という程の仕打ちではないだろう。
『川角太閤記』には、信長は光秀に徳川家康の饗応を命じたが、光秀が用意した魚が腐っていたのに腹を立てて光秀を罷免した、というおなじみの話が出てくる。しかし、一方で『川角太閤記』は、光秀が明智家の家老たちを説得する際に、信長への遺恨を語ると共に「老後の思い出に一夜なりとも天下の思い出をすべきと、この程光秀は思い切り候」と、天下取りの野心を告白したと叙述する。怨恨一辺倒ではないのである。同時期に成立した、竹中半兵衛の息子の竹中重門が著した豊臣秀吉の伝記『豊鑑』も、怨恨説と野望説を併記する。
天正年間に成立し、江戸初期に小幡景憲によって刊行された武田流軍学書『甲陽軍鑑』は、明智光秀が武田勝頼に内通を申し入れたが、勝頼側近の長坂長閑がこれを織田方の謀略と考えて光秀との提携に反対したため、武田家は滅亡したと記す。本能寺の変から逆算して創作された話だろうが、江戸初期までは光秀が野心家・策謀家であるというイメージが強かったことを示すものだろう。
怨恨が謀反の主因としてクローズアップされるようになるのは、本能寺の変から一世紀近く経ってからである。たとえば、斎藤利三をめぐる信長と光秀の確執が語られた。斎藤利三は稲葉一鉄のもとを去り、光秀に仕えた。さらに那波直治も稲葉家から明智家に移った。天正十年五月、信長は両人を一鉄へ返すように光秀に命じたが、光秀が従わなかったため、信長は暴力をふるったという(『続本朝通鑑』『武辺咄聞書』『宇土家譜』『稲葉家譜』『明智軍記』など)。
また、尾張清須朝日村の柿屋喜左衛門が戦国時代を生きた祖父の見聞談を書き留めた聞書集である『祖父物語』には、武田氏滅亡後の諏訪の陣中で、光秀が「骨を折った甲斐があった」と語っているのを聞きとがめた信長が光秀を折檻した、という逸話が見える。『川角太閤記』にも光秀が信長から折檻を受けたとの記載はあるが、どういう経緯で折檻されたかは説明されていない。ちなみに拙著『陰謀の日本中世史』(角川新書)でも触れたように、信長のせいで光秀の母親が敵に殺された、中国地方への出陣前に領地である丹波・近江志賀郡を信長に没収された(毛利領である出雲・石見への国替えを命じられた)といった話も、本能寺の変から百年以上経ってから登場するので、創作だろう。
このように、江戸時代になると信長が光秀にひどい仕打ちをしたというような話が次々と生まれる。これらの怨恨話は明和七年(一七七〇)に完成した『常山紀談』などの逸話集にまとめられ、光秀は信長にいじめられてかわいそうだというイメージが浸透していく。
光秀謀反の動機として、野望より怨恨が重視されていく背景には、社会の価値観の変化があったと考えられる。天下泰平の世になり、武士の主従関係が安定化すると、己の野望のために恩義ある主君を裏切るという戦国武将の価値観が理解されなくなったのだろう。怨恨による謀反の方がまだしもリアリティを持つようになったと思われる。
〈光秀=常識人・教養人〉像の形成
光秀への同情論が生まれるのと並行する形で、光秀は温厚な常識人であるという逸話も創造された。江戸中期の正徳三年(一七一三)に『老人雑話』という本が刊行された。永禄八年(一五六五)に生まれ、寛文四年(一六六四)に没した江村専斎という医者が語った内容を、専斎の弟子の伊藤坦庵が編集整理した聞書集である。この『老人雑話』には「筑前守(秀吉)は、信長の手の者の様にてその上磊落の気質なれば、人に対して辞常におごれり。明智は外様のようにてその上謹厚の人なれば、詞常に慇懃なり」とある。豪快な秀吉と異なり、光秀は謙虚で控えめな人間だったという。
光秀が温厚な常識人であるというイメージを定着させたのは、ベストセラーとなった『絵本太閤記』であろう。『絵本太閤記』は豊臣秀吉の生涯を描いた武内確斎作、岡田玉山画による大長編の絵入り読み本である。寛政九年(一七九七)に初篇が、享和二年(一八〇二)には第七篇が刊行されて完結した。
この『絵本太閤記』は、斎藤利三・那波直治をめぐる問題で信長から折檻を受けた、という前掲の話を採用している。また安土城の家康饗応については、光秀は信長から部屋飾りや膳が華美にすぎると?責を受け、饗応役を更迭すると伝えられた、と記す(ちなみに『明智軍記』も同様の話を載せる)。そして信長は光秀の不満の表情を見咎め、森蘭丸に打擲させたという。さらに丹波・近江の没収にも触れ、光秀の恨みの深さを強調する。
特に注目されるのは、武田滅亡後、光秀が信長に諫言した場面が描かれている点である。武田の残党が恵林寺に逃げ込んだ。信長は恵林寺に対し武田残党の引き渡しを命じたが、恵林寺は拒否した。怒った信長は恵林寺の焼き討ちを命じたが、光秀はこれに反対した。恵林寺は古刹で、住職の快川紹喜和尚はその名が天下に聞こえた高僧であり、比叡山焼き討ち、一向宗門徒の虐殺に続いて、快川を一時の怒りで殺してしまっては、世間の人々に仏敵・法敵と非難されるだろう、というのである。信長は「己の如き愚人に何が分かる」と激怒し、諸将の面前で光秀を激しく殴打した。『絵本太閤記』は光秀を、伝統的権威を重んじる常識人として造形しているのである。
また『絵本太閤記』は、光秀を誇り高い人物として描いている。秀吉の下風に立たされたことを光秀は「天下の人民に対し面目を失う」と語っている。主君から恥辱を受けたとしても、全ての家臣が謀反を起こすわけではない。それこそ小説やドラマで描かれる秀吉のように、主君の怒りを上手く受け流せる人間もいただろう。論理的帰結として、光秀は誇りを傷つけられることに敏感であったという人物造形になるのだ。
文政十年(一八二七)に成立し、天保七~八年(一八三六~三七)ごろに刊行され、幕末には尊皇攘夷の志士たちのバイブルとなった頼山陽の『日本外史』も『絵本太閤記』的な光秀像を踏襲し、発展させている。斎藤利三・那波直治をめぐる問題や家康饗応役の解任などの怨恨話を紹介するだけでなく、光秀の人物像にも踏み込んでいる。『日本外史』は信長の人となりを「将士を待つに礼節を設けず、嘲謔慢罵、以て常となす」、光秀の人となりを「文深(引用者註:「文法深刻」の略。几帳面の意)、このんで自ら修飾し、材芸を以て自ら高ぶる」と評している。高い教養を備える光秀はプライドが高かったため、家臣を罵倒する信長の振る舞いに我慢できなかった、と頼山陽は暗に示しているのだ。
けれども、光秀が誇り高い性格であったという主張には確たる根拠がない。拙稿「明智光秀と本能寺の変」で論及したように、光秀が名門土岐一族の出身であるという認識は江戸時代に広く浸透していたものの、事実かどうかは疑わしい。結局、江戸時代に創作された怨恨話を史実とみなし、本能寺の変という結果から逆算した人物評にすぎない。つまり「名門武士で教養人の光秀は(身分卑しい秀吉と異なり)誇り高いため、信長から屈辱的な扱いを受けたことを恨んで謀反を起こした」という、もっともらしいストーリーを組み立てたのである。
「逆臣」という非難
とはいえ、近世社会における光秀の評価は全体としては大きなマイナスであった。江戸時代には、儒教が社会の基本的な価値観を形作っていたからである。たとえば水戸光圀の死後、元禄十四年(一七〇一)に編まれた光圀の言行録『西山遺事』は、「明智日向守光秀は、君を弑す大賊臣なり」と光秀を非難している。
前掲の『絵本太閤記』でも、光秀家臣の宇野豊後守(秀清)が、光秀は「智勇謀略兼ねたる武士なれど、ただうらむらくは聖人の道に疎く仁義の行い暗ければ、謀反せんも計りがたし」と考え、謀反を思いとどまるよう光秀を諫めた。もともと光秀の領地・家臣は全て信長からいただいたものなのだから、旧領の丹波・近江を没収され、出雲・石見に国替えになることを不満に思うべきではない、身を殺して主君に仕えるのが臣下の道ではないか、と宇野は諫めたのである(なお宇野は謀反の露見を恐れた光秀に謀殺される)。
戦国時代の武士が上のような殊勝な倫理観を抱いていたとは思えないが、儒教に根ざした江戸時代の絶対的な忠誠心にはピッタリ合致する。人格高潔な名君に忠義を尽くすのは当たり前のことであり、極論すれば誰でもできる。真の忠義心は暴君に仕える時にこそ発揮されるのである。儒教の論理では、信長が暴君だから謀反を起こして良い、ということにはならない。主君がさしたる理由もなく家臣を手討ちにしようとした時、黙って斬られるのが江戸時代の武士道である。暴君の酷い仕打ちに堪えてこそ忠臣なのである。
実際、『絵本太閤記』中の光秀は、家老たちが信長の仕打ちについて不満を漏らした時、「君、君たらずといえども、臣以て臣たらずんば、あるべからず」という古語を引いて、彼らをなだめている(その後、国替えで謀反を決意する。『明智軍記』も同様の展開)。
したがって、仮に信長が光秀に暴力をふるい、恥辱を与えていたとしても、そのことは、光秀の謀反を正当化しない。光秀への同情は生まれても、それはせいぜい「情状酌量の余地はある」という程度の話であり、「逆臣」という絶対的なマイナスイメージを覆すものではないのだ。
前掲の『老人雑話』には「明智、亀山の北、愛宕山の続きたる山に城郭を構う。この山を周山と号す。自らを周の武王に比し信長を殷紂に比す。これ謀反の宿志なり……(中略、前掲の秀吉・光秀の人物評)……ある時筑前守、明智に云う様は、わぬしは周山に夜普請して、謀反を企つと人皆云う、いかんと。明智答えて云う。やくたいも無きことを云うやとて笑いて止みにけりとぞ」とある。明智光秀は城を築いて周山城と名づけたという。これは自らを周の武王、信長を殷の紂王(武王に討たれた暴君)になぞらえ、謀反の意思を込めたものだった。秀吉は光秀に謀反の噂について尋ねたが光秀は笑い飛ばした、というのだ。
端的に言えば『老人雑話』は、光秀は天下取りの野心を奥に秘めて表向きは謹厳実直に振る舞っていた、という解釈を採っている。ただの温厚で礼儀正しい常識人ではなく、その本質は野心家である、というわけである。近世における代表的な光秀の伝記である『明智軍記』にしても、光秀の怨恨を色々と描くものの、光秀を必ずしも温厚な人物とは描いておらず、己の能力に自信を持つ野心家の側面を示す。江戸中期成立の逸話集『明良洪範』も、光秀の謀反は数年前から計画されていたと説いている。
悪人から「正義の人」へ
庶民レベルで明智光秀像の形成に寄与したのは、読み本以上に芝居だったと言える。一例として、近松門左衛門が豊臣秀吉を主人公にした浄瑠璃『本朝三国志』を取り上げよう。『本朝三国志』の初演は享保四年(一七一九)で、『老人雑話』の刊行と同時代である。
なお、江戸時代において豊臣秀吉を賞賛することは江戸幕府批判につながりかねないため、実名での芝居はできなかった。『本朝三国志』では織田信長は平春長、羽柴秀吉は真柴久吉、明智光秀は惟任判官光秀という名前になっている。
さて『本朝三国志』では毛利攻めが蒙古征伐に改変されている。春長は真柴久吉を蒙古征伐の大将軍に任じ、光秀には久吉の麾下に入るよう命じたが、光秀が不満を述べたため、春長は激怒し、加藤正清(加藤清正)に光秀を打擲させた。
ただし、この怨恨が理由で光秀は謀反を起こすわけではない。光秀は「三年このかた天下を望む」野心家で、春長の嫡男春忠(織田信忠)を美女で骨抜きにするなどの策略を行っていた。光秀は怨恨を口実にして謀反を起こすのだ。
史実通り、光秀は敗戦し、落ち武者狩りによって哀れな最期を遂げる。『本朝三国志』はこれを「天罰」と評し、「永代末代に大逆不忠の名を流し」と光秀を非難する。
こうした光秀評は『本朝三国志』に限ったことではなく、近世の芝居では光秀は概ね悪人として描かれてきた。前述したように儒教的倫理観においては、いかなる理由があろうと主君への反逆は肯定されないからである。加えて、江戸時代の人気演目である太閤記物において、光秀は善玉秀吉の敵役であるという事情がある。同情を寄せられることはあっても、悪役という設定は維持されたのである。
ところが、光秀を主人公にした作品が生まれる。寛政十一年(一七九九)初演で現在でも盛んに上演される浄瑠璃『絵本太功記』である。「太功記」というタイトルは、秀吉の「太閤」と、主君の仇を討った秀吉の「大功」という意味を掛けたものである。タイトルだけ見ると、秀吉が主役に思えるのだが、実際の主人公は光秀である。光秀が謀反を決意する経緯から説き起こし、本能寺の変、中国大返し、山崎の戦い、光秀の敗死までを描く。以下にあらすじを紹介しよう。
尾田春長(織田信長)の重臣である武智光秀(明智光秀)が、寺社を弾圧する信長を諫めたところ、激怒した春長は光秀を諸将の面前で打ちすえた。その後、光秀は勅使饗応役に任じられるが、饗応が華美にすぎると春長から?責を受ける。春長は森の蘭丸に光秀の顔を打たせた(『絵本太閤記』を踏襲した展開だが、「勅使饗応役」としたのは赤穂事件を意識したものと思われる)。
それでも光秀の忠義の心は揺るがなかったが、中国攻めをしている真柴久吉への加勢を命じられ(久吉の麾下に入ることになる)、しかも丹波・近江から出雲・石見への国替えを通達されるに及んで、いよいよ光秀は我慢の限界に達した。光秀重臣の四王天田島頭(四王天政孝)は、春長は「西国加勢」を口実に領地を没収しようとしていると指摘し、周の武王が殷の紂王を討った故事を引いて、「不仁非道の尾田春長」を討って天下を取るべきと勧めた。九野豊後守(宇野豊後守)は「反逆謀反の輩が本意を達せし例はなし」と諫めるが、光秀は豊後守を討ち、謀反を起こす。
だが、光秀の母さつきは、主殺しという大罪を犯した息子を非難する。「心穢れた我が子の傍ら、片時も座を同じうせんは、我が日本の神明へ恐れあり」と述べ、「伯夷・叔斉」にならうと言って家出してしまう。伯夷・叔斉は武王の紂王への反逆を諫めた兄弟で、殷が滅亡した後は「周の粟は食らわず」と宣言して隠遁し、最後には餓死した人物である。さつきは、たとえ暴君であっても家臣が反逆してはならないという理念を示したのである。
母の非難に衝撃を受けた光秀は自害しようとするが、息子の十次郎(明智光慶)に押しとどめられる。田島頭は「春長、猛威に増長して、神社仏閣を焼失し、万民の苦しむる暴悪。神明これを誅するに光秀の御手をもって討たし給う。天の与うるを取らざれば災い、その身に帰す」と説得し、「下万民の苦しみを救い給え」と励ました。光秀は「一天の君の御為には、惜しからざりしこの命、暫しは長らえ事を計らん」と天皇への忠義を語り、自害を思いとどまった。
途中の展開を省略し、『絵本太功記』で最も有名な場面である「尼ヶ崎の段」を見てみよう。光秀は誤って母さつきを竹槍で突き刺してしまった。瀕死のさつきは「内大臣春長という主君を害せし武智が一類、かく成り果つるは理の当然。系図正しき我が家を、逆賊非道の名を穢す。不孝者とも悪人とも、譬えがたなき人非人。不義の富貴は浮かべる雲。主君を討って高名顔。天子・将軍になったとて、野末の小屋の非人にも劣りしとは知らざるか」と光秀を再び非難する。光秀の妻の操も改心するよう光秀に訴える。
しかし光秀は「遺恨重なる尾田春長、もちろん三代相恩の主君でなく、我が諫めを用いずして、神社仏閣を破却し、悪逆日々に増長すれば、武門の習い・天下のため、討ち取ったるは我が器量。武王は殷の紂王を討つ。北条義時は帝(後鳥羽上皇)を流し奉る。和漢ともに無道の君を弑するは、民を休むる英傑の志。女・童の知る事ならず」と言い放ち、聞く耳を持たない。暴君を討つのは万民を助けるための正義であるというのだ。
結局、光秀は戦に敗れて切腹し、ほどなく現れた真柴久吉は「光秀、主を討ちたる天罰の報いを思い知りたるか」と言って光秀の首をはねた(言うまでもないことだが、以上は全て虚構であり史実とは異なる)。しかしながら主君への反逆を肯定する『絵本太功記』の展開は、儒教的倫理観に支配された近世演劇において画期的だったと言えよう。なお本作に影響を与えた作品として、将軍家への謀反を企てる信長を止めるために光秀が謀反を起こす、『仮名写安土問答』という浄瑠璃の存在(ただし人気は出なかった)が国文学研究で指摘されている。
私怨が動機では謀反を正当化することはできない。そこで『絵本太功記』は天下万民のために主君を討ったという筋立てを用意したのだろう。『絵本太閤記』にも光秀の家臣たちが、周の武王や北条義時の例を挙げて光秀を勇気づける場面があるが、正義のための戦いという評価を前面に押し出して喝采を浴びたのは『絵本太功記』が嚆矢である。
今年の五月、光秀ゆかりの福知山市で「本能寺の変 原因説50 総選挙」というオンラインイベントが行われた。本能寺の変の原因として提起された五十の説のうち、自分が支持する説に票を入れるというものである。国内外から三万五千以上の投票があり、一位は「暴君討伐説」だった(約四千票)。光秀が正義のために謀反を起こしたというイメージは現在かなり普及しているが、その起源は江戸後期の『絵本太功記』にあるのだ。
(つづく)