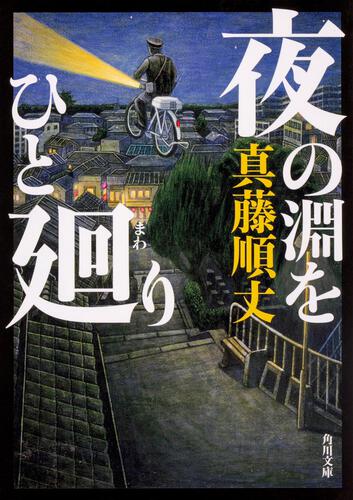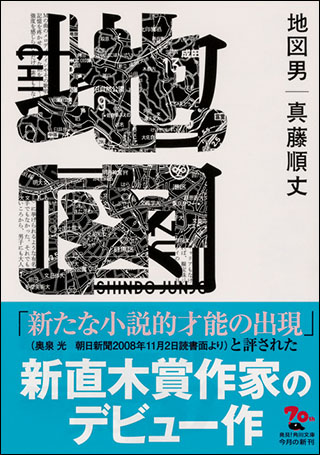【連載小説】風祭喜久子の行方は分からないけれど、在日ブラジル人の面々から聞く生活史は興味深かった。真藤順丈「ビヘイビア」#11-4
真藤順丈「ビヘイビア」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
城之内の言うとおりだった。
ロドリゴとマルコによる案内にも助けられたが、大泉町でブラジル人の人脈をたどるのはそれほど困難なことではなかった。相互のつながりが密で、結びつきが強く、〈知り合いの知り合いはわたしの知り合い〉という障壁の低さはウズベキスタン人にはない、ラテンの出自ならではの明朗
風祭さんに踊りを指導されたシニア・ダンサー、彼女に逢うまではサンバにふれたことのなかった在日ブラジル人にも話を聞くことができたが、だれも往時の師の行方を知らない。そこでありがたい協力者二人に頼んで、リベルダージの出身者、オリヴェイラ家の地元と縁の深い〈出稼ぎ〉ブラジル人の何人かとも話をしていた。
「カルロス・フェレイラを知っている人間は見つかったのか」
「こっちが長い在日三世だそうで、カルロスの派遣会社を介して日本に来たそうです」
数多くガフが会って話したなかで、二度目の面会を申しこんだのはこれから会う
「珍しくないです、マヌエルさんのような人は」
ロドリゴとマルコは、鈴木マヌエルの苦しんでいる姿をその目で見てきたという。
サンバに象徴される陽性の面ばかりではない、在日ブラジル人の苦難をその肩に背負ったような人物だった。数年前に派遣切りに遭ってからというもの、求職者でごった返すハローワークで何時間も待たされ、高熱を出しても保険証がないために病院にも行けず、ロドリゴやマルコの親との
木造平屋のアパートは築四十年以上は経っている。部屋の鍵は南京錠、トイレもシャワー室も他の住民との共用で、失業して工場の寮を追いだされてからは家賃の安さを条件に探し当てたこのアパートに住んでいる。六畳一間のマヌエルの部屋はきれいに整頓されていて、布団も端をそろえて几帳面に畳まれているが、そのぶん家具の少なさを際立たせ、整然としているぶんだけ安普請の寒々しさが強調されていた。
「もうずっといるよ、この町に十五年も……」
すでに夜も遅かったが、マヌエルの部屋で瓶のピンガを酌みかわす。
この人は、出稼ぎブラジル人の実像でもあるのだろう、と最初に会ったときからガフは思っていた。高い手数料と渡航費を払い、不退転の決意ではるばる地球の裏側にまで稼ぎにやってきて、無収入のままでは戻れないという執念が郷愁を抑えつけている。
「帰りたくはないよ、お金を貯めてから帰る。ブラジルにいま帰っても無駄になるよ」
大泉町でもリーマン・ショックの影響は大きかった。雇用の受け皿となっていた電気製品の工場が一斉に人員削減を進めた。近年になってすこしずつ求人が復活してきているとはいえ企業が優先して採用するのは、若くて体力がある日系人かよほどの熟練工だけ。ブラジル人用にポルトガル語で表記された求職の申告書類には、拒否(Recusado)、返事待ち(Aguardando)の文字ばかりが並んでいる。四十九歳という年齢もハンディキャップとなり、マヌエルが再雇用にありつくのは厳しいと言わざるをえなかった。
「東京に行ったら、仕事があるかな」
「どうかな、どこでも人手不足ではあるけど……」
「こっちより人いっぱいなら、仕事もあるでしょう」
「だけど監理団体と契約を結んでいたり、技能資格が必要だったりするから……」
「ブラジル人もいるでしょう」
「あまりいない、見なくはないけど」
毎日のようにマヌエルは大泉町を歩きまわって、スーパーマーケットや工事現場、農家や駐車場やガソリンスタンドなどに手当たり次第に飛びこんでは仕事がないかと聞いてまわっている。失業保険が切れてからは生活保護を申請しているが、この国で生きていくための権利のひとつであるにもかかわらず「働かずにお金をもらうはよくない」とマヌエルはみずからの現状を恥じているようだった。
派遣切りや雇い止めに遭った非正規労働者の困窮に対する支援の輪はひろがっていて、鵜飼弁護士たちのNPOも常時、健康や生活相談に当たっている。マヌエルのことには鵜飼弁護士もふれていた。「彼らはほとんどが派遣や
「鵜飼さんか」と城之内は言った。「あの人のやりかたで、ダイレクトに仕事にありつけるわけじゃないからな。そういうことならやっぱり
城之内が言いよどんだのもわかる。違法と合法の境界線ギリギリ、というより完全にあちら側に落っこちた仕事を
「もともと貧しさから脱けだすために、デカセギでこっちに来たのに」マヌエルは言った。「こっちでも貧乏しているはおかしい」
「それはわかる、ぼくもそうだったよ」
おなじ境遇を味わったガフがすかさず賛同する。
「こっちに来るのを決めたのは」マヌエルがつづけた。「二人の子を学校に入れるため、あとはお母さんの介護資金を貯めるため、貧乏とさよならするためだったよ」
二〇〇〇年代の半ばになっても、ブラジルの主要な都市で〈デカセギ〉は根強い人気を保ちつづけていた。稼いだ金で新築の家を建てたり起業したりといった成功談はひきもきらず、リベルダージでも日系人の人材斡旋ブローカーが幅を利かせていた。カレンやアシュレイの父であるカルロス・フェレイラの派遣会社に登録して、安くない手数料と渡航費を支払い、大泉町の電機メーカーの部品工場へと配属になった。すでにカルロスの派遣会社に斡旋されて働いていたおなじ日系ブラジル人の先輩がたくさんいて、工場勤めは初めての経験だったが同輩の存在が慣れない重労働の大きな助けになった。きつい・汚い・危険の俗に言う3K仕事で、連日の残業も応えたが、そのぶん給与は悪くなく、毎月寮の家賃と生活費だけを残し、出国時の借金をすこしずつ分割で返済して、家族にも仕送りをつづけることができた。当時はこの国の電化製品業界は活況を呈していて、増収増益を重ねる業界をマヌエルたちのような非正規労働者が支えていた。正社員よりも安価なコストで、工場側が雇用責任を負うことのないマヌエルたちが国を
米国でサブプライムローン問題をきっかけに住宅バブルが崩壊、資産価値の大暴落が起こり、名門投資銀行のリーマン・ブラザーズが経営破綻して、これによって世界的な金融危機へとつながった。日本国内で派遣切りが始まり、退職金も十分な補償もなくマヌエルたちは職場を追いだされた。たとえ非正規でもこんなあつかいはひどすぎる、と派遣元のカルロスの会社にも連絡を入れたが、そのころにはすでにリベルダージのカルロスの会社も倒産の憂き目にさらされていた。
「あとから聞いた話だと、カルロス・フェレイラの派遣会社はこっちの企業にも文句を言ったらしいよ」
派遣切りを行なった企業の建前としては、雇用期限および派遣期限の延長・更新をしなかったということになる。なかにはすべての責任を派遣元に押しつける企業もあった。増益のために不安定な雇用形態をつづけてきたそちらに非はないのか、と苦情を出したのはカルロスの会社ぐらいのものだったという。日本にやってきて心を病んだり、金属のプレス機で指をなくした人たちへの補償も手厚かった。入管法改定の以降、就労ルートの確保においても他の業者よりずっと抜きんでていた。
ブラジルの日系人社会で〈デカセギ〉が本格化したのは、長きにわたるインフレで人々の暮らしが疲弊し、消費低迷の直撃を受けたからである。二〇〇〇年前後は、日本とブラジルの賃金格差は十倍近かった。日本で一年働けばブラジルでの十年分の賃金を得ることができたのだから、カルロス・フェレイラは次々と出稼ぎ労働者を日本に送りこんだ。だけどそれも破綻して、今では派遣元の代表であったカルロスとの連絡手段を残している者はいなかった。
「カルロスの奥さんの家が、サンバの名門というのは聞いたことがあったよ」とマヌエルが言った。「〈ああ、あの有名な
「風祭喜久子、という人の名前は? 耳にしたことはなかったか」
「それは知らない」
マヌエルはそう言いかけて、はたと顔つきを変えた。
「ああでも、住むところをなくしたブラジル人を世話しているキリスト教会の人がいるよ。たしかその人が風祭という姓だった」
▶#12-1へつづく
◎第 11 回全文は「カドブンノベル」2020年10月号でお楽しみいただけます!