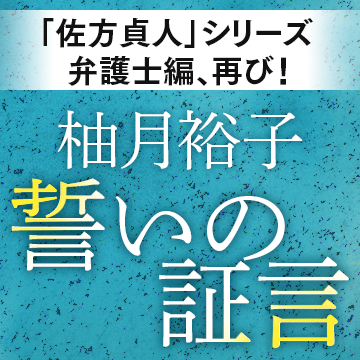【連載小説】ついに最終回! エンドクレジットを背に、有里はまた歩み始める。 赤川次郎「三世代探偵団4 春風にめざめて」#12-4
赤川次郎「三世代探偵団4 春風にめざめて」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
「それじゃ、ルイ、そのビデオはどこにも出ないのね?」
退院を間近にして、もう起きていられるようになった
「うん」
と、安田ルイは肯いて、「宮里さんから、撮影したデータを廃棄したって連絡があった」
「良かったじゃない!」
美沙はホッと息をついて、「私──ずっと申し訳なくて。ルイが
「美沙は、早く元気になることだけ考えればいいんだよ」
と、ルイは言った。
病院の休憩所で、二人は明るい日射しを浴びていた。
「私、働けるようになったら、ルイに楽させてあげるって決めてたの」
「そんなこと言って! まだ手術した後の検査もあるんだよ。ゆっくり体を休めて」
「ルイ……。あんたって、どうしてそんなにいい子なの? 私、ちょっとむかついちゃうよ」
と、美沙は言って笑った。
「そんなことないよ。ただ、人に嫌われるのが怖いだけ」
と、ルイが言って、「あ、メールだ」
「栗田先生? もしかして」
「うん。今夜食事することになってるの」
「いいじゃない! 安心して甘えておいで」
「でもね」
と、ルイは立ち上って、「もう行かなきゃ。バイトの時間だ」
「ね、デートの様子、後で知らせてよ!」
と、美沙がルイの手を握る。
「うん。それじゃ、また来るね」
と行きかけて、ルイは、「私、今夜食事のときに、栗田先生にビデオに出たこと、話そうと思ってる」
「え? どうして?」
と美沙が目を丸くした。
「だって、どこでどう話が出るか分らないじゃない。後ろめたい気持でいるの、いやだもの」
「だけど──」
「もう会いたくないって言われたら、それでいい。私、まだ十九だし、どう見たって、お医者さんの奥様って柄じゃないしね」
ルイはそう言って、「じゃ、またね」
と、手を振って、足早にエレベーターへと向った。
美沙は思わず、
「ルイの馬鹿!」
と言って、
「何か?」
そばを通りかかった看護師さんにジロッとにらまれてしまった……。
エピローグ
日射しはほとんど初夏のようだった。
ゴールデンウィーク初日の町は、若者たちがアマゾン顔負けの大河となって動いていた。
その中を縫うようにして、車からビルの通用口へと向う一団があった。
「──何度も引張り出して、すみません」
通用口で待っていた
「いいえ。気持のいい日だわ」
と、
「どうぞ中へ」
狭い廊下を抜けると、映画館の事務室に出る。
「おはようございます!」
社員たちが一斉にスターを出迎える。
「ご苦労さま」
と微笑んで、「お客は入ってる?」
と訊いた。
「立ち見はないので。席は完売です」
と、寺山が言った。
プレミアが話題になって、沢柳布子の主演作〈影の円舞曲〉は配給会社の「目玉作品」になり、ゴールデンウィーク初日の一般公開に決ったのである。
今日は初日の舞台挨拶。沢柳布子は、今や若者にも人気で、ネットでの「大スター」になっていた。
控室に入ると、内山医師が看護師を連れて待っていた。
「沢柳さん──」
と、内山が言いかけると、
「はいはい、血圧ね」
慣れたものだ。そして、
「やや高めですが、健康ですよ」
と、内山が肯いて言った。「でも、あまり興奮しないで下さいね」
「舞台挨拶も一回だけですから」
と、寺山が言った。
「まあ、爽やかですね、今日は」
控室に天本一家が入って来て、幸代が言った。「十歳は若く見えますよ」
「年寄はね、若作りすると却って老けて見えるの」
と、布子は言った。「本当に若い人には、どうでもいいことね」
そして、布子は有里の肩を抱いて、
「色々聞いてるけど、あんまりお母さんに心配かけないのよ」
「お母さんが何を……」
と、有里は文乃をにらんだが、文乃はわざとそっぽを向いている。
「じゃ、舞台挨拶の手順を」
と、映画会社のスタッフが声をかけて来た。
──有里は、この映画の撮影をしていた日々を、ずいぶん昔のように感じていた。
昔、は少しオーバーかもしれないけど、でも本当に、あれから色んなことがあったから……。
「やあ」
気が付くと、寺山の下で助監督修業をしていた
「二年生になって、忙しくて」
と、有里は言った。「彼女はできた?」
「今はそれどころじゃないよ」
と、加賀は笑った。「次の現場につくんだ、来週から」
「頑張って」
有里は、ちょっとお姉さんみたいな気持で言った。──若いっていいなあ……。
「映画、ご覧になりますか?」
と、寺山に訊かれて、
「もちろんよ!」
と、布子は即座に言った。「お金を払って見て下さるお客様が『もとは取った』って思ってくれるかどうか、客席で確かめないとね」
幸代と有里が布子を挟んで座ることになった。文乃は、
「私はどこか端の席でいい」
と、相変らずだ。
エンドクレジットがスクリーンに流れ始めると、場内が拍手で満たされた。
今の映画はエンドクレジットが長いので、その間に、布子たちは席を立ってステージの袖に回った。
「面白いものね」
と、布子が言った。「初号試写のとき、プレミアのとき、一般公開のときで、受けるところや反応が少しずつ違うの。役者はそこからも学ぶことがあるわ」
上映後の挨拶に布子が出て行くと、観客が一斉に立ち上って拍手した。
「本日は私の出演した映画をご覧いただいて、ありがとうございました」
布子はそれだけ言って、深々とお辞儀した。
袖から、有里は若者たちで埋めつくされている客席を覗いた。
「──あ、お祖母ちゃん」
と、有里は幸代を手招きした。
「どうしたの?」
「あの三列目……。香さんじゃない?」
幸代はちょっと目を見開いて、
「まあ、本当だわ」
香はスッキリしたワンピースで、真直ぐ正面を見て立っていた。
「生きてて良かった」
と、有里は言った。
「しっかり生活しているようね。声をかけずにいましょう」
と、幸代は言った。
布子が袖に戻って来て、ちょっと涙ぐんでいたが、ハンカチを目に当てると、
「これで、あの映画は独り立ちしたわね」
と言った。「私も次の旅に出なきゃ」
「お付合いしますよ」
と、幸代が布子の腕を取った。
「じゃあ、ともかく何か食べましょう」
「食事の後は病院へ戻って下さいね」
と、内山が言った。
「心配なら、内山先生も付合って」
「そうですな。沢柳さんの体にいいかどうか、ワインは私が試飲しましょう」
と、内山は言った。
「──有里は?」
と、幸代が訊く。
「私、歌のレッスンがあるの」
有里はそう言って、一人最後に袖から映画館のロビーへ出た。
観客が次々に出て来て、にぎやかにおしゃべりしながら表へ出て行く。
有里はその流れの中に入って行った。
大勢の中の一人。──でも私は私だ。
少し足取りを速めて、有里は人の間を目指す方向へと進んで行った。
了
*本作は小社より、単行本として刊行予定です。
◎第 12 回全文は「小説 野性時代」第210号 2021年5月号でお楽しみいただけます!