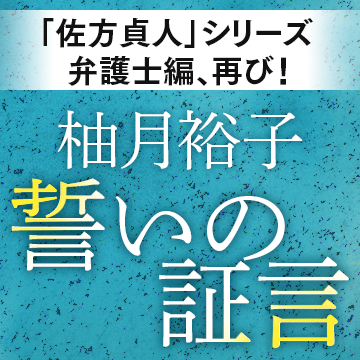【連載小説】手紙が明かす、すべての発端となった夜の真相とは―― 赤川次郎「三世代探偵団4 春風にめざめて」#12-3
赤川次郎「三世代探偵団4 春風にめざめて」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
17 春のきざし
二年生になる、ということは、後輩ができるということである。当り前だが。
でも、たった三年間しかない高校生活での二年目なので、当り前だけではすまない色々な変化というものが起るのだ。
ことに、演劇部では、
「先輩!」
なんて一年生に呼ばれると、何だかちょっと照れくさいようで……。
でも、有里はもともと「先輩後輩」という関係にはこだわらない性格だ。
ただ、文化祭などの行事に関しては、二年生が中心になる。合唱やダンスのレッスンも本格的になり、日々、忙しくてほとんどいつも駆け回っている状態。
それでも、入院している村上を見舞うことは忘れなかった……。
「やあ」
ベッドから村上が手を振る。
「ごめんね。なかなか来られなくて」
と、有里は言った。
「毎週のように来てくれてるじゃないか」
と、村上は言った。「学校があるのに、大丈夫なのか?」
「そりゃあ無理してるわよ。でも、いいの。村上さんが元気になるのを見てるのが楽しい」
「母親みたいだな」
と、村上は笑って言った。
「血色良くなったね」
「そうか? しかし、そろそろ歩くようにしないとな」
「傷の方はもういいの?」
と、有里は訊いた。
「まだ完全にはふさがってないんだ」
と、村上はお腹に手を当てて、「意外と深かったようでね。でも、お腹の脂肪が多めだったんで、少し助かったらしいよ」
「ちゃんと治すんだよ、時間がかかっても」
「ああ。こんなに休んじまうと、仕事に戻れるのか、心配だよ」
「吞気なこと言って! そりゃあ心配したんだからね」
と、有里は村上をにらんだ。
「分ってる。君は命の恩人だよ」
「本当にそう思ってる?」
「もちろんさ」
「それじゃ……」
有里は村上の上に身をかがめて、そっと唇を重ねた。──もちろん、これが初めてじゃなかったが、もうそれほどドキドキしなくなっていた。
いつまでもこの気持が続くものなのかどうか、有里自身も分らなかったが、無理はしないで、自然な流れに任せようと思っていた。
実際、学校でのあれこれが忙しくて、そう一日中村上のことを心配しているわけにいかなかった。
「──薬物の担当から感謝されたよ」
と、村上は言った。「あのバッグの中身は、末端価格で数億円あったそうだ」
「凄い。じゃ、あの田辺が必死だったのも分るね」
「そうそう。連絡しなかったけど、田辺が自首して来たそうだよ。逃げてると、
「そうなんだ。でも──殺されなくて良かったね。組織のことがもっと詳しく分るかもしれない」
「うん、担当が張り切ってたよ」
と、村上は言ってから、「──君には、ずいぶん危い真似をさせちまったね。もう普通の高校生に戻ってくれ」
「無理だよ」
と、有里は即座に言った。「あったことをなかったことにはできない。でも、もちろん、わざわざ危険なことに係らないよ」
「そう願うよ。君に何かあったら──」
「お母さんに怒られる?」
「いや、責任を感じるから。分るだろ?」
「まあね」
「だけど……」
と、村上は天井へ目をやって、「物騒なことをしてるときの君は、本当に活き活きしてたな」
「お母さんが聞いたら怒るよ、また」
と、有里は笑って言った。
「あの……」
と、おずおずと声をかけて来た人を振り返って見て、有里は、
「あ、マナさんの……」
「どうも、その節は」
「どうですか、マナさん?」
吉川が振り向いた先に、松葉杖を突いたマナの姿があった。
「歩けるようになったんだ! 良かったですね」
と、有里は言った。
ほぼ一か月も意識が戻らなかったマナだが、ある日突然、そばについていた祖父へ、
「お腹空いた……」
と言って、仰天させたのだった。
しかし、右半身には麻痺が残り、後は根気よくリハビリを続けるしかないということだった。松葉杖を使って歩けるのは大変な進歩なのである。
少し言葉も不自由だが、
「ありがとう……ございました……」
と、有里にゆっくりと言った。
「マナ君をこんな目にあわせた奴を必ず見付け出してやるからね」
と、村上は言った。「田辺から〈Kビデオ〉の人間を辿って行けるだろう。そのときは、力を貸してくれるね」
マナは黙ったままだが、しっかりと肯いた。
「もう田舎の家も処分して、ずっとマナのそばにいてやろうと思います」
と、吉川は言って、「刑事さんも、どうぞお大事に……」
祖父に伴われて、マナが病室を出て行くのを見送って、
「まだ若いんだもの、きっと元気になるね」
と、有里は言った。
「そう願うね」
と、村上は肯いて、「ビデオのことで、思い出した。あの黒いバッグの入ってたコインロッカーの中にね、他に小さな包みが一つ入っていたんだ」
「中なんか覗かなかったね。何だったの?」
「それが、あの宮里さんの撮ったビデオのディスクだったんだ」
「じゃ、〈Kビデオ〉で作品にするはずだった……」
「そうなんだ。編集前のデータで、それにね、スタッフに交って
「あのアパートで撮った分?」
「宮里さんに確認してもらった。
「香さんのバッグに、
「大方、誰かスタッフのバッグだと思ったんだろうな。これで、真田を殺したのも宗方だと推測できる。〈Kビデオ〉の幹部だった人間が見付かれば、詳しい事情が分るだろう」
村上は息をつくと、「──早く仕事に戻りたいよ」
と、今にもベッドから飛び出しそうな様子だった……。
「ただいま!」
有里は居間へ入って、いつもながら元気よく声を出したが──。
ソファにかけて、手紙らしいものを読んでいる幸代と、そばで立って、腕組みしている文乃、二人とも返事もせずにいるので、
「どうかしたの?」
と、鞄を置いて訊いた。
幸代が手紙をテーブルに置いて、
「香さんがね……」
と言った。
「どうしたの、香さん?」
「出てったのよ」
と言ったのは文乃だった。
「そう……。ずいぶん長くいるから、って気にしてたものね」
と、有里は言った。
香が気がねしていたことは分っていた。しかし、幸代は黙って手紙を有里の方へと差し出した。有里は受け取って読んだ……。
〈天本幸代様
本当に長い間お世話になりました。
ご親切に甘えていてはいけないと思いながら、あんまり居心地がいいので、一日一日と居続けてしまいました。ごめんなさい。
でも、もう皆さんと一緒にはいられません。それは、私の家が焼けて、両親が死んだ、あの夜のことを、思い出したからです。
いつから思い出していたのか、自分でもよく分りません。気が付くと思い出していたという感じなのです。
でも、今はっきり分っています。私が家に火をつけて、両親を殺したこと。
きっかけは、母が病気で伏せることが多くなったことでした。私は中学生になったばかりで、家事をするのに忙しく、勉強は遅れがちでした。父は酔うとよく母に手を上げる人で、母が病気になると私もしばしば殴られたのです。
でも、それだけでなく、酔った父は私を母の代りだと言って、抱くようになったのです。
私は恐ろしさと恥ずかしさで、逆らうこともできず、心を閉ざしてすべてを忘れるようにしていました。
でも、あの夜は、父に乱暴され、母に助けてと訴えると、母は、「それぐらい我慢しなさい」と言ったのです。それから何があったのか、気が付くと、燃える家の前で立っていました。
それまでのこと、すべて胸の奥にしまい込んで、私は途方にくれていたのです。そして思い出したのが宮里先生のことでした。
天本さんたちと短い間でも共に暮せたことは、私の宝です。でも、今、自分が両親を殺したことが分った以上、お宅にはいられません。
天本幸代さんの家に殺人犯が住んでいたなんて、世間に知られたら。
私は、両親を殺した罪を償わなくてはなりません。どうすればいいのか、心は決りませんが、一日でもここにはいられません。
どこかで死ぬか、もし死ぬ勇気がなかったら、どこかの小さな町で生きているかもしれません。
ともかく、ご迷惑をかけることはありませんので、安心して下さい。
文乃さん、有里さんにお伝え下さい。ひととき、家族のようでいられて幸せでしたと。
お元気で
香〉
有里は手紙を下ろすと、
「どこに行ったんだろうね」
と言った。
「モデル料を渡してたから、少しはお金を持っていたわ」
と、幸代は言った。「でも、何日も暮せないでしょう」
「捜しようがないわね」
と、文乃が首を振って、「どこへ行ったか、見当もつかない」
「どうするの?」
と、有里は言った。
幸代は微笑んで、
「自分で決めて出て行ったんだから、止めるわけにはいかないでしょう。それに──そう。きっとあの子は生きて行くわよ。ここで過した日々を憶えている限り、生きて行く。そして、いずれここへ連絡して来るわよ」
幸代の言葉は、自信に満ちていた。有里も納得して、
「──今夜のご飯、何?」
と、文乃へ訊いた。
▶#12-4へつづく
◎第 12 回全文は「小説 野性時代」第210号 2021年5月号でお楽しみいただけます!