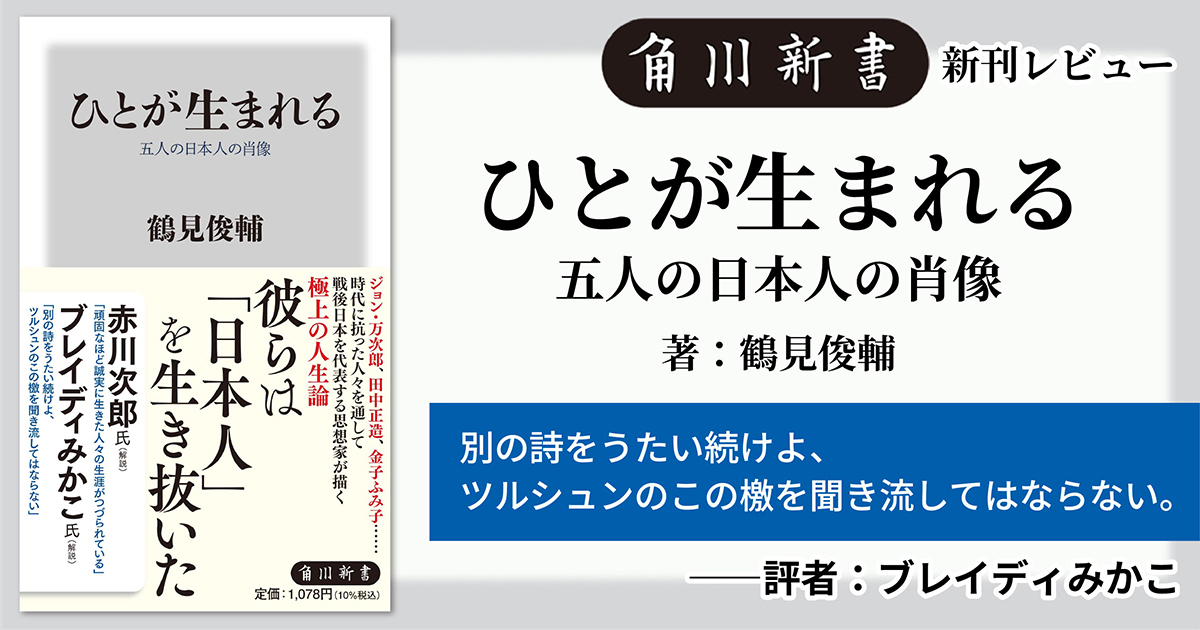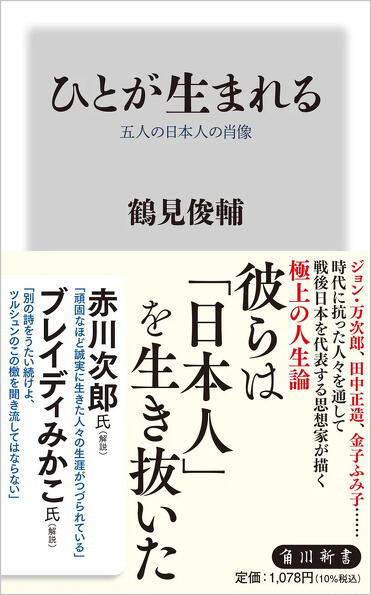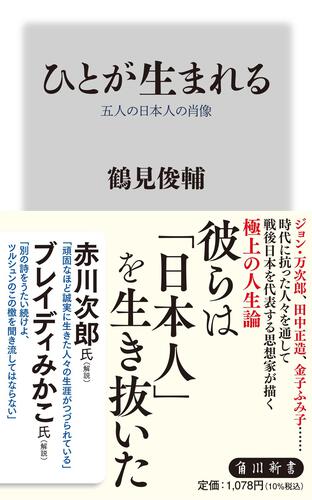鶴見俊輔『ひとが生まれる 五人の日本人の肖像』(角川新書)の刊行を記念して、巻末に収録された「解説」を特別公開!
鶴見俊輔『ひとが生まれる 五人の日本人の肖像』新書巻末解説
アナキズムの火を灯し、五人の生涯を照らす
解説
ブレイディみかこ(ライター・作家)
鶴見俊輔は、昨今の日本のアナキズム研究者界隈では「ツルシュン」などと呼ばれて読み親しまれてきた(影響を受けた人、否定する人、の双方いるが)。
わたし自身、アナキズムには好意的な読み手であり書き手であるので、五人の人物伝である本作を読んでいても、そうした思想が透けて見える箇所にやっぱり反応してしまう。
まず、冒頭の中浜万次郎だ。
2020年に死去した人類学者のデヴィッド・グレーバーを始め、海賊への憧れとシンパシーを抱くアナキストは数知れない(学生時代の伊藤野枝なんかも、玄界灘で海賊の女王になるかもなどと言っていたらしい)。ツルシュンもまた、海の上で生きる人間たちの姿にアナキズムの可能性を投影していた。
無人島で仲間たちと助け合いながら生き延びた時代、異国の捕鯨船に救助されてからの時代を経た万次郎は、「国家とか法律とか身分の上下をこえて、自然の力に対抗しておたがいを守る」者たちの特別な信義を知っていたという。さらに、(20世紀に入ってからは通信の発達で船もすっかり国家の支配下に置かれてしまったが)万次郎が船員として活動した19世紀までは、「人はいったん船にのって海上に出たならば、陸地にいた時のように国家の法律などを受けつけない別の世界」で生きていた。それは、「自然にたいして、人間が協同せざるを得ない、海のインタナショナリズム」だったとツルシュンは書いている。
命の恩人であり、主人でもあったアメリカ人の船長に向かって「友よ」と呼びかける万次郎は、無人島とアメリカで「人間の対等性」を学んだと彼は分析する。それは「世界じゅうの人間と対等の友だちとしてつきあってゆく志」であり、垂直な縦割り構造(支配・被支配)の世界ではなく、水平(友だち)な世界のありかたを希求するアナキズムの思想そのものと言っていい。
二人目の田中正造は、「勤王攘夷か佐幕開国か、というような国家の問題に自分をかかわらせることを軽く見るのはいけないが、自分としては、身近の生活上の問題に打ち込む」という政治哲学を貫いた人だ。「正造の思想は、全部の日本人だけが自分の同胞だという考え方から、世界の人間が自分の同胞だという考え方に進むと同時に、かれが自分の全力をあげて取り組むのは、故郷に近い栃木県谷中村の鉱毒問題ただひとつにかぎられることになる」のだ。
「思想はコスモポリタン(世界主義的)、行動はローカル(地方主義的)」だった田中正造は、社会を遠近両用メガネで見ながら、遠くばかりを見て観念的になり過ぎない、自らの足元が闘いの本拠であることを実践する地べた派のアナキストだった。立命館大学経済学部の松尾匡教授の『新しい左翼入門』を思い出した。氏は、日本の左翼運動は二つに分かれて宿命的な対立を繰り返してきたとし、それは「理想や理論を頭に抱いて、現実がそのとおりでないと「上から目線」で裁断して、現実を理想や理論どおりに変えようとする道」(ボルシェビスト=社会主義者的なもの)と、「現実の抑圧された大衆の中で、その実感に基づいて「コノヤロー」と立ち上がる道」(アナルコ・サンジカリズム=無政府主義的なもの)の間の相克だと言っている。
とは言え、ツルシュンは、アナキストもだんだん地べたから浮遊してきたと嘆いていた。『期待と回想』(ちくま文庫)収録の「アナキズムは何の方法か」の中で、「無政府主義そのものがきわめて知識人的になっちゃった」と発言し、「無政府主義者は国家を否定するという命題をポンと出すことで酔っぱらって、あとの細かいことを状況に合わせてくり返しやるということを回避しちゃった」と指摘した。そして、そこで「村の人だった田中正造」の名前を出し、国会議員をやめて農民のあいだで暮らし、村民の自治に基づく運動を支えながら死んでいった人だったと紹介しているのだ。アナキストよ、地べたからの「コノヤロー」を忘れるな。そんな意味を込めて、ツルシュンが田中正造について書いたのは腑に落ちる。
前述の二人に比べると、『富岡日記』の著者、横田英子(和田英)が三人目に選ばれているのは、ちょっとわかりにくいチョイスだ。が、ここでツルシュンがやろうとしたのは、家のために生きた「明治の代表的日本女性」の中にもアナキズムの精神を見ることはできるのだというパラドキシカルな技ではないか。「アナキズムというのは理想なんだけど、じつはもうここにあるということでもある」(「アナキズムは何の方法か」)のだから。
横田英子の生涯を貫いた精神は、母親の養育によるところが大きかった。彼女は、何かよからぬことをしたときにご先祖様に恥ずかしくないのかと言われて育った。しかしそれは、「そのご先祖様はすでに死んで形もなくなっているのだから、つまり、自分の心の中にいる正邪の尺度ということになる」のであり、ここで立ち上がってくるのは、誰かが決めた尺度に支配されるのではない、自主自律のスピリットである。「古いとされている忠と孝とが、彼女の場合には、日本に工業技術を入れる力として働き、自分の生涯を自分の意志できめて生きるという個性的な生き方のささえとなった」と彼は分析している。
「私の哲学は全部、おふくろのいったことに対する注釈」(『期待と回想』収録「かるたの思想」)と言ったツルシュンだけに、横田英子の評伝でも母の教えに関する筆致には力がこもっている。彼女の母親は「貧乏は恥ではない」と繰り返し言った。そして、子どもに言うだけではなく、自らも自分が言っていることを守った。うそをついてはいけないと子どもに教えているのだから、自分も子どもには絶対にうそを言わなかった。「おもちゃひとつにしても、あげるといったからには、なんとしてでも、やらなくてはいけない」のだ。
これなどはデヴィッド・グレーバーが、「Are You An Anarchist? The Answer May Surprise You!」という論考で書いたことにそっくりだ。大人は子どもに「自分がしてもらいたいように人にしてやれ」とか「分かち合え」とか説教するくせに、現実はそういう風にはできてないと考え、人間は基本的に利己的で競争的だと思い込んでいる。つまり、大人は自分の子どもに教えること(あるいは親に教わったこと)を信じていないのだ。だからグレーバーはこう言った。裏を返せば、アナキストとは、子どもに教えることを本気で信じている人々なのだと。
親の教えを忠実に守り、ご先祖様たちに恥じない生き方を心がけた横田英子の生涯を論じる一方で、家や国家といった枠組みから外れたところで育った無籍者の金子ふみ子(金子文子)を紹介しているのは、心のアナキスト、ツルシュンの真骨頂だろう。彼女についてはわたしも複数の本で書いてきたが、彼のふみ子論でわたしが特に好きなのは、彼女の思想の根っこにあった楽天性を指摘したところだ。子ども時代にこれでもかというほど虐待や理不尽を体験しながらも、彼女が生き延び、卑屈になることなく「ふてえ」アティテュードを持ち続けられたのは、究極のところで楽天的な人だったからだろうとわたしも思う。
ツルシュンは自分の哲学を「おふくろのいったことに対する注釈」と表現したが、ふみ子の哲学は自らが体験してきたことに対する注釈だった。「本を読むことを通して歩いていったのではない。自分の出会う一つ一つの体験について、自分で態度をきめてゆくこと、つまり自分の体験を読むことを通して、彼女は歩いていった」のだ。働いていると本が読めなくなるかもしれないが、働いていると本を読むより世の中の構造がありありと見えてくることがある。暮らしに育まれたプラグマティズムの知恵を重んじたツルシュンが、ふみ子に惹かれたのは当然のことに思える。
そして、本書のトリを飾る五人目の人物は、『わがいのち月明に燃ゆ』の著者で戦没学徒の林尹夫だ。最後に収められたこの章は、拍子抜けするほどあっさりと短く、そのアンバランスさに「え?」と思う人も多いだろう。しかし、その儚さが読者に妙な不穏さを感じさせるのも事実だ。
戦争で命を落とした学生の詩で本書が終わっているのはなぜなのだろう。その理由を探るヒントになるようなツルシュンの言葉を見つけた。
今村冬三の『幻影解「大東亜」戦争――戦争に向き合わされた詩人たち』(葦書房)という本には感心しましたね。かれは戦争が終わったとき十七歳だった。戦後に詩を読みはじめて、大東亜戦争下に詩人たちがどうして戦争賛美の詩を書いたのかがわからない、と考えるようになった。自分なりに探ってみて結論を得た。こうです。
「詩人は無名よりも有名であり続けることを欲した。戦争の時代に戦争賛美の詩を書くのはこの目的からいって当然である。詩人は有名を欲した。だから戦争賛美の詩を書いた。死ぬことは別の人がした。死ぬ側に立った人には別の詩があった」
(『期待と回想』収録「転向について」)
ツルシュンは、死ぬ側に立った人の別の詩をこの評伝集のラストに入れたのだ。
だんだん1930年代の世相に似てきていると知識人たちがこぞって指摘する現代に、この本に再注目する意味がここにあるのではないか。無所有の側からの国家批判がアナキズムの意味だと言った日本の哲学者の、別の詩をうたい続けよという檄を聞き流してはならない。
作品紹介
書 名:ひとが生まれる 五人の日本人の肖像
著 者:鶴見俊輔
発売日:2025年04月10日
彼らは「日本人」を生き抜いた――戦後を代表する思想家による極上の人生論
【ひとは社会の中の一人として、もう一度「生まれる」】
哲学から映画、マンガなど大衆文化を渉猟し、戦後日本を思索し続けた思想家、鶴見俊輔。彼が現代人の「生き方」を問い直すために選んだのは、誰もが認める偉人ではなく、社会の周縁で、時代に揉まれながら実直に生き抜いた5人の日本人だった。明治以前に米へと越境し、日本を相対化した中浜万次郎、町村を見つめ続けた田中正造、敗北を直感しながら飛び立った林尹夫……彼らの数奇な人生をたどることで、近代日本の相貌が鮮やかに浮かび上がる。
赤川次郎氏の文庫版解説を再録。新書版解説・ブレイディみかこ
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322404001069/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら