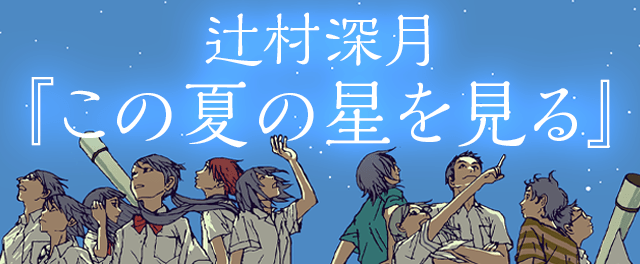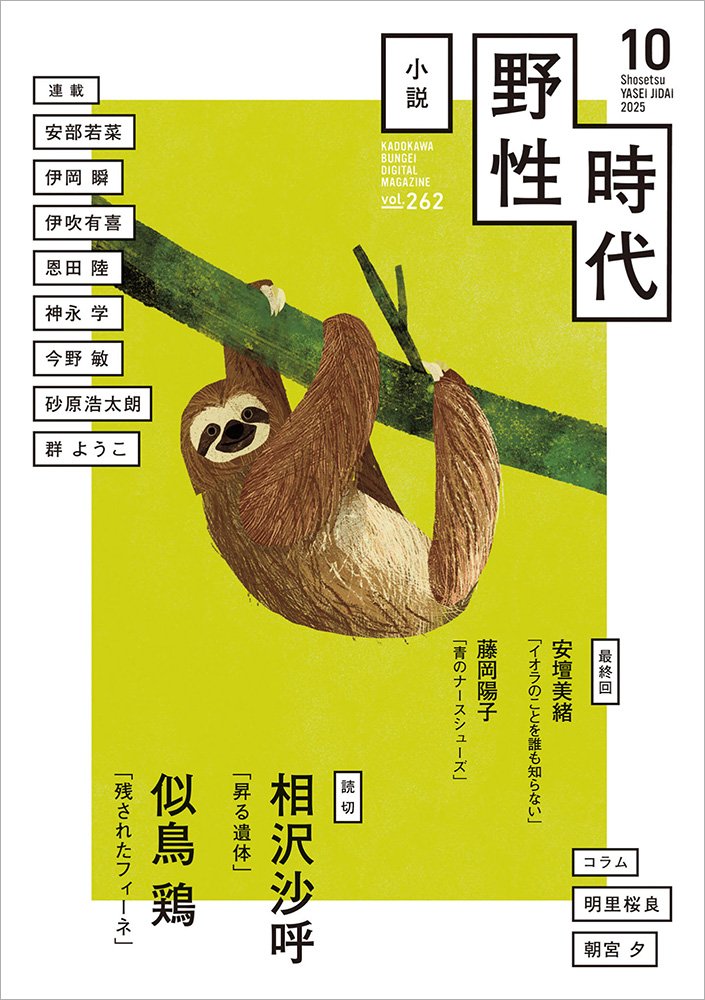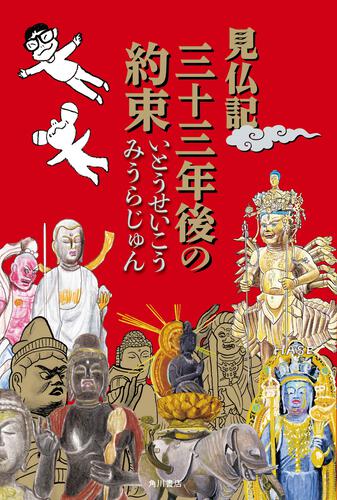1月31日(木)、重松清さんの新刊『木曜日の子ども』が発売となります。
刊行にあたり、1月31日(木)から、各界一流の読み手たちによる【刊行記念書評リレー】を配信いたします。

あえて「わからない」心に向き合う姿勢と覚悟
重松清はライフワークとして家族やいじめ、犯罪に魅せられる少年の心をテーマに据えた小説を書いてきた。本作もまたライフワークに連なる作品だが、従来の小説と比べてエンターテイメント性は群を抜いているところに特徴がある。あらすじはこうだ。
ニュータウンの一角にある旭ヶ丘中学校。かつて2年1組の給食の野菜スープに毒物を混入し、同級生9人を殺害した少年・上田祐太郎が少年院を出て、街に戻ってきたという噂が流れる。物語は主人公の会社員・清水と妻の香奈恵、そして香奈恵の前夫の息子の晴彦が、このニュータウンの一軒家に引っ越したところから動き出す。
晴彦は理不尽ないじめのターゲットになってしまい、転校を余儀なくされた少年だ。引越しでやっと平穏を手に入れたと思った矢先に、晴彦についてこんな声が聞こえてくる。上田少年にそっくりなのだ、と。やがて近所で起きていく怪事件の数々、そして学校にいないはずの少年と仲良くなったと出かけていく晴彦が抱える闇。「世界の終わりの始まり」とは何を意味するのか。清水はかつての事件を追いかけた作家とともに真相に迫ろうとするのだが……。
この小説の「文句なしのおもしろさ」を説明することは極めて容易である。第一に非常に魅力的な謎が立て続けに提示されることである。史上稀に見る、凶悪な少年犯罪を起こした上田少年とは何者なのか。近所で起きる怪事件の黒幕は誰なのか、彼らの目的は何か。前半で巧みに張られた伏線を回収していく後半の展開は、凡百のミステリー小説以上に謎解きの悦楽がある。
第二にリアリティーを担保する細部の描写である。ルポライター経験がある重松らしく少年事件の描写は報道するメディアの反応も含めて、いかにも起こりそうなもので構築されている。私もかつて全国紙記者時代、少年事件も含めてそれなりに事件取材をしてきたので、手に取るようにわかる描写がいくつもあった。
一例を挙げれば、上田少年が事件を起こす前、一学期のクラス委員選挙で獲得した票数の描写である。ごく普通の少年で、成績もそこそこ、部活にも打ち込んでいた上田少年は「七票」を得た。「七」という数字に、地味でもなければ目立つわけでもない存在という意味が込められる。数字というファクトが持つ力を重松は巧みに小説に取り込んでいる。
しかし、である。あえてこう問いかけてみたい。今作は確かに「おもしろい」。だが「おもしろい」だけの小説なのだろうか。重松が今作で描き尽くしたかった主題はそこにあるのだろうか。私の考えでは二つの問いはともに否である。
エンタメ性を極限まで高めているが、それはあくまで表層的な技巧に過ぎない。 小説のなかで重松が接近したかったのは、もっと抽象的な問い——、私の言葉で整理すれば、「わからない」ものを考える続ける姿勢であるように思える。
例えば家族とは何かという問いである。主人公の清水と晴彦は血が繋がっていない親子だ。血縁上の父親が母に暴力を振るう。そんな家庭で育った晴彦は清水に対して、思春期の中学生らしく明確に距離を置き、ですます調で話す。口調一つで清水の心は傷つき、ある人物から「(晴彦とは)赤の他人」だと言われることで傷はさらに深くなる。だが、それでもなお彼は父であることを行動とともに自覚していき、自らの役割を引き受けていく。彼は懸命に父であろうとするのだ。
小説で描かれた役割をネタバレにならない程度で書き記せば、人の死という現象に吸い込まれ、不気味な存在になっていく晴彦を受け止め、肯定していくことになる。
清水に込められた懸命と肯定――。自分たちの世界を懸命に生きることとは役割を引き受けることであり、そこから新しい物語を紡いでいくことだ。「物語」に予定調和はなく、正解もない。未来を自分たちでコントロールすることもできない。他者のわからなさに苦悶し、逃げ出したほうが楽なこともある。それでも清水は踏みとどまる。
彼が父として晴彦の心のわからなさを受け止めた上で、もう一度、親子として関係を結び直すと決意するシーンは今作のハイライトである。彼の決意は「家族とは血の繋がりである」「少年の心の闇」「ニュータウンの悲劇」といった、凡庸でわかりやすい「物語」の対極として描かれる。
なにかにつけ、わかりやすい物語ばかりが広がる日本社会にあって、懸命を生きることを肯定する小説を世に送り出すこと。それ自体が一つの批評となっていると言えないだろうか。そういえば、かつて重松はこんなことを書いていた。
安易で浅はかな『わかる』よりも、もっとたいせつな『わからない』があるはずだ、と
『増補新版 教育とはなんだ』ちくま文庫
この小説を読み終えて、あらためて思う。わからない、というのは突き放した態度ではないのだ、と。わからないからこそ、人間は誰かを深く知ろうとし、理解しようとするのだから。
☆試し読みはこちら
>>重松清『木曜日の子ども』
【『木曜日の子ども』刊行記念書評リレー】
① 近未来の「黙示録」――奥野修司(ジャーナリスト・ノンフィクション作家)
https://kadobun.jp/reviews/604/1ba6b39f
② 重量級の新たな傑作が生みだされた――池上冬樹(文芸評論家)
https://kadobun.jp/reviews/601/0190ff05
④この小説は、テレビドキュメンタリーへの警告である――張江泰之(フジテレビ「ザ・ノンフィクション」チーフプロデューサー)
https://kadobun.jp/reviews/606/5477207c
⑤7年前中学校で起きた、無差別毒殺事件。そして再び「事件」は起きた――「世界の終わり」を望む子どもたちに、大人は何ができるか――朝宮運河(ライター)
https://kadobun.jp/reviews/618/27da5648