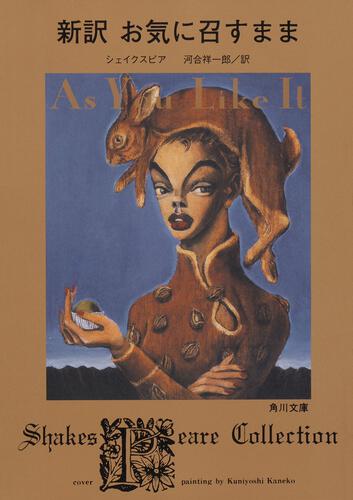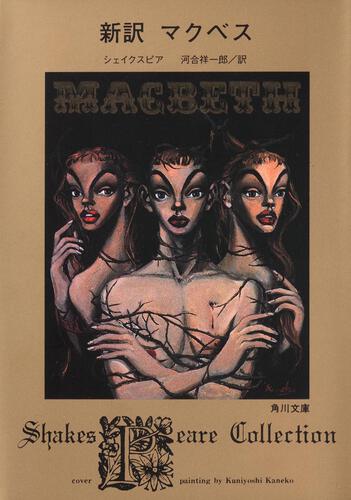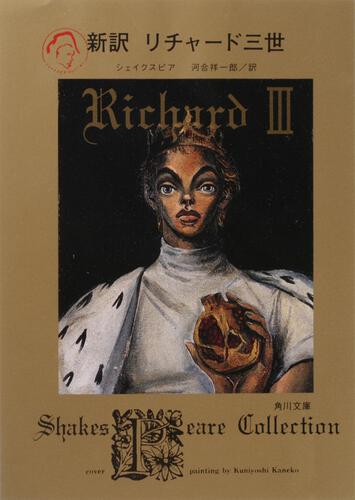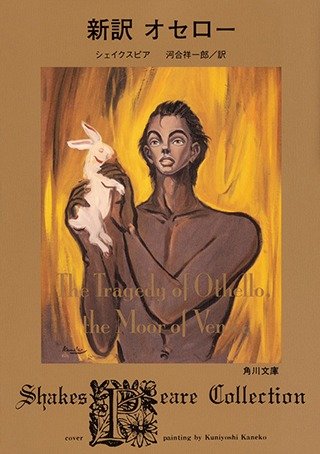『お気に召すまま』の初版は、一六二三年のシェイクスピア戯曲全集(フォーリオ版)であり、四折り版(クォート版)での出版がなされなかったため、フォーリオ版(F)のみが底本となる。なお、フォーリオ版には幕場割りはあるが、場所の指定はない。
一六〇〇年に書籍出版業組合に出版阻止登録(海賊版が出ることを阻止するために権利者がその出版権を主張する登録)がなされており、一五九八年に出版されたフランシス・ミアズの『知恵の宝庫』にこの劇への言及がないことから、一五九九年頃に書かれた作品と推定される。
三つの円熟喜劇『から騒ぎ』『お気に召すまま』『十二夜』は、この順で連続して書かれたと考えられるが、『から騒ぎ』の道化役ドグベリーは下卑た笑いが得意の道化役者ウィリアム・ケンプに当てて書かれたのに対し、『十二夜』の道化フェステは、ケンプの後継者として一五九九年に宮内大臣一座に入団した道化役者ロバート・アーミンのために書かれたと推察される。
『お気に召すまま』の道化タッチストーンを演じたのがケンプなのかアーミンなのかは、わからない。タッチストーンは、道化フェステをはじめ『終わりよければすべてよし』のラヴァッチ、『リア王』の道化などの賢い道化の系譜に連なるところもある一方、フェステや『リア王』の道化と違って歌を歌わないところを見ると、歌の得意でないケンプの役なのかとも思える。
本作の種本は、トマス・ロッジ作の牧歌物語『ロザリンド、ユーフューイーズの黄金遺文』(一五九〇)である。三人兄弟の末子で、オーランドーに相当するロサダーという青年が、国王の催したレスリングで勝利して、前国王の娘ロザリンドから首飾りを贈られるが、長兄の不当な扱いに耐えかねて、老僕アダムとともに森へ逃げるという筋も同じなら、ロザリンドが、前国王から王位を奪った現国王の娘アリンダとともに森へ逃れ、そこで青年ロサダーと再会し、男装で正体を隠したまま、恋愛ゲームを行うという筋も同じである。弟を不当に扱ったという理由で長兄も追放されて森へやってきて、そこでライオンに襲われそうになるところを弟に救われて二人が仲直りするのも同じだ。ただし、長兄は、ロザリンドとアリンダが山賊に襲われたところを助けた縁でアリンダと恋に落ちるというドラマがあったのを、シェイクスピアは二人が見つめ合ったとたんに恋に落ちる筋に変えている。アリンダたちの結婚式の日に、ロザリンドは正体を明かしてロサダーと結婚。原作では前国王のために貴族たちが蜂起して王座を回復するが、シェイクスピアはそこも速い展開にして、突然現国王が悔悛して王座を返還するという話に変えている。
シェイクスピアはこの劇をロッジの原作同様フランスに設定しているため、アーデンArdenの森というのは「アルデンヌArdenneの森」のつもりかもしれない。ただし、「アーデンの森」とは、シェイクスピアの故郷ウォリックシャー州にある森でもあり、「アーデン」はシェイクスピアの母方の実家の姓でもあるから、設定されている場所がフランスなのかイギリスなのかはっきりしないという二重性がある。
登場人物の名前でも、ル・ボーというフランス人が登場するかと思いきや、タッチストーン、ウィリアム、オードリーなどどう考えてもイギリスの名前の人たちも出てきて、どの場所に設定されているのかはっきりしない。
なお、シェイクスピアの喜劇の多く――『ヴェローナの二紳士』『じゃじゃ馬馴らし』『まちがいの喜劇』『ヴェニスの商人』『から騒ぎ』――がイタリアに設定されていることを考えると、本作がフランスに設定されているのは特殊である。翻訳にあたっては、フランス色をできるだけ活かすように配慮した。
たとえば、オーランドーやオリヴァーの父親の名前Sir Roland de Boysは英語発音では「サー・ローランド・ドゥ・ボイズ」となり、コヴェントリーの北にあるウェストン・イン・アーデンに住んでいたドゥ・ボイズ家と関係があるのではないかとする説もあるが、これは「サー・ローラン・ドゥ・ボワ」とフランス語読みをすべきと判断した。当時yとiは交換可能であり、Sir Roland de boisつまり「森のサー・ローラン」という意味なのであろう。そうなると、最後に登場する次兄の名前もフランス語読みして、「ジャック・ドゥ・ボワ」と読むべきであろう。Jaquesはフランス語読みでは「ジャック」なのだから。
ところが、同じ名前を持つ憂鬱の士の方は、韻律の関係上、二音節で発音するようにシェイクスピアが指定しているところがある。そこで、こちらはジャックではなく、十九世紀以来イングランドで多く用いられてきた「ジェイクィズ」と訳すことにした。
シェイクスピア自身が老僕アダムを演じたという伝説があるが、シェイクスピアが『ハムレット』の亡霊を演じたという伝説同様、証拠はない。初期の上演記録は残っておらず、一五九九年二月二十日にリッチモンド宮殿にて宮内大臣一座によって初演されたのではないかと推測されるのみである。また、一六〇三年十月から十二月のあいだにペンブルック伯爵の居城であるウィルトン城でジェイムズ一世が滞在した際に国王一座が呼ばれており、一座は十二月二日に報酬三十ポンドを受領した記録がある。このときに『お気に召すまま』が上演されたとする説もある。十八世紀には改作が上演され、一七四〇年にチャールズ・マックリンが原作復活上演を行った際に、トマス・アーンが劇中歌の作曲を担当した。
ロザリンドは、シェイクスピアの創った女性登場人物中、最も台詞量の多い人物である。十八世紀から当時の有名な女優たちが競って演じてきたが、二十世紀以降で例を挙げるなら、ペギー・アシュクロフト(一九五七)、ヴァネッサ・レッドグレイヴ(一九六一)、ヘレン・ミレン(一九七八)、スーザン・フリートウッド(一九八〇)、ジュリエット・スティーヴンソン(一九八五)、ケイティ・スティーヴンズ(二〇〇九)など名だたる女優が演じてきた。
私が観たなかで最も記憶に残っているのは、一九九一年のチーク・バイ・ジャウルによる公演である(デクラン・ドネラン演出、一九九四年再演)。男優のみで演じたこの公演で、ロザリンド役のエイドリアン・レスターはタイム・アウト賞を受賞したが、レスターがエピローグでふっと男に戻ってみせ、それまで観客が夢中で観ていた世界が虚構に過ぎなかったことを暴露してみせた演技は絶妙だった。ちなみにレスターは、二〇〇一年ピーター・ブルック演出の『ハムレット』で主役を務め、二〇一三年にナショナル・シアターでオセローを演じた際には、イアーゴー役のローリー・キニアとともにイヴニング・スタンダード紙優秀男優賞を受賞した男優である。
二〇〇六年のケネス・ブラナー監督の映画版は、日本が舞台になっている。ブライス・ダラス・ハワード主演。エイドリアン・レスターがオリヴァー役で出演している。
C・L・バーバーの『シェイクスピアの祝祭喜劇』(一九六三、邦訳一九七九)は、本作品の祝祭性を見事に浮き彫りにしてみせた批評だ。アレグザンダー・レガット著『シェイクスピアの恋愛喜劇』(一九八七)ほか、さまざまな批評があるが、ロザリンドを演じたジュリエット・スティーヴンソンがシーリア役のフィオナ・ショウとともに二人の結びつきについて書いた論考も興味深い(‘Celia and Rosalind in As You Like It’, Russell Jackson and Robert Smallwood eds, Players of Shakespeare II: Further Essays in Shakespearean Performance( New York: Cambridge University Press, 1988), pp. 55 ‐ 71)。
恋愛は古くて新しいテーマだが、この作品は男女の愛のみならず、女同士の愛もしっかりと描いている点を見逃すべきではない。当時はシーツを容易に洗えないといった事情もあって、同性で同衾するということはよくあり、『夏の夜の夢』や『から騒ぎ』でも描かれているように同性間の親密性が文化的に支えられていた。同性間の愛情・友情と異性愛のあいだの対立というテーマは、シェイクスピアは他の作品でも繰り返し取り上げている。
恋愛感情をどのように言葉で表現するかが重要となるため、羊飼いシルヴィアスは実は重要な人物だ。これまではフィービーにいいようにあしらわれる可哀想で情けない男のイメージでとらえられてきたように感じられるが、原文を見るとかなり詩的で、見事な恋愛詩人ぶりである。フィービーは、恋愛感情を詩的に表現するシルヴィアスの才能に明らかに一目置いている。
『ヴェニスの商人』で自分の最愛の妻ポーシャが男装して裁判官バルサザーとして登場しても夫バッサーニオはそれが妻だと微塵も気づかないし、『ヴェローナの二紳士』で小姓に変装したジューリアも、『十二夜』で小姓シザーリオに変装したヴァイオラも、『シンベリン』で小姓フィディーリに変装したイノジェンも、いずれも男装を見破られることはない。エリザベス朝演劇においては、変装して登場した人物が自らその事実を明かさないかぎり変装は見破られないという約束事があったと理解されてきた。だから、たとえば『リア王』において追放されたケント伯爵が変装して王につき従っても、エドガーが乞食のトムに変装しても、見破られることはない。こうした約束事があったために、オーランドーはギャニミードという変装を見抜くことはできず、目の前にロザリンドがいるにもかかわらず、しかもその人に「ロザリンド」と呼びかけているにもかかわらず、相手がロザリンドであるとはまったく気がつかないと理解されてきた。だが、この翻訳では、オーランドーはロザリンドと気づくのだと解釈した。以下にその根拠を示していこう。
まず、今述べた約束事は、本作の十年後の一六〇九年頃にはすっかり崩壊しており、シェイクスピアがそうした趨勢を先取りした可能性が考えられる。
ジョージ・チャップマンが一六〇九年頃に書いた喜劇『五月祭(May Day)』では、青年ロドヴィーコーがある夜に娘ルクリーシアの部屋に忍びこむと、ルクリーシアに猛然と斬りかかられ、実は娘ルクリーシアは男ルクリーシオだったと判明する。さらに、少年ライオネルに女の子の恰好をさせて、軍人イノセンシオを騙そうとするくだりがあるが、実はこの少年は本当は女の子だと判明する(しかも前述のルクリーシオの恋人だとわかる)。そして、観客にはこれらの変装を見抜くことが求められるのだ。少年ライオネルについて「いや、まったくきれいな顔をした子だね。女の子の恰好をさせたらぴったりなんじゃないか」(第三幕第三場)と言われるとき、その深い意味に気づいた観客だけがドラマをより深く楽しめることになるのである。
一六一一年頃にジョン・フレッチャーによって書かれた『夜盗あるいは小さな泥棒』(一六三三年ジェイムズ・シャーリーが改訂)では、小さな泥棒こと少年スナップがときどき漏らす独白から、スナップが実は女性であることを観客は見抜かなければならない。同じ作品のなかで、強欲な判事との結婚を嫌がって逃げだした娘マライアがウェールズ娘に変装して実家に帰ってくると、母親から「こんなふうに汚い恰好をして、声を変えたからって、お母さんの目をごまかせるとでも思っているのかい、マライア?」と言われて、変装はすぐにばれてしまう。フレッチャーの『忠実な家臣』(一六一八)では、侍女アリンダが異様なまでの武勇を示して、「今に私の真価(truth)がわかる」(第一幕第四場)と言うので、「真価(truth)」とは、実は彼女が男なのだろうと観客は気づかねばならない。
一六〇九年には観客が変装を見抜く力が試される芝居があと二本書かれている。ジョン・フレッチャーとフランシス・ボーモントが共同執筆した悲劇『フィラスター、あるいは愛は血を流して横たわる』では、ユーフレイジアという女性が、愛する王子フィラスターを救うために男装してベラーリオと名乗る。ところがこの事実が明かされるのは最終場面になってからだ。同様に、ベン・ジョンソンの喜劇『エピシーンあるいは無口な女』では、おしゃべりが大嫌いな男が無口な女と結婚してみたら、実は女は大変なおしゃべりだったという展開の末に、最後にその女は少年だったことが明かされる。観客も一緒になってこの女装に騙されることとなるが、変装をするときには必ず観客にそのことを伝えるという昔の約束事がすっかりなくなってしまっていることが確認できる。
シェイクスピアの時代、女性の役は少年俳優が演じていたわけだが、ジャコビアン演劇では舞台上に女装の少年俳優が登場したとき、それが女役なのか、それとも女装の男役なのか、観客がよくよく気をつけて判断しないといけなくなってきたのだ。前記の『フィラスター』の男装のベラーリオについて、シェイクスピア学者M・C・ブラッドブルックは、「ベラーリオの本当の性別は最後になるまで明かされないものの、この頃はもう、舞台上に小姓が登場したら男装の女かもしれないという時代になっていた」と指摘している(‘Shakespeare and the Use of Disguise in Elizabethan Drama,’ Essays in Criticism 2 (1952): 159‐168)。
女装の男として登場しておいて実は本当は女でしたというパターンは、トマス・ヘイウッドの『ロンドンの四徒弟』(一五九四)から始まり、ウォルター・ホークスワースのラテン語劇『迷宮』(一六〇三)、ヘイウッドの『ホグズドンの賢い女』(一六〇四)、ジョンソンの『新しい宿』(一六二九)などで使われている。トマス・ミドルトンの『寡婦』(一六一六頃)では、判事の妻フィリッパがたまたま知り合った男性アンサルドに女装させたところ、自分の愛人フランシスコがその「女」に惚れてしまうのを大いに興ずるのだが、実はアンサルドと名乗っていたのは娘であって、フランシスコはその娘と結婚してしまう。
舞台上の少年俳優は男性であっても、男性でも女性でも演技によって自由に表し得るというエリザベス朝演劇の伝統のなかで、ジェンダー表象を自在に転換させる遊びが生じたと言えるだろう。
フレッチャーがネイサン・フィールドとフィリップ・マッシンジャーとともに執筆した『正直者の運命』(一六一三)では、少年ベラムールがその主人を熱愛しているように見えるので、男装の女ではないかと疑われる。登場人物の一人、伊達男ラヴァダインは、「この子は女の子なんじゃないか? え、君、女の子だろ。こっちへおいで。触らせておくれ」(第四幕第一場)と言い、少年はふざけて、「あなたが相手では、秘密を隠しておけませんね。はい、実は私は女なんです。あなたをお慕い申し上げておりました」と答え、最終幕にラヴァダインの花嫁として女の恰好をして登場して、本当は少年が男であることを知っている他の登場人物たちを大いに楽しませることになる。どうして今まで男の恰好をしていたのかと問われて、「花嫁」は「お芝居の真似をしたんです」と答える。
かつて、一五八〇年代の芝居においては、たとえばジョン・リリー作の喜劇『ガラテア』では、男装の少女を見た人物が「美しい男の子だなあ、女の子みたいだ」(第二幕第一場)と言うとき、それは男装の事実を知っている観客を楽しませる劇的皮肉でしかないが、のちの時代になるともっと複雑なことになってくるというわけである。
男装に対するこうした変化は、当時の演劇で男装が大いに用いられたのみならず、現実においても男装が用いられていたことも影響しているかもしれない。一六〇五年にアン王妃の侍女エリザベス・サザウェルは愛人サー・ロバート・ダドリーと駆け落ちするときに男装したし、一六一一年には国王ジェイムズ一世の従妹のレイディ・アーベラ・ステュアートが愛人ウィリアム・シーモアと駆け落ちする際にも男装した。
そして、舞台上でそうした趣向が大いにもてはやされた結果、前述のチャップマンの『五月祭』では、こんな台詞さえ飛び出してくる。
帽子だのマントだのを替えて、お決まりの逃げの手を打つと、父親は自分の子供だとわからなくなり、妻は夫だとわからなくなるというが、実際はそんなことがあるはずない。たとえ道化服を着こもうが、ヴィオルのケースや旅行鞄に顎まで隠れようが、顔が見えていたら、こいつはロレンゾーさんだとわかる。だから、顔もほかと同様にすっかり替えるのでなければ、いくら変装したって意味ないよ。
第二幕第四場一五〇~八行
顔を隠さないといけないという意識は、少なくとも『冬物語』(一六一〇~一一)の時点でシェイクスピアにもあった。パーディタに変装させるカミローは、こう指示するのだ。「あなたの恋人の帽子をお取りなさい。そして目深にかぶって、顔を隠すのです」(第四幕第四場)。『コリオレイナス』第四幕第五場(一六〇八)でも、敵のオーフィディアスに会いに敵陣に入り込むコリオレイナスは顔を隠して行く(ただし、顔をあらわにしてもオーフィディアスにはコリオレイナスとわからないという展開になっている)。
フレッチャーの『巡礼』(一六二一)では、ヒロインのアリンダが顔に布当てをつけて、ひどい日焼けをしたかのように顔を黒く塗って少年に変装するが、知り合いと出会うと見つかってはいけないと思って必死に相手に顔が見えないように苦心する。急に背中が痛みだしたというふりをして、顔を背けるのである。
セベルト 顔をあげなさい。元気を出して。 アリンダ できません。 背中が、背中が、背中が!
第三幕第三場四〇~一行
さて、『お気に召すまま』ではどうなのか。変装が見破られる可能性を、『冬物語』より十年も前の作品においてシェイクスピアは考えていたのかどうか。
エリザベス朝演劇の新しい傾向に従うなら、オーランドーは森のなかでギャニミードに変装したロザリンドに出会うとき、その顔をしっかり見るのだから、何かしら気づくはずということになる。そのときオーランドーは何を思ったのか。この点については、第五幕第四場で、オーランドー自身が公爵に対して「最初にあの子と出会ったとき、お嬢様の兄弟ではないかと思った」と発言していることが参考になる。オーランドーは、ギャニミードの顔がロザリンドとそっくりであることに気がついているのである。
第三幕第二場で森のなかでギャニミードと出会ったとき、オーランドーが何を言っているか確認しよう。時の歩みの話を聞いたあと、オーランドーは、「可愛い人だね(pretty youth)。どこに住んでるの?」「この土地の生まれかい?」「君の言葉遣いは、こんな田舎暮らしでは身につかない洗練されたものだ」と突っ込んでいる。なにしろ愛するロザリンドと同じ顔をしているのだから、このギャニミードには何かあると考えるのは当然だろう。こういう質問がここで出てくるということは、その前の時の歩みの話のあいだ、オーランドーはじっとギャニミードの顔を食い入るように見つめて探りを入れようとするのではないだろうか。そしてギャニミードが止まらない勢いで時の歩みの話をするのも、そんな視線を感じてなんとかごまかそうと慌てているためなのではないだろうか。
そして、「美しい人(Fair youth)。僕が愛していることをぜひとも君に信じてほしい」とオーランドーが言うとき、ロザリンドは自分の変装がばれてしまったのではないかと大いに冷や汗をかくと考えられる。この時点でオーランドーがどこまで気づくのかはわからない。だが、彼はギャニミードという男装の向こうにロザリンドに通じる何かを感じているはずだ。さもないと彼がギャニミードの提案した恋愛ゲームに応じる理由がわからない。オーランドーは最初、ギャニミードの申し出を否定しておきながら、たった一行で態度を豹変させるのである。
オーランドー 治してほしいとは思わない。 ロザリンド 治してあげたい。僕をロザリンドと呼んで、毎日僕の小屋へ来て口説いてほしい。 オーランドー そうしよう、わが恋の真実にかけて。どこへ行けばいいんだい。
ロザリンドと呼んで口説いてほしいというその声のなかに、オーランドーはロザリンドの恋心を聞きとったのではないだろうか。
このあとの恋愛ゲームでは、ロザリンドは自分の変装がばれるのではないかとひやひやしながらも、「ロザリンド」を演じるというゲームにことよせて自分の気持ちを出していくことになる。となれば、オーランドーにしてみても、その演じられているとされている「ロザリンド」のなかに本当のロザリンドがいることに気づくだろう。あくまでゲームという前提に守られながら――シーリアが最初に言っていたように、「恋のゲームをしましょ。でも男の人に本気で恋しちゃだめよ。遊びのつもりでも深みにはまっちゃだめ。頬をぽっと染めて、何一つ傷つかずに戻ってこられなきゃ」という安全なガードを作りながら――二人は恋愛を楽しむのだ。
第五幕第二場でオーランドーが「もう想像だけでは生きていけない」と言うとき、彼は相手がロザリンドだとわかっていて、ゲームではなく本気で心を通わせたいと言うのだと解釈したい。この時点ではギャニミードはロザリンドだとわかったうえでゲームをしているのだろう。そうでないと、この直後に次のような台詞が続く理由がわからない。
オーランドー もしそうなら、どうして君に恋しちゃいけないの? ロザリンド 「君に恋しちゃ」って誰に言ってるの? オーランドー ここにはいない人、聞いてもいない人に。
オーランドーは、ついロザリンドに向かって、ゲームではなくて本気で恋をしたいと言ってしまうのだ。しかし、ゲーム中であることを思い出して「ここにはいない人、聞いてもいない人」とごまかすのだ。
最終場で、公爵兄がどきりとする台詞を言う。
公爵兄 あの羊飼いの少年は、どうも 娘にそっくりの顔立ちをしているように思えてならん。
すると、もうギャニミードはロザリンドであるとわかっているオーランドーは、あえて自分が守ってきたゲームのルールを公爵兄に教えるのだ。
しかし、閣下、あの少年は森に生まれ、 伯父からさまざまな学問の基礎を 学んだそうです。その伯父というのが 偉大な魔法使いで、この森のどこかに ひっそりと暮らしているそうなのです。
ここはオーランドーが観客に対して目配せをするところかもしれない。そうすれば観客と一緒になってオーランドーもゲームを楽しんでいたことがわかる。
もしオーランドーが森のなかでロザリンドと一緒にいながら、少しもロザリンドを感じ取ることができないような鈍感な男なら、恋する資格はないと言うべきではないか。
この新訳は、Kawai Project vol. 5 公演(二〇一八年九月六日~九日シアタートラム、九月十三日~十七日彩の国さいたま芸術劇場小ホール)のために訳したものである。キャスト・スタッフは以下のとおり。
【キャスト】ロザリンド=太田緑ロランス、オーランドー=玉置玲央、シーリア/小姓=山﨑薫、公爵兄/フレデリック公爵=鳥山昌克、タッチストーン/ジェイクィズ=釆澤靖起、アダム/コリン/婚姻の神=小田豊、オリヴァー=玲央バルトナー、シルヴィアス/ル・ボー/貴族=遠山悠介、フィービー=荒巻まりの、オードリー=岸田茜、ジャック・ドゥ・ボワ/デニス/ウィリアム/貴族=峰﨑亮介、チャールズ/サー・オリヴァー・マーテクスト/貴族=三原玄也、エイミアンズ=Lutherヒロシ市村、楽士=川上由美(シアタートラム)、後藤浩明(彩の国さいたま芸術劇場小ホール)
【スタッフ】美術・衣裳=小池れい、照明=阿部康子、音楽=後藤浩明、音響=星野大輔(サウンドウィーズ)、衣裳=多部直美、ヘアメイク=片山昌子、演出助手=小比類巻諒介/山田健人、舞台監督=村田明、小道具=高庄優子、演出部=川澄透子/梶原航、制作=加藤恵梨花、票券=水流あかね、宣伝美術=荒巻まりの、翻訳・演出=河合祥一郎
二〇一八年六月