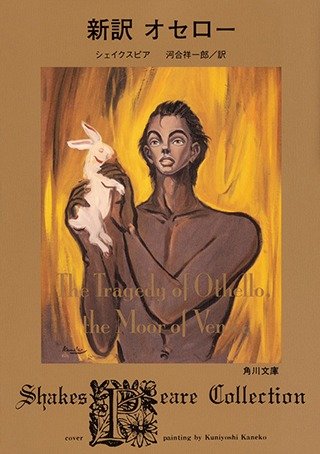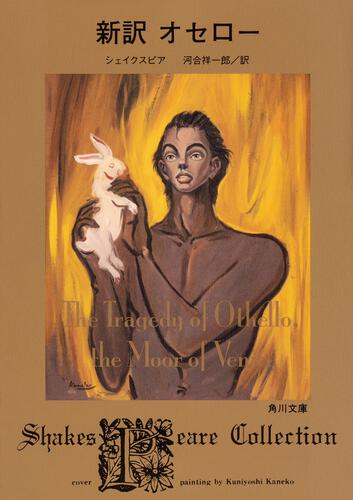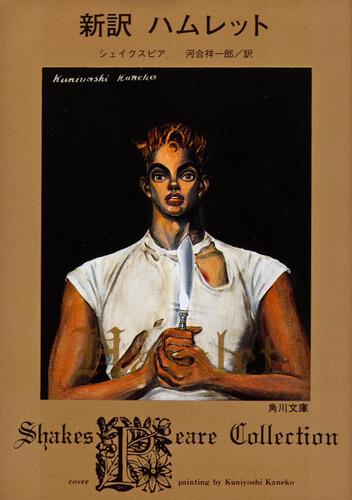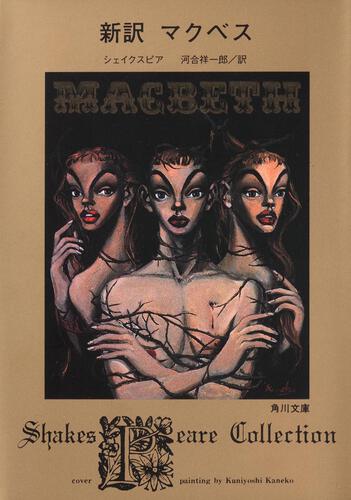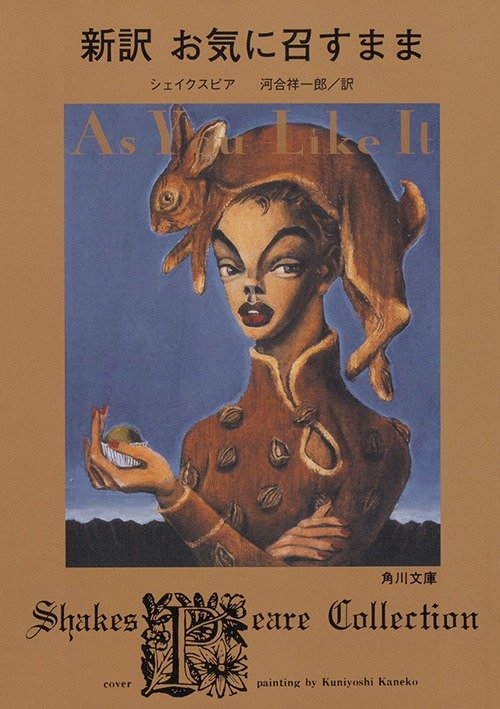本書の初版は一六二二年。そのクォート版(いわゆるQ1)の表紙には「ヴェニスのムーア人オセローの悲劇。グローブ座及びブラックフライヤーズ劇場にて国王一座によって頻繁に上演。ウィリアム・シェイクスピア作」とある。前年の十月六日に書籍業出版組合に登録された題名も『ヴェニスのムーア人オセローの悲劇』であった。一六二三年のフォーリオ(F)に収められた本作の題名も『ヴェニスのムーア人オセローの悲劇』であるから、これが本作の正式な題名と言えよう。
上演の記録で最も早いのは、一六〇四年十一月一日に『ヴェニスのムーア人』と題する芝居が宮廷のホワイト・ホールにて上演されたというもの。これが『オセロー』の初演と考えられるため、本作品が執筆されたのは一六〇三~四年であろうと推察されている。
本作にはめんどうなテクストの問題がある。Fのテクストは三千六百八十五行であり、Q1より百六十行ほど多いが、Q1にあってFにないところも十数行ある。本書十三ページの注7などに記したように、Q1は初演時の台本を反映しているところがある半面、Fには改訂が加えられているため、どちらを底本とすべきかについては議論が分かれる。多くの研究者たちの議論を総括して言えることは、Q1のテクストに加筆してFのテクストができたのではなく、むしろシェイクスピアの草稿から上演用にカットを加えてQ1ができたのであり、Fは草稿を反映していると同時に一六〇六年の罵声禁止令の影響を受けて罵声を削除するなどの編集が行われたのであろうということである。したがって底本をFとしつつ、罵声等の表現ではQ1を採用するというアーデン3の編集方針にこの翻訳も従った。
なぜオセローは最愛の妻を殺してしまったのか。なぜイアーゴーの正直さ(honesty)を信じ、妻の貞淑さ(honesty)を疑ったのか。まず、イアーゴーの正直さを信じたのは、軍隊という組織は上官と部下の絶対的な信頼関係に基づいて成り立っているからだと言える。上官の命令に部下は躊躇せずに服従せねばならず、上官は部下の命を預かる責任を負う半面、部下に全幅の信頼を置かなければやっていけない。オセローにイアーゴーを疑うという発想がなかったのは、部下を大事に思う上官としては自然なことであり、ましてや「正直なイアーゴー」という評判がある部下ならなおさらだった。
だからといって、部下を信頼したがゆえに最愛の妻を疑ったという単純な話でもない。むろん、ハンカチを見たというそれだけの理由で妻を疑ったわけでは決してない。彼が疑い始めたのは、自らの男性性に対する自信が崩れたためだ。
ヴェニス一の美女から愛されているという思いは、彼の男性性を支える大きな基盤となっており、だからこそ、自分に自信があるあいだは、妻の愛を疑うことなどなかった。その絶対的な自信が崩れたとき、自分は本当に妻に愛されているのかと疑い始めるのである。民族的な違いがあるにも拘わらずデズデモーナの愛を勝ち得たことは、それまでは彼の男性性を高揚させる勝利にほかならなかったが、彼が白人社会における黒人であるという他者性を指摘され、白人の文化をわかっていないと言われた瞬間、その自信にひびが入る。そのとき初めて、彼は困惑を口にするのだ、「そうなのか?」と(百二ページの注1参照)。
きっかけはそれだけで充分だ。小さなひびから堤防が決壊するように、あふれるばかりに湛えられていた自信は、堰を切って、疑惑という川へ流れ込む。
それでも、妻と会話をきちんとしていれば誤解は解け、ハンカチのような状況証拠を動かぬ証拠と思い込むことはなかったのではないか。そう思う人は多いだろう。早くも十七世紀に、トマス・ライマーが『悲劇管見』(一六九三)において、この劇をやり玉にあげ、この劇の教訓として「良家の娘は黒人と駈け落ちすべからず、人妻はハンカチ類をなくさぬよう用心すべし、夫は嫉妬をする前に証拠を十分吟味すべし」と述べて揶揄したのは有名な話だ。
オセローがイアーゴーに騙されて「疑惑」という苦痛を味わったすえにデズデモーナ殺害を決心したとしても、デズデモーナと直に言葉をやりとりするうちに誤解が解けるという展開にならないのはなぜか。サミュエル・ジョンソンが、自ら編集したシェイクスピア全集(一七六五)の序文で、オセローの「激しいまでのあけっぴろげな性格、度量が大きく、裏表がなく、信じやすく、人をとことん信頼し、愛情は激しく、決断は揺るぎなく、復讐心が強い」という性質を称賛しているが、それからもわかるように、オセローの激しい性格ゆえに、一旦火がついてしまったオセローの復讐心はデズデモーナを前にしてもおさまることはなかったと解釈されがちだった。だが、そうではないのだ。
実は、オセローが妻殺害に及んでしまう最大の罠はイアーゴーではなく、シェイクスピアによって仕掛けられている。その点を理解しないと、本作の真の面白さはわからない。
その仕掛けは、オセローがデズデモーナ殺害を決心してやってくる第五幕第二場にある。この場の冒頭でオセローが「それが理由だ、それが理由なのだ」と自分に言い聞かせていることからもわかるように、オセローの心は揺れている。百四十四ページで「妻と言い争うことはすまい。あの体と美しさで俺の決心が鈍るといかん」と述べているように、「決心が鈍る」こともあり得た。ところが、キャシオーが殺されたと聞いてデズデモーナは叫んでしまう。
Alas, he is betrayed!
これまでの翻訳では「あの人は計略に掛かったんですわ」「あの人はだまされたんだわ」「あの人は罠にかかった」「誰かに計られた」「あの人は敵の罠に」などと訳されてきた台詞である。しかし、原文のbetrayedには「騙された」という意味のほかに、「秘密がばれてしまった」という意味がある。デズデモーナは前者のつもりで言っているのに、オセローはデズデモーナが「ばれてしまった」と言ったと誤解し、ついに真実が確かめられたと思い込むのである(百八十四ページの注3参照)。この一行をどう訳すかが、この翻訳の課題の一つだった。
翻訳上の課題となった点をもう一つ付記しておこう。オセローがデズデモーナを殺した直後に、エミーリアがドアの外から「旦那様、旦那様」と呼びかけると、オセローが「何だ、あの音は?」と反応して、デズデモーナがまだ死んでいないのではないかと疑うくだりがある。今までどうしてもこのくだりが腑に落ちなかった。エミーリアがドアの外から声をかけると、どうしてオセローはデズデモーナが死んでいないと思うのか。松岡和子訳を除くこれまでの多くの訳がエミーリアの直前のデズデモーナの最期の台詞(O Lord! Lord! Lord!)を訳出していないことに気づいて疑問は氷解した。詳細は百八十六ページの注1に記したが、デズデモーナが口にしたLord! Lord!という音と、エミーリアのMy lord!と呼ぶ音が重なるのだ。この言葉の重なりをどう訳すかも、この翻訳の課題だった。
このように、シェイクスピアが意図した演劇的な言葉の仕掛けを日本語で表現しようと努めたのがこの翻訳の特徴である。これまでどおり台詞の響きやリズムを重視したのは言うまでもない。
本作の主たる種本は、一五六五年にヴェニスで刊行されたジラルディ・チンティオの『百話集』にある。そこではムーア人の美しい妻ディズデモーナに横恋慕した旗手が拒絶されたことを逆恨みして、ムーア人と一緒になってディズデモーナを砂袋で撲殺する話になっている。
しかし、種本と違って本作で描かれるイアーゴーには、単純な恨みだけでは説明のつかない、もっと根本的な悪への傾倒があるように思える。サミュエル・テーラー・コールリッジがイアーゴーのことを「動機なき悪意」(motiveless malignity)という言葉で描写したのもそれゆえだろう(四十七ページ注2参照)。イアーゴーは何度もオセローが憎い理由を述べているが、そうした「動機」よりももっと強い「衝動」に駆られて悪事を重ねているようにも思える。
種本と違うもう一つの側面は、本作には「二重の時間」(ダブルタイム)の構造があるという点だ。時間の流れを追っていくと、次のようになる。
第一幕 夜――デズデモーナがオセローと結婚。
長い時間経過(「思ったより一週間早く」キプロス島に到着)
第二幕第一場 キプロス島での一日目。
第二幕第二場 同日午後五時――「勝利と結婚を祝して夜十一時まで飲食自由」と布告。
第二幕第三場 同日午後十時から翌日未明――オセローとデズデモーナは新婚初夜を迎える。夜警たちの喧嘩。キャシオー解任。
第三幕第一~四場 翌日朝(二日目)――デズデモーナがオセローにキャシオーを赦ゆるすよう求める。キャシオーは拾ったハンカチをビアンカに与える。
第四幕第一~三場 二日目――オセローはキャシオーがハンカチを持っているのを目撃する。ビアンカが「さっきよこしたハンカチ」と言うので、同日。
第五幕第一場 夜(二日目)――夜の闇にまぎれてキャシオーを殺そうとする。
オセローが初めてデズデモーナと肉体的に結ばれてから一日もたたぬうちに、キャシオー殺害が仕組まれている。一方、そのあいだにもっと長い時間が経ったと思わせる台詞が多数ある。第三幕第三場でイアーゴーは「最近」のキャシオーの寝言の話をし、第三幕第四場でデズデモーナは「いつまでも結婚式のときみたいな心遣いは期待できない」と言い、ビアンカはキャシオーが一週間もお見限りだったと責め、第五幕第二場でオセローは妻が不倫を「数え切れぬほど重ねた」と言うのだから、ずいぶん長い時間が経ったとしか思えない。明らかに矛盾しているのだが、劇を観ているときはこの矛盾に気づかない。シェイクスピア・マジックである。
シェイクスピアがこの作品を書いた当時、異教徒や黒人に対して不当な差別がまかりとおっていたからこそ、アフリカ系黒人であるオセローがキリスト教社会で高い地位についたうえにヴェニス一の美女を妻にしたことに対してイアーゴーが不当な嫉妬を抱くという状況が生まれたと言えよう。当時の人種差別はひどいものであった。トルコ人は野蛮と決めつけられ(五十五ページ注5、七十四ページ注2参照)、インド人は卑しいと決めつけられた(二百三ページ)。キリスト教文化こそが唯一の文明社会の文化と看做され、異文化に対する偏見と蔑視ゆえに、異教徒は悪魔であるかのような言説がなされていた。特にイスラム教に対する無理解ゆえに、強大な力を持つイスラム教徒を恐れていた面もあっただろう。オセローが最後に自らを刺すときも、乱暴を振るう「異教徒の犬畜生」(ターバンを巻いたトルコ人)を殺すのが正義であるかのような言い方がなされている(二百三ページ)。当時、宗教問題は政治と密接に結びついていたため、政治的敵対が宗教的対立を助長した側面もあった。
シェイクスピアはユダヤ教徒への偏見を『ヴェニスの商人』で描いたが、『オセロー』では、キリスト教に改宗した黒人を主人公として、肌の色の違いによる人種差別を描いている。「白」を表す語(fair)が「美しさ」や「公平性」を表した一方、「黒」という色には「腹黒さ」や「穢れ」などの否定的な意味が籠められることが多かった。オセロー自身が「きれいだった妻の名は今や穢れて、俺の顔のように真っ黒だ」(百十四ページ)と語ることから、オセロー自身がそのような偏見を持つ白人文化のなかにいる矛盾が示される。
オセローがデズデモーナを殺害したと知ったエミーリアは、オセローのことを「真っ黒な悪魔」(百八十九ページ)と罵る。オセローがそうした肌の色に対する偏見を否定できないような残酷な罪を犯してしまうことに、オセローの悲劇があるとも言えよう。
こうした当時の強烈な差別意識を理解したうえでなければ、差別を前提として書かれているこの作品の本質に迫ることはできない。
オセローは、デズデモーナを「美しい本」「純白の紙」などと形容する一方で、彼女が犯したとされる罪の穢れを蛙や蠅を引き合いに出して糾弾する。そのとき「夏の屠畜場の蠅」(百五十四ページ)という表現が出てくるが、これに対しても注釈が必要だろう。肉食の歴史の長いイングランドにおいて、食肉の小売販売をする「肉屋」(butcher)という語には「動物を屠る者」の意味もあった。肉を売る者は自ら食肉解体作業を行っていたのである。特別な設備などはなく、戸外で行うために、特に夏場は蠅が群がった。その蠅に対する嫌悪感を表明しているのである。
当時の衛生事情は劣悪であった。下水設備も整備されておらず、排便にはおまるが用いられ、その中身の処分もいい加減で、家の外にまき散らすことすらあったという。ロンドンの街には蠅やネズミや蚤が繁殖し、ペストが蔓延して、膨大な数のロンドン市民がばたばたと倒れていた。「穢れ」に対する恐怖や憎悪は、命に関わるものとして今日より遥かに切実であったことは想像に難くない。
白いデズデモーナの美しさは外見だけのもので、なかは穢れて腐っているのだと思い込んだオセローの心のなかに、当時の悪臭を放つ穢れの強烈なイメージが入り込むのである。
シェイクスピアは、『ウィンザーの陽気な女房たち』、『から騒ぎ』、『シンベリン』、『冬物語』などの他の作品においても、妻が不倫を働いたという、あらぬ疑いを抱いて苦しむ夫たちを描いている。
「寝盗られ幻想」とでも呼ぶべきこの妄想は、当時の男性中心主義的な文化に蔓延していた一種の病だった。英語で「寝盗られ亭主」のことをcuckoldと呼ぶが、これは他の鳥の巣に卵を産みつける習性のある鳥のカッコウ(cuckoo)に由来する。知らないあいだに妻に浮気をされて他の男の子供を宿しても、寝盗られ亭主は自分の子供だと思って育てることになるためだ。『から騒ぎ』第一幕第一場で、ヒアローの父親である知事レオナートは「こちらが娘さんですか」と尋ねられると、「これの母親が、わしが父親だと何度も申しておりました」と答えるが、これなども、寝盗られたかもしれない可能性を踏まえての発言である。
どうしてエリザベス朝の夫たちは、妻に不貞を働かれるのではないかと、そこまでおびえなければならなかったのかと驚くほど、この「寝盗られ幻想」はさまざまな言説に蔓延していた。シェイクスピア以外のエリザベス朝劇作家の戯曲でも、「寝盗られ亭主」は多数描かれており、寝盗られ亭主の額には角が生えるという迷信が広く信じられていた。『お気に召すまま』のような恋愛喜劇においてさえ、結婚すれば夫は角を生やすものなどと、結婚生活が必ずしも幸せなものにならないことが揶揄されている。
エリザベス朝時代の男性がそのような強迫観念に悩まされていた原因を推察すれば、当時の社会では男性に過度の男性性が求められていたためであろう。身分のある男性は帯剣し、いつでも剣を抜いて自らの男ぶりを証明しなければならなかった。強い男性性の発露が求められるあまり、結婚とは、妻を完全に従属させることだという発想が生まれ、自分は妻を完全に従属させ得ていないのではないかという不安からそうした幻想が生まれたと考えられる。
『冬物語』で、突然リオンティーズが妻が姦通をしたと決めつける心理は現代人にはわかりづらいが、この時代には「寝盗られ幻想」があったのだとわかってみれば、少しは納得がいくだろう。『オセロー』においても、同じような「寝盗られ幻想」が前提となっていたことは知っておく必要がある。
当時の「嫉妬」(jealousy)は、今日の意味での嫉妬とはちがって、当時信じられていた四体液説に基づく「気質」(humour)という概念と密接に結びついていた。四体液説は、人間は血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁の四つから成るとする古代ギリシャのヒポクラテス医学に依拠するものである。
シェイクスピアと同時代の劇作家ベン・ジョンソンが『誰もがそれぞれの気質のなかで』(Every Man in His Humour)という芝居のなかで、妻が若い男と会っているのではないかと理不尽な嫉妬を抱く商人カイトリーを登場させているが、それというのも、「嫉妬」が不機嫌さ(choler)を司る黄胆汁から生まれると考えられていたからだ。つまり、四体液のうちの黄胆汁が過多になると、人は短気で気難しくなり、嫉妬深くなるのである。
『オセロー』において、嫉妬が「緑の目をした怪物」(百ページ)と表現されるのも、黄胆汁の緑がかった黄色と関連するためと言われている。
最も健康的で社交的な気質は多血質であり、やや鈍く穏やかでふっくらとした体つきをした女性に多い気質とされたのは粘液質だ。そして、黒胆汁質の人は、孤独で憂鬱になり、心の病に罹りやすいとされた。
オセローが第四幕第一場で興奮のあまり卒倒すると、イアーゴーはそれを「癲癇(epilepsy)」と呼んでいるが、当時の医学では「癲癇」は黒胆汁の過多によって起こると考えられていた。ヒポクラテスの四体液説はローマのガレノスに受け継がれていったが、『憂鬱の解剖』(一六二一)を著したイギリスの学者ロバート・バートンは、ガレノスの考え方に従って、「癲癇」とは憂鬱が引き起こす「脳の病気だ」としている。シェイクスピアの義理の息子のジョン・ホールは、ストラットフォード・アポン・エイヴォンの町医者だったが、癲癇の治療として、患者の鼻の下で鹿角精(炭酸アンモニウム)を燃やしたらしい。
さらに言えば、当時あらゆる物質は、空気、火、水、土という四つの元素から成ると考えられていて、この四元素は、四つの気質に結びつけられて考えられていた。すなわち、空気は多血質に、火は黄胆汁質に、水は粘液質に、土は黒胆汁質に関連するとされていたのである。
第三幕第四場で、デズデモーナは、夫オセローは嫉妬深くないのかとエミーリアに問われて、「あの人が生まれた国の太陽がそんな気質をすっかりなくしたんだわ」と答えるが、これは、オセローは南国出身であるため、熱い太陽によって黄胆汁質がすっかり燃え尽きて、オセローは多血質となったという意味であろう。ところが、そのオセローは、黒胆汁質のイアーゴーに唆されて、黄胆汁質の気質が増して火のような嫉妬と怒りに狂ったのだと、当時の医学的見地から言うことができる。
このように現代の常識とはかけはなれた文化においてシェイクスピアの作品は書かれているわけだが、それでもシェイクスピアの人間理解の確かさは、文化の差を飛び越えて私たちの心に訴えかけてくる。
なぜイアーゴーはエミーリアを殺してしまうのか。それは、彼が口封じのために自分の女房さえ殺すことをなんとも思わない悪党にすぎないからだというのが、これまでの一般的な理解だった。あるいはまた、卑劣で残虐な悪の権化に、なぜそんなひどいことをするのかと尋ねても仕方ないとも考えられてきた。しかし、そのように「悪」というレッテルを貼ってしまっては、イアーゴーの心の内は見えない。その複雑な心理を丁寧に考えてみることにしよう。
〈正直な軍人〉と〈悪党〉という二つの仮面を持つこの男は、仮面の背後に、ひた隠しに隠してきた素顔を持っている。それは、「絶対的男性性を失った男」としての醜くも情けない顔だ。他人の目を欺く〈正直な軍人〉という仮面の背後にあるのは、確かに〈悪党〉という眼光鋭い顔であるが、それも結局のところ素顔ではなく、自分の目を欺くために我知らず着けている仮面にすぎない。彼は社会のみならず自分に対しても嘘をつき、自分の男性性は完璧だと思い込もうとしているのだ。ところが、エミーリアが自分を裏切ろうとしたとき、虚勢は足元から崩れる。「悪魔の神学」を気取る〈悪党〉なら、女房も思いどおりに操るぐらいでなければならないが、自分の女房に裏切られても仕方のない「男性性を失った男」としての素顔が露見してしまうのだ。そして、素顔をさらけ出した彼は、自分を裏切る妻を暴力によって否定しようとする。女房は夫に属するものであるという父権制の思い込みに基づいて、彼は妻の不忠に対して、発作的に、絶対的男性として振る舞う――それが、エミーリア殺害である。
その行為を、人は悪党の所業であると言うが、自分を裏切る妻を殺してしまうのは、イアーゴーのみならず、オセローも同じである。それなのに、一方を悪党、他方を悲劇の主人公と解釈するだけでは、根底にある大きな問題を見逃すことになってしまう。イアーゴーとエミーリアの関係は、オセローとデズデモーナの関係とパラレルになっているのである。
エミーリアの夫への愛はこれまであまり注目されてこなかったが、それは、イアーゴーとともにエミーリアも、道徳心のない海千山千と誤解されてきてしまったためだ。とくに、全世界をもらっても不貞は働かないと言うデズデモーナに対して、全世界をもらえるなら不貞ぐらいかまわないと言うエミーリアは、モラルの低い女とみなされてきた。清く正しく美しいデズデモーナの輝きを引き立てるための、低俗な女でしかないというわけだ。しかし、そうなのだろうか。「全世界とひきかえなら、ほかの男と寝るか」というデズデモーナの問いに対して、エミーリアはそれが亭主のためになるのだったら「煉獄れんごくの苦しみにあってもやる」と言う。確かに、不倫は悪いことだ。しかし、愛する人のために自分を犠牲にできるかという問いに置き換えると別の意味をもってくる。この問題は『尺には尺を』でも追究される。『テンペスト』で、無邪気なミランダは、チェスをしながら、愛するファーディナンドにこう言う。
ファーディナンド たとえ全世界をくれると言われても、ずるい手などを指すものか。
ミランダ あら、指してよ、王国を二十も手に入れるためならね。/それも立派な手と言ってあげるところだけれど。(第五幕第一場一七三~五行)
ミランダが「ずるい手」を容認するように、エミーリアも容認する。それでも、ミランダは純真で、エミーリアは道徳心の薄い女と考えるべきなのか。
この新訳は、二〇一八年九月二日~二十六日の新橋演舞場における公演のためのものであり、台本作成に当たっては、演出の井上尊晶氏より表現について貴重な指摘を多数受けた。記して感謝したい。
オセロー=中村芝翫、デズデモーナ=檀れい、イアーゴー=神山智洋(ジャニーズWEST)、エミーリア=前田亜季、キャシオー=石黒英雄、ロダリーゴー=池田純矢、ブラバンショー=辻※萬長、ヴェニス公爵=田口守、ロドヴィーコー=大石継太、グラシアーノー=廣田高志、モンターノー=二反田雅澄、ビアンカ=河合宥季、その他の出演=塚本幸男、児玉真二、河内大和、澤魁士、プリティ太田、野澤健、澄人、鎌田雅尋、水谷悟、五味良介、上川路啓志、チョウヨンホ、桂佑輔、駒井健介、長谷川直紀、薄平広樹、原田翔平、光山恭平、尾瀧一眞、小野哲平、中村芝晶。
制作=松竹株式会社、演出=井上尊晶、音楽=松任谷正隆、美術=中越司、照明=原田保、音響=井上正弘、衣裳=前田文子、ヘアメイク=河村陽子、振付=井手茂太、擬闘=栗原直樹、演出補=大河内直子、演出助手=浅香哲哉、舞台監督=赤羽宏郎。
二〇一八年四月 河合 祥一郎
※「辻」は一点しんにょう