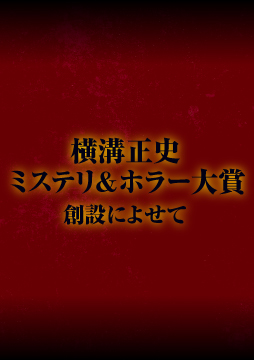書評家・作家・専門家が《新刊》をご紹介!
本選びにお役立てください。
(評者:織守きょうや / 小説家)
このシリーズにおいて、怪異に悩む人たちの助けとなるのは、探偵でも霊能者でもなく、タイトルのとおりの「営繕屋」、尾端です。建物を建築・改築したり、修繕したりするのが彼の仕事です。彼には霊能力はなく、霊と戦ったり祓ったりはしません。では、対話して理解しようとするのかというと、それもしません。知識や洞察力から怪異の正体に気づくことはあっても、彼にそれを見抜く特別な能力があるわけではないので、怪異の正体がはっきりしないまま――登場人物たちが怪異に向き合うことすらしないまま、物語が終わることもあります。
この作品群に登場する怪異は、時には、人間に何かを訴えていることもありますが、時には、ただそこにあるだけのものとして描かれます。人間に何かを求めているわけではないものに対して、人間は対処のしようがなく、ただ耐えて、そこに住み続けるしかない、あるいは、逃げ出すしかないかのように思えます。
尾端はそこへ現れて、あくまで営繕屋として、家を修繕したり、改築したりして、そこに住む人と怪異が「折り合いをつける」手伝いをするのです。
彼は営繕屋としての仕事をするだけですが、その結果として、怪異は人がその存在を受け容れることができるような形に落ち着き、怪異に脅かされていた人たちは平穏を取り戻します。少なくとも、一人でただ恐怖に耐えたり、怯えたりしなくてもよくなります。
そのやり方の無理のなさが、とても思慮深く、やさしくて、読んでいて嬉しくなってしまいます。
そして、この度発売となった「その弐」においても、それは変わりません。
「その弐」には六編の物語が収録されていますが、その一つ一つに、共通した安心感と、違った魅力があります。収録作の一つ、「まつとし聞かば」は、まさに、怪異を排除せず「折り合いをつける」話です。自宅で起きる不穏な出来事に、幼い子どもの父親である視点人物が感じる不安や恐怖は胸に迫り、子どもが怪異を怪異と認識していないことが、ますます彼と読者の危機感をあおります。
作品群の中で唯一、怪異に怯えるのではなく、怪異に魅せられてしまった男を描いた「芙蓉忌」、子どものころのおそろしい記憶にとらわれた人たちの登場する「関守」と「水の声」――この中では少し異色かもしれない「魂やどりて」は、怪異が起きる前から漂う不穏な気配と、視点人物だけがそれに気づいていない危うさと気持ち悪さにドキドキしました。
そう、「その弐」は、一巻にも増して、人間の心情や行動も、怪異の描写も、実にリアルです。においや手触りさえ感じられそうな、生きた人間と生きた怪異が描かれています。
それゆえに、この本はとても怖い。読んでいる最中は、最後には尾端が助けてくれるはずと思っていても不安になるくらいに、おそろしいです。
登場人物たちは、聖人でも悪人でもなく、どこにでもいそうな人たちです。余裕がないときは人を傷つけることもあり、でもそれに気づけば後悔する、普通の人です。だからこそ、自分が怪異に出会った登場人物の立場だったらと、読者は他人事ではないおそろしさを感じるのです。
最後に収録された「まさくに」には、これまでのシリーズを通しても一、二を争う、視覚的にインパクトのある怪異が登場します。人を怖がらせようとしているとしか思えない、そうでないとしたら、よほどの無念を抱いている霊に違いない。そんな霊と、どうやって折り合いをつければいいのか。いくら尾端でも、こんな霊を、気にせずに済むようにできるとは思えない――そう思ったのに、まさか、あんな風に着地するとは(読んで確かめてください)。
尾端が登場すると、彼を知っている読者は、「ああこれで大丈夫」と安心します。そして実際に、大丈夫なのです。
あれだけおそろしかった霊が、どうしようもないように思えた怪異が、姿を変える瞬間の鮮やかさ。魔法のように提示される解決策に、緊張と恐怖がとけていく感覚の心地よさ。
彼はただ、依頼主や怪異の発生源にとっての最善を考え、営繕屋としての仕事をしているだけですが、人も、怪異も、読者さえも、その誠実さに救われるのです。
誰が読んでも、それがいつの時代でも、変わらず楽しめるに違いない上質な物語です。怖い話がお好きな人にも、怖い話が苦手な人にも、是非読んでいただきたいと思います。
ご購入はこちら▶小野不由美『営繕かるかや怪異譚 その弐』| KADOKAWA
▷作品特設サイト