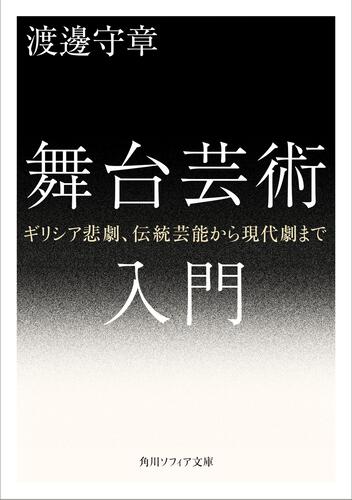文庫解説 舞台芸術入門 ギリシア悲劇、伝統芸能から現代劇までより
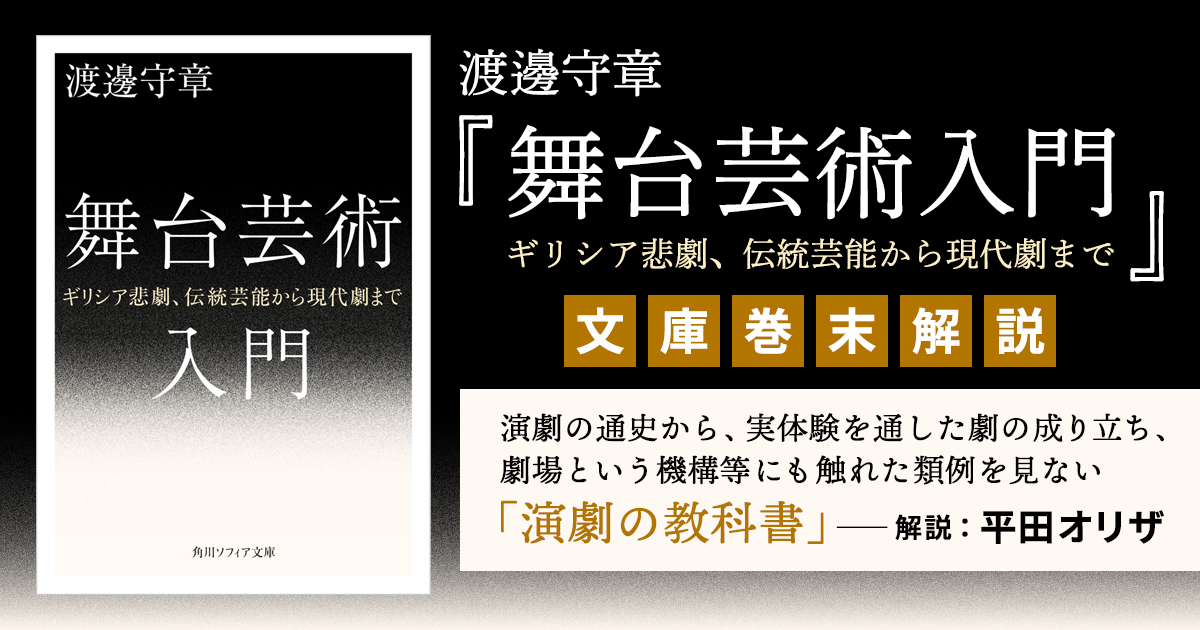
【解説】類例を見ない、まさに「演劇の教科書」――『舞台芸術入門 ギリシア悲劇、伝統芸能から現代劇まで』渡邊守章【文庫巻末解説:平田オリザ】
渡邊守章『舞台芸術入門 ギリシア悲劇、伝統芸能から現代劇まで』(角川ソフィア文庫)の刊行を記念して、巻末に収録された「解説」を特別公開!
渡邊守章『舞台芸術入門 ギリシア悲劇、伝統芸能から現代劇まで』文庫巻末解説
1999年初夏、パリ
解説
平田オリザ(劇作家)
1999年の初夏であったと思う。恵比寿の日仏会館で、新世紀に向けて、今後の日仏間の文化交流、とりわけ舞台芸術の交流をどう進めていくかというカンファレンスが開かれた。これまで日仏の文化交流において実績のあるプロデューサーや芸術家、そして渡邊守章先生や佐伯隆幸先生といった学術界の泰斗も顔を揃えた。フランス側も日仏会館だけではなく、在日フランス大使館の文化担当者、いわゆるフランス外務省文化部のメンバーも全員が出席していた。
95年に岸田國士戯曲賞を受賞した私の作品、『東京ノート』が、この会議の前年の98年にパリ郊外でリーディング上演され、それが思いのほかに好評で、この年(99年)の12月からフランスに滞在して年明けにはパリでの上演が決まっていた。日本の若手劇作家の作品がフランスで、フランス語で上演されることは当時、きわめて珍しいことで、大使館の面々からは強い期待もいただいていた。私は事前に言われていたので、『東京ノート』の上演に至るまでの経緯を5、6分で報告した。
会議は多少、退屈だったけれど、何しろ私はおそらく最年少だったから、とにかく黙って他の方の話を聞いていた。
ところが会の最後に、あるベテランのプロデューサーが、何を思ったのか「平田オリザなどというぽっと出の作家がパリに行っても成功するはずがない。ましてフランス語での上演なんて恥をかくだけだ」といった発言をした。おそらく知らないところで、私は何か恨みを買っていたのだろう。その方が、「ねぇ、渡邊先生」と渡邊守章氏に話を振った。辛口の批評で知られる渡邊先生ならば、この生意気な若手劇作家に鉄槌を下してくれると期待したのだと思う。私も、皮肉の一つでも言われるのだろうと思って身構えた。
ところがプロデューサー氏の意に反して、渡邊先生は困ったなという顔をしながら、以下のようなことをおっしゃった。
「まぁ、うまく行くかどうか、パリの観客の反応は分からないけれど、清水邦夫を持っていってもイギリスにはピンターがいるし、別役実といってもベケットがいるしで、今まで演出家はともかく、日本の劇作家の作品の上演では三島作品以外あまり成功例がないのは確かです。ただ平田オリザというのは、私もまだよく分からないけれども、おそらく似たような作家が欧州にいないかもしれず、存外フランスでは受け入れられるかもしれない」
渡邊氏は、確かに時に辛辣な毒舌家であったが、しかし生の芸術を前にしたときは、きわめて公正な方であった。それは終生、変わることがなかった。
私はこの翌年から桜美林大学で教鞭を執ることになり、文字通り付け焼き刃で演出論やアートマネジメントについて教えなければならなくなった。そのときから、常に教科書として本書や、このあとに続けて刊行された放送大学のテキストを使わせていただいてきた。もちろんそのことは、渡邊先生ご本人にも何度もお礼と共に伝え、逆にそれを喜んでもいただけた。
本書は一読してお分かりのように、伝統芸能から現代演劇までの演劇の通史だけではなく、渡邊先生の演出家としての実体験を通した劇の成り立ち、また劇場という機構等にも触れられた他に類例を見ない、まさに「演劇の教科書」となっている。日本以外の多くの先進国は、少なくとも高校の選択必修などに演劇という科目があるのだが、もし日本で、そんな科目が出来たとしたら、本書を以てその教科書のモデルとすべきだろう。なぜなら本書は、創る側と観る側の双方の巧者であった渡邊先生が、その相互の視点でお書きになっているからだ。それ故に、本書を手に取った読者はたとえ創る側ではなくとも、あるいはあまり演劇をご覧にならない方でさえ楽しんでいただける内容になっているのではないか。
人生でもう一度だけ、先生に褒めていただいたことがある。これは記憶も鮮明なのだが2010年の5月、当時、準備を進めていた通称「劇場法」について、京都で簡単な経緯の説明を兼ねた講演会を行った。30人ほどの小さな会で、京都の主立った演劇人が集まる中、当時京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)にいらっしゃった渡邊先生が何気ない顔で座っていらっしゃった。
私はたいへん困ったなと思った。何しろ、当時の私の構想はフランスの劇場システムを元に構築されており、この点において渡邊氏は私より数段、広範な知識を持っている。いや、私の知識の半分は本書を含めた先生の著作が元になっている。
冷や汗もので90分の講演を終え、質疑も済んだあと、先生は懇親会にもいらっしゃって私の隣の席に座られた。「素人が適当なことを言ってすみません」と先に謝ったら「いや、今日の話はよく出来ている。感心した。もしこれが実現すれば日本の演劇界は変わる」と手放しで褒めていただいた。まぁ、それは先生の理論や分析を、日本の実情に合わせて具現化しようとするプランだから、そうなってしかるべきではあるのだが、ここまで褒めていただけるとは思っていなかった。
その後、劇場法(劇場、音楽堂等の活性化に関する法律)は2012年に成立したが、私が構想したような、創作活動を主とする拠点劇場への重点的な予算配分は実現しなかった。まして本書でも触れられている芸術監督や総支配人の設置は、法律でその方向性が促されているにもかかわらず遅々として進まない。個人に大きな権限を委ねることを嫌う日本の政治風土が、これを邪魔している。先生も天国で「だから日本は……」と嘆いていらっしゃるだろう。
一方、私は日本で初めての演劇やダンスの実技が学べる公立大学の学長となった。舞台装置の制作、衣装製作なども出来るバックヤードを兼ね備えた劇場も創った。2021年の4月5日に最初の入学式が執り行われた。その6日後、私は渡邊先生の訃報を聞いた。先生にこの大学を見てもらいたかった。「まぁ、いろいろ足りないところもあるけど、とりあえずよくやったね」と皮肉交じりに褒めていただきたかった。それだけが心残りである。
作品紹介
書 名:舞台芸術入門 ギリシア悲劇、伝統芸能から現代劇まで
著 者:渡邊守章
発売日:2025年03月22日
理論と実践から東西の舞台芸術の系譜を一望する!
喜怒哀楽を操り、共同体を再生させ、時に神や亡霊をも呼び出す舞台芸術の魅力は如何に生み出されるのか。ギリシア悲劇を範とし、オペラやバレエへと拡散していく西洋演劇史を踏まえつつ、能、文楽、狂言、歌舞伎といった日本の伝統芸能や中国の京劇、バリ島の舞踏も取り上げ、その真髄を鮮やかに描き出す。自らも演出家として活躍した演劇研究の泰斗が、歴史・理論・実作を一本の線で結ぶ入門書の決定版。
解説・平田オリザ
*本書は、1996年に放送大学教育振興会より刊行された『舞台芸術論』を再編集し、改題のうえ文庫化したものです。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322408001379/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら