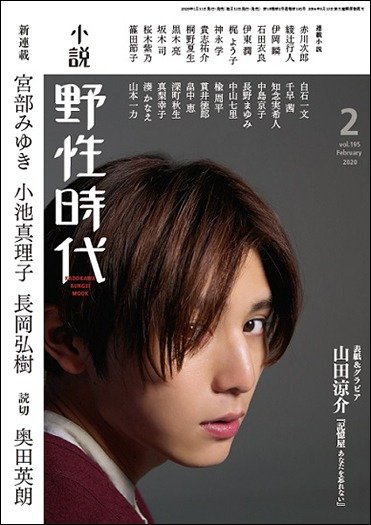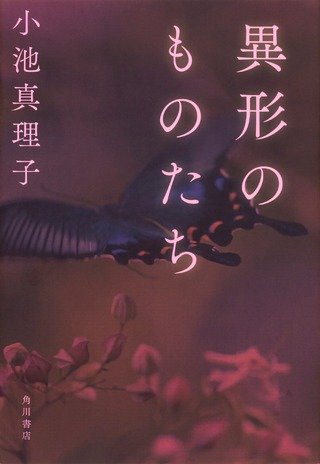文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(解説者:
平成から令和へと元号が変わる節目の年となった二〇一九年──私は夏から秋にかけて、平成の三十余年間に日本で生まれた幻想と怪奇の名作短篇を、全三巻に精選収録する大がかりなアンソロジー(創元推理文庫『平成怪奇小説傑作集』)の企画編纂に携わった。
小池真理子の作品については、あれも良い、これも捨てがたい、いや、やはりあちらを……などと、さんざっぱら思い悩んだあげく(アンソロジストにとっては苦しくも至福の時)、極めつきの怪談小説「命日」を採録することに決した。果たして、ウェブ上での読者の反響を拝見していると、「命日」の抜きん出た怖さを称揚する声が多数目について、我が意を得た思いしきりであった。
この作品は雑誌発表ではなく、五人の女性作家(他の四名は坂東眞砂子、篠田節子、今邑彩、服部まゆみ……いま書きながら気づいて
同書は、初期の角川ホラー文庫から出た一連のオリジナル競作集の中でも、全掲載作のただならぬクオリティの点で秀抜な一冊だったが、そんな中にあっても
未読の方のために物語の詳細にふれることは避けるが、松葉杖をついた愛らしい少女が「よいしょ、よいしょ」と近づいてくる、ただそれだけの描写が、無慈悲で不条理な怪異の象徴として比類なき恐怖感を醸しだすとともに、やり場のない悲哀と痛恨の念をも
しかしながら、小池怪談の真骨頂は、実はその先(あるいは奥もしくは底というべきか)にあった。次の引用をご覧いただきたい。
東 亡くなったお母様は、いわゆる〝視(み)える〟体質の方で、不思議な実体験も豊富だったそうですね。
小池 ええ、母の体験はずいぶん作品に使わせてもらいました。以前書いた「命日」という短篇は、高校の頃、家族と暮らしていた或る土地の社宅でのできごとをヒントにしたものです。そこはかつて脊椎カリエスで亡くなった幼いお嬢さんが療養していたという家で、母は引っ越した当初から「この家はなんとなくいやだ」と言っていました。静かな郊外に建つ、日当たりのいい平屋建ての旧い家でしたね。母があんまり気味悪がるので、結局、その家には数か月住んだだけで、また引っ越してしまいました。
これは怪談専門誌「幽」の第二十八号に掲載された、作者と私による対談記事の一節である。それによると、平成を代表する怪談の一篇となった「命日」は、かつて作者自身が実際に体験した出来事に由来するものということになる。対談をしながら、私が内心、あの光景を想起して総毛立ったことは申すまでもあるまい。よいしょ、よいしょ……。
いやはや、怪談小説の陰に怪談実話あり、とでもいうべきか。
ちなみに大正十二年(一九二三)、函館に生まれた作者の御母堂は、現世に立ち顕われる死者たちを視る能力の持ち主──作者の言葉を借りれば〈異形のもの、この世ならざるものと、何度も遭遇してしまう人〉(集英社文庫版『命日』所収のエッセイ「現世と異界──その往復」より)だったという。そして小池は、いたって日常的なお茶の間の話題の一環として、母親からナマの怪異譚の数々を聞かされて育ったそうなのである。
小池自身は、母の霊感体質をほとんど受け継いではいないと言うが、それでもある作品(『水無月の墓』所収の「私の居る場所」。神隠しの孤絶と恐怖を描いた屈指の名作である)を執筆後に奇妙な体験をしたと、インタビュー中で語っている。
雑誌の掲載時にそれ(引用者註:「私の居る場所」のこと)を母が読んで、「なんだか気持ち悪いわね」って言うのね。「どうして」って聞いたら、異界から現実に戻るときに、頭の中に古いラジオが入ってて、そのスイッチがバチンと切れるような音が実際にしたと。それは私は母からは聞いていないんですよ。母も、どう表現したらいいのか、その感覚を言葉にできなかったから言わなかったけれども、まさにそうだったと言うんですね。それを聞いて作者である私自身、ちょっとゾッとしたという後日談のある話なんですけれども。(「幻想文学」第四十七号掲載の「新・一書一会/言葉で紡いだ異界の光景」より)
さて、ここまで延々と「命日」に関わる話題を引っぱってきたのには、無論のこと理由がある。本書『異形のものたち』の巻頭に置かれた「面」は、かつて作者自身が体験した、母そのひとの怪異に由来する作品だからである。奇しくも本書(二〇一七年十一月刊)と前後する時期に
十四年ほど前のことになろうか。別荘客の大半が帰ってしまい、あたりが静まり返る季節。今にも暮れようとしている、夏も終わりかけた日の六時ごろだった。別荘地の中を一人で車を運転していて、私はふいに母を見かけた。
誰もいない、近くに建物が一軒もない、あるのは夏の間、生い茂った雑草や緑濃い木立ちばかり。そんな一角の、舗装された一本道を、高齢の大柄な女性が姿勢よく軽やかな足どりで、向こうからこちらに向かって歩いて来る。
おや、こんな時間に誰だろう、別荘の人たちはみんな帰ってしまったはずなのに、と思い、通りすがりざまに何気なく顔を見た。それはまっすぐ前を向き、にこにこ笑いながらリズミカルに歩いている母だった。
だが、母はその時、横浜の自宅にいた。そんなところを一人で歩いているはずがなかった。
他人の空似、たまたま母によく似ている人が散歩していただけなのだ、と思いながら、しかし、私はどういうわけか一瞬、頭の中が空白になった。慌てて速度を落とし、バックミラーを覗いた。見通しのきく一本道には、誰もいなかった。
この短い幻視体験が、本書の「面」において、どのように活かされているか、是非じっくりと読み較べてみていただきたいと思う。怪異の核となる部分のリアリティは残しつつも、その体験から喚起される様々な過去の出来事(先に引いた神隠し時の感覚も、たいそう効果的に活かされていることに注目)を巧みに融合させ、体験者である作中の男性とその家族をめぐる葛藤や悔恨の物語を、いとも鮮やかに浮き彫りにする……小説づくりの
さるにても、本書に収められた六作品の、いずれ劣らぬ充実ぶりは、どうだろう。
亡き母へ
異郷から恋人を慕って来日したオーストリア人女性の執念が陰々と籠もる呪物譚「ゾフィーの手袋」、山荘の地下室に黒々と
ちなみに「緋色の窓」は、幻想と怪奇の大いなる先達・泉鏡花の短篇「浅茅生」を
「文学の極意は怪談である」の名言で知られる文豪・佐藤春夫も、かつて渋谷道玄坂上にあった三階建の幽霊屋敷に、弟子の稲垣足穂らと暮らし、そこで目撃した怪異の数々を、師弟ともに作品化している(春夫の「化物屋敷」と足穂の「黒猫と女の子」)。
本書『異形のものたち』に収められた六篇の名作佳品は、そうした日本怪談文学史の良き伝統を現代に受け継ぐ、最新の達成と称して過言ではあるまい。
二〇一九年十二月 鏡花生誕地にほど近い金沢の
▼小池真理子『異形のものたち』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000643/