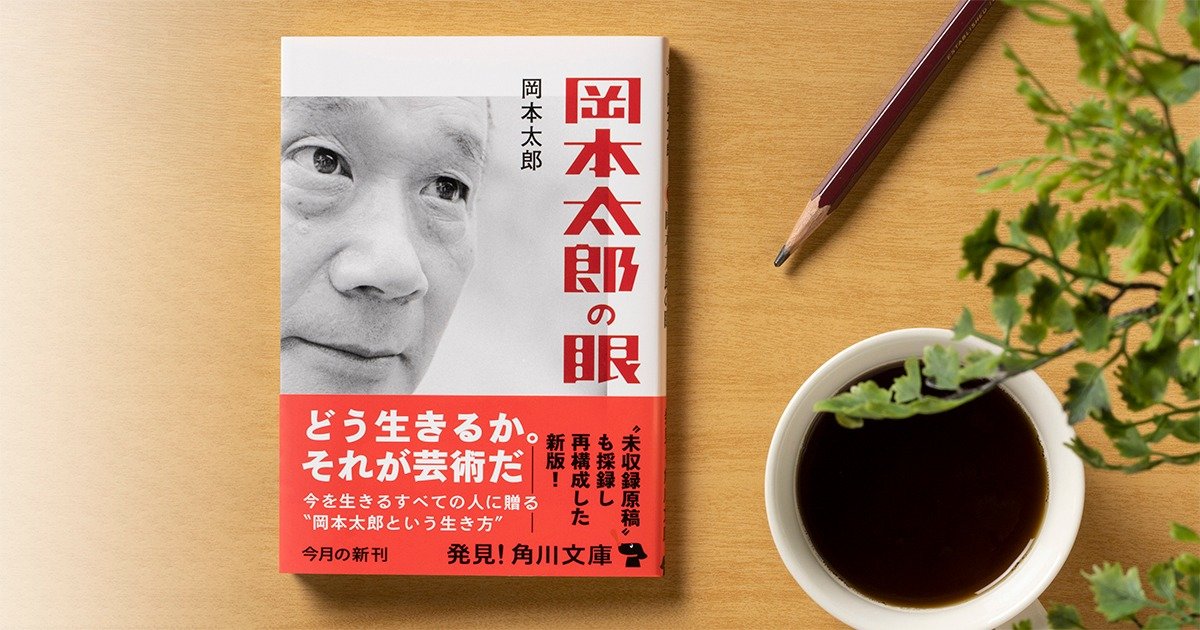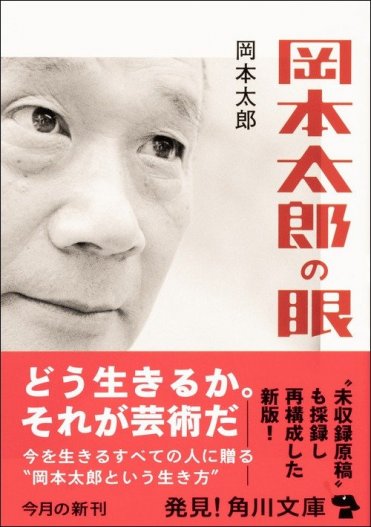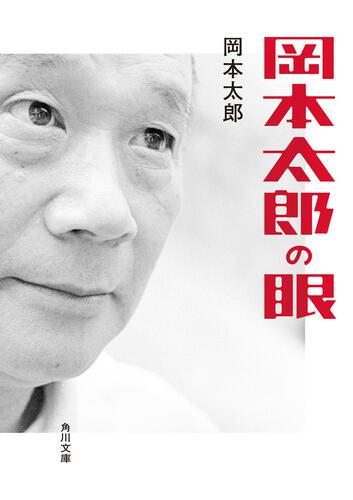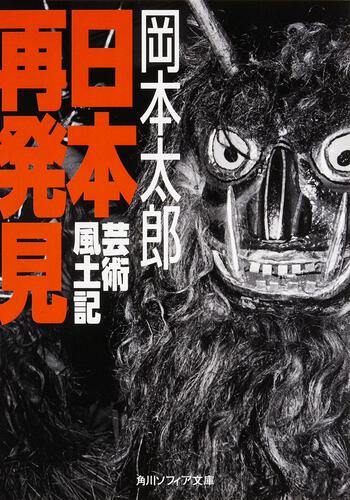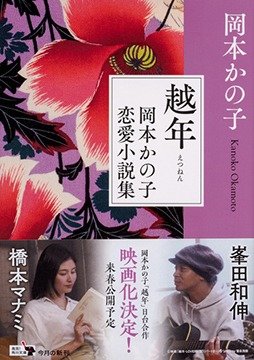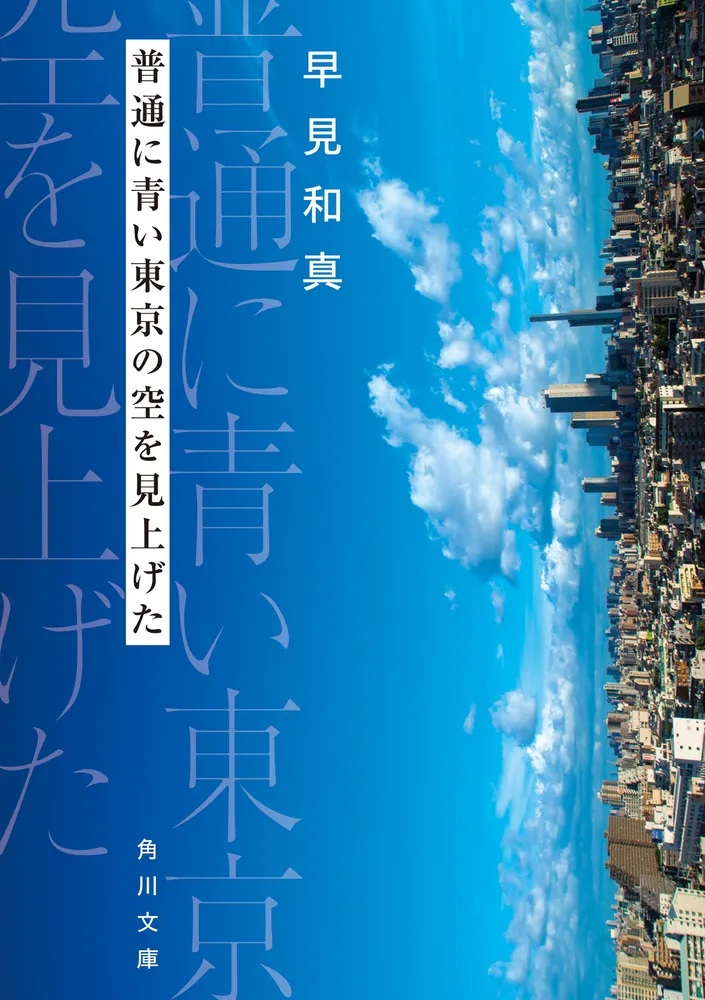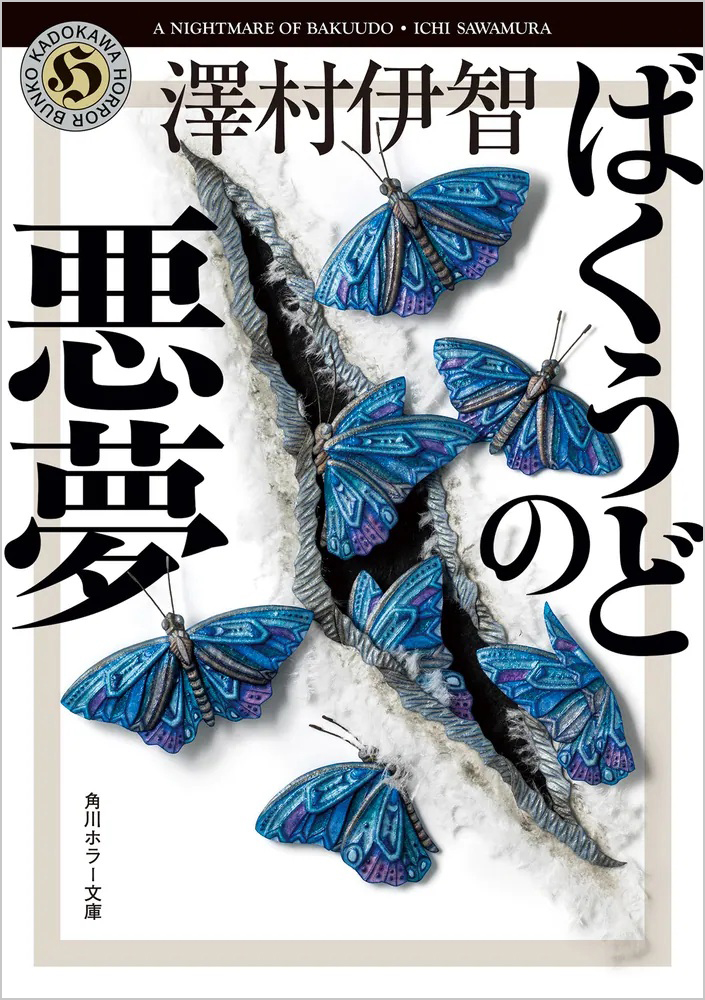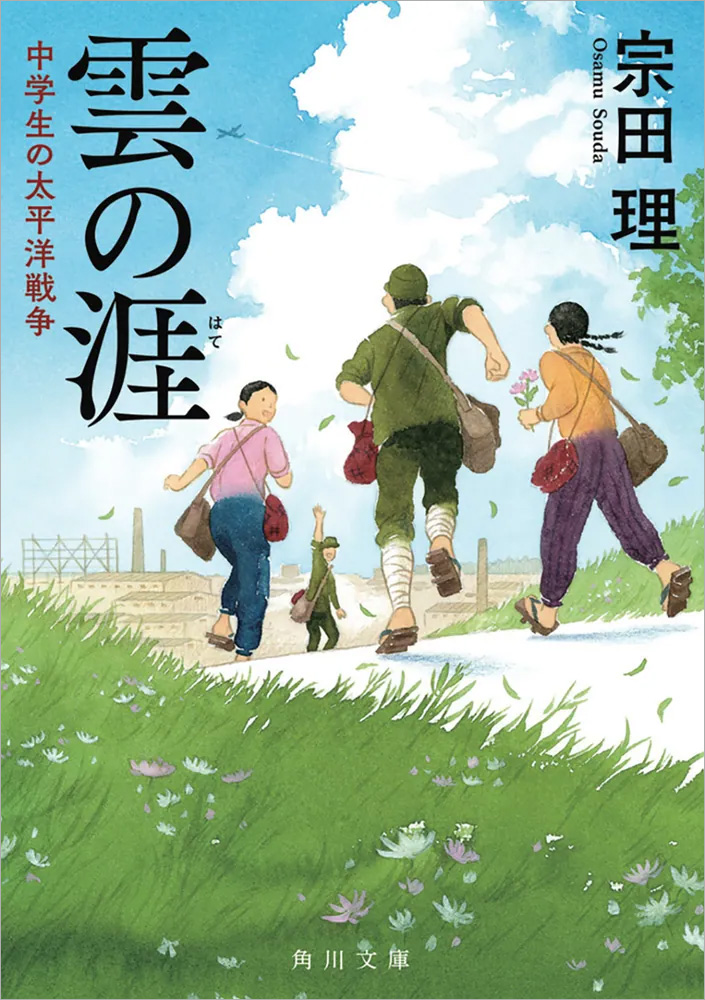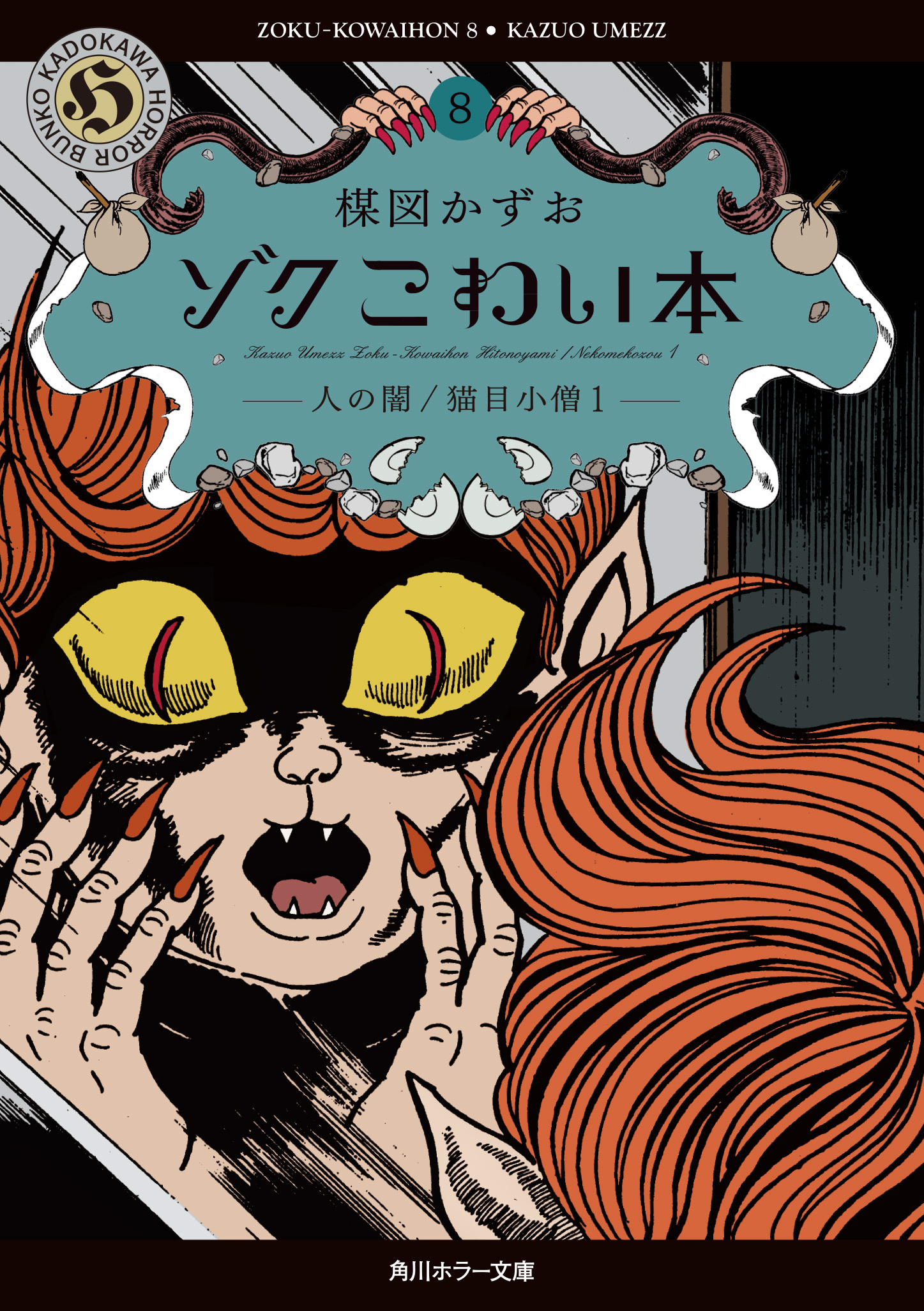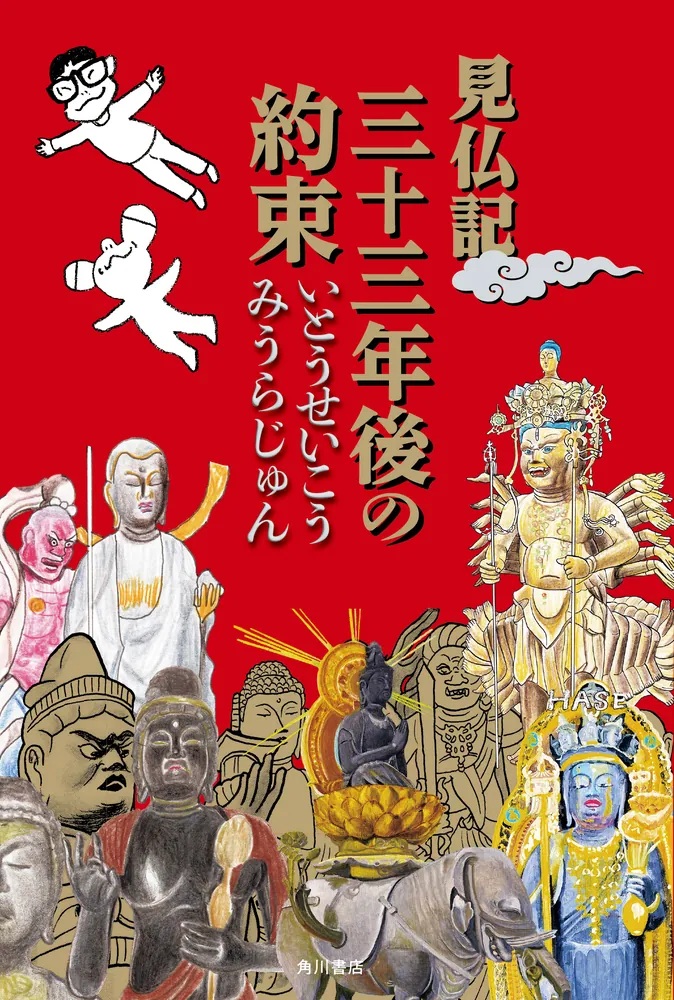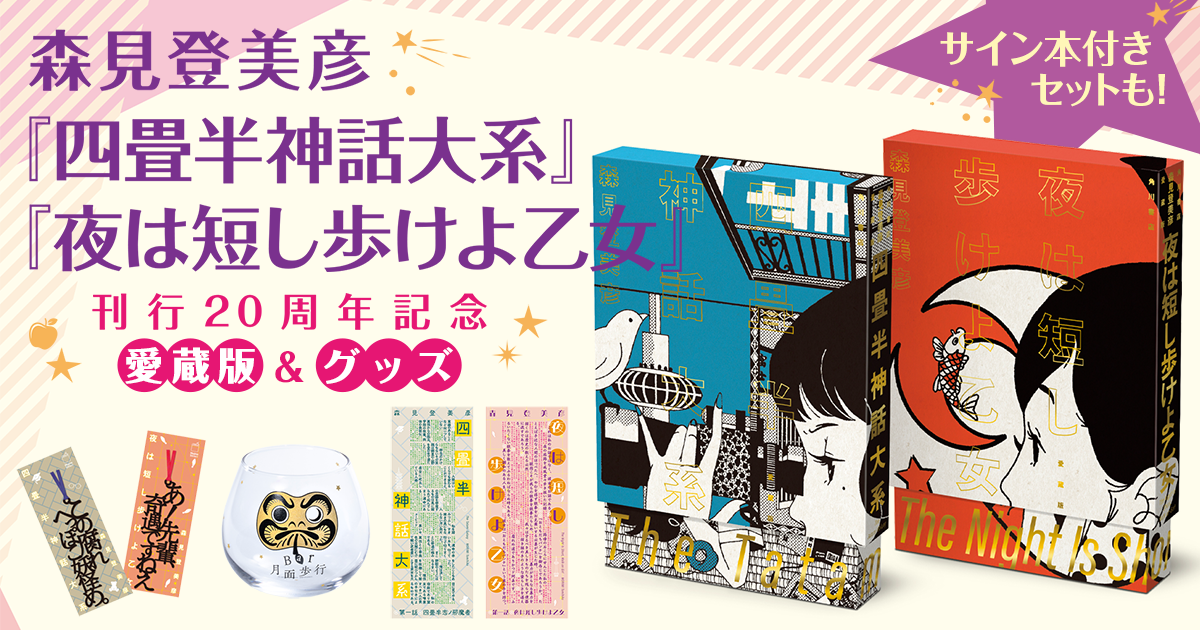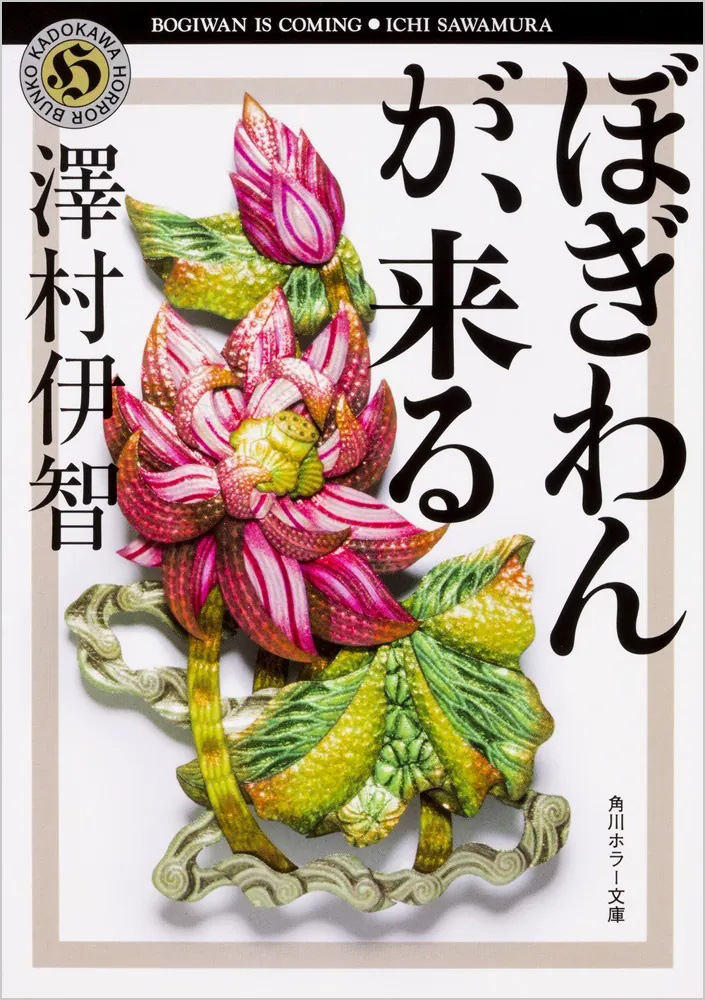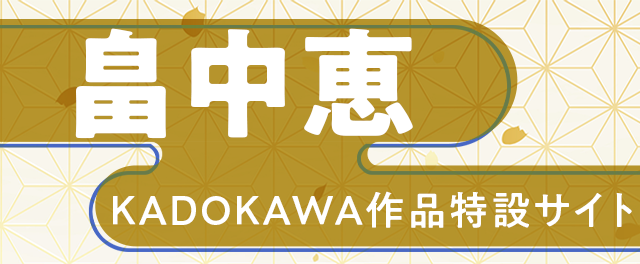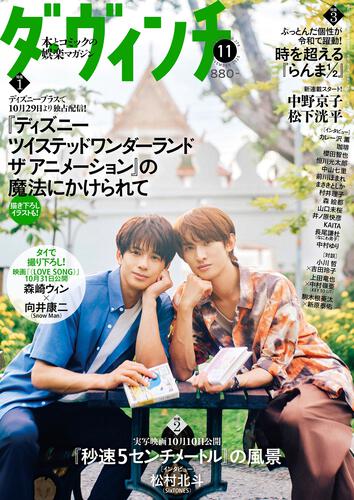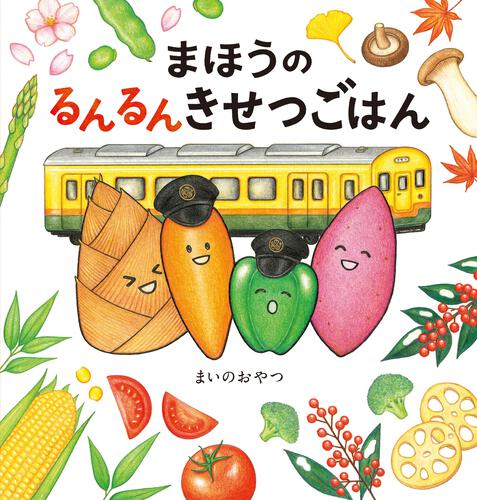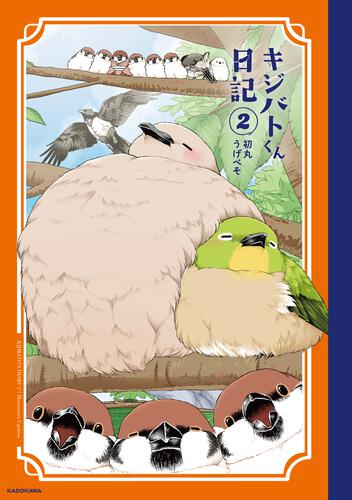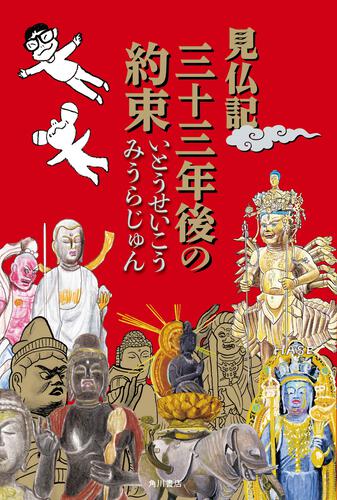文庫巻末に収録されている「おわりに」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(解説:平野 暁臣 / 岡本太郎記念館館長)
おわりに
世界をこの眼で見ぬきたい。
眼にふれ、手にさわる、すべてに猛烈に働きかけ、体当りする。
ひろく、積極的な人間像を自分自身につかむために。
窮極は、純粋に凝視する眼である。
まさに、そういう眼こそが現実を見すかし、現実の秘密を激しくえぐるのだ。
本書の冒頭に岡本太郎はそう書きました。
己れの「眼」をとば口に世界を洞観し、関係し、あえて衝突することで、フェアでアクティブな生き方をつかみ、世界の現実をえぐり出す。オレはそうやって生きていく。そう宣言しているのです。
この短い文章のなかに4回も登場するキーワード。それが「眼」です。
じつは本書に収録したテキストの過半は、1965年の1月から12月にかけて「週刊朝日」に連載されたエッセイで、当時のタイトルはズバリ〝岡本太郎の眼〟。
連載が終わると翌年に書籍化され(『岡本太郎の眼』朝日新聞社)、32年後の98年には、太郎の生涯にわたるパートナー岡本敏子が同書から抜粋したテキストをベースに『眼 美しく怒れ』(チクマ秀版社)を
じっさい「眼」は岡本太郎のトレードマークでした。リアルタイムで太郎を知る世代なら、〝岡本太郎〟と聞いたとたん、キッと眼を見開いて「芸術は爆発だ!」と叫ぶ、あの特異な情景を思い出すことでしょう。とりわけギリギリとエネルギーを放射する太郎の眼は、〝爆発おじさん〟のパブリックイメージを決定づける象徴的なアイコンでした。
作品づくりにおいても「眼」は重要なポジションにあります。まずはなんといっても絵にほぼ例外なく眼を描いていたこと。どの絵を見ても画題や意味は皆目見当がつかないけれど、画面に散らばる眼だけはわかる。描き込まれた無数の眼が、生命力をたぎらせ、群れをなして鑑賞者を
太郎にとって、眼は〝手〟とならんで現実世界をつかみとる中核的なメディアでした。
よく知られるように、縄文土器をぐうぜん目にしたことをきっかけに「縄文の美」を直観した太郎は、自然と闘い、自然と溶けあいながら誇らかに生きた縄文人の生きざまに「オリジナルの日本」を
こうして太郎は現実世界を自らの眼でつかみ、その本質を射ぬいていきました。その身体的な体験が作品や思想に結晶していったのです。
自分の眼で世界を「純粋に凝視」し、「猛烈に働きかけ、体当りする」。そして「現実を見すかし、現実の秘密を激しくえぐる」。それこそが岡本芸術を駆動する基本原理だったわけです。
反博? なに言ってんだい
岡本太郎はアトリエに引きこもって黙々と作品をつくるだけの作家ではありませんでした。たしかに一匹オオカミではあったけれど、視座はつねに社会にひらいていたし、視線はたえず大衆を見据えていたからです。
じっさい太郎ほど大衆社会とのコンタクトに情熱を傾けた作家はいません。数十作品にのぼるパブリックアートを全国にバラまき、
きわめつけは太陽の塔でしょう。太郎が引き受けたのは大阪万博のテーマプロデューサーであり、その職責はテーマ「人類の進歩と調和」をわかりやすく解説すること。あんな意味不明の巨像をつくって欲しいなどとはだれも頼んでいないのです。
しかし太郎は「人類は進歩なんかしていない。皆が少しずつ妥協する調和なんて卑しい」と公言し、あげくに勝手に構想した〝土偶怪獣〟を会場のド真ん中に突き立てます。すべては「産業技術の進歩が幸せな未来をひらく」という万博の近代思想に〝NON!〟を突きつけるためでした。
多くの文化人やアーティストが「反博」を掲げて万博ボイコットを呼びかけるなか、太郎は戦後最大の国家プロジェクトの中枢に陣取ります。それも「前衛芸術家がお上に
いま振り返れば、安全なスタンド席から旗を振っていただけの〝反博文化人〟たちに対して、太郎はひとりマウンドにおり立ち、からだを張って直球を投げたことがよくわかります。それが芸術の本分だと考えていたからです。「反博? なに言ってんだい。いちばんの反博は太陽の塔だよ」。太郎はそう言って笑っていたらしい。
このように太郎は次々に物議をかもす
いまや知る人は少ないけれど、じつは太郎のメディア進出はけっして大阪万博以降の〝爆発おじさん〟からではありません。60年代にはすでに一般の芸術家とは次元のちがうプレゼンスを確立していました。
教育番組でピカソを解説するいっぽう、雑誌の対談で大女優と恋愛論をたたかわせ、クルマの全面広告に登場したかと思えば、ヘリコプターでゲレンデに降り立つヒロイックな映像を電波にのせる。良くも悪くも太郎のあつかいは現代の「マルチタレント」そのもので、こうした立ち居振る舞いが〝異端の芸術家〟というイメージを醸成していった大きな要因です。
それだけではありません。文筆活動への並外れた創作意欲も、一般の作家とは決定的にちがっていました。太郎は戦後、芸術活動を再開した直後から途切れることなく文章を発表しつづけ、膨大な著作をのこしました。ほとんどが岡本敏子による口述筆記で、芸術論・文化論はもとより、恋愛論からスキー論にいたるまで、テーマは人間活動のおよそすべてにわたっています。
多くの美術作家にとって執筆はせいぜい余技であり、なかには邪道として毛嫌いする者もいますが、太郎にとって「言葉」は重要な戦略的手段であり、芸術運動の柱でした。おそらくは絵画や彫刻と等価だと考えていたにちがいなく、体内に湧きあがる創造の炎を外に吐き出すいわば〝
特徴的なのは、芸術論を超えたあらゆる問題を
なにしろ著書に「
もちろん太郎の性格と美意識によるものですが、もうひとつあるのは彼の芸術観です。社会の行方や世間の風潮に対して〝NON!〟を突きつけること。それこそが芸術家の責務だと考えていたのです。
あらゆる問題に発言し、憤り、憎まれ口をたたき、闘い、広い視野から、現代日本の生き方に食込んでみたい。
日本人とは何か、を考え、一般にこれが日本人だと安易に思いこんでいる形式をひっくりかえし、本来の姿をつきつけたい。
「はじめに」の一節にあるとおり、本書の底流にあるのは〝透明な怒り〟であり〝聡明な憤り〟です。矛先が向けられているのは日本と日本人。だれもが無意識・無自覚のうちに「そんなもんだろ?」「だって、昔からそうだったんだから」と思い込んでいる状況に
芸術とは、どう生きるか
伝統、青春、沖縄、教育、戦争、スキー、子供の絵……。軽妙な〝お正月論〟から真剣な死生論まで、本書で語られるテーマやジャンルはじつに多彩です。しかし読み進めていくうちに、すべてがひとつの問題意識のうえに立脚していることがわかります。
〝どう生きるか〟です。
「あなたは絵描きでありながら文章も書く。どちらが本職なのか」と問われて、「『人間』だ」と答えるくだりが出てきますが、それはけっしてレトリックではありません。
たしかに太郎は生涯にわたって数多くの作品を制作しました。しかも美術の
忘れてならないのは、それらには一貫した芸術思想が流れていること。
芸術とは一部の金持ちやマニアのものではないし、芸術主義者や伝統主義者のものでもない。後生大事にしまっておくようなものでもなければ、対価に応じてチビチビ小出しにするようなものでもない。芸術は民衆のものであり、日々の暮らしに生きるもの。芸術なんてなんでもないんだ。道ばたの石ころとおなじなんだよ──。誤解覚悟で言い切ってしまえば、それが太郎の芸術観です。
太郎は「芸術こそ生活なのだ」と言いました。ひっくり返せば「生活こそが芸術だ」ということです。芸術とは生活そのものであって、つまりは〝どう生きるか〟。だから「本職は『人間』」なのであり、それが芸術家・岡本太郎の本分、岡本芸術の本質なのです。
太郎がのこした膨大な作品群から最重要作をひとつ選べ。こう問われたら、ぼくなら迷わず「人間・岡本太郎」と答えます。岡本芸術最大の作品は、岡本太郎という存在そのものだと考えるからです。言い換えれば、太郎が生涯をかけてつくり上げたただひとつの作品、それが「岡本太郎」です。
本書で語られているのは、いわゆる芸術論ではなく社会論であり人生論ですが、太郎がそんなジャンル分けを意識していたはずがありません。それどころか、太郎にとっては「あらゆる問題に発言し、憤り、憎まれ口をたたき、闘い、広い視野から、現代日本の生き方に食込」むことも、「日本人とは何か、を考え、一般にこれが日本人だと安易に思いこんでいる形式をひっくりかえし、本来の姿をつきつけ」ることさえも芸術でした。そう考えれば、本書だって、まぎれもなく岡本太郎の芸術論なのです。
岡本太郎という生き方
いま若い世代に太郎への共感の輪が広がっています。〝動く岡本太郎を見たことがない〟10代20代の若者たちが、太郎に熱い視線を送っているのです。
ここでも大きな役割を果たしているのは「言葉」です。巨大なスケール、強烈な色彩、エネルギーの躍動、生き生きとした生命感……といった作品のインパクトに加えて、太郎から放たれる言葉の圧倒的な強度と熱量が若者たちをとらえているのです。
言葉にウソも
思ったことは言う。言ったことはやる。
愚直なまでの、このシンプルな言行一致が太郎の信条でした。自らの信ずる生き方を駆け引きなしで世間にさらし、それをそのまま人生を
なんてカッコいいんだ。いまこそそういう生き方をすべきなのに、まわりの大人たちは打算と保身しか考えていないじゃないか。できることなら太郎のように生きたい。もし太郎みたいな人間になれたら──。
太郎に惹かれる若者たちの気分はよくわかります。強く潔い生き方に鼓舞されると同時に、純度の高さが
これがオレだ! という決意と誇り。それを太郎は〝スジ〟と呼びました。生きている以上はつらぬくべきスジがある。自分の生きるスジはだれにも渡してはならない。そんな使い方です。
南青山の岡本太郎記念館には連日多くの若者が訪れますが、きっとそれは〝スジ〟の気配がいまも生々しくのこっているからでしょう。「血が沸きたった」「壁にぶつかったらまた来ます」と笑顔で語る彼らを見ると、〝生きるスジ〟を求めて日々もがいていることがわかります。
戦後日本で活動を開始したときから死の瞬間を迎えるまで、岡本太郎は一貫して〝スジ〟をとおしました。言うこともやることも、おもしろいほど変わっていません。盟友・花田清輝が言うように、まさに「
人間とはなにか、芸術とはなにか
本書に収録したテキストは、そのほとんどが半世紀前に書かれたものです。「全学連」や「アカ」など、すでに死語になっている事柄が無いわけではないけれど、語られていることはちっとも古くない。それどころか、いまこそ読むべき提言であり、いまの時代にこそ必要なアイデアばかりです。
太郎の文章がいつまでも古くならず、時代を超えて心に響くのは、彼の言葉がすぐれて普遍的だからです。太郎と同時代を生きた世代のなかには、テレビ映像の表層イメージから「奇矯な言動を売りにしたパフォーマー」くらいに思っている向きもあるようですが、じっさいは逆。太郎はウケを狙って奇をてらったり、突飛な思いつきで衝動的に行動するタイプの人間ではありません。それどころか、頭のなかにあるのはものごとの本質、根源、原点だけ。語っていたのはすべてほんとうのことであり、しごくまっとうなことを言っていただけなのです。
半世紀の時空を超えて、太郎の言葉はぼくたちの胸にまっすぐ届きます。むしろ先の見えない不安な時代だからこそ、ズシッと響くのかもしれません。そして読み進むうちに、いつのまにか自信が湧いてきて、誇らかな気持ちになる。不思議な感覚です。
やっと時代が太郎に追いついた。そう言う人もいるけれど、ぼくの見方は少しちがいます。追いつく対象ならやがて追い抜かれるはずだけれど、けっしてそうはならないと考えているからです。
再生を果たした太陽の塔が50年のときを超えてぼくたちを挑発するのは、太郎が未来を先取りしていたからではありません。太郎は生涯をとおして「人間とはなにか」「芸術とはなにか」を考えつづけただけです。
人間の本質は千年や二千年では変わりません。太陽の塔がいつまでも古くならないのは、きわめて高度な普遍性を備えているから。おなじように太郎の言葉も古くなりようがないのです。
▼岡本太郎『岡本太郎の眼』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322002000934/