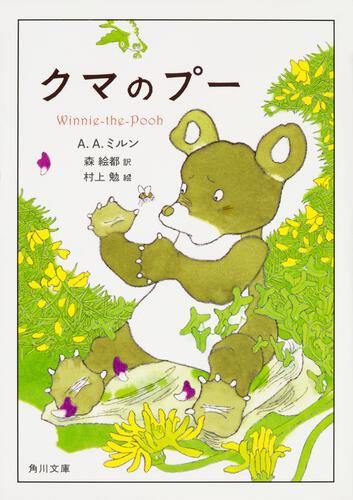一九世紀から二〇世紀初頭にかけて全盛をきわめた英国において、いまなお時代と世代と国境をこえて愛され、読み継がれている子ども(とおとな)のための文学がつぎつぎと生まれた。
〈未熟なものへの説諭〉をおのれの使命とするそれまでの児童書と異なり、ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』、エドワード・リアの『ノンセンスの本』、J・M・バリーの『ピーター・パン』、ケネス・グレアムの『たのしい川べ』は、きびしい教訓を説かず、〈子どもへの娯楽〉という側面を遠慮なく打ちだした。当然ながら子どもたちはアリスの冒険に心を奪われ、リアのノンセンス詩を口ずさみ、夜ごとネヴァーランドへと旅立ち、川べの動物たちとともに泣き笑いした。
『クマのプー』は英国児童文学のいわゆる黄金期の一角をなすと思われがちだが、ほかの作品よりやや遅れて、一九二六年、いまから九〇年ほど前に誕生した。思いのほか長引いた第一次大戦で消耗した英国は、もはやかつてのように吞気に牧歌的な楽園を讃美できる心理状態にはなかった。作者ミルン自身も従軍し、塹壕戦で辛酸をなめている。にもかかわらず、この作品には古きよき時代を懐かしむがごとき古風な味わいがある。〈遅れてやってきた〉作品だからなのか。
幅広い年齢層の読者を対象におこなわれた英国の調査(二〇一六年)によると、クマのプーさんが、二位のハリー・ポッターを大きく引き離し、あまたある児童文学でもっとも人気のある主人公の栄誉に輝いた。
原作の挿絵の魅力はいうまでもなく、ディズニーアニメによるキャラクター化とも相まって、日本でも抜群の認知度を誇る『クマのプー』だが、その原作者A・A・ミルン(アラン・アレクサンダー・ミルン、一八八二―一九五六)が劇作家として名を成した人物であり、クマのプー・シリーズが二冊の物語と二冊の詩集から成ることは案外知られていない。そこで、まず、プーの世界の原点を求めて、作者の生い立ちをたどってみたい。
一八八二年一月一八日、ミルンはロンドン北部、現在はセント・ジョンズ・ウッドと呼ばれる地区で、男子のための小さな私立学校を経営するジョン・ヴァイン・ミルンとその妻マライアの末子として生まれた。理解ある両親の愛情に包まれ、ふたりの兄たちとともに、元気で利発な少年に育った。
父のジョンは、もと教師だった妻とふたりで、学校の経営と生徒の教育に心を傾けた。「愛情のない教室は、きびしく、心をくじく。だが、愛情があれば、教室は家庭についで良い場所になりうる」。校長ジョンのこの信念にもとづき、形式的で無意味な規則で子どもを縛ることのない、当時としては開明的な学校運営がおこなわれた。末っ子アランが、父の学校に入学した兄たちが羨ましくて、自分もはやく入学させてと父にせがんだほどに。
あるとき、校長は「この世でもっとも美しいと思うものを挙げよ」という作文の課題を与えた。「習ったことを書かせるのではなく考えさせる」狙いがあった。「笑顔の子ども」と書いた生徒の解答用紙には、「わたしもです」という校長のコメントが添えられて返却された。
父は息子たちにできるだけ戸外で活動し、自然をじっくりと観察せよと勧めた。「自然の女神の展覧会はすごいぞ。お休みなしで、お代はただ」と。
アランはとくに次兄ケンと気が合い、父の言葉を忠実に守った。朝早く起きると、まだ寝静まっている街路でフープ回しをしてから朝食のために家に帰ったり、竹の棒を振り回して戦いごっこをしたりと、楽しく充実した子ども時代を満喫したのだった。
現在のセント・ジョンズ・ウッドは、ケンジントンやチェルシーと並ぶロンドン屈指の高級住宅街だが、アランの少年時代はロンドンの北のはずれで、すぐそこまで野原や森が迫っていた。まだ幼いアランはケンとふたりきりで、当時は先端的な乗り物だった自転車をロンドンの市内で走らせ、週末には郊外への遠乗りにもでかけたものだ。また、家族そろって避暑地で毎夏の休暇をすごし、徒歩旅行にでかけた。
アランが八歳九か月のとき、父と兄たちに同行したサセックス州のアッシュダウンの森への徒歩旅行では、三日間で七〇キロ以上を踏破した。後年、この森が世界にその名を轟かせる物語の舞台になるなどと、このときのだれに予測できただろうか。
語り手としてアランに範を示したのは、暖炉の前で幼い息子たちに物語を朗読してくれた父である。週日は『狐のレナード』といった動物寓話やジョージ・マクドナルドの創作おとぎ話、日曜日はジョン・バニヤンの『天路歴程』と決まっていた。自分で本が読める年齢になると、アランは『宝島』『ビーヴィス』『スイスのロビンソン一家』といった冒険物語を読みふけり、戸外の生活や無人島に思いをはせた。家族の温もりは心地よく、癒されたけれど、自立心の強い少年アランにとって、自由はもっとたいせつだった。
一八九三年、一一歳半にして、伝統あるパブリック・スクールのウェストミンスター・スクールに奨学生として進学する。しかし試験での不当な評価に反発し、得意だった数学に興味を失い、図書室でディケンズやジェイン・オースティンの小説を読みあさる。一足先に学業を終えて事務弁護士見習いになっていた次兄ケンと合作で軽妙詩を作るのが、当時の趣味だった。試験の不本意な結果が、間接的にせよ、アランに文学を生業に選ばせるきっかけとなったのだ。
一九〇〇年、名門ケンブリッジ大学トリニティ学寮に入学すると、一八八九年創刊以来、ジャーナリズム界の名士を輩出していた学生雑誌「グランタ」に投稿した作品(ケンとの合作「愛についてのソネットその他」)が掲載される。
一九〇二年、当誌の編集長となり、各号の誌面のほとんどを自分の文章で埋めた。ユーモア作家として機知と嗅覚を磨いた修業時代である。苦労は報われた。有名な風刺雑誌「パンチ」の編集長に才覚を買われて、卒業後はフリーランスを経て、「パンチ」の副編集長に就任する。
一八四一年の創刊当時は反体制的で過激な政治批判で鳴らした「パンチ」だが、その後、軌道修正がなされ、ミルンが大学生のころには、風刺の毒が抜けて、ちょっと粋で楽しい「国民的読み物」として、広く保守中流の読者層に読まれていた。ミルンが同誌に寄稿した数々の記事は、のちに数冊の随筆集にまとめられて人気を博した。
「パンチ」の常連寄稿者だった一九〇五年、ミルンは生涯を決定する出会いに恵まれる。すでに劇作家・小説家として不動の地位を築いていた『ピーター・パン』の作者J・M・バリーとの友情である。劇場で『ピーター・パン』を観て感激したミルンは、作者バリーの知己を得て、バリーのクリケット・チームの一員になる。劇作家志望のミルンの才能を見抜いたバリーは、二〇歳以上年下の新進作家A・A・ミルンをロンドン演劇界に紹介する。
J・M・バリーとA・A・ミルンには共通点が多い。ともに一九世紀後半から二〇世紀前半のイギリスで活躍し、児童文学の名作を著したが、いずれも児童文学作家をめざしたわけではない。ふたりともジャーナリスト出身で、ウェルメイド・プレイの系譜に属する軽妙な戯曲を世に送りだし、劇作家としてつとに人気と名声を得ていた。
ミルンが才能を開花させた二〇世紀初頭とは、いかなる時代だったのか。ミルンの文学的特徴に、この時代がいかなる影響をおよぼしたのか。
一九〇一年、ミルンが大学に入学した翌年、ヴィクトリア女王が亡くなり、長らく皇太子だったエドワード七世が即位する。功利主義の追求と無限の進歩を肯定したヴィクトリア時代は、裏返せば、説教じみた画一的な価値観念を押しつける抑圧の時代でもあった。
女王の逝去とともに、イギリスは心理的な頸木から解放されたかのように、楽天的で審美的な気分を求めるようになった。謹厳実直な母ヴィクトリア女王と対照的に、遊び好きの粋人エドワード七世の個性は、そのまま、エドワーディアンと称される一〇年間の治世の特徴でもある。
この浮き浮きした高揚感は第一次大戦の勃発前夜までつづく。J・M・バリーもA・A・ミルンも、無邪気で享楽的な生にあこがれるエドワーディアンの風潮に敏感な作家だった。
こうした英国全体の雰囲気のなかで、ミルン本来のたくまざるユーモアのセンスはのびやかに開花し、それがのちにクマのプー・シリーズを誕生させる原動力となったのだろう。
折しも一九一四年、第一次大戦が勃発する。もともと平和主義を信奉していたミルンも、挿絵画家E・H・シェパードや多くの同時代人とおなじく、「あらゆる戦争を終結させるべく戦列に加わる」と宣言する。翌年、高邁な理念を胸に、みずから志願して兵士となる。しかし、四年にもおよぶ辛い経験は、ミルンに生涯消えぬ深い傷を残した。後年、あの苛烈にして無意味な四年間を、「あの精神的・道徳的頹廃の悪夢」を抹消できたらと慨嘆する。とはいえ、朗報もあった。一九一七年、試練の戦時期に自作の戯曲がはじめてプロの劇団により上演される。その後、やつぎばやにヒット作をくりだし、劇作家として揺るぎなき地歩を固めたのである。
人気劇作家のミルンは、一九二四年、詩集『ぼくたちがとても小さかったころ』(When We Were Very Young,邦訳『クリストファー・ロビンのうた』)で、子ども部屋の詩人として華々しいデビューを飾った。友人の勧めで軽い気持ちで執筆したのだが、出版するなり大当たりをとったのである。セレブリティの概念がなかった時代に、父と息子はちょっとした有名人に祀りあげられ、新聞や雑誌でもてはやされた。とりわけモデルとみなされたクリストファーは人気者となり、本人もまんざらではなかった。すくなくとも最初のうちは。
翌二五年、「イヴニングニュース」紙のクリスマス・イヴ号に、クリストファー・ロビンとテディベアをめぐる書き下ろしの物語が掲載される。これが『クマのプー』第一章の原型となる。もっとも、挿絵を描いていたのは、今日、なじみ深いE・H・シェパードではない。クリストファー・ロビンも、シェパードのやや古風な佇まいの、華奢で女の子と見まがう中流階級然とした長髪ではない。J・H・ダウドの描くクリストファー・ロビンは、Tシャツのようなものを着て、がっちりした男の子らしい体型で、階級は特定できない。
そもそも、プーとはなにものなのか。複数の次元において曖昧である。くまなのに、本物ではない。ぬいぐるみである。もっとも、たいていの生きたくまより、はるかに生き生きしてはいるけれども。ミルンの息子クリストファーは、老舗デパートのハロッズで両親が購入したぬいぐるみのくまを与えられた。ところが、E・H・シェパードの挿絵に登場するくまは、じつは、このくまではなくシェパードの息子のくまらしい。
さらに、物語でプーの兄貴分を演じるクリストファー・ロビンは、ミルンの息子をモデルにしているが、クリストファーそのひとではない。生身のクリストファーとぬいぐるみの動物たちが、現実の森のようでありつつも、そうともかぎらない幻想の森で、たいてい笑いながら、ときには笑われながら、無邪気にくりひろげる遊びの世界とみえて、そうでもない。ほのぼのとした印象にくるまれて、さまざまな次元が、ゆるやかにオーバーラップする。事実と虚構の境界線がたくみに抹消され、時間と空間の境界線があえて錯綜する。
プーの素朴さにつられていかにも単純とみえるけれども、じつは手練れの劇作家ミルンの面目躍如というべき絶妙な造りの物語といってもよい。
一九二六年当時、粋で洒脱なエッセイそのままに、軽妙な知性と逸らさない人柄ゆえに、ミルンは文壇や出版界に広い人脈を張りめぐらせていた。
家庭的にも恵まれて、妻ドロシーとひとり息子クリストファーとともに、ロンドンの高級住宅地チェルシーにある自宅とアッシュダウンの森近くのコッチフォード・ファームを行き来していた。洗練された都会の文化を愉しみ、のどかな田園の自然を愛でるという、いわばいいとこどりの生活は、ある意味で中流イギリス人の理想であり、ミルンは筆一本でこの生活を手にいれた。
同年一〇月、『クマのプー』(Winnie-the-Pooh)は出版と同時に大評判となり、ミルンはいよいよ知名度をあげる。
しかしミルンは、翌二七年の二冊目の詩集『さあぼくたちは六歳』(Now We Are Six,邦訳『クマのプーさんとぼく』)、さらに二八年の二冊目の物語『プー横町にたった家』(The House at Pooh Corner)の出版をもって、ひとまずプーと決別するつもりだった。ところが、そうはいかなかった。プー物語の凄まじいほどの人気に、自分のこれまでの作品が忘れ去られるだけでなく、物語に登場させた息子とのあいだに生じた確執が自分の死までつづくことになろうとは、さすがのミルンも想像できなかった。
子ども、ぬいぐるみのくま、そして舞台となる森。のんびりおっとりした冒険のおぜん立てがそろい、ミルンはぬいぐるみを使った息子と妻の遊びを書きとめた。
時間の止まったような戸外の遊びは、たしかにアッシュダウンの森を彷彿させる。だが物語そのものには一九世紀末の時代があきらかに刻印され、ミルン自身の快活な少年時代の息吹が感じられる。ロンドン北部で小さな私立学校を経営する父の薫陶をうけた少年のミルンは、フープ遊びや自転車に興じ、犬と戯れ、チクチクするハリエニシダが茂るプーの森への徒歩旅行にでかけた。次兄ケンとの健康的で大胆な遊びにあふれた子ども時代をすごした。この点で、一人っ子のクリストファーとは異なる。
息子の誕生に触発され、ミルンのなかでみずからの子ども時代の記憶がよみがえり、ノスタルジックな物語へと結実したのではないか。物語が執筆された時期にしてはどことなく古めかしく、いささか時代錯誤的な味わいさえするのはそのせいか。プーがミルンの子ども時代にやってきたのか、ミルンがプーの世界に入りこんだのか。プー物語の真骨頂とは、「プーのはなうた」のような、ほどよくいい加減な曖昧さにあるのかもしれない。
亡くなる数年前の一九五二年、ミルンは「ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン」紙の依頼で韻文の自伝を著す。最後の二連はこうだ。
作家たるもの、なぜ書かぬ、
目に入ることども、そのすべて。
されば――子どもの本、というわけで、
一種の間奏曲気どり、
書いたときには考えもせず、
ペンとインクの日々の汗、
かき消えるとは、この四冊の
子どものためのおもちゃの陰に。
作家が語る胸のうち――
傑作ばかりはとても無理。
お説教が受けまいと、
ユーモアがいっかな通じまいと、
それでもなおかつ愉しいものだ、
書くとはよろこびつきぬもの。
古い古い農家に憩い、
このしあわせな冒険は、
そろそろおわり(そうだと思う、
いまやわたしも七〇歳)。
しめて、年々歳々愉しんだ。
それだけは疑いもなく。
いささか自虐的な物言いながら、最晩年に作家ミルンはみずから構築したプーの世界を受け入れ、そこに慰めをみいだした。
プーが誕生九〇周年を超え、ミルン没後六〇周年を超えたいま、あらたな訳があらたな挿絵とともにこの世に生まれ、あらたなプーが読者のみなさんのもとに届けられたことは、大いによろこばしい。プーはいつの時代もちょっぴり古めかしくて、しかも、いつだって新しい。時代に寄り添いつつも、ちょっとだけズレている。それこそプーがプーである所以なのだから。