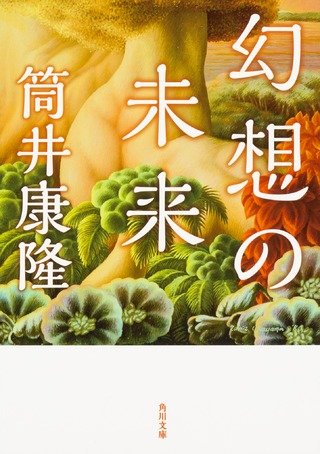涼宮ハルヒという名詞がついたタイトルの文庫本が文庫の売れ筋ランキングでずらずらずらずらと上位を占めはじめたことに気づいたのはもう何年前になるだろう。シリーズとして十巻十一冊が並んでいて、それぞれが何十版も版を重ねていることにずいぶん驚いたものだ。ちょうど文芸書の売上げ低迷が続いていておれの本も滅多に重版がかからなくなっている時だったから、これはずいぶん羨ましかった。調べてみるとそれまでも何度か耳にしたことがあるライトノベルという種類の小説であるらしい。そして文庫のランキングを見ると「涼宮ハルヒ」シリーズを書いた谷川流以外の作家のライトノベル(以下ラノベと略称)も、結構版数を伸ばしているのである。大文豪でありながら言うまでもなくそもそも節操のないおれであるから、ようしおれも書いてやれ、書いて版数を伸ばして大儲けしてやれと思ったのは当然のことであったろう。しかしそのラノベとはいったいどんな代物なのか。それを知らないままに書くことはできないので兎にも角にも「涼宮ハルヒ」シリーズの第一作目とされる「涼宮ハルヒの憂鬱」から読み始めた。と同時にこの作品がどの程度ジャンルの定石を踏襲しているかを知るために、ラノベが一般にどう定義づけられているかについても調べた。まずは読後の感想を述べる。
「涼宮ハルヒの憂鬱」はラノベである以前に優れたユーモアSFであるということだけはまず言っておく。最初のうちは性格的に周囲と乖離している女子高校生を主人公にした青春ドラマかと思いながら読んで行くうち、だんだんとんでもないことになってきて、語り手のキョンと綽名で呼ばれる少年を除く副主人公たちがそれぞれ宇宙的な組織から派遣されているAI、未来から来た少女、正体不明の機関に所属する超能力者であることがわかってくる。ここで物語は青春ドラマから一挙にラノベで言うところのセカイ系なる物語となり、副主人公それぞれがSF的ペダントリイを駆使して語るのだが、このあたり作者はSFの知識を充分に咀嚼していてなかなか堂に入ったものだ。つまりこの作品はわざわざラノベを呼称することもない立派なSFであると言えるのだが、ラノベの読者が冀求するコミックやアニメのキャラクター類似の美少女たちをちゃんとキャラクターにしていて、またそうした所謂萌え絵を表紙や挿絵で描いているという最低限のラノベの定義を踏襲している以上は、やはりSFというよりはラノベに分類されるべきものなのであろう。一方で前記セカイ系という評論家東浩紀によって提唱された呼称の意味は、例えばこの作品の場合は、語り手も含めた主人公たちによる小さな関係の話が、世界の危機とかこの世の終りといった大問題に発展してしまう小説のことであり、これもみごとにセカイ系の定石を踏襲しているのだ。
この作品は株式会社KADOKAWAが主催するスニーカー大賞を受賞し、スニーカー文庫に収められている。そして前記のように「涼宮ハルヒ」シリーズ最初の作品である。よくここまで定義を守ってジャンル内で屹立した作品に仕立てあげたものだと感服する。これが受賞した第八回では選考委員たち全員が推したというのも頷けることだ。特に感心したのは、これがシリーズ化されることを見越して書かれていることだ。最近はラノベのコンテストにおいて特にシリーズ化を意識したような作品が多いらしいのだが、この「涼宮ハルヒの憂鬱」に限って言うならばさほど引きネタが目立つわけでもない。そのあたりが作者の目配りのよさだろう。強いて引きネタと言えそうなものは悪役の朝倉涼子が姿をくらますところで、のちのち再登場があることを半ば予告的に書いていて期待を持たせるのだ。そして読者がいちばん再会を望むのは勿論、萌えキャラの朝比奈みくるである。この時をかける少女は「未来で待ってる」と言わんばかりに二十歳前後の成長した姿でちらりと登場し、のちの再登場をいやが上にも期待させるのである。
しかし何よりもこの作品の大きな魅力は、主人公涼宮ハルヒのエキセントリックなキャラクター造形にある。この美少女は男を男とも思わず、自分の興味の赴く方向にしか行動せず、その志向するところがどれだけ一般と異なっていようとかまうことではないというとんでもない性格の持ち主であり、なぜそんなキャラがこの世に発生したかの謎が明かされてからはそれをきっかけとして物語が大きく変貌し、読者を多元的な異世界へと否応なしに引きずり込んでしまうのだ。
こうして涼宮ハルヒとそのレギュラーによる物語の読者は、「涼宮ハルヒの憂鬱」に続く「~の溜息」「~の退屈」と読んできて、突然それまでと明らかに雰囲気の異なる「~の消失」に遭遇する。この第四作についての詳細を未読の読者のため明らかにすることができないのは残念だが、それまでの単なるSFとは違って不条理感のあふれる純文学的要素が極めて強く、読者はある種の感動に襲われる。この感動の存在は強ち小生だけではなくわが周辺の編集者たちによる「シリーズで一番の傑作は『~の消失』だ」という意見の一致で証明されるだろう。そしてこの感動は最初から「~の消失」だけを読んだからと言って生まれるものではない。シリーズを順に読んできて第四作目に到り、やっと生まれる感動なのである。つまりは、まるで友人や家族のように涼宮ハルヒとそのファミリーにつきあい、何もかも知り尽くし、そのストーリイを日常のように思いはじめているさなかに突然やってくる衝撃なのだ。この第四作がなければ、あるいは小生、自分もラノベを書いてやろうなどという気は起こさなかったかも知れない。即ち如何によく売れていようとこれは自分の書くべきジャンルではないと決めていたかもしれないのだ。にもかかわらず書こうと決意させたのは他でもない、この作品によって、ラノベでも文学的主張が可能なのだと知ったからであった。
ではどのようにしてラノベに文学的主張を盛り込むのか。それはまさに谷川流が最もラノベらしいラノベをと志向したことを反転させ、ラノベでありながらラノベらしさを逆手にとって読者の意識を宙吊りにすることである。そうすることによってラノベというジャンルを越境し、読者にある種の不安を齎し、精神の一隅に文学的不安の種を蒔こうと企むのだ。言い換えればメタラノベとでも言うべき、ラノベを批評するラノベなのだが、それが成功しているかどうかは小生唯一のラノベたる「ビアンカ・オーバースタディ」をご一読願いたい。他の著者の作品の解説で自作の宣伝をするなど本来以ての外の行為ではあるが、小生が「涼宮ハルヒ」シリーズに触発されて「ビアンカ~」を書いたことはよく知られているから、この解説がこうなることは著者も編集者も一部の読者も予想していたことであった筈だ。ここから先のなりゆきは拙著「ビアンカ~」のあとがきに詳しいので、評判になった「太田が悪い」のフレーズも含めて、そちらをご覧いただきたいものである。
さてこの度本書はスニーカー文庫から本来の角川文庫へと移ることになり、その機会に小生が解説を書くことになったのだが、これを以てしても本書がもはやラノベの域にとどまらず、文芸的な小説として認められたばかりでなく、文壇的事件として文学史の一頁となったことを示している。
尚、前記「書いて版数を伸ばして大儲けして」やろうという小生の卑しい目的は達することができたかどうか。残念ながら数十万部とはいかず、いささかがっかりであったが、版を重ねて十万部には近づいたのだから、まずまず近頃にない収穫であったとは言えるだろう。
レビュー
紹介した書籍
関連書籍
おすすめ記事
-
特集
-
連載
-
試し読み
-
試し読み
-
特集