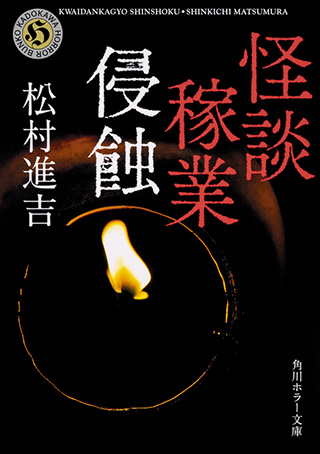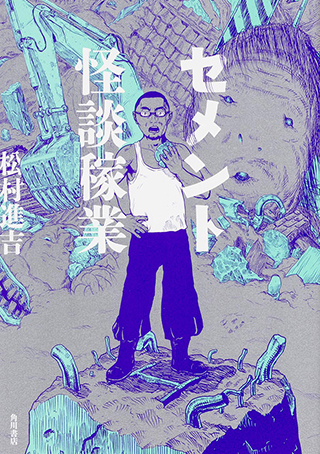環太平洋規模で噴火や地震が相次ぐ不穏な昨今だが、怪談実話の世界でも、ここ数年来、大規模な地殻変動が進行中である。
ちなみに、ここでいう「怪談実話」とは、実話怪談とか実録怪談などと業界内外で通称されている、あのどこか胡散臭くて、それでいて魅力あふれるジャンルの正規の名称である。
え、正規? べつに実話怪談でも怪談実話でも、どっちでもいいじゃん!
……と不審に思われる向きもあろうが、ちょいと考えてみていただきたい。
たとえば怪談映画や怪談漫画といったジャンル名を、映画怪談とか漫画怪談などと前後を入れ替えて表記したら、意味合いが変わってしまうのは一目瞭然だろう。
映画怪談とは映画がらみの怪談――たとえば自分が出演した憶えのない怪奇映画の噂に翻弄される女優の不安を描いた文豪・谷崎潤一郎の名作「人面疽」のような作品のことだし、漫画怪談といったら……それを読んだ人間が怪異に見舞われる呪われた漫画作品や、漫画家の身に妖しい出来事が起きる類のメタな話が想起されるだろう。
したがって、ジャンルの呼称としては、実話怪談や実録怪談ではなく、怪談実話と表記するのが妥当というか真っ当な人の道なのである。
どうして私が、そんなことに拘るようになったのかといえば、二〇〇四年に怪談専門誌『幽』を創刊するに際して、「怪談小説・怪談漫画・怪談実話を三本柱に据えた総合的な怪談専門誌、誕生!」という煽り文句を案出するにあたり、小説や漫画といった隣接ジャンルも視野に入れて、この分野を眺める必要に迫られたという、いたって即物的な理由ではあるのだけれど。
さて、本書巻頭の「みだりに長い前口上」みたいに思わず前置きが長くなってしまったが、その『幽』で松村進吉が、二〇一二年末から連載を続けている「セメント怪談稼業」をまとめた怪談実話集の第二弾が、本書『怪談稼業 侵蝕』である。
角川ホラー文庫には初参戦となることもあり、ここで著者の作家としての歩みを手短に振りかえっておこう。デビューは二〇〇六年、怪談実話に特化した文庫シリーズの老舗である竹書房文庫で開催された著者発掘コンテスト「超―1」で、応募作が第一位を獲得。以後、同シリーズの看板というべき〈「超」怖い話〉シリーズの中心的な書き手の一人として活躍してきた。生まれ育った徳島で家業の建設土木作業に従事しながら、兼業怪談作家を続けている。ユンボと呼ばれる大型工作機械を、ガンダム乗りさながら自在に操る特技を有するとか。いっぺん見てみたいと思いながら、まだ果たせずにいる。
私が松村作品に注目したのは、『異聞フラグメント 切断』(二〇一〇)あたりからだったように記憶する。
そこには、自身のルーツでもある〈「超」怖い話〉シリーズの定型の呪縛から、何とかして抜け出そうとする野心と気概が、嬉しいくらい満ち満ちていたのだった。
もっとも、その意欲と情熱は、必ずしも常に成功しているとはいえず、力が入りすぎて空回り気味な作品も目についたのだが、そうした試行錯誤も含めて、怪談実話の新たな展開をがむしゃらに模索しようとする姿勢に、とても好感を抱いた。
『幽』での「セメント怪談稼業」連載開始は、まさしく、そうした試みの延長線上に位置づけられるものだったといえよう。
当時の『幽』における実話連載陣は、〈新耳袋〉的なスタイルを文学的にブラッシュアップして継承した感がある名手・福澤徹三、〈「超」怖い話〉の定型となるショッカー手法を確立した平山夢明、怪談史学のスタンスから独自の考証的スタイルを追求する小池壮彦、いわゆる視える書き手であると同時に練達のドキュメンタリー作家でもある工藤美代子、山の怪談のエキスパート安曇潤平など、それぞれに独自の方法論を有する一騎当千の猛者たちであった。そこに平山が抜けた後を継ぐ形で、新進気鋭の松村が抜擢されたわけだ。
連載を始めるにあたり、おそらくは相当なプレッシャーがあったことと察せられる。しかしながら松村は、われわれ編集サイドも予期しなかった驚くべき発想の転換によって、見事、期待に応えてみせた。
すなわち「怪談実話にして私小説」という、一見すると、水の中で火を点すかのごとき試みの実践である。
私小説についての定義はさまざまだが、ここでは分かりやすい説明例として、三省堂版『スーパー大辞林 3.0』の語釈を引用しておく。
「作者自身を主人公とし、自分の生活や経験を虚構を排して描き、自分の心境の披瀝を重視する日本近代文学に特有の小説の一形態」
いかがであろう。すでに本書を読み終えた方ならば、「作者自身を主人公」「虚構を排して描き」「心境の披瀝を重視」といった、右に指摘されている私小説の特質のいちいちが、本書にも見事に当てはまることにお気づきだろう。
誤解されている向きもありそうだが、書き手の体験や所感をありのままに描いて、文学作品として成り立たせることは、決して容易な技ではない。むしろ、程よく虚構を交え、フィクションの衣をまとわせたほうが、はるかに書きやすいし、読者の興趣をつなぎとめやすいはずなのだ。厳然たる事実を事実として、ありのまま作品化することは、並々ならぬ技倆と熟慮を必要とする文学的営為なのである。
おや、と思われただろうか。そう、これは私小説のみならず、怪談実話においても本来、必須の課題であるはずだ。
たとえば男女の情痴であれ、骨肉相食むいざこざであれ、赤貧洗うがごとき生活苦であれ、あるいは死霊生霊との遭遇であれ、人形の祟りであれ……書き手が直面する何らかの事実(とされる出来事)を、能うかぎり「あったるがまま」に、ありありと読み手に伝える文芸という点においては、私小説と怪談実話は奇妙な相似形を成しているのであった。
その意味で本書の作者が、怪談実話のリアリティをとことん突き詰めようとした果てに、怪談実話にして私小説というスタイルに到達したのは、理の当然といえるかも知れないのである。
いみじくも、単行本として刊行された前作『セメント怪談稼業』(二〇一四)の推薦帯文において、京極夏彦氏が「怪談実話がこの方向に舵を切るのは必然。もう後戻りはできませんね」と喝破されていたように。
ここで冒頭の話題に戻る。
現在進行中の怪談実話の地殻変動――新たに台頭してきた注目作家たちに共通する傾向を抽出するならば、「文芸志向」および「ルポルタージュ志向」ということになるのではなかろうか。
たとえば黒木あるじや郷内心瞳や小田イ輔ら、みちのくの実話作家たち、あるいは『里山奇談』の共著者トリオ(coco、日高トモキチ、玉川数)には文芸志向が顕著だし、怪談実話本としては空前の大ヒットとなった『山怪』の田中康弘をはじめ、『禁足地帯の歩き方』の吉田悠軌、『出没地帯』の川奈まり子らにはルポルタージュ志向が躍如としている。
文芸志向を文章力、ルポルタージュ志向を取材力と言い換えてよいかも知れない。
もちろん文章力と取材力なくして、商業作品としての怪談実話が書けるはずもないわけだが、ここでは一頭地を抜く文章力・取材力――先述したような、事実をあったるまま、ありありと読み手に伝える技倆と考えていただきたい。
さて、ひるがえって鑑みるに、右に挙げた作家陣に先駆けて、誰よりも早く怪談実話の革新に取り組み、文章力と取材力の両面において卓越した作品を生み出してきたのが、とりもなおさず、松村進吉なのであった。
本書に収められた「撮れなかった映画の件」や「ほろ苦いアンパンの件」や「薬を飲んだら治るの件」といった慄然たる逸品の数々を一読されれば、私の云わんとすることがお分かりいただけるだろう。ユーモアやウィットをふんだんに交えつつ鋭く人情の機微を突く達意の語り口、他人の不幸を取材する自らへの突き放した視点、そして何より地方都市の日向臭い日常に見え隠れする仰天ものの怪異――怪談実話であり私小説であると同時に、本書は一級の上質なエンターテインメント作品たりえているのだから。
二〇一八年六月
紹介した書籍
関連書籍
-
レビュー
-
レビュー
-
連載
-
連載
-
レビュー