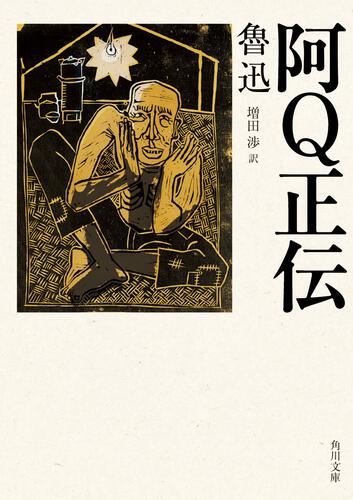私は作家を、生に重心を置く人と、死に重心を置く人に分けている。私の中で前者の代表が魯迅であり、後者の代表が三島由紀夫である。
魯迅は『魯迅選集』第十二巻(松枝茂夫訳、岩波書店)所収の「死」という文章に、次のような箇条書きの遺書を残している。
一、葬式のためには、誰からも、一文たりとも受け取ってはならない。――ただし、古くからの友人のは、この限りにあらず。 二、さっさと棺に納め、埋め、片づけてしまうこと。 三、記念に類することは、一切やってはならない。 四、私を忘れ、自分の生活のことを考えること。――さもなくば、それこそ大馬鹿者だ。 五、子供が大きくなって、才能がないようだったら、つつましい仕事を求めて世すぎをさせよ。絶対に空虚な文学者や美術家になってはならぬ。 六、他人が与えるといったものを、当てにしてはならぬ。 七、他人の歯や眼を傷つけながら、報復に反対し、寛容を主張する人間には、絶対に近づいてはならぬ。
この中の、特に三に私は博たれる。「記念に類することは、一切やってはならない」である。
魯迅は死を美化してはいない。野垂れ死ぬより野垂れ生きることをさえ主張している。
たとえば、本書所収の「孤独者」で、作中人物に、
「僕はまだしばらく生きねばならない!」
と言わせ、こう呟かせる。
「以前は、まだ僕に生きてもらいたいと思ってくれる人がいたし、僕自身もまたしばらく生きたいと思ったが、その時には、生きて行けなかった。いまはもう、すっかりその必要はなくなったが、しかし生きて行こうと思う……」
三島由紀夫は太宰治を嫌悪したが、太宰の中に野垂れ生きる精神を見たからだろう。
もちろん、生を絶対化すると、どんなことをしてでも生きることがいいことだとなってしまう。そうではなくて、生に重心を置くということは日常を大切にするということである。あるいは、平凡をいつくしむ。
死をキイワードにした三島に対して、魯迅は生および生活をキイワードにした。
魯迅の短文にこういうのがある。
虎に追いかけられたら、自分は木に登る。そして、虎がいなくなった後に降りてくる。虎がいつまでも待ちつづけたらどうするか。木に自分の体を縛りつけて、死骸も虎に食わせない。
これは潔くは死なないという思想である。死は決して潔いものではない。死を潔いとするのはエリートの思想であり、魯迅はそれに対して、泥まみれになっても生きてやる、と打ち返した。
ニーチェは「神は死んだ!」と叫んでキリスト教に反逆したが、魯迅は儒教に徹底的に抵抗し、その教えを引っくり返した。
たとえば、魯迅に傾倒したジャーナリストのむのたけじは、河邑厚徳著『むのたけじ笑う101歳』(平凡社新書)の中で、魯迅に「最も惹かれたのは、論語を真っ正面から敵視したことだな。孔子を真っ正面から叩いたのが彼で、私も本当にそうだと思ったの」と告白し、「左の端にも右の端にも行くな、真ん中で行くのがいい道徳だ」という『中庸』はおかしいと続ける。そして、こう結論づける。
「私は貧乏人の子で、権力支配を受けてきて、それはとんでもないと思っていた。貧乏人が問題を突き詰めて考えて勝負してこそ、世の中を変えられる。真ん中でプラプラやっているのはごまかしだと思ってね。だから私は孔子の論語はごまかしだと思っている」
誰もが疑わない「親孝行」でもそうである。
魯迅の「朝花夕拾」に「二十四孝図」が入っている。これは儒者が二十四人の孝行者とされる歴史上の人物を絵入りで解説した通俗本について、魯迅が否定的に書いた評論である。
その中の一つに「郭巨、児を埋む」がある。
ある子どもが母親の腕に抱かれてニコニコ笑っているが、彼の父親は、いましも彼を埋めるために穴を掘っている。その説明に言う。
「漢の郭巨、家貧し。子あり、三歳なり。母かつて食を減じて之に与う。巨、妻に謂って曰く、貧乏にして母に供する能わず、子また母の食を分つ。盍ぞ此を埋めざる?」
「坑を掘ること二尺に及んで、黄金一釜を得。上に云う天、郭巨に賜う、官も取ることを得ず、民も奪うことを得ず、と」
この話を引いて魯迅はこう考える。
私は最初、その子どものことが気がかりで、手に汗を握った。黄金一釜が掘り出されて、やっとホッとした。だが私はもう自分が孝子になる気がなくなったばかりでなく、父が孝子になったら大変だという気がした。そのころ私の家は左前になっていて、父母がしょっちゅう食いぶちの心配をしているのが耳に入った。それに祖母は年老いている。もし父が郭巨のまねをする気になれば、埋められるのはこの私ではないか。もし郭巨の時と同様に一釜の黄金が掘り出されれば、むろん、この上ない仕合せである。だが、そのころ私はまだ小さくはあったが、世の中にそんなうまい話はザラにあるものではない、というくらいの智慧はあったと思う。
つまり、貧しくて母親に食を与えることができないので、自分の子どもを埋め殺してしまうのは当然であって、それが親孝行の道だと儒者は説くのだが、魯迅は、自分の父親が郭巨のような孝行息子だったならば、自分が埋められてしまう立場になるという子ども時代の恐怖を語っている。
日本でも、特に戦時中の天皇制教育は、教育勅語に象徴されるように、上から下への儒教的イデオロギーだったが、しかし、道徳は上から押しつけられた途端に腐ってしまう。それは自発的なものではなくて強制的なものになり、道徳ではなくなるのである。
魯迅は鋭くその点を告発した。
「報復の論理」も儒教的には否定されるだろう。しかし、魯迅はそれを否定しない。
〝日本の魯迅〟といわれた竹内好は、『魯迅評論集』(岩波文庫)で、魯迅についてこう書いている。
「苦しくなると、とかく救いを外に求めたがる私たちの弱い心を、彼はむち打って、自力で立ちあがるようにはげましてくれる。彼がとり組んだ困難に比べれば、今日の私たちの困難はまだまだ物の数でないのだ。これしきの困難に心くじけてはならない。ますます知恵をみがいて、運命を打開しなければならない。魯迅は何ひとつ、既成の救済策を私たちに与えてくれはしない。それを与えないことで、それを待ちのぞむ弱者に平手打ちを食わせるのだが、これ以上あたたかい激励がまたとあるだろうか」
努力すれば必ずそれは報われる、という考え方がある。「苦あれば楽あり」という因果応報的世界観だが、これは「苦あれば楽あろう」、これだけ努力すれば必ず報いられるだろうという祈りにも似た願望が短絡したものであり、〝現実〟は「苦あっても必ずしも楽あらず」である。
それではそれこそ報われない、と言う人がいるかもしれないが、見当ちがいの努力もあるだろうし、どう努力しても浮かびあがれない人もいる。たとえば、魯迅が「故郷」で描いた閏土は〝努力〟しなかっただろうか。
そう前提した上で魯迅は「報復の論理」を展開する。
「花なきバラの二」は、一九二六年三月十八日、中国の時の軍閥政府によって多くの青年が虐殺された「民国以来最も暗黒の日」に書かれたものだが、 「これは一つの事件の結末ではない、一つの事件の発端だ。 墨で書かれたタワ言は、血で書かれた事実を隠しきれない。 血債は必ず同一物で償還されねばならぬ。支払いが遅れれば遅れるだけ、いっそう高い利息をつけねばならぬ!」
という激しい文字で綴られている。
報われ難い〝現実〟があるからこそ、「報復の論理」は必要なのであり、「血債は償還され」ていないからこそ、必ず「償還されねばならぬ」のである。
「挫折」は多く、これだけ努力すれば報いられるであろうという「期待」と、「現実」をとりちがえたところから生まれる。そこには当然、無意識的にもせよ己れの力に対する過信がひそんでいる。
私が名づけた「まじめナルシシズム」の腐臭はそこからたちのぼる。
魯迅がそうした腐臭と無縁なのは、己れの力などなにほどのものでもないことをハッキリと知っているからであり、「努力」が報われ難い〝現実〟であるからこそ、「絶えず刻む」努力が必要であることを知っているからである。
「私は人をだましたい」や「フェアプレイは時期尚早」といった魯迅の刺言を読んで、私は「至誠天に通ず」式のマジメ勤勉ナルシシズムから自由になった。
マジメ主義者や「誠実」讃美者(とかくこれらの「主義者」は他人に対するマジメや誠実よりも己れに対するそれを優先させる)は、よく「真実」を他人に預けて(「告白」!)自分の重荷を軽くする。
竹内好は「日本文学にとって、魯迅は必要だと思う。しかしそれは、魯迅さえも不要にするために必要なので、そうでなければ魯迅をよむ意味はない」と喝破した。日本文学にとってだけでなく、日本人にとって魯迅が必要なのだと私は思うが、魯迅精神を体現した竹内のある日の日記の次の記述は私を仰天させた。
「ニセ札に報償金がついた。三千円以上と言う。今まで発見されただけで二百枚に近い。これでまた話題になるだろう。ただ私は、ニセ札をあつかうジャーナリズムの態度が気に入らない。ニセとは何か、本物とは何かをもっと疑わねばならぬのに、そうしていない。必要流通量以上に放出される通貨はすべてニセではないのか。お上の御威光がうすらいだ今ではニセ札感覚も変っているはずなのに、その機微をとらえようとしない新聞記者や漫画家はみんなナマケモノだ。ニセ札事件をインフレーションと結びつけて論じる評論があらわれぬのはおかしい。ニセ札の鑑別法や図柄だけが話題になるジャーナリズムは健全でない」
たとえホンモノであっても、「必要流通量以上に放出される通貨」はニセなのだというこの指摘に私は瞠目した。
一九九八年秋に、私はNHKの「課外授業 ようこそ先輩」で、郷里の小学生に、それぞれのお札をつくってもらったが、ヒントはここにあったのである。
「私は天国をきらひます。支那に於ける善人どもは私は大抵きらひなので若し将来にこんな人々と始終一所に居ると実に困ります」
魯迅はある人への手紙でこう書いている。魯迅は「いわゆる聖人君子の徒輩に少しでも多く不愉快な日を過させたいために」生きた。竹内もそれは同じだった。
「秀才たちが何を言うか、私だってこの年まで生きていれば大方の見当はつく。たぶんそれは全部正しいにちがいないのだ。けれども正しいことが歴史を動かしたという経験は身にしみて私には一度もないのをいかんせんやだ」
一九六三年一月十八日付の竹内の日記である。
魯迅は、とりわけ卑屈なドレイ根性、ドレイ精神を排した。学生時代に私は友人に、日本人にはマルクスやウェーバーよりも魯迅を読むことが必要だという手紙を書いたことがあるが、残念ながら、その思いはいまも変わらない。多数に従う「いい人」ばかりになっている日本には、いまこそ、魯迅というある種の爆薬が必要なのである。