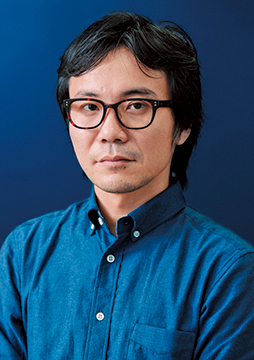本書『ずうのめ人形』は、第二二回日本ホラー小説大賞の大賞受賞作『ぼぎわんが、来る』で颯爽とデビューしたエンタメホラーの俊英・澤村伊智の第二作である。
著名な新人賞を受賞した新人作家にとって、受賞後第一作はプロとして最初にクリアすべき高いハードルだ。自由に原稿に向かっていたデビュー前とは異なり、限られた期間内に、読者と編集者を満足させうるだけの作品を求められるからである。このプレッシャーに耐えられず、フェイドアウトしてしまう作家も少なからずいる。
しかし、澤村伊智にそんな心配は無用だった。『ぼぎわんが、来る』以上に技巧と趣向を凝らした『ずうのめ人形』で、そのハードルをあざやかに飛び越えてみせたのだ。ホラー系の書評家として、いや、率直にいってただのファンとして、わたしは刊行された澤村作品はリアルタイムで読んでいるが、著者の潜在能力にあらためて驚かされた作品として、本書はとりわけ印象が深い。
あらすじを簡単に紹介しておこう。オカルト雑誌『月刊ブルシット』編集部でアルバイトをしている主人公・藤間洋介は、編集長に命じられ、音信不通となったライターの湯水の自宅を訪ねる。そこで発見したのは冷たい屍体となった湯水と、ところどころ焼け焦げた跡のある分厚い原稿用紙の束だった。
湯水の変死はこの原稿の束に関係がある。そう主張する『ブルシット』スタッフの岩田にすすめられ、藤間は原稿の複写を手に取った。そこに記されていたのは、来生里穂という中学生の視点で綴られる実話風の小説。原稿を読み進めた藤間はやがて、「ずうのめ人形」という不気味な都市伝説の記述にぶつかる。
「ずうのめ人形」はある屋敷の土蔵から発見された、古い人形にまつわる話だった。黒い振り袖を着て、顔を赤い糸でぐるぐる巻きにされた日本人形。それは関わった人に災いをなす。のみならず、その話を見聞きするだけでも呪い殺されるという。
半信半疑だった藤間だが、湯水に続いて岩田が死亡したことを知り、呪いの効力を認めざるを得なくなる。四日後に迫った死を回避するため、藤間はオカルトに詳しいライターの野崎、その婚約者で強い霊能力のある比嘉真琴とともに、「ずうのめ人形」の背景を探りはじめた――。
この話を聞いたらお化けがくる、何日後かに取り殺される。
そうした類の都市伝説を、誰しも子供時代に一度は耳にしたことがあるだろう。たとえ嘘だと分かっていても、この手の話にはなぜか無視しきれない不穏さ、気味の悪さがつきまとう。そこにあるのは自分が怪談の当事者になってしまう恐怖、そして虚構が現実を侵食してくるようなえもいわれぬ心細さであろう。澤村伊智はその怖さを正面から取りあげ、都市伝説など信じない大人の読者をも震え上がらせる現代ホラーに仕立て上げた。
それにしても澤村伊智のホラーはなぜ、怖いと評されるのか。それはキャラクターから筋の運び、文体、不気味な響きをもつタイトルにいたるまで作中のあらゆる要素が、読者に「恐怖」を喚起するために配置されているからだ。澤村はこの配置を、内外のホラー小説や怪談を読むことで身につけたのだろう。つまり非常に技巧的に組み立てられた小説世界なのだが、読んでいる間はそんなことを忘れてしまうくらいに怖い!
切迫した語り口で読者をずるずると異様な世界に引きずりこむ序章、里穂のもとに初めてずうのめ人形が現れる戦慄の一夜、放課後の教室でのこっくりさんなど、本書にも忘れがたいシーンが多数含まれており、傑出した怪異描写を堪能できる。
死へのタイムリミットを遠くから徐々に迫ってくる人形で表現したのも、秀逸なアイデア。もし部屋に日本人形を飾っている人がいたら、場所を変えてから読むのが賢明だろう。古来、動き回る人形を描いたホラーは数多く書かれてきたが、日本人形が本書のような使われ方をしたのは初めてかもしれない。
意外な形で事件に深く関わることになる真琴は、『ぼぎわんが、来る』でもめざましい活躍を見せた霊能者だ(『ぼぎわんが、来る』『ずうのめ人形』『ししりばの家』の三作には真琴とその姉妹が登場している)。しかしその能力は決して万能ではなく、今回もずうのめ人形相手に苦戦を強いられることになった。レギュラーキャラといえども安全地帯にはいられない。その緊張感と容赦のなさがさらなる怖さを生んでいる。
本書のあらすじを読んで、鈴木光司のベストセラー『リング』を思い浮かべた方もいるかもしれない。不運にも呪いにかかってしまった主人公が、その解除方法を求めて奮闘する。呪いを媒介するのがビデオテープか原稿かの違いこそあれ、両作の骨子はそっくりである。この類似はもちろん意図的なものだ。以前著者ご本人にうかがったところによると、デビュー作『ぼぎわんが、来る』が『リング』と比較されることが多かったため、二作目ではあえて『リング』的な世界に正面から挑んでみたのだという。
これは里穂の愛読書が『リング』であること、原稿の作中時間が『リング』が空前のブームを巻き起こした一九九七年から九八年に設定されていること、里穂のあだ名が「サダコ」であることなどから、割とあからさまな形で示されている。澤村伊智はあえて『リング』との類似性をオープンにすることで、「似ているようでまったく別の話だ」と差異を強調しているわけだ。
こうしたメタ・ホラー性は澤村作品のひとつの特徴だが、本書はとくにその色が濃い。先行作の到達点を意識しつつ、そこに新たな恐怖を盛りこもうとする『ずうのめ人形』のいき方は、綾辻行人らによって展開された「新本格ミステリ」のホラー版のように思えて興味深い。
本書のさらなる魅力としては、陰影に富んだ人間ドラマの要素があげられよう。家庭内に問題を抱え、中学校でも居場所を見つけられない里穂にとって、市立図書館だけが心安らげる場所だった。里穂が好んで読むのは、ホラー小説やホラー映画に関する書籍。孤独だった里穂はある日、図書館内にすえられた「交流ノート」でゆかりという同好の士を見つけ出す。インターネット普及前夜、ノートを介して大好きな本について語り合う二人の姿は、読書好きの共感を誘うはずである。
ホラーを愛してやまない里穂。都市伝説に魅入られたゆかり。ホラーを「逃避」と決めつける教師や、知識を振りかざしてマウンティングしてくる悪しきマニア。オカルト好きが高じてマスコミ業界に飛びこんだ藤間と、彼をとりまく風変わりな大人たち。ホラーという趣味を介し、いくつもの人生が時代・世代を超えて交錯する。
評論家の千街晶之が「ミステリとしても非凡な出来映え」と評したとおり、本書後半はかなり謎解きミステリのテイストが強く、トリッキーな展開を含んでいる。藤間たちが知ることになる「ずうのめ人形」に隠された真実は、予想をはるかに超える意外性とおぞましさで読む者を戦慄させる。
なお本書は二〇一六年末の各種ミステリランキングで多くの評を集め、一七年には第三〇回山本周五郎賞にノミネートされた。怖さと面白さを兼ね備えた本書が、エンターテインメントとして多くの心を揺さぶった証左だろう。
一八年十二月には『ぼぎわんが、来る』の実写映画化作品、『来る』の公開が控えている澤村伊智。今後その傑出した筆力はますます広く、世に知られてゆくことになるはずだ。そして本書『ずうのめ人形』はその最初期に、才人が鮮やかなジャンプを決めてみせた傑作として、末永くホラーファンに語り継がれていくに違いない。