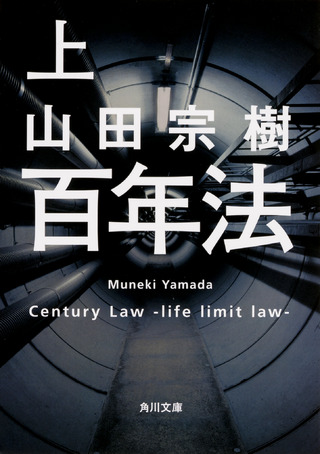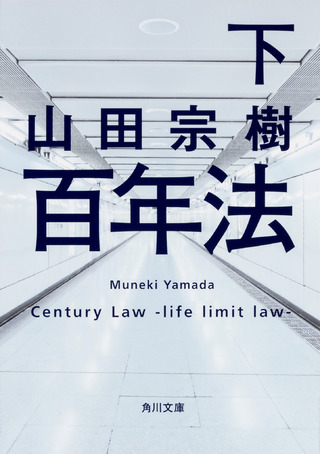『代体』は、傑作『百年法』(二〇一二)から新たな一歩を踏み出し、先に向かおうとする山田宗樹の力強い意志が漲った作品である。
どのような新たな一歩を踏み出しているのか。
それは、脳科学などの知見を用いた、「人間」観のアップデートであり、その新しい人間観によって複数の人物が織り成す社会のダイナミックな動きを描くエンターテインメントを実現させようとする道への一歩である。
未知の広大で肥沃な領域に向けて、果敢なチャレンジを行っている小説。それが、この『代体』である。
タイトルとなっている「代体」とは一ヶ月使える、人工的に作られた代理の「身体」である。そのような人工身体に「意識」を移す技術が実用化されるようになった社会が作品世界で描かれる。
「代体」は、法的に使用期限が決められている。人工物であるが故に劣化してしまうというだけではなく、法による規制の結果である。「代体」から「代体」へと乗り継げば技術的に不老不死に近いことが実現できそうなものだが、それが法的に禁止されているので、法によって生の継続を断念せざるを得ない人たちが出てくる。彼らは必ずしも法に従わず、地下組織などによる抵抗が行われたり、違法に意識を転送させたりする。このドラマが、本作の読みどころのひとつだ。
このドラマの部分は、これまでの山田宗樹作品の延長線上にある。
山田宗樹は、デビュー当初から、生命、医療、死のテーマを扱い続けてきた。作品で言えば、『死者の鼓動』(一九九九)、『黒い春』(二〇〇〇)、『天使の代理人』(二〇〇四)、『人は、永遠に輝く星にはなれない』(二〇〇八)、『百年法』などがそのテーマに属する。
無理に一貫性を見出そうとするならば、第18回横溝正史賞を受賞したデビュー作『直線の死角』(一九九八)もまた、生命保険などを用いて人間の生命を金に換えようとする残酷な主体を描いていたという点では、半分ぐらいこのテーマに属すると言っても良い。
『代体』はこのテーマの延長線上にありながら、シンギュラリティSFや脳科学の知見を取り入れ、飛躍しようとした作品であると位置づけることができる。
本作の特徴を明瞭にするために、第六十六回日本推理作家協会賞を受賞した『百年法』と比較してみよう。『百年法』は、現時点での、山田宗樹の手法とテーマが最良の形で結実した、最大最高の集大成的な作品であると考えられる。少しだけ内容を紹介する。
作品世界では「ヒト不老化技術」が実現している。しかし、人間は一〇〇歳で死ななければならないという「生存制限法」があるという社会。技術と、法と、その中で生きる人間の感情や行動から織り成される架空の未来社会が多面的かつ動的に描き出される。伝統的に、日本の小説は、複数の人間が関わる社会や政治的状況を描くのが苦手であると批判されてきたことを考慮すると、ある技術が導入されたときに何が起きるかを、社会・政治・法・倫理・感情などの多角的な視点からシミュレートし、エンターテインメントとして成立させたその力量は、瞠目に値する。
医療、生命、法、死などの主題を扱うという点では、『代体』の出発点は、『百年法』と近い。
しかし、大きく違う点、大きく飛躍している点がある。特に、後半だ。少しばかりネタバレになってしまうが、その点について、解説していきたい。
これまでと大きく異なる点は、シンギュラリティSFと、脳科学の大々的な導入である。
特にその中でも「意識」に焦点を据えているのが本作なのである。タイトルは『代体』だが、身体から取り出される意識の方もまた、重大な問題となってくる。その「意識」という問題系の追究こそが、本作の読みどころだ。
設定として、身体と意識を分離させることを可能にする架空の技術が作品世界に導入されている。特殊な技術で脳をスキャンし、それを人工的に作られた脳細胞や、別の人間の脳に移植することが可能になっている。
シンギュラリティSFと呼ばれるSFの潮流では、人間の身体から解き放たれた意識なり精神なり魂なり知性なりを描く傾向がある。もちろん、すべてがそうではないのだけれど、代表作であるチャールズ・ストロスの『シンギュラリティ・スカイ』や『アッチェレランド』などでは、そのような展開が描かれる。
「シンギュラリティ」ものとして重要なのは、デジタルデータと化した意識や人工知能が、「技術的特異点」(シンギュラリティ)を超えていくという瞬間への期待である。主に人工知能などの技術が発展していき、現在の人間が想像しうる範囲を超えてしまうのが、「技術的特異点」以後の世界である。「シンギュラリティ」への期待は、フィクションとしてのSFの中だけではなく、人工知能にかかわる論者などから発せられることも多い。実際にそれが実現されるか否かは、様々に議論がある。
『代体』は、この「シンギュラリティSF」の潮流に位置づけられるべき作品だろう。
だが同時に、本作を理解するためには、「脳科学」を導入したフィクション(ぼくの言い方では、「ニューロ・フィクション」)の潮流のことも少し踏まえておくべきだろう。
脳科学の知見を導入し、新しい人間観を導入して小説作品やエンターテインメント作品を作ろうとする挑戦が目立つ。歴史的に、小説や芸術は、新しい科学や技術によって生まれた新しい世界観や人間観を導入し、新しい作品を生み出す傾向がある。その「脳科学」版が、現在起こっている。
具体的な作品名を挙げるとしたら、脳科学者の茂木健一郎が書いた小説作品『プロセス・アイ』(二〇〇六)、SF界に「伊藤計劃以後」なる言葉を生み出すほどのインパクトを与え大ヒットした伊藤計劃の小説『虐殺器官』(二〇〇七)、『ハーモニー』(二〇〇八)、芥川賞作家・円城塔との共作小説『屍者の帝国』(二〇一二)、ゲームクリエイターである小島秀夫監督のゲームを小説化した『メタルギア ソリッド ガンズ オブ ザパトリオット』(二〇〇八)、冲方丁がシリーズ構成を行ったアニメ『攻殻機動隊ARISE』(二〇一三―二〇一四)などがそれに該当する作品である。
テーマとして注目を浴びているのは、「意識」である。
「意識」は、「自己」とか「自我」とか「魂」とは少し違う。今これを読んでいるあなたが、自分自身について感じている「それ」のことである。文庫本を持っている手の感触、字を読んで頭に浮かぶ思考などがないだろうか。空気の感触や、音もあるかもしれない。それらの、あなたにとっては掛け替えもなく、疑い得ない「感じ」それ自体が、一体どのようにして発生しているのかが、ここで問われていることである。普段、意識はあるのが当たり前なので、それこそ言われないと「意識」されないものであるが、いざ考え始めてみると、これは相当な難問なのである。脳科学で現在難問として探究されている意味での「意識」とは、このような「感じ」を伴う「意識」のことである。「クオリア」とも言う。
「意識」とは不思議なもので、ぼくらは生活の大半を「無意識」に処理している。呼吸をいちいちどうするかとか、心臓をどう動かすかとか、どうやったら歩けるのかなどをわざわざひとつひとつ考えて行ったりはしない。「無意識」が自動的に処理して行っているのである。感情にしろ、ある出来事に対して、ぼくたちが「この感情になろう」と命令して感情が生まれているわけではない。意識は、自分が自分自身の主だと思っているが、意外と仕事をしていないのである。では、こいつは何のためにあるのか、何なのか。本当は意識などなくても、結構自動的に生きているのではないか、という説も出てくる。
「意識」についての考え方を大きく転換させたのが、ベンジャミン・リベットの実験だ。ぼくたちは普通、意識が命令をして、何か行動を起こしていると思っている。しかし、リベットが、脳などの電位を測定した実験によると、「意識」が何かをしようと「意図」するよりも先に、身体がそれを行うための準備を行っていたのだ。「意識」が意図するよりも早く、行動に移す決定がされていたことを強く示唆するこの実験は、ぼくたちの常識に反しており、世界観を覆してくれる。「意識」は命令している主などではなく、行動の結果のレポートを送られているだけなのに、自分が主だと勘違いしているイタイやつのように思われ始めたのだ。
脳科学で「意識」が重要な問題となってきたのは、人工知能や計算機科学の発展とも関係している。人工知能を作るために人間の知性を解明しようとしたり、その逆の研究が行われ続けてきた。その結果、両者の差と類似性が問題として浮上してきた。「意識」は両者を分ける究極のポイントのひとつである。意識、つまり、感覚などを感じる主体の有無は、倫理的にも、存在論的にも、重要な問題の焦点になる。なぜなら、コンピュータや人工的な脳神経を模したものにも「意識」が宿るのだとすると、「痛み」を感じているのかもしれないではないか。それは倫理的に問題を感じるだろう。逆に、人間という存在の「特別さ」のようなものと漠然と考えられているものも、深刻な捉えなおしが必要になってくる。所詮ぼくらは性能のいい計算機に過ぎないのだと思うのは、そう簡単なことではない。
物質たる脳神経と、そこに流れる電気や放出される化学物質などの物理現象と、「意識」はどのように関係しているのか。この二つを架橋しているのは何か。これを哲学者デイビッド・チャーマーズが「意識のハード・プロブレム」として提起した。これは、脳神経科学・認知科学・哲学などの領域で挑戦され続けている未解決の難問である。脳科学者やその周辺の人々はこの問題について様々な意見を提出しているが、それは完全に実証的なものではなく、思索的なもの、つまりは、想像力によって創造的に生み出されたものであることも多い(実証でわかっていることをベースにして、さらにその先を語ろうとすると、自然にそのような「想像」「創造」で考えられる領域は発生するのだ)。最先端の科学の中で、科学者が行っているこの「想像・創造」の部分において、文学者や物語作家が議論に参入し、知見を積み重ね、貢献しうる余地が発生するし、フィクションと科学が有益に相互参照しうる未知の肥沃な領域が発生しているのだ。
意識はなぜ存在するのか。意識は人間の主の座についているのか。なぜ物質としての脳から、主観や感じを含む、この意識なるものが生まれるのか。そのような問いが、「私」や「個」の問題を描いてきた文学の一部を刺激し、新しく更新せんとするモチベーションを生んだのは想像に難くない。たとえば、純文学者である中村文則の書いた『私の消滅』(二〇一六)も、脳科学パラダイムに移行した人間観で小説を書くチャレンジだった。
脳はどうやら周辺にある雑多なデータを勝手に繋ぎ合わせて「物語」を作り上げているマシーンであるらしいなどという知見もある。「物語」のプロフェッショナルたちがそれに刺激を受けることは想像に難くない。実際本作の「人の意識とは魂のような不変不滅のものではなく、無数の情報から構成される流動的な物語に過ぎない」「意識とは、その物語の語り手にほかならない」(P213)という箇所などに、その片鱗を見つけるのは難しくはないだろう。
脳科学を用いてフィクションをアップデートするという作業は、挑み甲斐のあるチャレンジではあるが、実は成功するのが非常に難しい。その理由はいくつかある。意識と「物語」の関係性について踏み込んでいくと、「物語とは何かについての物語」、すなわちメタフィクションに作品は必然的に近づいていき、構造が複雑になってエンターテインメントとしては読みにくくなってしまうのがひとつ。人間観をアップデートしてしまうと、いわゆる近代小説やリアリズムの手法で描くような「個」を前提とした書き方では書けなくなってしまうというのもひとつ。本気でやろうとすると前衛小説のような手法や書き方になってしまって、多くの読者を置いてけぼりにしてしまう危険性がある。
「個」や「主体」のあり方がこれまでの「人間」とは異なるようになってしまった状態を描きつつ、複数の登場人物がいる社会を描き切り、なおかつ読者の脳が快を感じるようにエンターテインメントをするというのは、非常に難易度が高く、様々なジレンマの処理に高度な技術を必要とするチャレンジである。本作は、山田宗樹という作家が全力でそれを試みた作品として位置づけられる。
難しいチャレンジなので、全面的に成功したと言いうる作品はそれほど多くはない。実際、本作にも、不完全燃焼感を覚える読者もいるだろう。個人的には、法の問題を絡めつつ、ある技術が実装された架空の社会像を作り上げ、集団を複合的に描くという稀有な才能と、この題材との融合が、もっと有機的かつ複雑に進む方向性も読みたかった。
『百年法』から『代体』へと果敢なる一歩を踏み出した山田宗樹の先には、まだまだ広大で肥沃な領域が広がっている。ひょっとすると、そこには、小説の力による、人類のあり方の根本的な更新、革命の予感すらあるのかもしれない。『百年法』の先に位置する『代体』には、そのような予感が満ちている。
紹介した書籍
関連書籍
-
レビュー
-
レビュー
-
連載
-
連載
-
レビュー