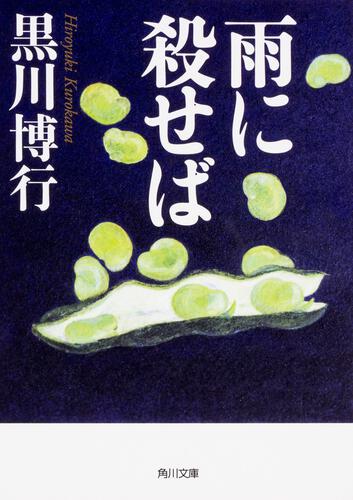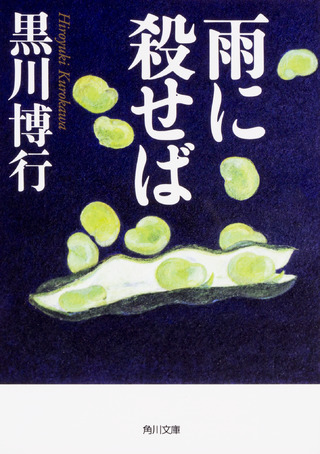黒川博行は、危険な作家だと思う。読み始めると止まらなくなる中毒性はもちろん、最前線の犯罪や不正を取材する嗅覚と胆力、そして事件を人間の目線で伝える筆力。その作品は、ミステリー、ハードボイルド、ピカレスクロマン、ノワール……などさまざまに称されるが、その作家性は、いずれのジャンルも当てはまるようでいて、その本質は語り尽くせないようなもどかしさが残る。
例えば映画化された『後妻業』は、小説が発表された数か月後に高齢男性の連続不審死事件が明らかになり話題になったことが記憶に新しい。また直木賞を受賞した『破門』の疫病神シリーズ一作目『疫病神』では、産業廃棄物処理をめぐる巨大利権が社会的に表面化する前に緻密な取材を重ね、いちはやく小説で告発している。同シリーズの『喧嘩』では、有名議員の自宅と事務所に火炎瓶が投げ込まれた実際の事件をもとに、政治家と暴力団の関係性を再検証した。もちろん人物名や地名などは変えているが、〝事実は小説より奇なり〟を地で行く不正を克明に描いて、新聞記事では焦点が見えづらかった事件の裏側を暴いている。時には報道に先立って事件や不正を告発して警鐘を鳴らし、時には、問題が充分に検証されないまま消費されたニュースをすくい上げる。つまり、フィクションという隠れ簔をまとって〝不都合な真実〟を書き続けているのが、黒川博行という作家なのだ。
本作『雨に殺せば』も例外ではない。この作品は、デビュー作『二度のお別れ』に続いて二年連続でサントリーミステリー大賞の佳作を受賞、一九八五年に単行本が刊行された。大阪の都市銀行を舞台に、バブル経済より以前に金融業界の諸問題を問うた意欲作で、その確かな先見の明に改めて驚かされる。もちろん、今から33年前に執筆された作品だけに、携帯電話やインターネットがない時代のアナログ感はあるし、女性にまつわる描写に至っては前時代的な箇所もある。だからこそ、時代が移り変わったにも関わらず、金融問題の本質や組織不正の〝かわらなさ〟が生々しく際立っている。
事件が発生するのは、12月の大阪。大阪湾にかかる港大橋の上で現金輸送車が襲われ、運搬していた銀行員二人が射殺された。犯人は現金一億一千万円を奪って逃走。さらに翌日、事情聴取を受けた銀行員が公営住宅から飛び降り自殺をして、遺体で発見される。この事件を担当するのが、大阪府警捜査一課の名物刑事・黒木憲造と亀田淳也の〝黒マメコンビ〟だ。主人公は、仕事熱心な敏腕刑事、でも女心には鈍い独身男性の黒木。20代の陽気な相棒マメちゃんこと亀田と一緒に上司にこき使われながらも、持ち前の気力と推理力で、海千山千の刑事たちとやりあいながら捜査を進めていく。
最大の謎は、目的地に到着するまで駐停車が禁じられた現金輸送車が、なぜ港大橋の上で約10分間も停車した後に襲撃されたのか。そして自殺した銀行員は事件に関与していたのか否か――。さまざまな手がかりや状況証拠が次々と浮上するにも関わらず、なかなか決定的な証拠が掴めずに、捜査は二転三転してまったく先が読めない。しかし事件の裏側に、銀行の不正融資が絡んでいる可能性が発覚するあたりから、単なる強盗殺人事件よりあくどい犯罪が明らかになり、話は一気に深みを増していく。
爼上に上げられるのは、現在も公正取引委員会が独占禁止法違反としている「歩積両建預金」を含む銀行の拘束預金と、その社会的責任にある。「歩積両建預金」とは、銀行がその融資と引き換えに、融資額の一部をその銀行に預金させることで実質金利を上げる取引条件で、預金は拘束され引き出せないことが多い。つまり銀行が自身の優位的な立場を利用した不公正取引だが、未だに残る商慣習でもある。不正融資の行方を追って捜査チームがサラ金業者を事情聴取するシーンでは、緊迫した両者の攻防戦から、金融業界の功罪が紐解かれる流れが圧巻だ。銀行はサラ金業者から儲け、サラ金は銀行からはじかれた社会的弱者からカネを吸い上げる。弱い者がさらに弱い者を叩く、その構造が肯定も否定もされず、事実にもとづいて克明に綴られる時、「銀行は誰のためのものだったのか」という大きな問いが横たわる。
「輸送はいつも銀行の方が?」
「はあ、特に多額の現金を運ぶ場合は警備会社や専門の輸送業者に依頼しますが、一億前後の現金なら私どもが運びます。保険にも入っていますし……『運送保険普通保険』というのがそれで、現金の輸送と取り扱いを対象とした総括契約を結んでおりますから、実害はありません」
朝野はこともなげに答えた。我の強そうなえらの張った顔に細いフレームの眼鏡をかけている。かなりの長身だから、マメちゃんを見下ろして話す。
「ほう、金さえ戻れば実害はないといわはる。さすが銀行さんや、我々とは発想の原点が違いますな」
同僚二人が強盗犯に射殺されても、盗まれた現金は保険でカバーされるから、銀行としての実害はない。銀行の貸付課長の何気ない一言は、物語全体に流れる閉塞感を象徴していると同時に現代を反映している。高度経済成長とバブル景気を経て、いかに市民社会は〝マネーファースト〟の金融資本主義に蝕まれてきたか。それは必ずしも金融機関だけではなく、既に社会全体を覆っていることがわかる。例えば、黒マメコンビが行きつけの喫茶店のママの話からは、現代美術の世界でもその兆候は蔓延し、美術作品がもはや金融商品のひとつに成り下がった業界の惨状が明かされる。また後半では、行政主導で進められた公園が着工段階で生態系を崩した問題もさらりと触れられていて、都市空間が市民の手から離れた現状が垣間見える。とはいえ、作家の視線は「市民が善」で「権力者が悪」という単純な二元論には陥らない。不正や腐敗がはびこる組織や経済構造をもつ社会で、だれもが善人ではいられなくなった時代に、個人がささやかな暮らしを守っていくために対峙しなければならないものは何なのか、常に試され揺さぶられるのは、読み手側になる。
暗澹たる時代の状況が活写されていく中で、ページをめくるスピードを落とさせないのは、全編に散りばめられた大阪ならではの笑いの力が大きい。カネや権力ではなく、笑いに包むことで、自分の主張を通したり、人を動かしたり、苦境をも乗り越えていくという生きる智恵や大阪人のパワーが凝縮されていて、小説を読む旨みを存分に味わえる。
絶妙な会話の応酬は黒川小説の醍醐味だが、まだ科学捜査が発達していない時代に書かれた本作では、警察小説という側面において、会話がより重要な意味を持ち精彩を放っている。現代のように犯人の交友関係をSNSで追ったり、防犯カメラや高精度のDNA型鑑定でたやすく物的証拠を集めることができないからこそ、刑事たちは生身の「人」を相手にしなければならない。地を這うように足で情報を稼ぎ、取り調べでは正面突破の追及だけでなく、容疑者の心情も慮る誠実さで問いかけ、牽制したり、時にはいなされてみたりと、押したり引いたりする人間対人間のぶつかりあいがそこにある。
誰かの手によって意図的に隠された〝不都合な真実〟。必要悪と黙認され見えにくくなった不正や不祥事。まだ表沙汰にはなっていない犯罪手口の最前線。黒川小説では世の中に埋もれたさまざまな悪事がミステリーの謎として設定され、それらはひとつずつ人間の本質をえぐるように暴かれていく。実社会では警察やマスコミが動くまで時間を要したり、立証されずに埋もれてしまった事件も少なくない。警察も司法もマスコミも証拠主義が基軸にあるからこそ、状況証拠や心証だけでは警察は犯人を逮捕できないし、マスコミは報道することができない。その間に法律の抜け穴を縫うような犯罪は蔓延していく。こうしたジレンマに苦しむ刑事たちの憤りや無念さに押し出されるように、捜査はクライマックスへと向かっていく。
まさかの展開を迎えるラストは、デビューしたばかりの黒川博行という作家が、これから何を書いていくか、世の中に向けた所信表明のように思えた。それは〝資本を保有するたった1%の富裕層が支配する世界〟とも言われる現代社会に照らし合わせるなら、「99%側の人間の視線から書くハードボイルド小説」なのだと思う。実際にこれまで執筆されてきた多彩な作品群を振り返ると、その立ち位置は本質的にブレがないことがわかる。ヤクザが主人公のシリーズも、そこにヒーロー性は持ち込まれない。むしろ彼らを狂言回しに、本当の悪はどこにあるのかを問い続けている。
その作家性を考える時、思い出すエピソードがある。直木賞受賞の記者会見で、カメラマンからガッツポーズをリクエストされた黒川さんは、それを断って神妙な顔つきで写真に納まっている。その理由を尋ねられると「受賞されてない人もいるわけやからね」と受賞には至らなかった他の作家をやんわり気遣っていたという。サントリーミステリー大賞を受賞した時も同様で、立場の異なる人に寄り添う姿勢は変わっていない。そこには「権力や地位には責任が伴う」という意識がどこかにあるのではないかと思っている。
たぐいまれな取材力をもちながら、その表現手段として、なぜノンフィクションを選ばなかったのだろうと不思議に思うこともある。しかし、インターネットの時代に入って、ジャーナリズムもエンターテイメントと同列に評価され、調査報道が衰退を遂げるという由々しき事態が続いている。フェイクニュースが台頭し、市民の権利や未来を守る情報を精査する報道機関そのものが危ぶまれる中で、〝不都合な真実〟を書き続ける黒川小説は、ジャーナリズムをその本義に立ち戻らせ、賦活する力を持っているという点で、最後のフロンティアだと思わずにはいられない。