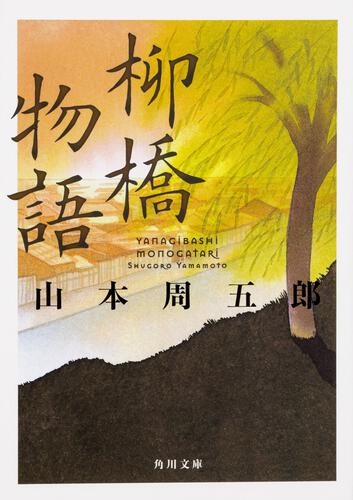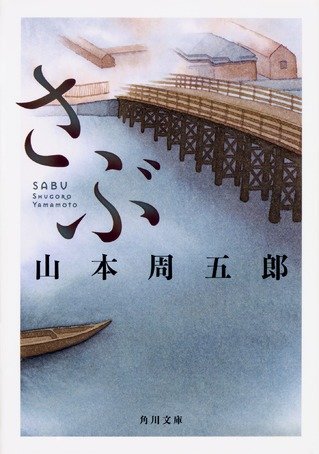当然と云えば当然のことながら、どんなに好む作家と云えど、その中には強く魅かれる作と、さほどでもない作がある。
私にとって本作『五瓣の椿』は、長く後者の側に属するものであった。
最初にこの作を読んだのは、今は昔の十七歳か十八歳――と、記憶力の良さだけは自信のある私にしては、一寸この辺りが定かではないのだが、とあれそれは優に三十年以上の前の頃だ。
私がいつの間にか山本周五郎の愛読者になっていった経緯については新潮社版の、『山本周五郎長篇小説全集』第二十五巻の巻末エッセイにも記したのだが、そもそもの出会いは十六歳時に、或る文庫アンソロジー中に収録されていた『寝ぼけ署長』シリーズの一篇を読んだのが嚆矢だった。
が、それは主として昭和二十年代のミステリ小説のアンソロジーであり、他の収録作家の怪奇と論理の濃厚な味付けの物語に陶然としていた年少の私には、このときは『寝ぼけ署長』の淡白な味わいの一篇には、そうさしたる魅力を感じることができなかった。
該作を含め、山本周五郎の小説の真価が自分なりに解ってきて、徐々に――そしてすっかりその面白さの虜となり果てたのは、それから十年を経たのちであったと云う次第も、先述のエッセイ中ですでに述べているところである。
で、『五瓣の椿』は件の、未だ周五郎世界の無理解状況中に、ポツリと散発的に目を通したものだった。勿論古本屋の均一台の、三冊百円也のくたびれた文庫本でもって読んだのである。
つまりそれは、至って何んの気なしのアプローチである。曩時金もなく友もなく、最も廉価に娯楽を得る手段として安いセコハン文庫を読みまくっていたときに、単にその三冊中の組み合わせとして、たまたま選んだ一冊に過ぎぬものであったのだ。
そしてこれは、安アパートに戻って改めてカバー裏の内容紹介文に目を晒したときに、ふとゲンナリした気分に襲われたのである。
次に解説を読んでみて、いよいよこれに手をのばしてしまったのは失敗であったとも思った。
どうもこれは、淫奔で不誠実な母親――その血統に嫌悪と恐怖を抱く娘がそれらのすべてを清算しようとする復讐の物語であるらしきことを知り、何やら気持ちが萎えたと云うのである。
自分自身の、心の痛みを思いだしたが為に気持ちが悴けてしまったのだ。
私の実父と云うのは江戸川区のはずれで零細の運送店を営んでいた。が、これがとんでもない性犯罪で逮捕されて一家を解体させた陋劣な男であれば、かの物語の主題は一読者たるこちらにとっても些か切実な意味を含むものではあった。
不浄の血。――と、こんなのは傍目には甚だ大袈裟な或いは恰も何かに酔ったかのような大仰な物言いでしかないであろうが、それが因で生育の地から文字通りの夜逃げをし、以降は母方の姓に変わって絶えずその〝性犯罪者の倅〟との不様な事実に引け目を感じ続けていた身にとっては、まだその記憶を何一つ浄化できぬまま、生々しく抱え続けていた時期でもあっただけに、かようなテーマの物語には一寸こう、目を背けたい思いが確かにあったのである。
で、そのような云わば消極的な気持ちで巻を開いたこともあり、初読時の本作の印象は決して心地良いものではなく、むしろ全篇に対し、軽ろき不興をさえ覚えた。
敬愛する父の死に際しても、他の男と不義を働く母。しかも自分はその父の子ではないことを知らされて憎悪が極限に達し、母や浮気相手の男たちを順々に惨殺してゆく女主人公のおしの――。
サスペンス仕立ての小説としては、現代の視点では至極ありきたりな筋の運びに感じたし、またそれだけにおしのの復讐心理にも不自然な――一口で云ってしまえば共感を重ねることがなかなかに難しかった。
なので、のちに山本周五郎の短篇小説群を読んでその構成の妙に唸り、『樅ノ木は残った』や『さぶ』、『青べか物語』に接していよいよこの作家に傾くようになっても、本作は冒頭で述べたところの、〝さほどでもない作〟との感想のまま、二度読み返すこともなかったのである。
そして三十年余の星霜を経たわけだが、先の、『山本周五郎長篇小説全集』配本の際に本作を再読してみて、私は過去の自身の大いなる不明を恥じぬわけにはいかなかった。
当然、細部については完全に忘れきっているから、それは殆ど初読に等しい復読である。
今度は若年時に感じた、おしのの心理に対する不自然さは露ほども感じなかった。
結句、小説を読む際は単純に、どこまでもその物語の中に没入した方が得なのである。昔に読んだときには解らなかった語り口のうまさと緊密な構成力とが、今度はハッキリと本作にもあらわれていることを知った。
三十年と云う歳月が、こうも同じ作の読後感を変えるものかと驚いた次第である。
と、同時にかような年月――時間の経過が、斯くも人の心に変化をもたらすものならば、或いはおしのにもまた、その作用が働いていたのではないかとやり切れない気持ちにもなる。
私にしても小説の読みかただけではなく、父親の事件のことも四十年が経ち、被害に遭われたかたへの申し訳なさは変わらぬものの、こと父親個人に対する心情の変化は確かにある。
怨みもつらみも時の流れがゆるやかに忘却の淵へと導いてゆくのなら、おしののその復讐の行動は、やはり性急に過ぎたのではあるまいか――。
が、その点については終章の最後に千之助が呟く、
「おまえのしたことが正当であったかなかったか、私にはわからない、だがおまえはそうしたかった、そうせずにはいられなかった、ということだけは真実だ、――しんじつそうせずにいられなかったとすれば、それをしたことについて悔やむ必要はないよ」
との言葉が、余りにも優しい。
そしてこの言は作中に繰り返される、
この世には御定法で罰することのできない罪がある。
との嗟嘆への一つの明快な答えとして示されると共に、読む者の心を浄化しつつも、しかし重い何かを投げかけてくるのである。