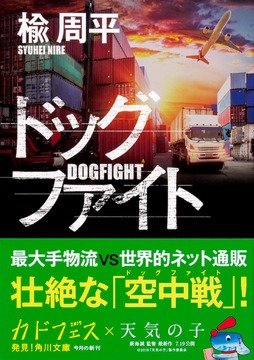手遅れになる前に
「本書はフィクションであり、実在する人物、団体、事件などには一切関係ありません」
本書の末尾には、こう記載されている。
見慣れた文言ではあるが、この小説の場合、この言葉をどうしても深く受け止めてしまうのである。本書はほんとうにフィクションなのか、と。
この本に書かれている日本の危機的状況は、フィクションと割り切るにはあまりに生々しい。まさに今ここにある危機であり、そう遠くない将来、自分や子供たちを襲うのではないかと思わざるを得ず、無理矢理にでもフィクションだと信じることで安心したくなるのだ。
それと同時にこうも思う。本書の主人公のように危機に立ち向かう人物が現実に存在して欲しい、と。危機をリアルに感じるが故に、主人公がもたらす希望がノンフィクションであって欲しいと願ってしまう。
本書が刊行されたのが二〇一四年六月(産経新聞への連載は二〇一三年六月一日~一四年三月三一日)である点も気になる。本書の主人公が危機回避の重要な要素としている東京オリンピックまでの時間が、執筆当時とくらべ現在では相当に少なくなっているのだ。既に手遅れなのでは
――そんな不安も覚える。
それほどまでに現実を考えさせられる一冊なのだ。
その小説の主人公となるのが甲斐孝輔。三十三歳。日民党結党以来最年少の青年局長だ。父親は五年にわたって総理大臣を務めた甲斐信英。要するに二世議員だ。
だがこの二世議員には骨があった。世襲議員が親から引き継ぐのは、地盤、看板、鞄だけでなく、親が残した負の遺産――甲斐政権の政策がもたらした格差の拡大や赤字国債による債務残高の拡大など――も受け継ぐ覚悟があってしかるべきと考えているのだ。孝輔は、政界を引退した九十三歳になる元総理大臣から、この国を担う人物として長期的な視点でこの国をどう導くかを考えて欲しいと要望され、同時に中国を震源とする危機(軍事衝突に限らない)を示され、この難局に立ち向かうことを決意する。自分が主宰する勉強会を通じ、同じく二世議員にして二歳年上の新町薫子を相棒にして……。
という具合に冒頭を紹介すると、本書は甲斐孝輔が総理大臣の座を目指して頑張っていく姿を描く小説と思われる方がいるかもしれない。それはまあ確かにそうなのだが、本質はそこにはない。孝輔の目的が総理になることではなく、この国を救うことだからだ。それ故に、孝輔は危機から目をそらさない。危機の解決を先送りして、現状に安住したりはしない。問題の把握、解決策の検討、その実現に、必死に取り組むのである。その姿が読者を惹きつけ、頁をめくらせる。危機から目をそらす者たち(それは政権の側にも国民の側にもいる)に立ち向かい、この国を滅亡から救うべく知恵を絞るその姿は、まさにヒーローそのものだ。
しかもこのヒーローは、いわゆる口だけ番長でもなければ、机上の理想像を他人事としてしたり顔で語るような人物ではない。解決策を案出するだけではなく、それを現実にすべく、政界の魑魅魍魎たちのなかで、押したり引いたりの奮闘を重ねながら、一歩ずつでも確実に前に進んでいくのである。頼もしい。
その一方でこのヒーローは、目をそらしたくなる現実を、読者に容赦なく突きつける。少子高齢化がどんな将来をこの国にもたらすのかを示し、なぜ『家族は、互いに助け合わなければならない』などという当たり前のことを政権が憲法に押し込もうとしているのかを説明し、現実を読者に直視させるのだ。その重苦しいリアルは、抜群の説得力を備え、しかも我が身の問題であるだけに、フィクションだとことわられてもなお、読み手としては頁をめくる手を止められないのである。
さらに楡周平は、孝輔や薫子という政治家の視点だけではなく、民間企業の視点も取り入れている。政治の力だけではこの国を救えないと考え、民間の側にもヒーローを配置したのだ。それが神野英明である。IT企業の社長である彼は、二人で始めた会社を急成長させ、十六年で従業員五百名、時価総額五千億円の企業に育て上げた。この人物が、薫子とはまた異なる形で、孝輔とタッグを組むのである。神野は、アイディアを現実の事業に展開し運営していくためのシビアな現状分析や行動力を企業経営者として備えており、彼のそうした力が、孝輔の〝闘い〟において重要な役割を果たす様も読み逃せない。政界と民間の連携の理想像が、それも現実の深刻さを見据えた上での現実的な理想像が、ここに描かれているのである。
本書はまた、「正義の青年」対「悪の年長者」というような単純な構図ではない点も魅力だ。意外な人物が意外なところで意外な度量を見せたりするから油断は出来ない。
こうした具合に、とにかく読ませる小説に仕上がっているのである。ほぼ全体が国の問題点に関するディスカッションで成立しているこの小説が、ここまで読みやすく、しかもワクワクするものに仕上がっているのは、もはや奇蹟と呼びたくなるほどだ。
実際には奇蹟でもなんでもなく、楡周平の力によるものなのだが、その幹となっているのが、孝輔が中心となって構想し、仲間とともに実現に邁進する政策そのものである。孝輔が(つまりは楡周平が)問題の根本原因を考え抜き、目先小手先でない解決案を提示したからこそ、その政策に説得力が生まれ、問題解決に有効だという納得感を得られるのである。それ故に読者は孝輔に惚れ、この小説に惚れ込む。その政策の凄味を――そして希望を――たっぷりとご堪能いただきたい。
外資系企業在籍中に書き上げた『Cの福音』で、楡周平は一九九六年にデビューした。
朝倉恭介という悪のヒーローが主人公のクライム・ノヴェル『Cの福音』がヒットしたことを契機に会社を辞め、専業作家として活動を開始した彼は、二〇〇一年にかけて『Cの福音』を第一作とした六部作を完成させる。その六部作は、悪のヒーローと正義のヒーローが交互に活躍し、最後の第六作で両者が対決するというユニークな構成のシリーズであった。そしてこの六作は、アクションを前面に押し出しつつも、その背後にはしっかりとしたビジネスモデルが――非合法な要素を含むが――確かにあるという点も特徴としていた。
その後も『マリア・プロジェクト』『無限連鎖』などのエンターテインメント小説を放ち続けた楡周平だが、やがてそのビジネスセンスが経済小説としても開花することになる。
二〇〇五年に発表した『再生巨流』が、その第一歩であった。左遷された男が、新たなプランを手に〝再生〟を目指す様を、楡周平は読み応えたっぷりの小説として描き上げたのである。翌〇六年には、世界有数の電機メーカーの社員の苦闘を描いた『異端の大義』、そして物流に着目した『ラストワンマイル』と二冊の経済小説を上梓するなど、この分野でもしっかり地歩を固め、さらに、新車開発を題材とする『ゼフィラム』(〇九年)、電子書籍戦争を扱った『虚空の冠』(一一年)、世界最大のフィルムメーカーが新戦略に挑む『象の墓場』(一三年)、ある商人の栄枯盛衰を綴った『砂の王宮』(一五年)など、それぞれに特色のある経済小説を放ち続ける。
こうして経済を見つめるなかで、楡周平は少子高齢化問題への言及を深めていく。
その問題への意識が最初に強く打ち出されたのが、〇八年発表の『プラチナタウン』であった。大手商社の部長職から、財政破綻寸前の東北の町の町長へと転身せざるを得なかった山崎鉄郎が、高齢者ばかりのその町で起死回生のアイディアを現実にしていく物語である。山崎鉄郎がさらに十年先、二十年先を見通して苦悩し、先手を打つ姿を描いた『和僑』(一五年)とあわせ、本書読者には是非ともお読み戴きたい。甲斐孝輔が立ち向かう日本の危機を、さらに多面的に実感できるようになるだろう。
楡周平はまた『衆愚の時代』(一〇年)という著作を通じ、現代日本への問題意識を直截に語っている。ちなみに『衆愚の時代』は小説ではなく、楡周平の言葉がそのまま綴られているのだ。派遣切り、格差社会、天下り、当時の与党(民主党だ)の未熟さなど、様々な問題について、当たり前のことを当たり前に、そして目をそらさずに論じた本なのである。その点で甲斐孝輔の視線と共通しており、注目すべき一冊だ。
政治についていえば、『プラチナタウン』と同じく〇八年に発表した『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京』という上下巻の長篇にも注目しておきたい。いくつもの病院を経営する両親の下で生まれ、東大を卒業して大蔵省に入り、ハーバードへの留学も経験した有川崇に、与党の閣僚経験者の娘との結婚話が持ち上がり――そしてどろどろの物語が続いていくという大作だ。続篇の『血戦―ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京2』(一〇年)では非情な選挙戦の緊張感を味わうことが出来る。『ミッション建国』での政界描写を堪能した方には、こちらも読んでおいて戴きたい。
現代日本の問題を、こうして見つめ続け、考え続け、本の形にして世に問い続けてきた楡周平である。彼だからこそ、この『ミッション建国』は書き得たのだ。
そして本書で指摘された危機は、今なお危機である。二〇一四年の発表当時より、さらに危機である。
だからこそ、『ミッション建国』は、今すぐに読むべき本なのだ。手遅れになる前に、読むべき本なのだ。本書が指摘した危機を自分自身の危機として認識し、政治家は政治家として行動し、そして有権者は有権者として行動すべきだ。
本書は、その際の拠り所として、実に貴重で、実に有用な一冊である。