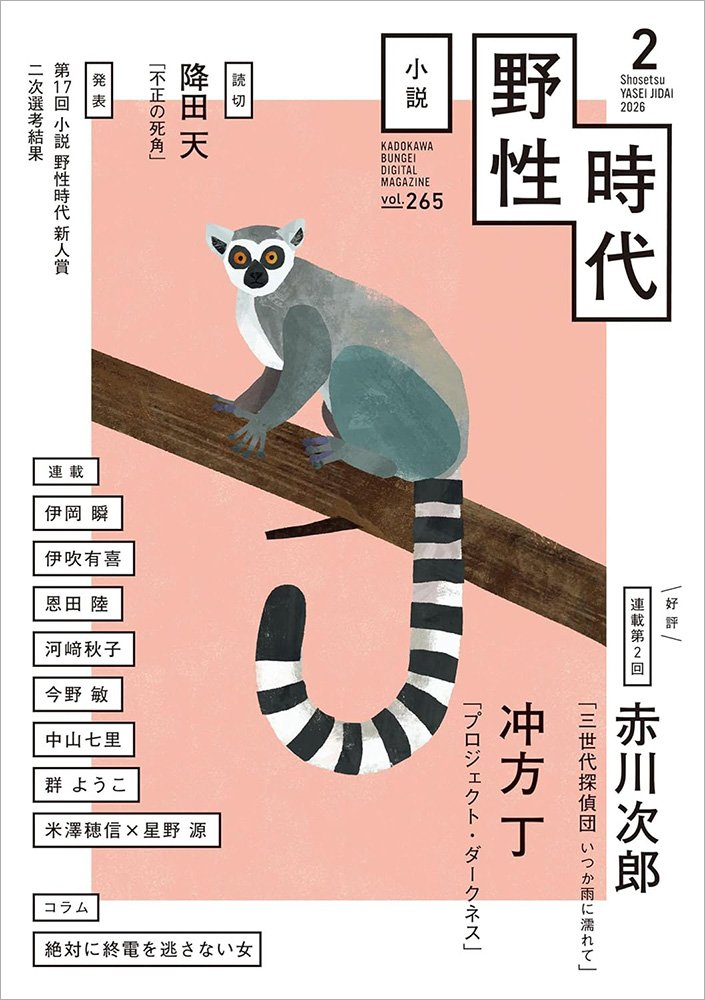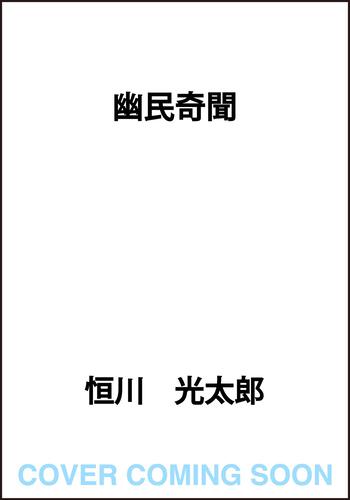「文芸カドカワ」2018年12月号では、藤井太洋さんの新連載「第二開国」がスタート!
カドブンではこの新連載の試し読みを公開いたします。

近未来の奄美大島はリゾート施設の建設に沸きかえっていた。
父の怪我を機に島に戻った昇雄太は住民の変化を感じ取る。
「雄太くん、ちょっといいね?」
野菜の棚でジャガイモを選んでいた昇雄太は、開店直後の店内のざわめきを縫って届いた大きな声が、鮮魚コーナーからだと気づいた。
声の主はすぐにわかった。田中さんだ。
毎朝、高丘のNTT社員寮から歩行補助カートを押して、開店と同時にやってくる老婦人だ。気軽な口をきいてくるのは、同窓生の田中真由美の母親だから。
反射的に「どうしました」と出かけた言葉を昇は飲み込んで、島口での言い方を探したが、どうにもわざとらしい「いもーれ(いらっしゃいませ)」や「うがみんしょーら(こんにちは)」ぐらいしか思いつかなかったので、無難な言い方を選ぶことにした。
「おはようございます。まゆちゃんのおばさんじゃがね。どうしました」
田中夫人は、まだ砕いた氷を敷き詰めただけの鮮魚ケースを指差した。
「チラシのあれよ。カツオはまだ出とらんね? たたきにして欲しいんだけどね」
そうきたか。
「ちょっと待ってくれんね」
そう言って、広さだけは立派なアマンコープの店内に首を巡らせた昇だが、十時前のこの時間にはまだ、鮮魚コーナーを助けてくれるパートタイマーの峰山さんが来ていないことはわかっていた。昨日の打ち合わせでは、開店前に店長の徳田英一が片付けておくということだったのだが、たたきどころか、その材料になるカツオすらケースに出ていない。
乳製品ケースの前では、先輩にあたるパートタイマーの叶恵美が、高い位置で結んだ髪の毛を揺らしながら品出しをしていた。
声をかけるかどうか迷ったが、やめておいた。この半年、彼女が鮮魚を手伝っているのを見たことはない。アマンコープのスタッフとしては先輩筋にあたるのだが、年齢は二つ下の三十歳だ。
中学の陸上部で後輩だった彼女が、何の因果か十七年後に現れて「先輩」になるとは思っていなかったが、よく考えれば当然の話ではある。奄美大島の最南端にある古仁屋は、昇が中学卒業とともに島を離れた十七年前ですら人口六千人、今は四千人を切る小さな港町だ。年齢が近ければ必ず学校で先輩後輩になるし、ある年代までは強制されていた部活動のバリエーションも多くない。
とにかくカツオのたたきだ。
作れないわけじゃない。一枚ぐらいならなんとかなるだろう。
昇は田中のおばさんに「ちょっと待っとってね」と言ってから鮮魚コーナーの奥に足を踏み入れた。
流しの周辺を取り囲む消毒マットで安全靴の底を拭い、消毒済みのエプロンを巻いたら、薬用石鹼で手を洗う。最後に、除菌のためのアルコールを手首までスプレーして、ひんやりとした感触を味わいながら、フィルム状の手袋をつける。紙の帽子と、唾液が飛び散らないようにするための、透明な衛生マスクをつければ準備完了だ。
昇は鮮魚ケースの裏に積んであった、氷詰めの発泡スチロールケースに手を突っ込んで、カツオを一匹ひっぱりあげた。
さあてうまく捌けるか、と思っていた昇の前には、田中のおばさんの他にも客が並んでいた。
田中さんに肘を貸しているのが、古仁屋港の向こう側にある大湊でデイケアセンターを経営している山野さん。隣には、毎週月曜日に朝九時着のフェリーかけろまで、大島海峡を渡って買い出しにやってくる具さん、そして居酒屋をやっている同級生、繁野の奥さんに、文具店の豊さん、自衛隊の前田さん、信用金庫の寮母をやっている栄さん、小学校前で駄菓子屋をやっていた二のばあさんに、Uターンしてきて粕谷電器店で働いている夢ちゃんと、町会議員の安さん。全部で十名だ。
一枚ぐらいなら綺麗に作れるだろうが、十枚まとめてなんて作りきれるだろうか。お客さん全員の名前がわかる程度には、帰ってきた古仁屋に馴染んでいることに安堵しながらも、青ざめた昇をからかうように、田中のおばさんが声をかけてきた。
「ほら、雄太くん。お客さんを集めとったからね、稼がんば!」
「じゃあ、田中さんのから」
昇がまな板にカツオを寝かせると、田中のおばさんが素っ頓狂な声を上げる。
「ちょっと待たんね。あんた、きっつけはそんなに上手くないでしょ。三匹ぐらい練習せんばよ(練習しなきゃ)」
「大丈夫」と反論したが、田中のおばさんは「三匹下ろしてからよ」と譲らない。
昇は構わず、包丁をカツオの背に入れる。水揚げされたばかりのカツオはぴんと皮が張っていて、包丁の滑り込みこそ良かったものの、背骨と中骨を切り離すために包丁を深く差し込んだところで、ねっとりとした赤身に咥え込まれてしまった。
「ほら見んね。あげたばかりのカツオは刺すたびに刃を拭わんば、脂で包丁を咥えるっちょ。一回一回、拭って刃を濡らさんば(濡らさなければ)」
田中のおばさんが勝ち誇ったように言った。そういえば彼女は、昇が中学生ぐらいの頃まで旦那が釣ってくる魚を売る、小さな鮮魚店の店先に立っていたはずだ。
「教えてくれんね」と昇は素直に言った。「拭って、濡らせばいい?」
田中のおばさんが大げさに頷く中、昇はカツオを五尾捌いてから串を打ってガスで表面を炙り、刺身包丁で丁寧にたたきの皿を作っていった。
「やっしゃい(見苦しい)刺身じゃがな」とか「キバレ(頑張れ)っちょ」などと囃したてられながらではあるが、大きな失敗をせずに十皿のたたきを作り終えた時には、たっぷり三十分が経過していた。
「あぃがっさまりょうた(ありがとうございました)!」
昇は、最後のたたきを手に取った安に深く頭を下げる。
オーナー店長の徳田英一からは、そんなに丁寧に応対しなくてもいいと言われているが、東京で十年以上も勤めてきたイーモールでの習慣はなかなか抜けるものではない。
昇は手袋と帽子、衛生マスクを流しの手前にあるゴミ箱に捨ててから、出刃と刺身包丁の刃に軽く砥石を当てる。雑な手入れなのはわかっているが、本格的な研ぎ方はまだ習っていないし、そもそも三十分前にやりかけていた配達に出かけなければならない。
昇は、これ以上カツオのたたきを求める客がやってこないことを確かめてから、そそくさと店内を横切って、集めている途中だったジャガイモを箱に詰めると、バックヤードに向かった。
バックヤードに入ると、三十分前に用意しておいたケージカートが出迎えてくれた。檻のような鉄枠の中に積み上げられているのは、大小二つのクーラーボックスと段ボール箱、それに米袋だ。大型のクーラーボックスは鹿児島からやってきた二十キロの冷凍豚肉、小さな方はアマンコープが契約している、嘉鉄の泊養豚所が三日前に落としてくれた絶品のロース肉。
段ボール箱は人参、玉ねぎがそれぞれ二十キログラム詰め込んである大きな箱と、キャベツ、ピーマン、落花生の十キロ箱。そして一番安い米が十キログラムの袋で五つ。今日は夕食に五十人分のカレーを作るのだという。
あとは業務用のサラダオイルの一斗缶に、衣類、住居、食器用の各種洗剤とトイレットペーパーなどの日用品が詰め込まれたプラケースが一番上に置いてある。
合計二百キログラムでお値段にして十八万円、粗利はざっと六万円にもなる。これだけのものを一週間に三回も買ってくれるお得意様は、古仁屋から車で一時間走ったところにある西古見集落のリゾート建設現場だ。
昇は店内から持ってきたジャガイモの段ボールをケージに入れて、照明の少ないバックヤードを押していった。プレハブ事務所のような大型冷凍庫が一基に、銀色の冷蔵庫が三基、サイズは大きくないが専用のチルド庫まで並んでいる。
反対側の壁には薄緑色の鉄製棚がびっしりと並んでいて、洗剤や定番の商品がぎっちりと詰め込まれている。昇が東京で見てきたスーパーマーケットでは、バックヤードの倉庫機能を削って売り場に背の高い什器を置き、倉庫よろしく商品を積み上げる店舗が増えてきていたが、客の八割が高齢者のアマンコープで、そんな売り場を作るわけにはいかない。
東京では見かけなくなった在庫棚の前を通り過ぎたところが、目的の搬入スペースだ。他より一メートルほど高くなった天井には、むき出しになった十文字の梁と、その梁を自由に動けるレールクレーンが設えられている。
搬入口は二つ。駐車場に面した正面のシャッターと、左手の鉄扉だ。
鉄扉の向こう側はすぐ海になっていて、アマンコープに横付けされた台船からレールクレーンで貨物やコンテナを搬入できるのだが、昇は二度しか使ったことがない。
今日使うのも、もちろん正面のシャッターだ。
閉じられているシャッターと床の境目が輝いているのに気づいた昇は、肩を落として足を止めた。安全靴のぶ厚いソールは、シャッターの隙間から差し込んだ亜熱帯の陽光で、レーザーが横薙ぎにしたかのように照らされていた。同じ光は搬入スペースの床を真横から照らして、微妙な起伏と散らばった砂つぶが縞模様を描いている。
まずい、と昇はつぶやいた。
(このつづきは「文芸カドカワ」2018年12月号でお楽しみください)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。