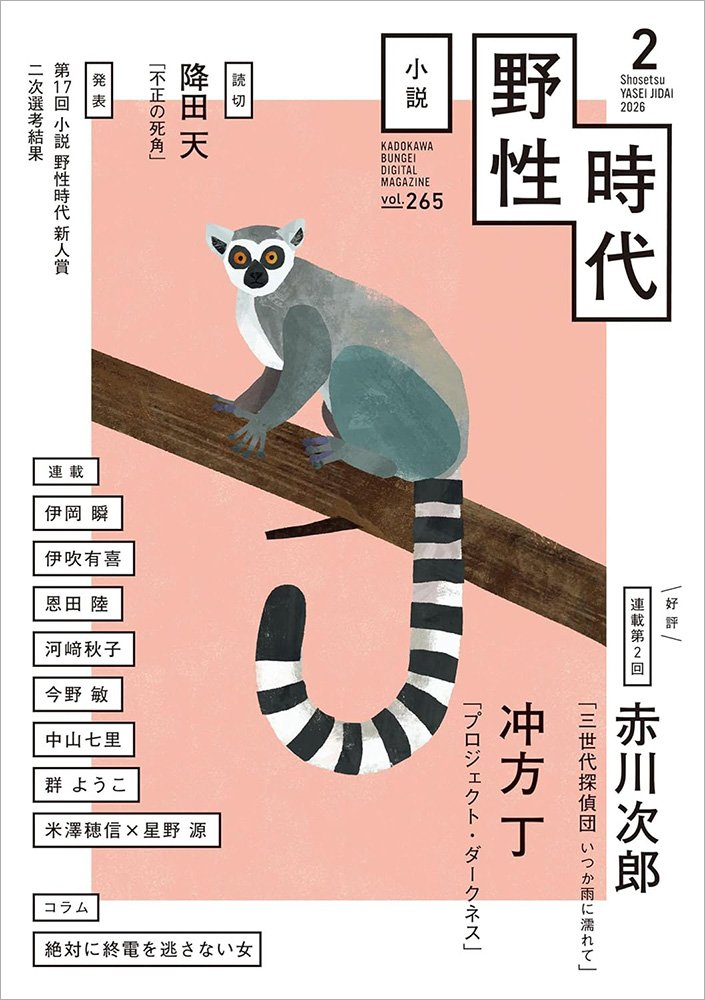ファンタジーから歴史ものまで、多岐にわたるジャンルで活躍している平谷美樹さんの新刊『よこやり清左衛門仕置帳』(角川文庫)が4月25日に発売されました。冤罪と思われる者を見つけだし、無実の者を救う小伝馬町の牢屋同心、清左衛門の活躍を描く同作。冤罪が多かったとされる江戸時代、実際の牢内の様子はどのようなものだったのでしょうか?

『よこやり清左衛門仕置帳』では、身に覚えのない放火の罪で入牢させられた材木問屋の手代、昌造の無罪を晴らす清左衛門たちの活躍が描かれています。昌造のように無事娑婆に戻れる人はいいですが、無実の罪で獄死した人も少なくありませんでした。
なかなか口を割らない囚人は獄舎のそばにある拷問蔵(せめぐら)と呼ばれる部屋で拷問を受け、その結果命を落とす者もいたそうです。やってもいない罪に対して拷問を受けるのは、肉体的にはもちろんのこと、精神的な苦痛も多分に伴うものだったでしょう。それでは具体的にはどんな拷問があったのか、いくつかを紹介します。
・キメ板……キメ板とは本来、入牢者が番人に買い物を依頼するときなどに使うもので、長さ二尺五寸(約75センチ)ほどの板。これに品物を書いて渡すと買い整えてくれるのだが、キメ板を使って入牢者を叩くこともあった。
・笞打……いわゆる鞭打。正規拷問の前段階として、罪を認めない未決囚に最初に施された。
・石抱……上記の鞭打でも口を割らない未決囚に施された拷問。後手に緊縛され、囚衣の裾をはだけて脚部を露出させ、十露盤板と呼ばれる三角形の木を並べた台の上に正座させたのち、さらにその太ももの上に石を載せて苦痛を味わわせた。
・背割り……背中への肘鉄。正座の態勢から両肩を押さえられて行われ、中には背骨を損傷する者もいた。
上記の拷問以外に牢役人による私刑(リンチ)も行われており、これも壮絶なものだったそうです。牢内には囚人たちを仕切る役人組織があり、牢名主を頂点として、上座、中座、下座、小座などの階位が設けられていました。それぞれ、与えられる畳の枚数が格を表していたそうです。私刑はこの牢役人に対して反抗的な態度を取ったとり、喧嘩をした者などに行われました。
そのほか、無実の者をスケープゴートするために密かに手を回して毒殺する、牢内に短刀を入れて自刃を促す、というようなこともあったと、江戸中期の牢内の事柄を記録した『牢獄秘録』には記されています。
(cf. http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267010)
牢内の自治は牢役人と囚人たちに委ねられていたというから、時として獄舎は無法地帯と化すこともあったとか。
そんな状態の牢内から冤罪者を救い出す清左衛門は、当事者の目にはまさにヒーローと映ることでしょう。
■あらすじ
小伝馬町の牢屋同心、清左衛門は、冤罪と思われる者を見つけだして町方の詮議に疑義を唱え、独自捜査を行うことから「よこやり清左衛門」と呼ばれていた。そんな清左衛門の助役となった政之輔は、初出仕日に火付けの罪で入獄している昌造と面会する。無実を訴える昌造を助けるため真相究明に乗り出す二人だったが、やがて事件は幕閣の政争にまでたどり着き……。罪なき者を救うべく奔走する男たちの姿を描いた、感動時代小説!
https://www.kadokawa.co.jp/product/321901000151/