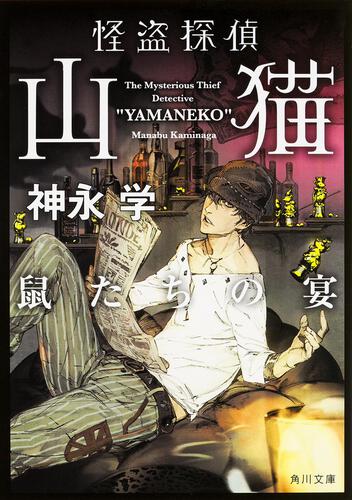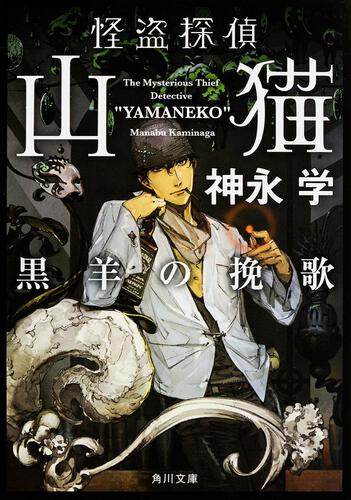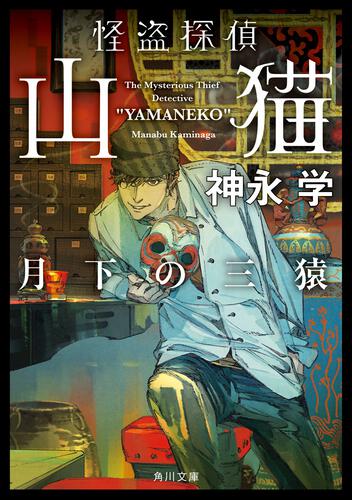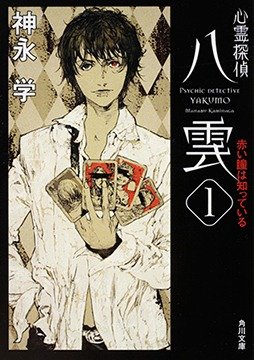16
「何で、この女を連れて来た?」
バーに戻るなり、山猫が不機嫌な態度を隠そうともせずに詰め寄って来た。
勝村は、カウンターのスツールに座ったまま、黙っていた。
何でと問われても、特別な理由などない。
「
山猫が、顔を近づけ勝村を
「あのまま、あそこにいたら、あいつらに何をされるか分かったもんじゃない。放っておけるわけないだろ」
勝村も、ついむきになり、食ってかかるような口調になる。
テーブル席に座っているサキは、生きているのを疑いたくなるほど顔色が悪く、無気力にうな垂れていた。
「この女は、お前をあいつらに売ったんだぞ。お前のすっとぼけた頭でも、それくらい分かるだろ」
山猫の
「分かってるよ。それくらい」
「分かっているなら、なぜだ?」
「そんなこと言っても、仕方ないじゃないか。あんな奴らに囲まれて、彼女に、他に選択肢があったとでも?」
「本当に、お前って奴は、思いの外面倒臭い男だよ。冷静かと思えば、すぐに熱くなる。そのうえにお節介だ」
「余計なお世話だよ」
勝村は、山猫から目をそらした。
さくらにも、同じようなことをよく言われていた。そういう気質なのだから、言われて直せるものでもない。
「お前の世界じゃ、お
山猫が、勝村の胸に何度も指を突きつける。
安い挑発だと分かっていながらもついつい熱くなり、山猫の手を払いのけた。
「言っとくけど、ぼくは、君の世界の住人になったつもりはない! 今井さんの事件の謎を追うために、仕方なく一緒に行動しているだけだ!」
「おうおう、言ってくれるね。俺だって、お前なんて願い下げだね」
「ごめんなさい」
二人の男の子どもじみた言い合いに、サキが割って入った。
マスカラの混じった黒い涙がボロボロと頰を伝う。
女性の涙を目の前にして、争いを続けられるほど無神経ではない。勝村は、言いかけていた言葉を飲み込んだ。
「私が……
「いや。君のせいじゃない」
勝村は、テーブル席に移動し、彼女の震える肩に触れ、落ち着かせようとする。
サキが、上目遣いの、すがるような視線を向けて来た。
彼女は、男に依存するタイプなのだろう。誰でもいいから、誰かに支えてもらっていないと不安で夜も眠れない──そんな風に、勝村には感じ取れた。
「勝村さん。私、これからどうすればいいんでしょう?」
サキが、勝村に抱きつきながら言う。男は、本能的にこういうタイプの女性に弱い。
「そんなものは、自分で考えろ! 俺たちの知ったことじゃない!」
山猫の厳しい言葉に、サキが顔を上げた。
今までそんな
山猫は、サキの反応などお構いなしに、冷凍庫の中から氷を取り出し、タオルで包み、
「
それを受け取ったサキは、しばらく何かを求めるように山猫を見ていたが、やがて氷囊を頰に当て、
山猫はいかにも合理主義を気取っているが、意外に情が深いのかも知れない。
考えてみれば、サキのことが気に入らないのなら、このバーに来る途中で置き去りにすることもできたはずだ。
だが、山猫にはそれができなかった。
勝村は、今まで、都市伝説のように得体の知れない存在であった山猫を、急に身近に感じてしまった。
「この女の対応は後で考えよう。それより、例のネックレスは?」
山猫が、マッチで煙草に火を
勝村は、スツールに戻り、ジャケットのポケットからネックレスを取りだし、カウンターの上に置いた。
改めてそのネックレスを観察してみる。
銀色に光る細いチェーン。桜の花弁の装飾。
よく見ると、装飾の裏には不規則な数字が並んでいた。〈981469〉。見たことのない数字だし、連想されるものは何もない。
何か細工がないかと、いろいろいじってみたが、チェーンの部分も含めて変わったところは何も見当たらない。
「何か気付いたことはあるか?」
山猫はくわえ煙草で、ダーツの矢を指先でクルクル回しながら
「見当もつかない」
勝村は、大きく首を振った。
「今井が隠した、情報の在り
山猫が、ぼやくように言う。
──この数字が場所を示すためのキーワードになっているのだろうか?
文字が入っていれば、それも考えられるが、数字だけでは判別のしようがない。
「やっぱり分からないよ」
勝村は、虚脱感に襲われ、顔を上げた。
さっきまで一緒にネックレスを見ていた山猫が、真剣な
サキは、タオルを頰に当てながらも、周囲に視線を走らせ、しきりに何かを警戒している。
ひゅっ──。
山猫は、突然ダーツの矢をサキに向かって投げつける。
矢は、寸分の狂いもなく、円テーブルの中央に突き刺さった。
サキが「きゃっ」と小さく悲鳴を上げて立ち上がる。
「危ないじゃないか!」
勝村の抗議を無視して、山猫は驚きで固まっているサキの近くに歩み寄り、クンクンと犬みたいに音をたてて彼女の臭いを
サキは、身を硬くして、じっと息を殺している。
「いつからだ?」
山猫が訊ねると、サキが驚いた表情で顔を上げる。
「な、何が……でしょう……」
事情は分からないが、サキが誤魔化そうと必死になっているように感じられた。
目が、アニメのキャラクターのように
「
勝村は、山猫の放った意外な言葉に驚き、サキに視線を向けた。その表情は、仮面を
「……一ヶ月くらい前から」
しばらくの沈黙の後、死に際の遺言のように頼りない口調で、サキが言った。
「
サキが顔を背ける。
だが、山猫はそれを逃がさない。回り込んでサキの視線の前に立ち
「今井さんの友だちから……」
「もっと他の言い方があるだろう」
山猫が、
「あの人たちです……」
「あの人たちとは、お前と一緒にいた奴らのことだな」
念押しする山猫の言葉に、サキが
そのやり取りを聞いていた勝村は、信じられない思いで、貧血を起こしそうなほど頭が真っ白になった。
サキは、最初から、彼らを知っていたということなのか──。
「奴らは何者なんだ?」
「知りません。私は、あの人たちがお店に来た時に、売ってもらっていただけなんです……。本当です。信じて下さい……」
サキが、山猫の両手を握り必死に訴える。
おそらくサキがあの二人組の顔は知っていても、名前を含めた素性を知らないというのは本当だろう。
買い手に自分の素性を明かすなど、売人にしてみれば自殺行為だ。
山猫はサキの手を振り払い、勝村の隣のスツールに腰を下ろし、
「どうして、彼女がマリファナをやってるって分かったんだ?」
勝村は、疑問をぶつけた。
「臭いだよ。マリファナの常習者には、煙草と同じように独特の臭いがつく」
山猫は、当たり前のように口にした。
「もしかして、甘酸っぱい臭いだったりするの?」
勝村は、サキに初めて会った時のことを思い出し、口にしてみた。
「その通りだ。フルーツみたいに甘酸っぱい臭いがする」
「ぼくは、香水かと思ってた」
「だから、お前はバカなんだよ」
山猫はそう言うと、身を乗り出し、カウンターの下からグラスを二つと、ウィスキーのボトルを取り上げる。
「あ、ぼくは飲まないよ。できればウーロン茶とかにして欲しい」
「ガキみたいなこと言うな。色は一緒だろ」
山猫は、それぞれのグラスにウィスキーを注ぎ、カウンターに置いた。
勝村は、ちらっとサキに視線を向けた。
彼女は、じっと俯いたままピクリとも動かない。山猫の言う通り、彼女を助けるべきではなかったのかも知れない。
少し
山猫はそれを見て鼻で笑うと、これみよがしにグラスの中身を一気に飲み干す。
「これで、一つ謎が解けた」
山猫が、腕で口を
「謎?」
「そうだ。俺には不思議でならなかった。今井という男は、なぜ、あの女を通じて情報を伝えるなんて、回りくどい方法をとったのか……」
──確かにそうだ。
直接メッセージを届けてくれればいいのに、わざわざサキを通してメッセージを伝えた。それはなぜか?
勝村は、すぐにその理由に思い至った。
「彼女が、マリファナをやっていることが、ヒントになっているってこと?」
「多分な。それに、さっきの話の流れからして、今井も、奴らと面識があった」
山猫の言葉は、心に深い影を落とした。
今井は麻薬を売るような連中と、いったいどんな付き合いがあったのか?
それだけじゃない。自分の恋人がマリファナをやっていると知り、なぜ止めなかった?
──あなたは、ぼくに何を託そうとしているんですか?
勝村は、ネックレスを手に取り、ゆらゆらと揺れる花びらを眺めた。
このつづきは製品版でお楽しみください
▶神永学『怪盗探偵山猫』| KADOKAWA
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
▶神永学シリーズ特設サイト