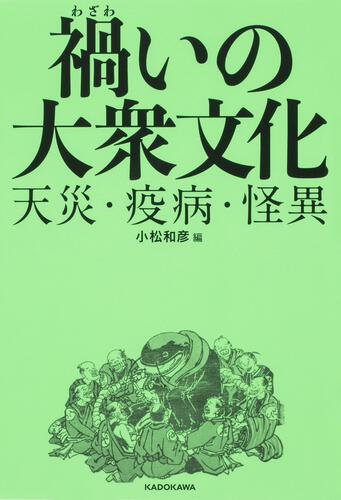『禍いの大衆文化――天災・疫病・怪異』試し読み 第2回
致死率最大50%! 恐怖の感染症に人々はどう対峙したのか。『禍いの大衆文化――天災・疫病・怪異』(KADOKAWA)から、香川雅信先生(兵庫県立歴史博物館)による、「疫病を遊ぶ――疱瘡神祭りと玩具」の一部を再編集して、特別公開します。
▼第1回はこちら
疫病や災害の中にあっても、なぜ人々は新たな表現を生み出してきたのか……妖怪学の第一人者・小松和彦先生による、疫病と天災をめぐる大衆文化論の試し読み
https://kadobun.jp/trial/wazawainotaishubunka/7vo5rkqvx88w.html
疫病を遊ぶ――疱瘡神祭りと玩具(香川雅信)
恐れられた疱瘡
疱瘡(医学用語としては痘瘡、天然痘とも)は、かつて全世界で流行し、最も恐れられた疫病の一つだった。
非常に強い感染力を有し、感染すると7~16日の潜伏期間を経て発症する。発熱などの初期症状の後、全身に豆粒状の
しかし、1796年にイギリスのエドワード・ジェンナーによって開発された史上初の予防接種である種痘(牛痘種痘法)が普及したことで、この疫病は根絶への道を歩み始めることになる。1977年のソマリアでの報告を最後に自然感染は見られなくなり、1980年、WHO(世界保健機構)は疱瘡の地球上からの根絶を宣言した。これはヒトに有害な感染症として人類が根絶することのできた唯一の事例である。
日本においては、『続日本紀』に記された735(天平7)年の
「疱瘡神祭り」とは何か
貝原好古が1683(天和3)年に著した『大和事始』には、「又今の
痘科(疱瘡の専門医)であった池田錦橋が1806(文化3)年に著した『
国々によりて、神棚具 物 祭の法などちかふ事ありといへとも、大体 家の入口に注連縄張りて、紅紙 にて幣を垂れ置、又房の入口にもさのとふりするハ、穢気 不浄を避る為なり。房 内に神棚設けて〈一尺程たかくかざるもあり又天花 板のしたへつるもあり〉紅紙を敷、猩 々達磨猿面等赤き色の人形を置、或は目 出 度 人形なとかざり置もあり。何れも紅色をとり祝を取りたるなり。又御酒徳利紅紙にて口をかざり、常燈明を点し魚 菓 を具へ〈紅餅紅団子赤 小 豆 飯赤鯛あかめたるほうぼふ糸より鯛かながしらのたぐひを具ふ〉何れも紅色なるを供ふる事なり。伝へきくに、唐土 にても痘の正色 ハ紅を貴 ひ、喜慶 のことにも紅色を用 るによりて、痘瘡ある家には紅色をこのむよし。
ここにあるように、疱瘡神祭りには、赤い紙や赤色の人形、また
1703(元禄16)年に小児科医・
つまり、疱瘡の病人の身のまわりを赤い色のもので埋め尽くすのは、「似たものは似たものを生む(like produce like)」という思考法に基づいた「類感呪術(homeopathic magic)」に相当するものであると言える。
赤色の人形や玩具の役割
ここで注目したいのは、「猩々達磨猿面等」の赤い色の人形や玩具が疱瘡神の棚に飾り置かれた、という点である。こうした赤い色の人形・玩具は、見舞いの品としても多く用いられていたが、疱瘡神祭りという儀礼そのものの中に組み込まれ、重要な役割を果たしていたのである。
1798(寛政10)年刊の『疱瘡心得草』には、「疱瘡神祭る図」として下図のような挿絵がある。手前には疱瘡にかかった子どもとその両親、その後ろに疱瘡神を祭る壇が設けられ、供え物を載せた皿や御神酒・灯明などが置かれているのがわかる。目を引くのは、壇の中央に置かれた人形である。右手に柄杓、左手に盃を持ち大きな酒甕に乗った姿で表されたこの人形こそが、『国字痘疹戒草』でも触れられていた「
猩々とは、元来は人の顔に猿の体、人語を解し、酒を好むという中国の想像上の動物であった。しかし、なぜか日本では、猩々は海中に棲み、汲めども尽きぬ酒が湧き出す酒甕を有する福神として能の中に登場するようになった。その姿は、赤い髪、赤い顔の童子であらわされ、江戸時代には木彫りや張子の人形のほか、笛人形(笛を吹くと酒甕に乗った猩々が回転する)や浮人形(水に浮かべる人形)など、玩具の題材として好まれた。
江戸生まれの旅芸人・富本繁太夫の日記『
当所は疱瘡神を祭に猩々祭りと言て張子の猩々人形酒甕に干杓抔持し形有り、是をさんだわらの上へ為乗、其脇へ張子の達磨を置く。都て余は江戸の通り
ひるがえって「疱瘡神祭る図」を見てみると、中央に「張子の猩々人形酒甕に干杓抔持し形」、そして確かに脇に張子の達磨らしきものが置かれている。「猩々祭り」の別名があったことからもわかるように、猩々の人形を疱瘡神祭りに用いることは、少なくとも京都ではポピュラーであったようだ(ちなみに『疱瘡心得草』は京都の平安書林の刊行である)。
もっとも、富本繁太夫が「
猩々 、達磨 、ミミズク
猩々の人形が疱瘡神祭りに用いられるようになった理由が、「赤色」を第一の特徴としている点にあるのは明白だろう。猩々は酒好きであり、そのためいつも赤ら顔ということで、能の中では赤い色の面をつけている。また、髪も着物の色も赤く、その人形はまさに疱瘡にとって縁起のよい「赤ずくめ」である。下鴨神社(
また張子の達磨は、倒しても起き上がるというところから、病人が「起き上がる」こととかけて病気平癒のまじないとしたというのが理由の一つのようである。例えば1850(嘉永3)年刊の『疱瘡画本雛鶴笹湯寿』には、張子の達磨について、「なげほかしてもおきあがり、色も赤くいろどりしものゆゑ、疱瘡の子おきあがるを祝ひて疱瘡第一の手遊とするはよしあることなりけり」という記述がある。ここに見えるように、達磨の赤い色も大きな理由の一つであった。赤い衣をまとった達磨大師像は、すでに宋の時代から描かれていたという。
一方、張子のミミズクについては、なぜ疱瘡神の棚(疱瘡棚)に飾られるようになったのかはよくわかっていない。1767(明和4)年の『風流狐夜咄』巻ノ四「疱瘡神の迷惑」に「それに近年はほうそうのまじないなりとて、小ともの持あそびにこしらへ置たるはりこの耳づくを、荒神のたなへあげ、みきそなへをくうしまつるなり」とあることから、やはり18世紀の半ばには張子のミミズクを疱瘡神祭りに用いることが始まっていたと考えられる。また、達磨とミミズクを並べて飾る習慣が、それからしばらくして定着を見たことが、1779(安永8)年刊の噺本『気のくすり』に見える次の
けふ珍らしい物を見た。「何を「両国の薬うりの所に、生た木兎が有た「それが何、珍らしい物だ。おれハ度々見た。木兎の生たハ随分見かけるが、だるまの生たのがないものさ
この小咄は、生きたミミズクがおそらくは客寄せのために薬売りの店先に置かれていたということも伝えてくれている。1824(文政7)年刊の『
ただ、達磨とミミズクをセットで飾るということには、何となく作為的な匂いがする。こうした風習は、玩具を商う人々によって「創られた」伝統ではないかという疑念を覚えずにはいられない。これは猩々の人形に関しても同様である。
創られた「疱瘡神祭り」
1749(寛延2)年の板行とされる草双紙『
実は、この『疱瘡除』という草双紙は、京都・大坂で行われた疱瘡神の開帳に合わせて作られたものであったようだ。若狭小浜の町年寄であった
組屋六郎左衛門家に伝り候疱瘡の神の事は、永禄年中に組屋手船北国より上りし時、老人便船いたし来り、六郎左衛門方に着。しばらく止宿にて発足の時、我は疱瘡神也、此度の恩謝に組屋六郎左衛門とだに聞は疱瘡安く守るべしとちかひて去ぬ。六郎左衛門其時の姿模様を画にうつし留し也。今有所の物かくの如し。寛延年中京大坂にて開帳あり
組屋六郎左衛門は小浜随一の豪商で、その家には疱瘡神の御影とされる絵が伝わり、疱瘡の守り札を戦後に至るまで出していたという。注目したいのは、末尾の「寛延年中京大坂にて開帳あり」という記述である。組屋六郎左衛門家に伝来する疱瘡神の御影の開帳を行う際、その霊験を喧伝するためにこの『疱瘡除』という草双紙が作られ、ネガティブなイメージのある疱瘡神をポジティブなものに転換するために、めでたい猩々のヴィジュアルが用いられたと考えると、猩々の人形を疱瘡神祭りに用いることもまた、これに合わせて「創られた」と推測することができる。このように、玩具を用いる疱瘡神祭りが成立した背景には、出版にたずさわる者たちや玩具・人形を扱う業者などの関与を考える必要がある。
いずれにしても、猩々、達磨、ミミズクの張子といった玩具を疱瘡神祭りに用いる風習が、18世紀半ば頃を境に定着していったことは間違いないだろう。ここであらためて、現代に生きるわれわれが感じるであろう疑問を発してみることにしたい。なぜ、疱瘡という忌まわしい病気に対し、その疫病神を祭るという儀礼が生まれたのか? なぜ、病気とは対極の位置にある「楽しさ」の象徴とも言える玩具が、儀礼の中に組み込まれることになったのか?
それを解き明かすために、江戸時代において疱瘡とはどのような病気だったのかについて見ていくことにしよう。
――
人々は疱瘡をどのように「遊ぶ」のか。昨年注目を集めた「アマビエ」とは何だったのか――。このつづきは本書でお楽しみください。
(参考文献)
立川昭二『近世病草紙─江戸時代の病気と医療─』/ジェームス・G・フレーザー(小野泰博訳)「共感的呪術」、喜田貞吉「福神としての猩々」/谷川健一他編『日本庶民生活史料集成 第二巻 探検・紀行・地誌(西国篇)』/佐藤文子「近世都市生活における疱瘡神まつり─『田中兼頼日記』を素材として─」/木戸忠太郎『達磨と其諸相』、藤岡摩里子「疱瘡除けミミズクの考察─―疱瘡絵を中心として」/藤岡摩里子『浮世絵のなかの江戸玩具 消えたみみずく、だるまが笑う』/大島建彦『疫神とその周辺』
小松和彦編『禍いの大衆文化――天災・疫病・怪異』
<目次>
序 疫病と天災をめぐる大衆文化論の試み(小松和彦)
第一章 疫病と怪異・妖怪──幕末江戸を中心に(福原敏男)
第二章 疫病を遊ぶ――疱瘡神祭りと玩具(香川雅信)
第三章 鯰絵と江戸の大衆文化(小松和彦)
第四章 幕末コレラの恐怖と妄想(高橋 敏)
研究ノート 火事・戯文・人名――『仮名手本忠臣蔵』のパロディをめぐって(伊藤慎吾)
第五章 風の神送ろッ――説話を紡ぎ出すもう一つの世界(高岡弘幸)
第六章 大蛇と法螺貝と天変地異(齊藤 純)
第七章 岡本綺堂と疫病――病歴と作品(横山泰子)
第八章 近代、サイの目、疫病経験――明治期の衛生双六にみる日常と伝染病(香西豊子)
第九章 変貌する災害モニュメント――災害をめぐる記憶の動態(川村清志)
小松和彦編『禍いの大衆文化――天災・疫病・怪異』
定価:2,750円(本体2,500円+税)
▼小松和彦編『禍いの大衆文化――天災・疫病・怪異』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000165/
amazonページはこちら