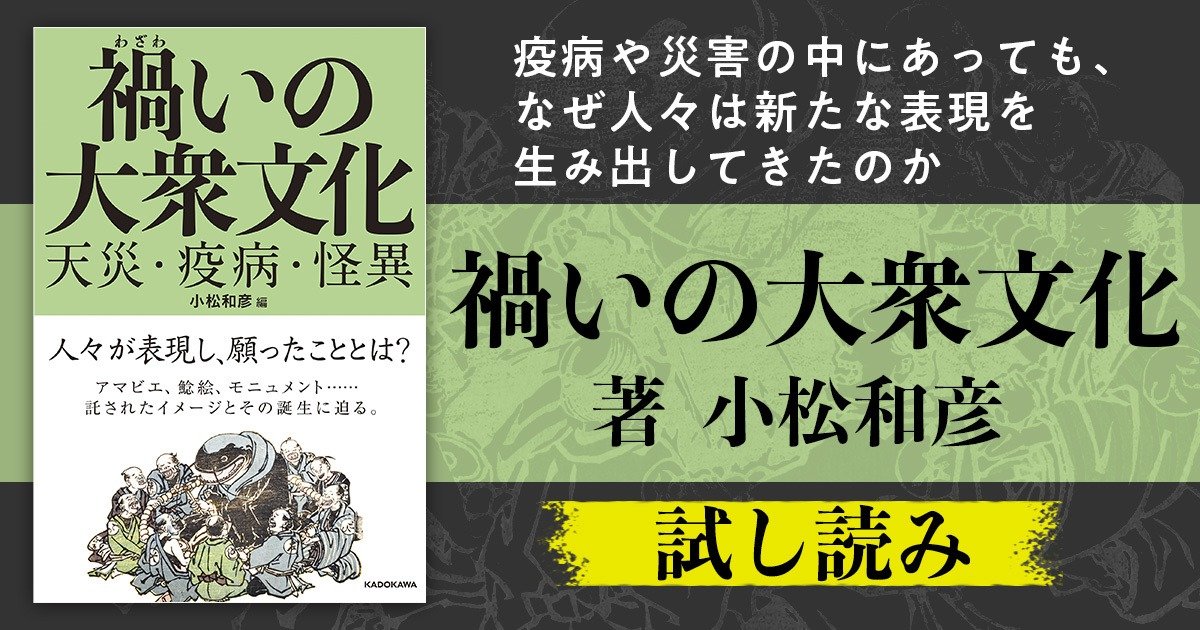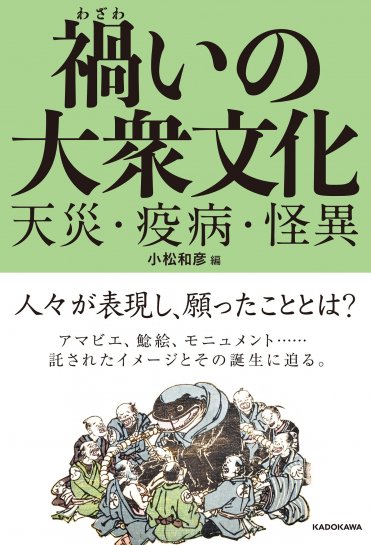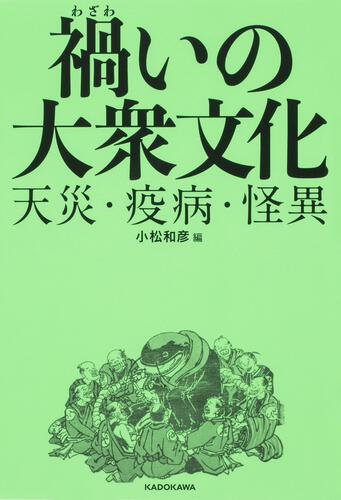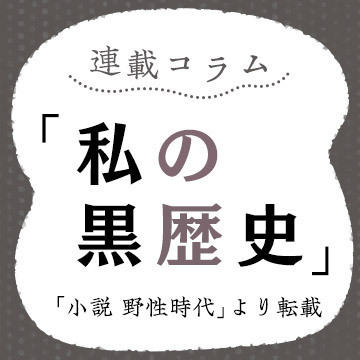キーワードは「欲望」!? 『禍いの大衆文化――天災・疫病・怪異』(KADOKAWA)から、序の一部を特別公開します!
疫病と天災をめぐる大衆文化論の試み(小松和彦)
日本列島は災害列島だとしばしば評される。たしかに、日本の歴史を振り返ると、毎年のようにどこかで大雨や地震などの被害を受け、疫病の流行が繰り返されてきた。
本書のテーマは、こうした自然がもたらす災厄・災害に対して人々がどのように対応してきたのかを、「大衆文化」に焦点を当てて探ることにある。
疫病や地震などの「禍い」に襲われた大衆の反応は、いうまでもなく「恐怖」であり、それから逃れるためのさまざまな工夫であり、「怒り」や「悲しみ」などの昂ぶる感情の鎮静化であった。そしてそうした体験は大衆の想像力を大いに刺激し、やがて文学や絵画、芸能などに表現され、また防疫・防災の強化やモニュメントの建設などにつながっていった。ここで言う「禍いの大衆文化」とはこれらすべてを指している。
ここでは「大衆」という語を用いているが、「民衆」や「庶民」「常民」「人民」と置き換えてもかまわないと考えている。もちろん、それぞれの用語にはそれぞれの定義がなされ、また重なりあう面もあればズレもある。しかし、そこに共通して見出されるのは、本書に先だって通史的意味をもって編集された『日本大衆文化史』で喝破されているように、「群れ」としての人々である。すなわち、ここで言う「大衆文化」とは、この「群れ」が生み出した文化であり、当然のことながら、その「作者」は「群れ」であるわけだが、さらに念を押せば、その文化を享受したのも、この「群れ」であった。
詳しくは前掲書を読んでいただきたいが、本書の編者なりの「群れ」についての理解を簡単に述べておこう。この「群れ」としての「作者」と「群れ」としての「享受者」は、協同・共犯関係にある。そして、この関係を支えているのは、快楽やカタルシスなどのさまざまな「欲望」である。この「欲望」は、直截に表出する場合もあれば、無意識の状態で示される場合もあるが、いずれにしても、「享受者」の「欲望」を十分に満たすものが大衆文化として定着したものであった。そこには芸術的であるとか高級であるとかいった評価も含まれてはいるが、それよりもまず優先されたのは、この「欲望」が何かを嗅ぎつけ、それに応えるように作られた作品であることだった。
もちろん、大衆文化を生み出し送り出す「群れ」のなかには、無名に混じって有名な人もたくさんいる。しかし、彼らも「群れ」としての「享受者」の「欲望」が何かを察知し、その「欲望」に応えるために、「群れ」としての「享受者」に代わって「欲望」に「言葉」や「形」を与える人々であって、それに成功するかどうかが彼らの生活を左右していたのである。
「享受者」の「欲望」は多様であった。ときに体制批判であったり、性(エロス)であったり、災害であったり、身の廻りで起こる事件であったり、珍奇なもの、グロテスクなものへの嗜好でもあった。それは「興味本位」「低俗」「下品」などといったレッテルを貼られて軽く見られがちであるが、大衆の特徴はそこにこそ見出されるべきなのである。
「群れ」としての大衆文化の「作者」とその文化の「享受者」は、同じ「欲望」に支配されているという点で深く結びつき重なる。そしてその両者を媒介したのが、マス・メディアすなわち大量に情報(文化表象)を送り出せる媒体であった。
この媒体は、日本では、まず木版技術の発達による摺り物として現われ、それを広く頒布させたのが、「本屋・絵双紙屋」であり「読売」(かわら版屋)であった。それがやがて近代になると活版になり、声という情報を可能にしたラジオやレコード、さらに映像という情報を送り出した映画やテレビが加わっていった。
留意したいのは、こうしたメディア(媒介)の助けをえながらも大衆文化の発達・浸透に大きな役割を果たしたのが、劇場や路上などで演じられる芸能であった。そこでは、「群れ」としての「作者」(もしくはその代弁者)と「享受者」が、対面的な協同・共犯関係にあり、双方の「欲望」に合致したものが「大衆文化の核」として定着した。
さきほど「享受者」の「欲望」は多様であると述べた。このことは、ある大衆文化は多くの人々の「欲望」を満たすが、ある大衆文化は「一部の群れ」の「欲望」しか満たさないようなことが生じる、ということでもある。後者がいわゆる「サブ・カルチャー」と呼ばれるものである。つまり、大衆文化としてひと括りにされているが、じつはその内部には大小さまざまな規模のサブ・カルチャーが存在しているのである。それは大衆文化内部の「分衆文化」とも言えるかもしれない。
見逃せないのは、為政者・支配者層に属する人々は、ときには「群れ」の「欲望」が自分たちの体制への批判に向かわないよう弾圧し、ときには「群れ」の「欲望」つまり大衆文化を利用して自分たちの好ましい方向に誘導したりもすることである。ようするに、「群れ」の「欲望」はまことに厄介な側面も抱えもっているのである。
(このつづきは本書でお楽しみください)
小松和彦編『禍いの大衆文化――天災・疫病・怪異』
<目次>
序 疫病と天災をめぐる大衆文化論の試み(小松和彦)
第一章 疫病と怪異・妖怪──幕末江戸を中心に(福原敏男)
第二章 疫病を遊ぶ――疱瘡神祭りと玩具(香川雅信)
第三章 鯰絵と江戸の大衆文化(小松和彦)
第四章 幕末コレラの恐怖と妄想(高橋 敏)
研究ノート 火事・戯文・人名――『仮名手本忠臣蔵』のパロディをめぐって(伊藤慎吾)
第五章 風の神送ろッ――説話を紡ぎ出すもう一つの世界(高岡弘幸)
第六章 大蛇と法螺貝と天変地異(齊藤 純)
第七章 岡本綺堂と疫病――病歴と作品(横山泰子)
第八章 近代、サイの目、疫病経験――明治期の衛生双六にみる日常と伝染病(香西豊子)
第九章 変貌する災害モニュメント――災害をめぐる記憶の動態(川村清志)
小松和彦編『禍いの大衆文化――天災・疫病・怪異』
定価:2,750円(本体2,500円+税)
▼小松和彦編『禍いの大衆文化――天災・疫病・怪異』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000165/
amazonページはこちら