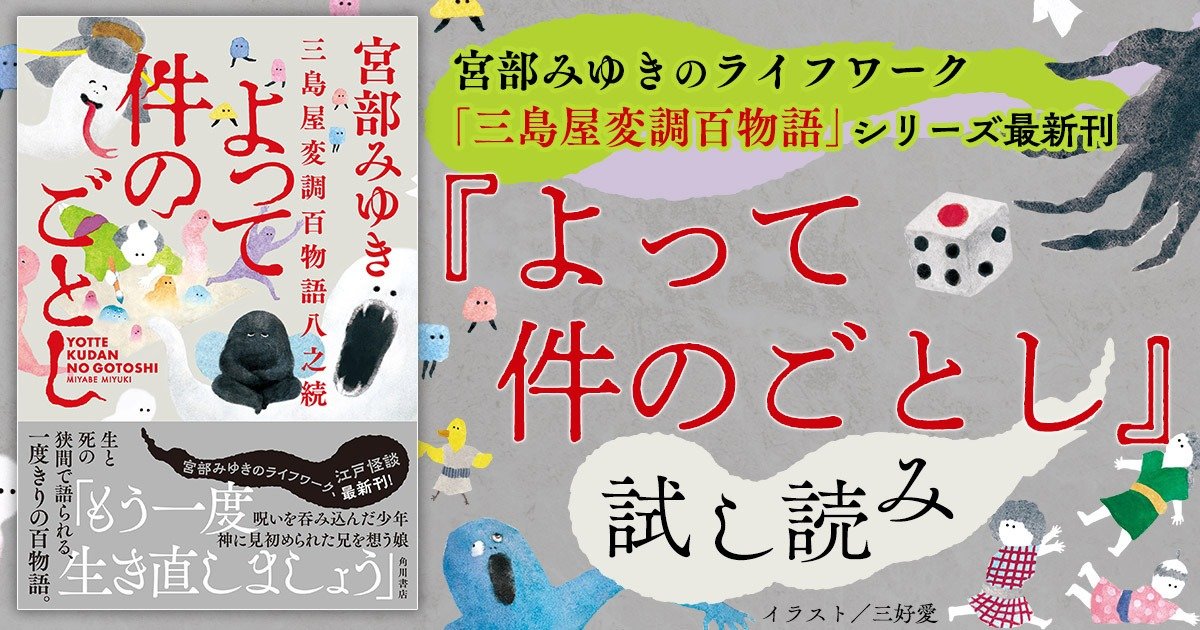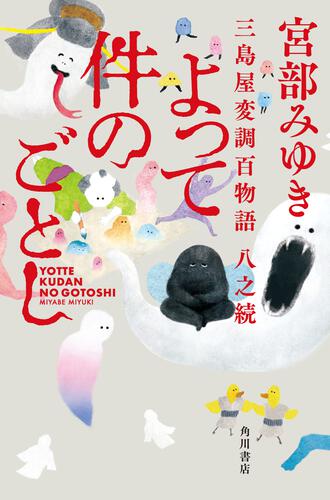それなのに。
祝言まで、あと半月足らずというときになって、いきなりおりんが返されてきた。
よく晴れた菊日和の朝で、父ちゃんと兄ちゃんは畑に出ていた。餅太郎は担ぎ売りに出かけようと、背負子に売り物を積んでいた。編み込み草鞋と干し柿と、村のあちこちに咲いている白と黄色の野菊の花束。花は小さいが香りがいいので、大畑村の旅籠ではよく売れる。
支度をしていると、遠くから何やら
だんだん近づいてくる。やがてその音に、男たちが張り上げる声もまじってきた。
「はたまぁ、むらの、まついち~、まつたろう~」
呼んでいる。あれ? うちの父ちゃんと兄ちゃんの名前じゃねえか。
「おりんが~、もどったぁでぇ~」
「おりんに~、あぶがぁ、ついたぁ」
そこまで聞き取って、餅太郎はぽかんと口を開いた。何だって? 何が起きたさ。
姉ちゃんに
語り手の座の餅太郎は、さっきの短い
富次郎の側にも、ちょっとだけ戸惑いの名残がある。語りに耳を傾けていたら、餅太郎の歳が、やっぱりわからなくなってきたのだ。
人の年齢は声にも出るが、むしろしゃべるときの調子や言葉の選び方によく表れる。これは一言二言ではなく、しゃべり続けているとよくわかる。餅太郎のそれは、富次郎と同じ歳ではなく、三十路前後でもなく、もっと年長で老成していた。
「あぶが、ついた」
念を押すために、富次郎はゆっくりと問い返した。
「今、そうおっしゃいましたよね。わたしの聞き違いじゃございませんよね」
「へえ。あぶは、ぶんぶん飛ぶあの虫でさ。真っ黒けの人を刺す虻ですよ」
「そんなものが人に憑くってのは」
気色悪いし胸が悪い。富次郎はつい、げぇっと声を出してしまった。
「いったい、どういう意味なんですか」
あいすみませんと、餅太郎は首を縮める。「あっしの
これにはちゃんと由来がある。「昔むかし、その昔」と前置きするのがふさわしい、お
「長くなりますけども、しばらく辛抱して聞いてやっておくんなさい」
大畑村があるあたり一帯、連なる山々と深い森と幾筋もの川を守護し治める
熱心に賭けて遊べば遊ぶほどに、産土神様は強くなった。いつしか、
ろくめん様は大きな勝負に挑んでは勝ち、挑んでは勝ち続けた。手持ちの山を賭けて勝ち、一夏この地に降る雨を賭けて勝ち、春の山で産声をあげる全ての獣の
勝負の相手の神々も、自分の持ち物である大事な自然や生きものや産物を賭けてくる。ろくめん様はそれらを勝ち取り、ご自分の土地のものとした。
大畑村の鎮守の
近隣のどこにもないのに、ここらの野にだけに咲く花々。優れた生薬の
博打に強いろくめん様のおかげで、大畑村の一帯は豊かになった。
だけど、どんなに強い博打打ちでも、いつかは負けるときがくる。ろくめん様もあるとき、賭け双六の勝負でこっぴどく負けた。ろくめん様が道半ばも行かないうちに、相手はさっさと上がってしまった。
「その相手が、虻の神様だったんでさ」
虻の神。そんなものがいるというのが、まず富次郎には驚きだ。
「え。虫の神様じゃないんですか。虻だけの神様なんて……」
餅太郎は、富次郎の驚きに鼻白む。
「善い虫も悪い虫もいるんだから、神様だってそれぞれいるに決まってらあね」
なるほど。すみませんでした。
「ろくめん様はその勝負に、自分の治める土地の畑で一年のうちにとれる作物全部を賭けちまってたんです」
ろくめん様を手厚く敬い、慕ってやまぬ氏子たちが汗水たらして耕した畑の作物を、まるごと賭けてしまっていた。
これは参った。負けた以上は賭けたものを奪われる。氏子たちが
ろくめん様は大慌てで虻の神に謝り、我が氏子たちのために、どうか勘弁してもらえぬかと頼み込んだ。
─そのかわり、今後我の治める土地では、二度とあなたを殺さぬ。氏子たちにはあなたを叩き
勝負を見守っていた八百万の神々は、これまでさんざんろくめん様に負かされていたから、そんな手前勝手な申し出が通るものかとお怒りになった。
しかし、虻の神は承知した。
「虻の神様はまるっきりのバカだから、ものの損得がわからねえんだ」
そもそも虻の神が勝負に勝てたのも、おつむりの方はさっぱりで何も考えていないため、無欲だったからなのである。賭け事にはしばしばそういうはずみがあり、だから怖いし面白いのだ。
虻の神は承知して、しかも大いに喜んだ。
─これまで、どこのどんな神が治める土地でも、我と我が
さらにろくめん様は、怒りが収まらぬ他の神々に、今日を限りに二度と丁半博打も賭け双六もしないと誓った。だが、皆様は今後も賭け事を楽しめるよう、賽子を差し上げよう。我が氏子どもが我に
これでようやく八百万の神々の怒りが解け、ろくめん様は許されて、虻の神を伴ってご自分の治める土地へ帰ってきた─
「と、こういうお伽話なんですけども」
餅太郎はふうと息をつき、指で鼻筋をほりほりと
「大畑村と六つの分村では、本当に虻を殺さねえんです」
父ちゃんが子供のころからそうだった。父ちゃんの父ちゃんのころもそうだった。うんと昔からの習いなのだ。
「ろくめん様が、鎮守様の
それもまたお伽話ふうである。
「刺されると血を吸われて、
念の入ったことに、毎年夏の虫送りの焚き火の際には、数日前から人びとが畑や道ばたで、「虻様はよけていなされ~、虻様はよけていなされ~」と呼ばわるのだそうだ。虫送りの行事をしているあいだ、虻はどこかに逃げて隠れておれ、と。
「だから、うちの方じゃ虻がみんなでっかく太りかえって、
その様を思い浮かべると、富次郎はまた「げぇ」という気分になった。
「そうすると─餅太郎さんの故郷では、虻は産土神のろくめん様が自ら招かれた賓客の神なんですね」
「ひんきゃく?」
「あ、大事なお客様ということです」
そうそうと、餅太郎はうなずく。
「けど、ちゃんとしたお社や
居候でも神は神だ。ろくめん様の氏子はみんな、虻の神様の氏子にもなる。氏子は神様を拝み、守護やご利益を願う。神様は氏子の願いを受け止める。
そこが厄介なのだった。
「そもそも、人や獣の血を吸う害虫の神様ですよ。善いことを願ったってかなえられやしねえ。バカだから、やっちゃいけねえことがわからねえ。だもんで─」
ろくめん様の氏子たちは、ろくめん様にはお聞かせできない後ろ暗いこと、
そう、他人を呪う悪しき願いだ。
蝉みたいに太りかえった虻どもは、みんな虻の神の眷属だ。ろくめん様の土地を、好きなように飛び交っている。
呪いを胸に秘める者は、山道でも畑でも、沢でも森のなかでもいい、行き合った虻に己の血を吸わせて名を名乗り、こう呼びかければいい。
─虻の神様にお取り次ぎくだせえ、お願いがござんす、お取り次ぎくだせえ。
呼びかけ続け、血を吸わせた虻の数が九十九匹目に達したとき、邪な願いは聞き届けられ、呪いは成就する。
虻の神様はバカだから、やっちゃいけないことがわからない。聞き届けちゃいけないことでも聞き届けてしまう。
ちょっと声を落として、餅太郎は続ける。「虻の神様の呪いは、呪った者じゃなくて、呪われた相手の方に〈しるし〉が示されるんですけども」
その〈しるし〉を知れば、本人だけでなく、まわりの誰にでも虻の神の呪いだとわかる。不快で残酷なその〈しるし〉とは、
「呪われた者が何か食おうとしたり、飲もうとしたりするとね」
その食べ物や飲み物のなかに、虻が出てくるのだ。
よそったばかりの
蝉と見間違うほどに太りかえり、黒々とした
「し、し、し」
悪寒を堪えて、富次郎は問う。
「し、
語り手の座の餅太郎は正座して、
ああ、言いにくい。申し訳ない。けど言わねえわけにはいかねえから、
「死にかけなんです。じじっ、じじって音を出して、脚を動かしてて」
「うわぁ」
思わず富次郎は身をよじり、四つん
「三島屋さん、あっしはここで帰ります。やっぱりこんな話─」
「ううう」
雪見障子を開け放って縁側まで出て、縁先から小雨の滴る庭へ頭を突き出して、富次郎はえずいた。気が済むまでげえげえやって胸が空っぽになったら、座り直して大きく息を吸う。
─しっかりしろ。こんなんじゃ、おちかに合わせる顔がない。
「こちらこそ失礼しました」
もとのように障子を閉め、羽織の前を揃えて整えて、ちゃんと立って歩いて着物の裾を払って、聞き手の座に戻る。
「それから餅太郎さん、わたしのことは〈三島屋さん〉ではなく、富次郎でけっこうですよ。何なら
むきになって言う声が、まだちょっぴり震えてしまう。
「ああ、へえ……そんな、ねえ」
餅太郎はぺしゃんこに
「あいすみません。どうぞお話を続けてください。みっともないところをお見せしましたが、これも、虻の神様の呪いの怖さがよくよく身にしみたからでございます」
そんな〈しるし〉をつけられた日には、呪われた者は、一切飲み食いできなくなってしまうじゃないか。
「誰かほかの人に食べさせてもらったり、飲ませてもらった場合でも、その、虻は出てくるんでしょうか」
おそるおそる富次郎の顔色をうかがい、目を
「そうなんです。たとえば、そばにいる者に食わせてもらおうと、飯や汁をあ~んってやっても」
「その
「そう、本人には見えちまう。この〈しるし〉の虻は、呪われた当人にだけ見えるんさ」
この虻は憑きものなのだ。だから〈虻が憑いた〉と言うのである。
富次郎は言った。「こんな呪いをかけられたら、わたしは三日と正気でいられる自信がありません」
三日というのは、ちょっと強がった。本音を言えば、一日だって
「姉ちゃんも、大村長の家で、飲まず食わずで五日も辛抱したんだけども」
その五日間、大村長は走り回って手を尽くしてくれた。何とか呪いを解く
だが、どうにもならなかった。虻の神の呪いは、ろくめん様にも解けない。ろくめん様には虻の神に譲ってもらった恩があり、ろくめん様が虻の神をこの地に招いたのだから。
愚かな虻の神は、呪いの意味さえわかっているかどうか怪しいのに。
おりんは覚悟を決め、玄一郎との破談を願った。そしてうちに帰りたいと。
─どうせ死ぬなら、うちで死にたい。
「もう自分では歩けなかったから、大畑村の男衆に送ってもらって」
せめてもの守りにと、魔除けの鉦を鳴らしてもらいながら、畑間村に戻ってきたのだ。
「男衆の負う背負子に座って、転げ落ちねえように、しごきでぐるぐるに縛られて」
血の気を失い、背負子の枠につかまる力もなく、それでもおりんは、かけつけた父ちゃん兄ちゃん餅太郎に向かって微笑んだ。
─ごめんね。
その顔の前を、黒光りする虻が一匹、ぶうんと羽音をたてて横切っていった。
家に帰っても、おりんは寝たきりだった。飲まず食わず続きで弱り切っているから、一人では
「男手じゃ世話するのは無理さ。あたしらに任せな」
そう言って、隣のおばさんと、糸繰家でいちばんの古株のおつね婆さんが家に来てくれる。最初は、着替えの
「虻の神さんはおつむりがよくねえで、こっちが出し抜ければいいんやさねえ」
おつね婆さんはまず、冷ました重湯を竹筒に
ぎょっとしたおつね婆さんは、すぐさま竹筒を
隣のおばさんは、おりんが眠っているあいだに、竹筒をくわえさせて水を流し込んだらどうかと考えついたが、これも空しかった。まわりの者たちが、何か飲み食いさせようという意図を持って近づくと、おりんはたちまち目を覚ましてしまうのだ。聞けば、頭のまわりで虻の羽音がわんわんする上に、そいつらがみんなしておりんの顔にたかってくる夢を見るので、寝ていられないのだという。
どうにかして、水だけでも飲ませたい。工夫しては失敗し、やっとこさ、綿を丸めて玉にして水を含ませ、それでおりんの口元を軽く叩くようにして
「これじゃ、死に水だあ。死に水をとるやり方とそっくりさ」
父ちゃんはそう言ったけれど、餅太郎は気にしなかった。おばさんたちと交代で、日に何度もこうやっておりんに水気を与えた。
「おらはもうこの歳さね、明日死んでもええ。虻の神様に見間違いをさせて、おりんちゃんの代わりになれんもんかねえ」
と言って、おつね婆さんはおりんの着物を着て、白髪頭を結っておりんの
「おつねさん、気持ちはわかるさ、いくら虻の神様でもそれじゃ
おばさんは苦笑したけれど、餅太郎と兄ちゃんは、おつね婆さんの背中に手を合わせた。
親身になってくれるおばさんや婆さんたちとは逆に、おりんとその家族を遠巻きにする村人たちも少なくなかった。
「なんで呪われてンのかわからんさ、うっかり近づいたら巻き添えをくうかもしれん」
「おりんさ、誰かに呪われるくらい恨まれるようなことをやったんだ? だったらしょうがねえやさ」
隣のおばさんとおつね婆さんは、こういう連中は「虻の神様よりバカだ」と怒った。
「おりんちゃんがこんな目に遭っとるのは、玉の輿を妬まれたからに決まってるさ。ほかに何があるもんかえ」
父ちゃんも兄ちゃんも、餅太郎もそう思う。妬んで、呪っているのがどこのどいつなのかわからないのが歯がゆくってたまらない。
畑間村の村長も、この「誰か」をひどく気に病んだ。おりんを妬んだ呪い主が、同じ村の者だったらとんでもないからだ。事実、こうなってからこっち、村長のところへ、糸繰家仲間のお
村長は段取りを整え、畑間村の村民を一人残らず、厳重に調べ上げた。もしも村長が怪しいと感じるようなふるまいがあったら、そいつが誰であれ、言い訳なんぞ聞かずにすぐ追放してやる! という勢いだった。
こうして、みんなをぎゅうぎゅうに締め上げた結果、村長は父ちゃんに言った。
「おりんを呪ったのは、この村の者じゃねえ。あの良縁を
─もう、姉ちゃんは死ぬことに決まってるって言い方だ。
こっそり盗み聞きしていた餅太郎は、そっちの方が胸に刺さった。
おりんを返して
猪鼻屋からは、誰かがおりんの見舞いに来るわけでもなく、人を寄越してくれることもない。玄一郎の母親であるおかみにいたっては、
「やっぱり、野良育ちの娘を嫁にもらおうとしたのが間違いだったんですよ。これでやり直しになったんだから、玄一郎にはかえってよかった」
なんて、
呪いを解く手立てを探し回ってくれた大村長も、打つ手がないと知れてからは、がっくり気落ちしたっきりである。大村長のおかみさんは、やっぱり女の気持ちというものがよくわかっているから、お嬢様から台所女中まで、大畑村のあらゆる女たちの耳に入るよう熱心に説いて回った。
「誰がおりんを呪ったのであれ、叱ったり
悲しいかな、この呼びかけに応じる声はあがらなかった。
「虻の神様は、呪いをかけてくれって頼む者の命はとらねえのかな」
「先に九十九匹の虻に血を吸わせてるさ、そんでいいんじゃねえか」
「呪われる方は、一日刻みに刻まれるように苦しんで死んでいくんさ。そんなんじゃ足りやしねえで」
台所で朝飯を食いながら、父ちゃんと兄ちゃんがぼそぼそやりとりしている。兄ちゃんの声には怒気がこもっている。父ちゃんの声は疲れ切っている。
おりんが戻って九日目の朝だった。餅太郎が目を覚まし、明かり取りの押し開け窓をカタンと開けてみたら、空は雲に
夜中でも、おりんの様子がちょっとでも変わったらすぐわかるように、あまり間をあけずに水気を取らせてやれるように、餅太郎は寝床のそばについている。昼間はどうしてもおつね婆さんと隣のおばさんに頼り切りで、
─
と説かれたりして、おりんの襁褓を取り替えたり、身体を
そうやって付き添っていて、ふと思いついたことがあった。もしかしたら、この手を使えば姉ちゃんを呪いから助け出すことができるんじゃないか、と。
でも、なかなか踏み出せない。怖いからではない。思いつきでしかなく、あやふやだからである。
迷っているうちに日が経って、姉ちゃんはどんどん弱っていく。
─姉ちゃんの目が開いてるうちに。はっきり、呪いの虻を見られるうちに。
そうでないと、この手は意味がなくなってしまう。でも、ホントにこんなことで大丈夫だろうか。姉ちゃんに代わって、餅太郎が虻の神様の呪いを引き受けられるのか。
もう迷っているひまはない。一か八かだ。とにかくやってみるんだ。
餅太郎は台所へ行き、土間に下りて、水瓶からおりんの飯茶碗に水を汲んだ。これはもう、朝も昼も夕も、一日のうちに何度もやる習慣になってしまった。
「
朝飯を終えた父ちゃんが問うてくる。陰気な雲のせいで、台所は薄暗い。
「べつに、変わらんかったよ」
「おまえはちっとは眠れたんか。すまんな」
兄ちゃんは黙りこくっている。兄弟のあいだでは、おりんのために交わす言葉は尽きてしまった。
水を満たした飯茶碗を小さな盆に載せ、餅太郎はおりんの寝ている奥の板の間へと引き返してゆく。いつもならば、この盆の上には新しい綿の玉も載せるのだけど、今朝は飯茶碗だけだ。
餅太郎はそうっとおりんの枕元にしゃがみ込み、「姉ちゃん、おはよう」と声をかけた。
おりんの
飯茶碗の水をこぼさぬよう、盆をいったん床に置いて、餅太郎はうんと自分に気合いを入れた。やるんだ。これで姉ちゃんを助けられるかもしれねえ。やってみるんだ。
「もちだよ。姉ちゃん、今朝はちょっと起きてみようか」
寝床に張りついたみたいに薄っぺらになってしまった、おりんの身体。抱き起こそうと両腕を回すと、
小雨模様でも、明かり取りの小窓からは朝の光がさしこんでくる。姉ちゃん、ちっとでも明るい方を向いてくれ。
「雨が降ってる。こういうのを
餅太郎もまだ十一の子供だ。これから試みようと思っている事がおっかなくて、声が震えてうわずってしまう。
それを聞き取ったのか、おりんがうっすらと目を開けた。命が尽きかけて白くなっている肌と、光を失いかけて濁り始めている
「……餅ちゃん」
おりんは、餅太郎が担ぎ売りに出かけるようになると、ちゃんづけで呼ばなくなった。一人前の男になり、一人で商いをして稼いでくるんだ。もう子供じゃない。必ず「餅太郎」、どうかすると「餅太郎さん」と呼んでくれることさえあった。
なのに今は、思い出したように、
「餅ちゃん……どうしたの……」
堪えきれなくて、餅太郎の目には涙が浮かんでいた。おりんはちゃんとそれを見てとり、おぼつかなげに瞬きさえした。
「泣いてる……の」
餅太郎は左肩と左腕でおりんを支えたまま、右手で飯茶碗を持ち上げた。
「姉ちゃん、これ見ておくれ」
おりんの顔の前に、水を満たした飯茶碗を持っていく。飯茶碗は使い込んで縁が欠けてしまっているけれど、買ったばかりのときには
「この茶碗で水を飲もうよ。姉ちゃん」
おりんはまた弱々しくまばたきした。瞳が泳いで、飯茶碗の方を見る。
とたんに、痩せ衰えたその身体のなかに、恐怖と嫌悪の波が走り抜けるのを、餅太郎は感じた。近づけた頬から頬へと伝わってきた。
「やっぱり、嫌らしい虻がいるかい?」
確かめねばならない。ごめん、姉ちゃん。答えておくれ。
「この茶碗の水のなかで、でっかい虻が脚を動かして、目玉をぎろぎろさせてさ、じじ、じじって鳴いてるかい?」
おりんは必死に顔を背けようとする。
いるんだ、いるんだ、呪いの虻が。
よし、それでいい。
「じゃあ、姉ちゃん。この虻はおいらがもらうよ!」
言うなり、餅太郎はおりんの飯茶碗を持ち上げて口につけ、一滴残らずぐびぐびと飲んでしまった。
ただの水だ。変な味はしない。大きな虻を呑み込んでしまう感じもしない。冷たい水が
これじゃあ駄目なのか。
「ちょっと餅っちゃん!」
大声を張り上げ、仕切り戸を
「あんた何やってんさ!」
餅太郎はまだおりんを抱きかかえて座り込んでいたから逃げようがなく、いきなりおばさんに横っ面を引っぱたかれてしまった。
「これでおりんちゃんに水を飲ませたの? なんてバカな」
おばさんがもう一発餅太郎の頬を張ろうと手をかざすと、おりんも手を動かした。おばさんを止めようと、遮ろうとした。
「も、餅ちゃん、のろ、いを」
呑み込んじゃったの、あたしの代わりに。おりんは必死になって、おばさんに告げようとしている。餅太郎の身を案じてすがりついてくる。餅太郎も姉ちゃんを抱きしめ返す。
そのとき─
餅太郎の頭のなか、耳の奥に、いきなり虻の羽音が
一匹や二匹じゃねえ。大群だ。黒光りする目玉、大粒の豆のようにぶっとくて硬い身体、びんびんと
虻の大群が、餅太郎の頭のなかから飛び出してくる。目から、耳から、鼻の穴から、言葉にならない言葉で叫ぼうと、大きく開けた口のなかから。
「うぐぁぁああ!」
餅太郎はおりんの身体を布団の上に放り出した。跳ねるように立ち上がると、両手で耳を
ここにいちゃいけない、離れるんだ離れるんだ、おいらは虻まみれだ。
裸足で土間に飛び降り、戸口の板戸にぶつかってよろけながら、裏庭に飛び出した。小作人小屋の並ぶこのあたりは村のなかでも低い場所なので、ちょっとした雨でもすぐ水溜まりができて土がどろんどろんにぬかるんでしまう。
餅太郎は水溜まりに足を突っ込み、盛大に泥水を跳ね上げた。きつく閉じたくちびるの隙間から、
「あぶ、あ~、ぶぅ!」
それだけ叫んだら、声と同時にげぶりと吐いてしまった。だから両手で口を押さえ、頭を下げて前かがみになって、暴れ牛のように、怒った猪のように、ただまっしぐらに走って、山に登る沢に入る
走る、走る、餅太郎は走る。村の真ん中を横切る道を走り抜け、荷車置き場を通り抜け、井戸端を通り過ぎるときには誰かに水をかけられて、
「餅太郎、しっかりせいや、どうしたんさ、頭を冷やせ!」
聞き覚えのある声で怒鳴られた。ごめんよ、けどおいらの頭は冷えてるよ。ただ虻の群れでいっぱいになってるだけさ。
走って走って、つんのめって地べたに手をついて、え? 手をついたつもりなのに、なぜか指が
両脚も地面から浮いている。
ぶうん、ぶんぶん。大きな羽音がする。今度は頭のなかからじゃなくって─
頭の真上からだ!
「─とんびに
餅太郎は言って、そのくちびるが久しぶりにへろへろと震えた。
「でっかい虻に掠われて、あっしは飛んでいたんでさ」
米俵ほどの大きさの虻だった。化け物だ。そのぎざぎざのある脚で小袖の襟首をつかまれ、身体は宙ぶらりんになっていた。
「そういうことになってるんだって気がついたとき、ちょうど、村の出入り口のところにある番小屋を飛び越したんです。そしたら、ぶらんぶらんしているあっしの右足の
「それで、あっしは夢を見てるんじゃねえ、これはホントに起こってることなんだって」
聞き手の座で、富次郎は目を
─確かに、このお話じゃあ。
餅太郎が最初に、「誰にも信じてもらえっこない」と言っていたのも納得である。貸本屋で人気の『お化け草紙』に、虻の神様の挿絵つきで
─おちかはこういうの、聞いたことがあったかなあ。
富次郎が初めてだとしたら、ちょっと
「あっしは寝起きの
虻はどっちに向かっているのか。ぶらんぶらんするばっかりの餅太郎には見当がつかないのだが、さっきちらりと右端をよぎっていったのは、大畑村の火の
「おい、この大虻のバカ野郎、おいらをどこへ連れていくんだって、訊いてみたんですけども」
虻はぶんぶん唸るだけだった。飛び続けるうちに雲のなかに入り、まわりが霧のようなものに覆われて、どっちを向いても景色が見えなくなってきた。
「冷えて寒いし、小袖の襟をぎゅっとつかまれてるんできゅうくつだし、行き先はどこでもいいから早くおろしてくれよって、あっしはもう捨て鉢な気分でした」
逃げようとは思わなかったのか。思わなかったんだろうなあ。富次郎は感じ入った。餅太郎は当時たったの十一歳。よくそこまで腹をくくれたものだ。
「そのうち、くたびれてうとうとしちまったみたいで─」
虻にぶうんと大きく揺さぶられ、落っことされるのではないかとぎょっとして目が覚めた。
「そしたら、すっかり夜になってたんです」
まわりに立ちこめていた霧のようなものは次第に薄れていく。雲から抜け出したのだ。足元が広く開けて、景色がよく見えた。
真っ暗な山の森のなかに、ぴかぴかの
町だ。山道に沿って町がある。庇の上に看板を掲げ、
「子供のあっしが知っている旅籠町といったら、大畑村だけですから」
虻に掠われて秋雨と雲と霧のなかを飛び回り、結局は大畑村に帰ってきたのか。なぁんだ─と思っているうちに虻はさらに地面に近いところまで降りてきて、餅太郎を地べたへ放り出した。
勢いがついていたので、餅太郎はぐるん、ぐるんとでんぐり返った。その勢いのまんましたたかに何かにぶつかったと思ったら、ばちゃんと水がはねかかってきた。
─何なんだよ、いったい。
手をついて起き上がる。おでこを打ったせいで、目がぐるぐる回る。
餅太郎がぶつかったのは、
畑間村には、こんな
痛ぇ。おでこをさすりながら、餅太郎はぐるりを見回した。虻は飛んでいってしまって影も形もない。
今、餅太郎が座り込んでいるのは、上から見おろした旅籠町の外れ、町を貫く道の端っこだ。振り返れば真っ黒な森が、夜空の半分の高さまで立ち塞がっている。
夜空にはなぜか月も星もないけれど、餅太郎がまわりの様子を見てとれるのは、道の左右にずうっと配されている
こんなの、大畑村にもない。
前方に目をやれば、金柑ではなく
とんちんしゃん、てんてろてん、ぺんぺんのでんでんの、とんちんしゃん。
三味線と
「どおっと、止まれ止まれ、三の目!」
「そうは問屋がおろすかい」
「おっと、次の勝負はいただきだよ」
─博打やってる。
すっごいだみ声と、野太い声と、きんきん甲高い声。入り交じってどやどやと。
─熱くなってら。
笑ったり
ここは、やっぱり大畑村じゃないな。大畑村の旅籠では、こんなにおおっぴらに博打をやったりしない。お咎めをくらってしまう。
それにしてもヘンだよ。さっきから何か臭くねえか? くんくん。これ、臭ってるのっておいらの身体か?
おまけに、肌に触るとべたついている。さっき天水桶にぶつかったとき、水がはねかかってきた。そのせいかな。
気持ち悪くなってきて、道ばたの石灯籠の一つに近寄り、小袖の
そして、自分の手にべったりと血がついていることに気がついた。
「うわぁ!」
何だ何だ何だこれ、おいらの血か? おいら怪我してる? あのでっかい虻に刺されてた? 血ぃ吸われてたのか? 身体のどっかに穴あいてねえ? どこ? どこに?
それでわかった。これ水じゃねえ。
「血だ!」
血だ血だ血、天水桶のなかに血が溜まってる! 何だコレどうなってるんだ誰がこんなことしやがったんだよ!
「うわぁぁぁあ!」
餅太郎の悲鳴をかき消すように、窓明かりに満ちた旅籠のあちこちで大きな声があがる。歓声、怒声、喜んだり悔しがったり。
「おうさ、この勝負はもらったぞ!」
「ぐぬぬ、また山をとられたぞい」
とんちんしゃん、とんちんしゃん。鼓の音が高くはね上がる。
逃げなきゃ、ここから逃げなきゃ。餅太郎は地べたを引っ掻いて立ち上がる。足がもつれてすぐ倒れる。しっかりしろ、立って走るんだ、逃げるんだよ!
ぴゅううう、どん!
旅籠町の方から
飛んできたものの勢いに背中を押され、餅太郎はびゅんと前に跳んで地べたに突っ伏した。石灯籠のなかのろうそくの炎が、またたきするみたいに揺らめいた。
試し読み
関連書籍

書籍週間ランキング
1
管狐のモナカ
2025年12月8日 - 2025年12月14日 紀伊國屋書店調べ
アクセスランキング
新着コンテンツ
-
特集
-
特集
-
試し読み
-
レビュー
-
文庫解説
-
特集
-
レビュー
-
文庫解説
-
連載
-
連載