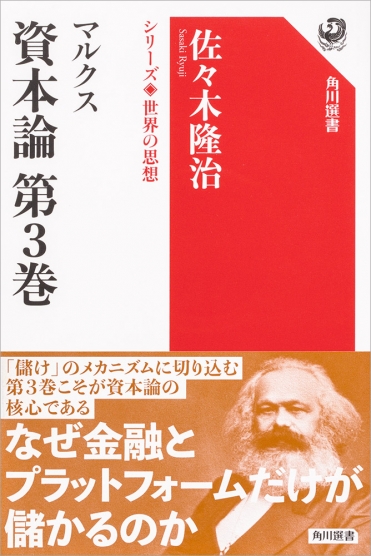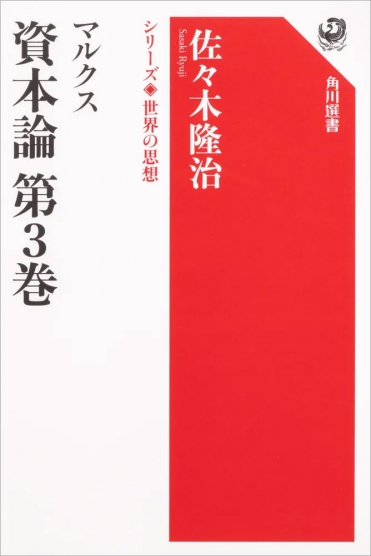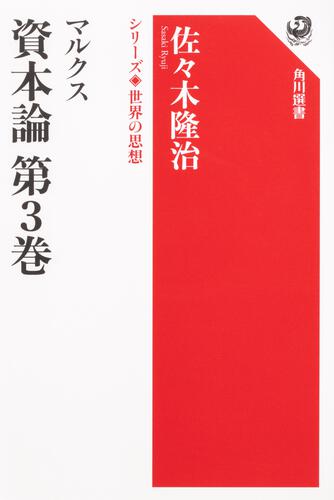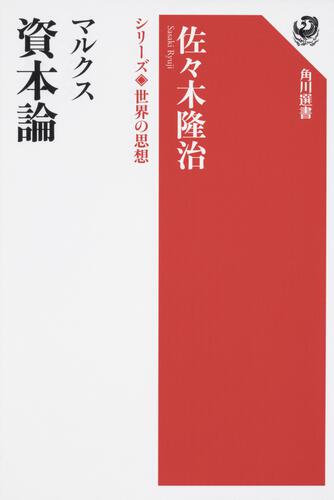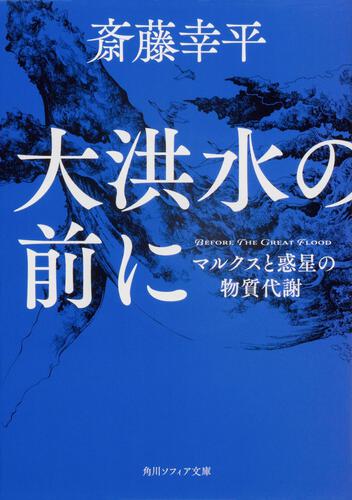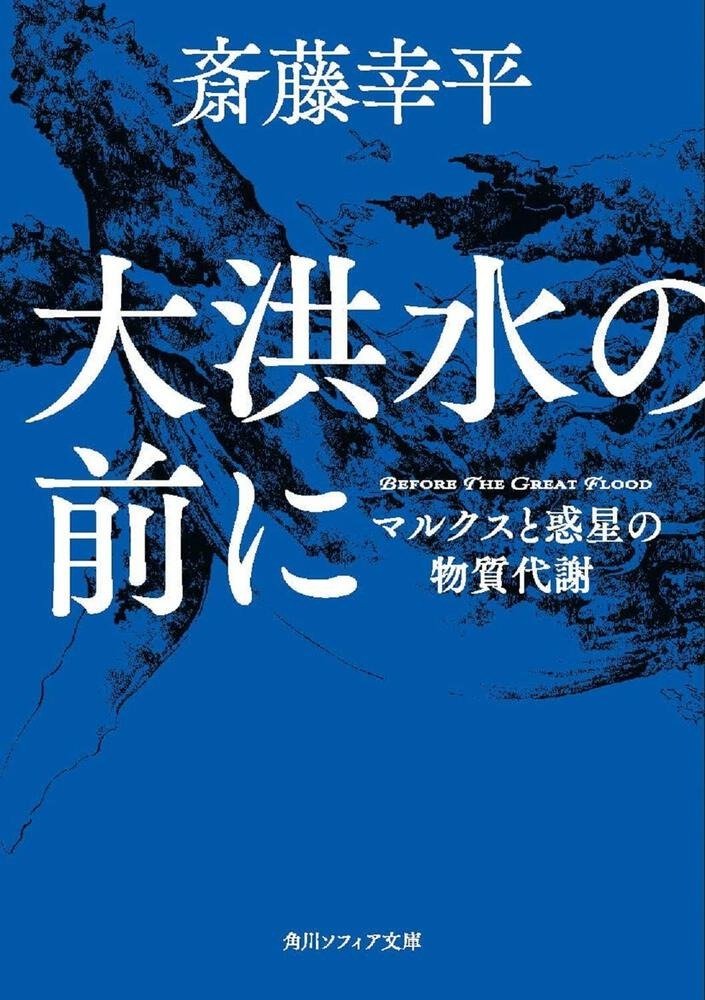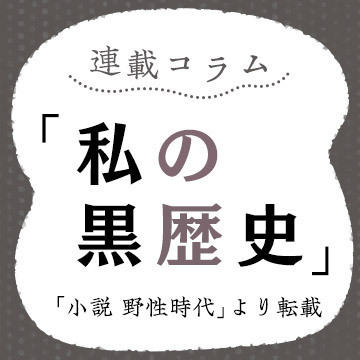マルクス 資本論 第3巻 シリーズ世界の思想
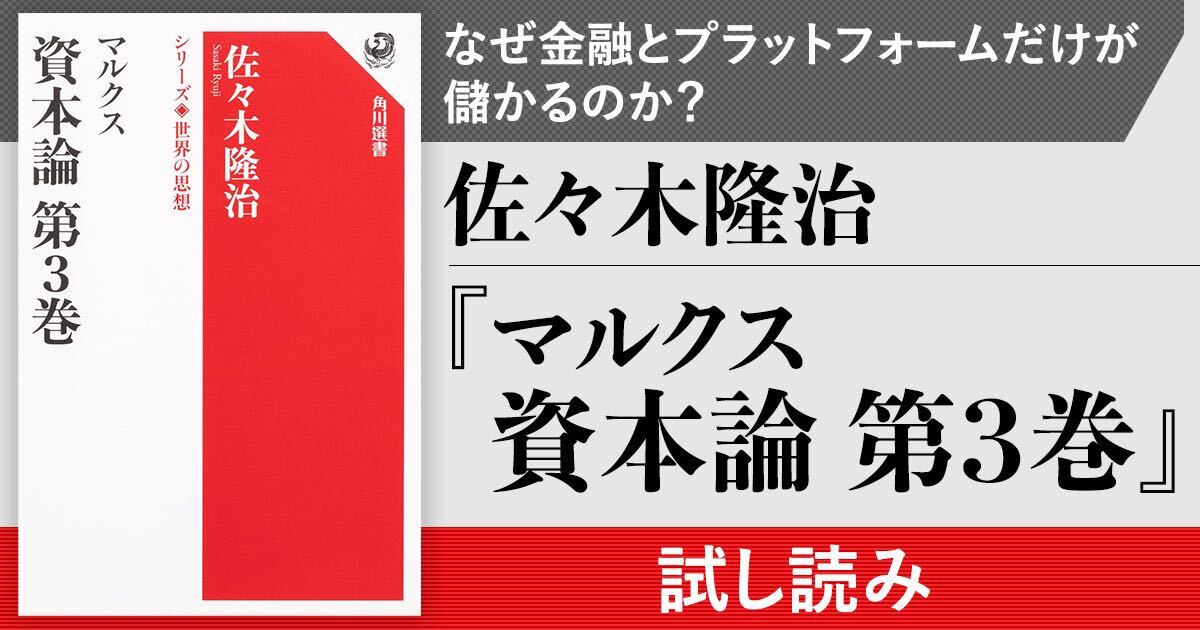
佐々木隆治『マルクス 資本論 第3巻』はじめに 試し読み
不平等の拡大、気候変動対策の停滞、インフレの加速。人々の生活の苦しみが増し、経済システムにたいする批判が高まりつつある今も、資本主義はそのシステムをより強固にしているかに見えます。
資本家と労働者の間に権力構造が発生するのはなぜなのでしょうか?
現代社会の混沌とした状況を解き明かし、危機を克服するためには、「儲け」のメカニズムを徹底的に分析する第3巻の解読が重要なカギを握っています。
マルクスも完成を見ることなくこの世を去った難読の書を明快に解説した佐々木隆治先生著『マルクス資本論 第3巻』の「まえがき」を、試し読み公開します!
『マルクス 資本論 第3巻』はじめに 試し読み
はじめに
本書はカール・マルクス(一八一八─一八八三)の『資本論』第三巻についての解説書です。『資本論』第一巻については、本書と同じ「シリーズ 世界の思想」から拙著『マルクス 資本論』が刊行されていますから、本書はその続編ということになります(なお、『資本論』第二巻についての解説書も同シリーズから刊行する予定ですが、さしあたり前作の『マルクス 資本論』を読んでいれば、本書は理解可能です)。
『資本論』第一巻では、資本がいかに労働者を搾取して利益をあげるか、利益を至上目的とした資本の運動がいかに失業者を生み出すかといった、私たちの生活と密接に結びついた資本主義の本質的なメカニズムについて論じられました。それにくらべて、『資本論』第三巻では「一般的利潤率の形成」や「利潤率の傾向的低下法則」などといった耳慣れない議論が登場し、「利子率」や「有価証券」などその存在は知ってはいるけれども、いかにも「経済学」的な、生活からは縁遠く感じられるようなテーマが扱われています。もしかしたら最初は取っ付きにくいかもしれません。
しかし、じつは『資本論』第三巻で扱われるこれらのテーマは、現代の資本主義システムを理解するうえで、決定的な意味を持っています。というのも、それらは一九七〇年代以降に進行した資本主義の構造転換と密接な関係があるからです。この半世紀の間に、先進国のみならず、グローバルな規模で製造業の成長がスローダウンし、金融収益や実物的な資産の所有から得られる「レント」(賃料ないし使用料)がますます大きな重要性を持つようになってきました。資本主義の「黄金時代」を支えた「ものづくり」によって収益を増大させることが困難になるなかで、金融部面での投機活動、あるいは知的財産やデジタルプラットフォームの独占をつうじた収益の拡大が追求されるようになってきたのです。
まさにこうした事態を解明するためのカギを与えてくれるのが、『資本論』第三巻にほかなりません。というのも、そこではなぜ資本主義においては「経済成長」がスローダウンせざるをえないのか、あるいは、金融収益やレントはいかなるメカニズムによって発生するのかといった問題について考察されているからです。しかも、気候危機やコロナ禍を背景として、こうした傾向はさらに強まっており、『資本論』第三巻はますます現代資本主義分析に欠かせないものになっていると言えるでしょう。
前作の『マルクス 資本論』を刊行した二〇一八年の時点でも環境破壊や格差などの資本主義の矛盾は深刻な状態にありましたが、その後、これらの問題はいっそう深刻化しました。氷床や永久凍土の融解の進行、大規模森林火災や熱波、水害の頻発化及び大規模化、農作物の不作やそれにともなう難民の発生など、気候危機がもたらす被害は拡大する一方です。二〇二〇年には、資本主義のグローバル化が森林伐採やブッシュミートの商品化、アグリビジネスの拡大などをつうじてパンデミックを生み出すのではないかという従来からの懸念が現実のものとなってしまいました。いわゆる「新自由主義」政策によって、医療体制が弱体化させられてきたことも致命的でした。
経済的不平等の拡大もとどまるところをしりません。いまや上位一〇%の人々が全世界の所得の約半分、資産では七五%以上のシェアを占めるにいたっています。この傾向はコロナ禍のもとでの金融政策や「デジタル・トランスフォーメーション」によって促進され、九九%の人々の所得が減少するなか、大富豪たちは資産を倍増させました。さらに、この危機的な状況に追い打ちをかけるように、ロシアによるウクライナ侵攻が勃発しました。この戦争そのものによる諸々の被害はもちろんのこと、エネルギー安全保障のために気候変動対策が停滞し、すでにコロナ禍のもとで始まりつつあったインフレが加速するなど、様々なかたちで人々の生活を苦しめています。
このような状況をうけ、資本主義という経済システムにたいする批判も高まりつつあります。それを象徴しているのが、近年の「ジェネレーション・レフト」の台頭です。若い世代の左傾化が世界中で進行し、その多くが資本主義に懐疑的である一方、社会主義に好感を持っていると言われています。実際、その傾向は選挙結果などにも明確に現れています。もちろん、ここでいう「社会主義」とはかつてのソ連や現在の中国のような強権的な政治体制を指すのではなく、民主主義的な方法で経済システムを制御することによって持続可能な社会の実現を目指すといったような、新しいタイプの社会主義を意味しています。
とはいえ、他方で見逃してはならないのは、このような危機の深まりにもかかわらず、資本主義はますます自らを強固なものにしつつあるように見えるということです。実際、多くの論者が指摘しているように、「監視資本主義」、「プラットフォーム資本主義」、「テクノ封建制」、「レント資本主義」などと呼ばれるような、資本主義の新たな形態が台頭しつつあります。この新たな形態は、その特徴的な現象形態だけに注目すれば、デジタルプラットフォームを中心とする様々なテクノロジーをつうじたデータの抽出と独占にもとづく「レント」の徴収体制だと言うことができるでしょう。これは、たんにGoogleやAmazonなどのデジタル企業の巨大化、高収益化だけを意味するのではありません。自動車や家電などの製造業、教育・医療・介護・保育などのケアワーク、さらには商業や金融など、あらゆる領域においてデータ独占にむけての産業構造および業界構造の再編が進行しています。私たちの生活領域はますます商品経済に包摂され、資本が収益を獲得するための手段となりつつあるのです。
だとすれば、もはや問題は、たんに資本主義が構造転換を遂げ、金融収益やレントに利益の比重が移りつつあるというだけではありません。そうした変化のなかで未曽有の危機に直面しながらも、まさにその危機を生み出し続けている資本主義システムがむしろ強力になっているという逆説について問わなければならないのです。世界中で若者の左傾化が進み、暴動やストライキが頻発するなかで、あるいは日本でも、資本主義を批判する言説をメディアで目にすることが珍しくないような状況が生まれるなかで、それらを飲み込むような資本主義の強大化がなぜ、いかにして可能になっているのか。一言で言えば、これほどの危機の深まりにもかかわらず、なぜ資本主義というシステムは──少なくとも今のところ──揺るがないのか。
『資本論』第三巻は、いわゆる「経済学」的な問題にとどまらず、こうした社会的権力関係をめぐる問いについても重要な示唆を与えてくれます。すでに『マルクス 資本論』を通読した読者の方は容易に予想できると思いますが、『資本論』第三巻はたんに金融収益やレントが発生する経済的メカニズムについて解明しているだけではありません。そのメカニズムのなかでいかに人々を従属させるような権力が発生するのかという問題についても、繰り返し論じています。現代資本主義の混沌とした状況を解き明かし、幾重にも折り重なった危機を克服するための展望を考えていく際にも、頼りにすることができる著作なのです。この意味でも、『資本論』第三巻は「最強の理論的武器」だと言えるでしょう。
さて、以上から『資本論』第三巻のアクチュアリティについて大まかなイメージをもっていただけたかと思いますが、本書を読むにあたり留意しておかなければならないことがあります。それは『資本論』第三巻特有の「難しさ」です。
もちろん、第一巻もけっして簡単ではありませんが、それでもマルクス自身によって完成させられ、マルクスの生前に実際に刊行された著作です。そのため、完成度が高く、マルクス自身の意図も明確に示されていますので、長年の『資本論』研究をつうじてその大枠は解明されてきたと言えるでしょう。実際、第一巻の全体について解説した前著の『マルクス 資本論』も「わかりやすい」という評価を多くいただき、予想を遙かに超える読者の方に読んでいただくことができました。
それにたいし、第二巻や第三巻はマルクスの死後に盟友のエンゲルスが未完成の遺稿を編集して刊行したものであり、完成度が低く、マルクス自身の意図が明確に示されているとはいえません。とりわけ第三巻は、長年にわたって多くの草稿が書かれた第二巻と比べても、さらに完成度が低く、マルクス自身の意図がどこにあったのか判然としない箇所が頻出します。さらに悪いことに、マルクス自身のテキストを尊重しつつも、できるだけ読者に読みやすい本に編集しようとしたエンゲルスのサービス精神が、マルクスの叙述を歪め、その本来の意図を把握することをいっそう困難にしてきました。そのため、第三巻についてはいまだに研究者の間でも決着がついていない問題がいくつも存在します。
以上のような事情があるため、これまで『資本論』第三巻の全体について詳細に解説するタイプの入門書はほとんど出版されてきませんでした。第三巻について紹介するとしても、各々の研究者の問題意識に合致する部分だけが論じられるか、非常に雑駁なかたちで全体像が示されるにとどまってきたのです。しかし、そのような部分的な、あるいは大雑把な紹介では『資本論』第三巻の核心に迫ることはできません。やはりマルクス自身の意図に肉薄するには、なんらかの工夫をこらして、その全体に取り組む必要があるでしょう。
そのため、本書は二つの特徴を持っています。第一に、本書では、マルクスの死後にエンゲルスが編集し刊行した『資本論』第三巻ではなく、マルクス自身が執筆した『資本論』第三部草稿のテキストを収録しています(なお、草稿全体の翻訳は筆者をふくむ研究グループがすすめており、桜井書店より近刊予定です)。これによって少なくともエンゲルスによる善意の「歪曲」の影響を被ることはなくなります。
とはいえ、エンゲルスの影響を排除したとしても、第三部草稿はあくまで草稿にすぎず、未完成なものであることには変わりありません。たんに叙述として完成していないというだけでなく、理論そのものの記述が不十分であったり、場合によっては矛盾していることさえあります。第一巻や未完成とはいえ完成に近づいていた第二巻とは異なり、ただテキストを「マルクス自身のテキストとして虚心坦懐に読む」だけでは包括的な理解に到達することはできません。
そこで、第二に、本書では、未完成ながらもマルクスの叙述のなかに存在する一貫した論理を意識的に抽出し、それにもとづいて内容を整理するという方針をとっています。これによって、かなり見通しがよくなり、また理解しやすくなったのではないかと自負しています。ただ、前作の『マルクス 資本論』と比べて、筆者自身の解釈が入り込む余地が大きくなっている点には留意していただければと思います。やはりご自分で整合的な解釈にトライしてみたいと思われる方は、ぜひ近刊予定の第三部草稿の翻訳をお読みください。本書は、そのような独自の読解のさいにも、一つの参照軸として役立つことでしょう。
(続きは本書でお楽しみください)
書籍紹介
マルクス 資本論 第3巻 シリーズ世界の思想
著者:佐々木 隆治
発売日:2024年01月24日
なぜ金融とプラットフォームばかりが儲かるのか? 儲けの本質を解き明かす
「資本主義的生産は、人間や生きている労働の浪費家である」
『資本論』第1巻の草稿を書き終えたマルクスが次に取り組んだのが、「儲け」のメカニズムに切り込む第3巻だった。産業資本主義が生産し、実現した剰余価値はいかに分配されるのか? 最新の草稿研究によって明快に読み解く解説書の決定版!
不平等の拡大、気候変動対策の停滞、インフレの加速。人々の生活の苦しみが増し、経済システムにたいする批判が高まりつつある今も、資本主義はそのシステムをより強固にしているかに見える。資本家と労働者の間に権力構造が発生するのはなぜか? 現代社会の混沌とした状況を解き明かし、危機を克服するためには、「儲け」のメカニズムを徹底的に分析する第3巻が要となる。マルクスも完成を見ることなくこの世を去った難読の書を明快に解説。
詳細ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/322203002323/
amazonページはこちら
プロフィール
佐々木 隆治(ささきりゅうじ)
1974年生まれ。立教大学経済学部教授。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了、博士(社会学)。日本MEGA(『新マルクス・エンゲルス全集』)編集委員会編集委員。著書に『マルクス 資本論』(角川選書)、『カール・マルクス‐「資本主義」と闘った社会思想家』(ちくま新書)、『マルクスの物象化論[新版]資本主義批判としての素材の思想』(堀之内出版)などがある。