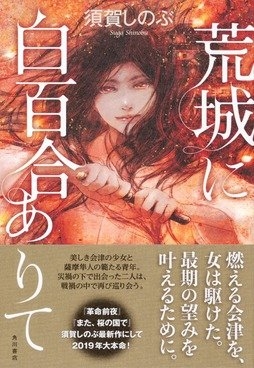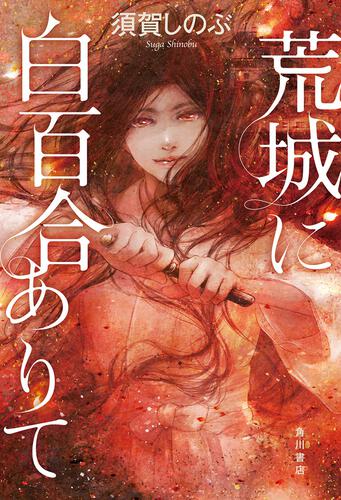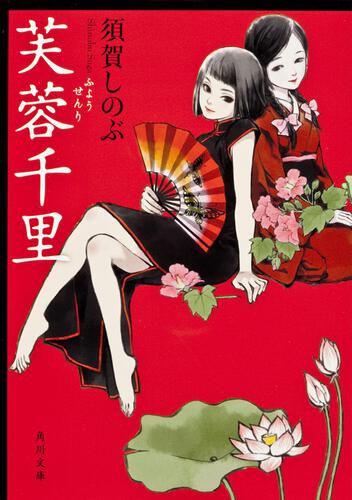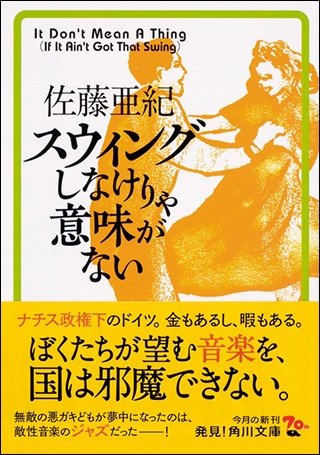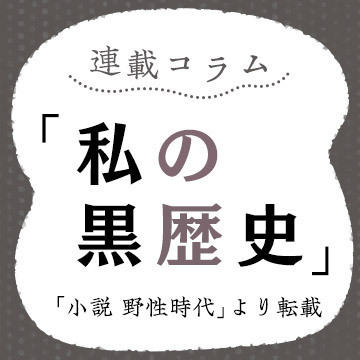荒城に白百合ありて

舞台好き必見! 重厚にして華麗な滅びの物語『荒城に白百合ありて』試し読み#4
幕末という「世界の終わり」が近づいていた時代、志士たちは何を思い、なんのために戦ったのか。
書店員さんからは「舞台化希望!」との声も多数。
魅力的な登場人物が多数登場しますので、舞台化キャストを想像しながら第4回目もお楽しみください。
>>前話を読む
三
眼前を、赤い葉がはらりと落ちる。
正午を過ぎたばかりにもかかわらず、あたりはぼんやりと暗く、その中で葉の赤がやけに目についた。いや、暗いからこそかもしれぬと思いあらためて足下を見れば、階段のそこかしこに赤い葉が落ちている。踏めば、
伊織はおよそ緊張とは無縁な男だが、この地に立つと、さすがに身が引き締まる。
杏壇門の先にもやはり短い階段があり、その先には堂々たる
江戸の、いや日本の学問の中心。幕府唯一の官学教育機関『昌平坂学問所』の中核だ。
大成殿の孔子像に参拝を済ませると、伊織は案内に従い、広大な敷地の北西部へと向かった。平屋の長屋づくりの棟が南北に並び、これが書生の寮だと聞いた。昌平坂の生徒は「稽古生」と「書生」にわかれている。稽古生とはすなわち、幕臣の子弟。正規の生徒である。もともと昌平坂学問所は幕臣の教育のために開かれた官学(
一方、各藩からの留学生である書生には吟味はない。要は聴講生である。各藩
伊織もここで、朱子学はもとより数々の学問を会得するつもりだった。たとえば、江戸最高の学者と呼ばれ、昌平坂の教授でもある
足取り軽く寮に近づくと、ちょうど中から一人の若者が出てくるところだった。年の頃は伊織よりいくらか上で、髪は総髪の儒者頭。いかにも学者然とした男だが、体つきはどっしりとして胸は厚い。剣の腕も相当に立つだろう。どこか不満そうな顔をしていたが、伊織に気づくとさがっていた口角があがり、面長の顔がほころんだ。
「見ない顔だ。もしや新入りか」
伊織は
「お初にお目にかかる。薩摩から参上つかまつった。岡元伊織と申す」
「これはご丁寧に。
「斎藤殿、
すると斎藤は困ったような笑みを浮かべた。
「ああいや、ちょうどここから出ていくところなのだ。おそらく俺が抜けた部屋に貴殿が入るのだろう」
「なんと、そうでしたか」
昌平坂には在学期間の決まりはない。大半は頃合いを見て藩から呼び戻されるが、十年近く居座る者もいるという。そのため、定員数が八十と決まっている書生寮がなかなかあかず、藩から送り出されたものの入校できぬ者もいると聞く。その場合は
「庄内に戻られ、教鞭をとられるのでしょうか。庄内藩の
「いや俺は郷士でな、藩校は出ていないのだ」
さらりと斎藤は言った。
昌平坂は武士以外にも門戸が開かれている。聴講だけならば町民も可能だ。郷士は武士ではあるが、士分に入るかどうかは藩によってちがう。半農半士の郷士のほうが俸給の少ない下級武士より裕福なことは多く、目の前の斎藤もそういう
「七年前に江戸へ参り、長らく
「二月末?」
聞き違えかと思った。三ヶ月も経っていない。顔に出ていたのだろう、斎藤は
「そうだ。三ヶ月もいなかったな。ふむ、立ち去る身でなんだが、ここで会ったのも何かの縁。舎長の部屋へ案内ぐらいはしよう。ついてこい」
斎藤は身を翻し、北側の寮へと向かった。
「新入りは南寮だ。八畳と六畳があり、それぞれ三人と二人で使う。君は八畳だな、しばらくこき使われて勉強どころではないから覚悟しておけよ」
愉快そうに笑いながら、斎藤は北寮へと入った。
「おめはほんとに
突然の大声に、伊織は立ちすくんだ。
「屁理屈とはなんじゃ、
「
「馬鹿とはなんだ! いくら秋月殿とて、水戸学を
凄まじい勢いで、声が突き刺さってくる。出所はどうやら一番奥の部屋だが、ここにいても実によく聞こえた。すばらしい声量だった。どちらも相当、冷静を欠いている。
「はあ、またか」
斎藤は額を押さえた。
「斎藤殿、これは」
「舎長の秋月殿と、水戸の
「な、なるほど。ご忠告痛み入ります」
目を白黒させる伊織に、斎藤は苦笑した。
「まあそうは言っても、避けることなど不可能だろうがな。今はどこもかしこも攘夷攘夷だ」
斎藤はうんざりした様子で歩を進め、奥の障子の前に立った。
「秋月殿、原殿。新入生が到着しましたぞ」
声をかけると、すっと障子が開いた。うかがうように顔を出したのは、目つきの鋭い若者だった。
「なんだ斎藤殿、まだいたのか」
「これ、市之進。斎藤殿、造作をおかけした」
奥に座る小柄な男が、手前の男を
「ようおいでなされた。たしか薩摩の岡元殿でしたな。舎長の秋月と申す。こちらは水戸の原市之進」
秋月と名乗った舎長は穏やかに笑った。斎藤しかり原しかり、昌平坂の書生は全国から集まっているというものの
「ほう、薩摩か」
手前の原市之進が、鋭い眼光をわずかに緩める。
「近頃は薩摩の藩士がよく
「東湖……おお、
水戸藩の前藩主・徳川
水戸学とは、第二代藩主・徳川
今年の開国以来、そこに攘夷思想が結びついた。以前より水戸は攘夷論が強い藩である。
江戸に出てしばらくは
「市之進は藤田先生の
秋月がからかうように笑うと、原は目尻をつりあげた。
「なにを申される! 国を揺るがす
「まああれだけ海防について大口を
「口ばかりとは失敬な。米利堅との条約締結はのらりくらりと引き延ばし、その間に軍備を強化して攘夷を実行せよと言っておるではないですか。実際、水戸ではおのが力だけで巨大な大砲を七十五門も造りましたぞ!」
「ふん、ご老公お得意の〝ぶらかし論〟がし。先送りばかりでなんの意味もない。海防ならば我が会津のほうがよほど現実を知っている。今までもさんざん外洋警備に駆り出され、黒船が来てからは
秋月の顔に苦々しい色がまじる。痛いところをつかれたのか、原も「む、むう」と
「参勤交代を免除されておりながら、砲弾が飛ばねで海さ落ぢっちまう大砲を七十五門も造ったご老公に海防など語られたくはないわ。大口を叩くなら身を削れと言っているのだ。我らは攘夷など不可能だとよく知っておる」
「国を売るつもりか、この会津っぽ!」
「国を守るためにも、もはや開国は不可避と言っているのだ。そもそも
早口で繰り広げられる舌戦をぽかんとして眺めていた伊織は、突然水を向けられて、目を瞬いた。が、にこやかな秋月の目の中に探るような色を認め、同じように笑みを浮かべた。
「さようです。藩主を襲封されて以来、積極的に西洋の技術を取り入れております」
「大砲は造っているのか」
語気荒く、原が問い詰める。
「はい、
「見ろ市之進、新入りのほうがよほど今が見えておるぞ」
満足げに秋月は頷き、怒りのあまり顔がどす黒く変色した原を見やった。
「ふん、薩摩守様は
「これ、市之進」
「このままでは庇を貸して母屋を取られることにしかならんと言っておるのだ。なぜわからんのですか」
「真に攘夷を実行したいのなら、屈辱を飲んで敵の技術を取り入れるぐらいはせねば。これが本当の攘夷ではないがし」
「思想なき技術などいずれ首を絞めるだけだ。このまま各藩が倣って次々西洋に
「失礼、お二方」
再び議論が活発化しそうな気配を察し、斎藤は素早く口を挟んだ。
「岡元殿はこちらに着いたばかりです。そのあたりはゆっくりと改めてどうぞ。まずは部屋に案内したいのですが、部屋は原殿のところでよろしいのですかな」
伊織は耳を疑った。今、原の部屋と言ったか?
「ああ、そうだな。ちょうど俺の部屋が空いた」
原は少しばかり落ち着きを取り戻し、居住まいを正して伊織と向き合った。
「岡元と申したか、よろしく頼むぞ。今日からじっくり水戸学を仕込んでやろう。なに、西洋かぶれの薩摩者も、東湖先生と一度お会いすればみな尊王攘夷の素晴らしさに目覚めるからな」
にやりと笑う原に、伊織はかろうじて笑顔をつくり「本場の方に水戸学を直接ご教授頂けるとは光栄の極み」と言った。原は満足そうに頷き、秋月は苦笑している。細めた目は、「頑張れよ」と半ば
「まあ、このような次第だ」
舎長室を離れるなり、斎藤はため息まじりに言った。背後からはまた怒声が聞こえている。
「皆さん、あのような感じなのですか」
「あんなものではない。毎度、最後は取っ組み合いになる。原殿も血の気が多いが、まあ舎長にはさすがに殴りかからんな」
「なるほど。それにしてもさすが昌平坂。あれほどの書物が容易に手に入るとは」
それだけで胸が躍る。薩摩にいたころは書物、とくに洋学関係のものを手に入れるのにずいぶん苦労をした。当時の藩主の島津
「その点はたしかに素晴らしい。そら、あそこが文庫だ」
外に出たところで、斎藤は北側の大きな建物を指し示した。
「書生ならば好きな時に読める。ここに入ってよかったと思えることではあったな」
「宝の山ですね。薩摩だとなかなか読めませんから」
「まあ、書を読むのは大事だ。されどそれだけならば、わざわざ昌平坂におらずともできる。江戸ならばいくらでも手に入るのだから」
そう言ってから、斎藤は気まずそうに頭を搔いた。
「いや、すまぬ。水を差すつもりはないのだ。ここも愉快は愉快だ。さきほどの秋月殿や原殿をはじめ、八十名の書生はみな各藩の誇る俊才だからな。弁が立ち、議論はじつに面白いぞ」
「なれど斎藤殿は議論ばかりでは何もならぬとお考えなのですな」
伊織の言葉に、斎藤は苦笑した。
「ふむ、会ったばかりの者にも見抜かれるとは」
「さきほど、郷士だと申されたゆえ。郷士は士族に比べると行動力がある、というのは私見ですが。おそらく行動に移される頃合いなのだろうと判断いたしました」
「ほう」
斎藤は微笑を消し、まじまじと伊織を見た。
「なかなかの洞察力だ。さすがにその若さで昌平坂に推挙されるだけある。俺は、実はあまり士分は好きではないのだが、岡元──と言ったか、貴殿はなかなか好ましい」
「お褒めにあずかり光栄です。されど、なにぶん薩摩は人口の四分の一が武士ですし、私は士分とはいえ一番下。武家という自覚は正直、乏しいのですよ」
「たしかに貴殿は薩摩
斎藤は検分するように伊織を眺めて言った。
「はい。斎藤殿も見事な腕前と推察いたします。どちらの道場ですか」
「
無念そうに、斎藤は書生寮を
「ここでいくら話を交わしたところで何が変わるわけでもない。それにやはりここは武家のための学問所だ。皆、出世と
「郷士は陪臣ではない。士分に比べるとたしかに縛られてはいない。あなたのような方には、昌平坂は物足りないやもしれませんね」
今日来たばかりのくせに、わかったような物言いが我ながらおかしかった。しかし、この昌平坂で最初に会った人物が、今まさにここを去ろうという郷士であるということは、意味があるように思えてならなかった。
「どうやら貴殿にも物足りぬものとなりそうだがね」
「そんなことはありません。私はここから学ぶことが山積みです。さきほどの議論も楽しく拝聴しましたよ。藩の特色というのも実に興味深い」
「面白がれるのならば、それでよい。だがいずれは、その差異を超えたところを見てほしいものだな。その気になれば、俺の塾に来てくれ」
「塾を開かれるのですか。何を教えられるので?」
伊織は
「無論、世を変える道だ」
斎藤は迷いなく言い切った。
「重要なのは実践だ。学問とは正しい道を行き、正しく実践するためのもの。開国も攘夷も、ここで理屈をこねくり回しても何も始まらん。かといって理論なき行動は、ただの蛮勇で終わる。俺は文武両道の、回天の意志をもつ者を育てたいのだ」
回天。これは大きく出た。伊織は、目の前の男を改めて見つめた。頑丈な体、意志の強そうな顔。弁は立つ。そして鍛え抜いた体には、はち切れんばかりの大望を抱いている。
果たしてそれが分を越えた妄想か、それとも本当に回天をなし得る傑物か。それはまだわからない。だが、こうして相対していて高揚させるものをもっているのは確かだった。
「それはいつかぜひうかがいましょう。どちらに開塾されるか決まっているのですか」
「
「良い名ですな」
「ああ、塾を開いたなら斎藤の姓を捨てる。新たな名は清河八郎だ。よろしく頼む」
快活に笑い、わずか三ヶ月たらずの学生は、昌平坂を去って行った。武家のための学問所、その最高権威に背を向けて、たしかな足取りで歩いていく道が、伊織にはまぶしく見えた。
そして改めて、黒塗りの大成殿を見る。訪れた時は威厳があると感じたが、今は日射しを拒否して闇にうずくまろうとする意固地な老人のように見えるのが不思議だった。自分も現金なものだと笑う。
「江戸には愉快な人物がいるものだ」
さきほどの斎藤、いや清河。秋月、原。いずれも才能溢れ、そして全く異なる見識をもつ若者たちだ。
岡元伊織は得な男で、たいていどこに出向いても、誰からでも好かれる性質を備えている。男ぶりがよいと評される姿に穏やかな笑顔、弁舌も巧みであった。生来の資質はもとより、多くは努めて身につけたものである。ごく幼いころから、相手の思考を読み、その通りに動く傾向があった。そうすれば衝突が少なく、万事もうまくいくとその時すでに知っていたように思う。
血の気の多い薩摩隼人の中にあって、子どものころから大きな
ただ、穏やかに過ごしていても何も野心がないわけではない。伊織もまた、他の若者たちと同じように焦燥を抱き、切望していた。この身命を
あいにく、
まだわからない。しかしきっと、ここなら見つかる。その予感に、伊織は微笑んだ。
岡元伊織という人生は、ここから始まるのだ。
〈第5回へつづく〉
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ご購入はこちら▶須賀しのぶ『荒城に白百合ありて』| KADOKAWA