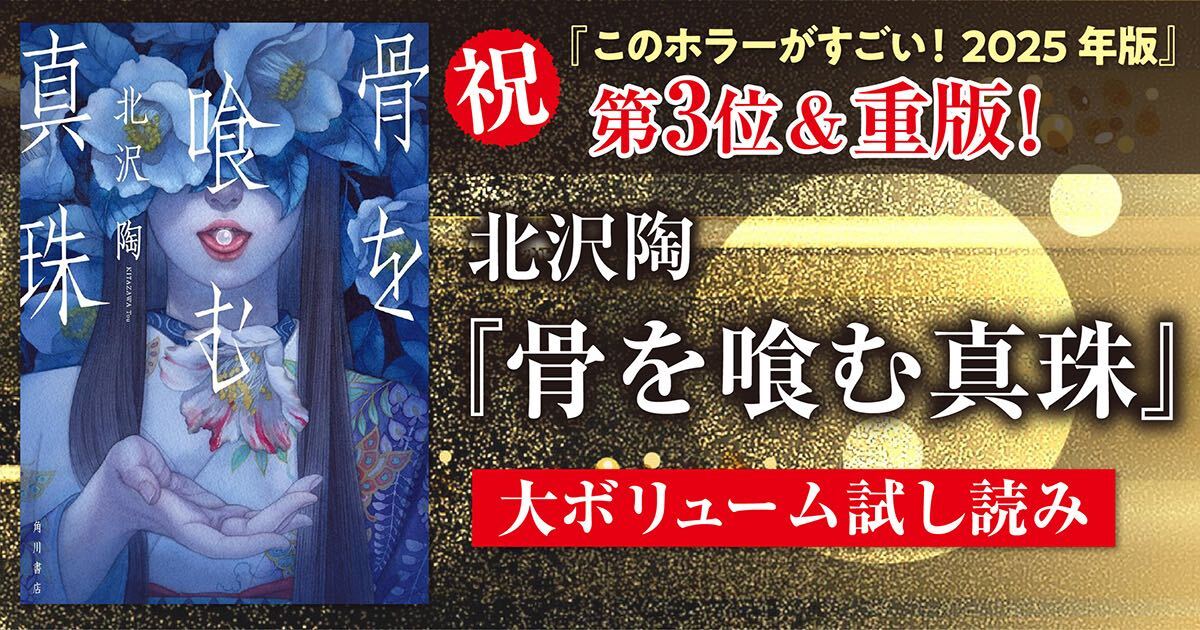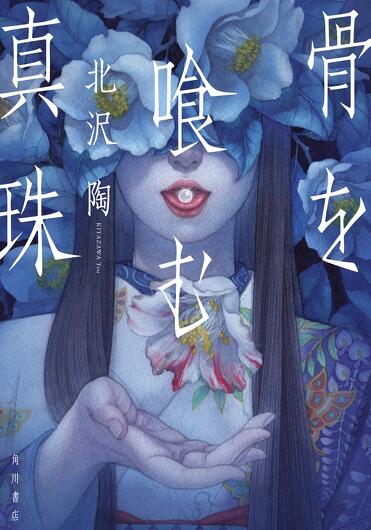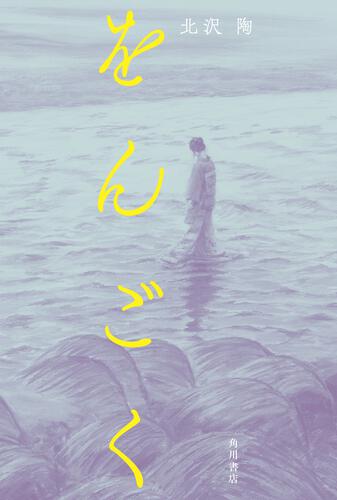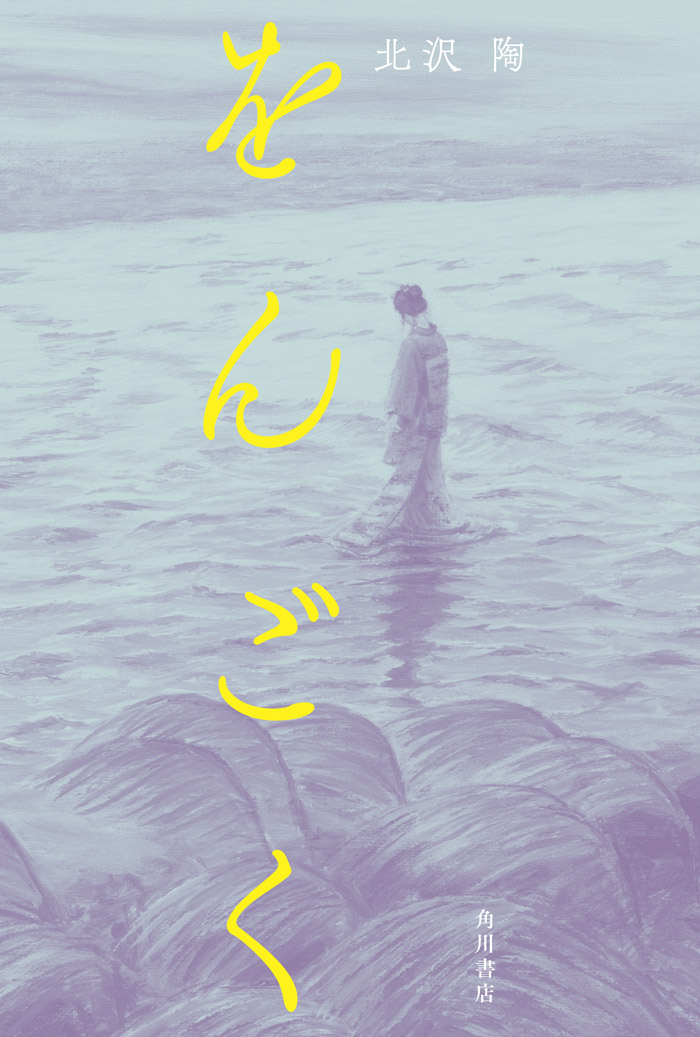第43回横溝正史ミステリー&ホラー大賞で3冠を獲得し『をんごく』で印象的なデビューを果たした北沢陶さん。ホラー界の新鋭による第2作『骨を喰む真珠』は『このホラーがすごい!2025年版』(宝島社)で3位を獲得!重版も決定し、今大注目の作家です。
ランクインを記念して大ボリューム試し読みを公開します!
大正14年、大阪。婦人記者・苑子は、大手製薬会社・丹邨製薬の社長令息から奇妙な投書を受け取り、不審を覚えた。記事を書くため、身分を偽って丹邨家に潜入するが、調査を進めるうちにその異様さが明らかになってきて――。
「丹邨家に巣くう災厄をあなたが払えることを祈ります」
北沢 陶『骨を喰む真珠』試し読み
第一章 神効有リ
一
私は
青い家の中で朽ちていきます
いずれ
私は
ひと目見て分かるほど、奇妙な手紙だった。
――送り先を
苑子が記者として働く
どうせ編集室に手紙を運んでくる給仕が間違えたのだろうと
身上相談欄には様々な投書が来る。結婚や家族に関する悩みといったありふれたことから、「人間として正しい生き方が分からない」といった抽象的な相談まである。抽象的なものは若い読者から寄せられることが多く、同じ悩みを抱える者もいるだろうと何度か取り上げたこともあった。しかし、このような手紙を受け取ったのは初めてだった。
思案にふけっているうち、ふいに編集長の「おい
約二週間前の大正十四年四月一日、大阪は近隣の地域を合併し、日本一の大都市となった。当日、男性記者たちは中央公会堂での市域拡張記念式典や造花で飾られた市電、百貨店の記念割引大売り出しの記事を書くため市内を駆けずり回り、締め切りに追われた編集室が殺気立つほどだった。ほかの新聞社が飛行機を飛ばし、編集長が悔しがっていたのが思い出される。
半月ほど経った今でも編集室にはまだせわしなさが残っており、男性記者たちは石墨の粉を原稿用紙に散らしながら、鉛筆を走らせていた。
苑子は手紙を机の隅に置いて、まだ封を切っていない投書に手を付けた。この忙しい中で、意味の分からない詩に構っている暇などない。
――私は本年十八の女です。
――経済的な困窮のため、両親が妹を芸者にしようとしております。妹は親の言うことならと従うつもりなのですが、私は妹が芸者になるのには耐えられず、なんとかして救いたいと――
読んでは考え、取り上げないと決めて隅にやることもあれば、保留のつもりで別の場所へ置くこともある。「身上相談は婦人記者に任せるのがいい、婦人は細やかな心で人々の悩みに答えるだろうから」と、理由をつけて苑子に身上相談の回答を押し付けてきた編集長が憎らしい。新聞の身上相談欄は悩める人々に手を差し伸べるものではない。読者の興味を
苑子は不満げに息をついて、保留にした手紙の中から、今回の身上相談欄で採用するものを選び始めた。勝ち気な娘に手を焼く父親の相談か、両親から結婚を迫られる職業婦人の相談か……。
これ、と決めた手紙を机の奥に置いて原稿用紙を広げたが、ふと机の隅に置いてある手紙の束に目がいった。
やはり、あの詩がどこか気になる。
「何考えてるのよ、妙な顔をして」
横合いから唐突に声をかけられ、苑子はびくりとした。隣の席で、同僚の
「けったいな手紙が来たんやがな。詩みたいなんやけど、表書には身上相談欄て書いてあるし……」
束から取り出した手紙を見せようとしたが、操はひらひらと
「打ち
「帯?」
操は黙って苑子の背中に手を伸ばし、お太鼓結びにした帯の隙間から
男性記者からの
受け取った紙を見てみると、
「
と、大きな文字で殴り書きをされていた。
不遜。傲慢。この新聞社に入ってから、陰で、あるいは大っぴらに、何度言われたか分からない言葉だった。しかし幾度告げられようと、湧いてくる感情は同じだ。
苑子は席から立ち上がると原稿用紙を掲げ、編集室中に響き渡る声で怒鳴った。
「こんなことをするんは、どこのどなたでっか」
誰も答えない。編集長は別の記者と話し込んでいるし、並べられた机に向かって鉛筆を走らせたり、辞書を引いたりしている男性記者たちは顔を上げもしない。うつむきがちになっている記者のひとりが、笑いを誤魔化そうとしてひとつ
もう一度問おうとして息を吸い込んだところで、操が
「よしなさいってば。そうむきになるから、向こうがおもしろがるのよ」
苑子は相手を見下ろすと、
「そやかて、こんな嫌がらせされて黙っとるのは業腹やないの」
つまんだ原稿用紙を
「馬鹿ね、何年婦人記者をやってるの。私たちが言っていいのはね、『はい』『すみません』『すみません』だけ」
苑子は悪口の書かれた原稿用紙を丸め、
「『すみません』が二回あるんは」
「一回目の『すみません』は単なる謝罪。二回目は『女のくせに筆など執って、男の世界に入ってきてすみません』ってこと」
「女で筆を執って許されるのは、少女雑誌に投稿する詩とか作文までよね、とどのつまりは」
「その作文を社に送って記者になったんやないの、あんたはんもわても……。合点が行かへんわ」
愚痴を言ったところで、不満が収まるわけでもなかった。身上相談にとりかかろうとしても、うまい回答が思いつかない。何度か筆が止まったあと、苑子は万年筆を机に放り出した。無造作に置かれたままの、例の妙な手紙が目に入る。
そういえば、あの詩を書いたのはどんな人物なのだろうか。
普通は手紙の最後に「悩める女」や「T男」などの仮名があるものだが、それすら書かれていない。封筒を裏返して、差出人の名前を見てみる。
「丹邨……」
思わず口に出していた。覚えがある名字だ。めずらしいものだから、ほとんど間違いようがない。
苑子は原稿用紙に向かっている操に声をかけた。「なぁに」という、面倒くさそうな一言だけが返ってくる。
「あんたはん、丹邨家の訪問記を書いたことあるやろう。二年くらい前……ほら、丹邨製薬の」
その名字を聞いた途端、操の鉛筆ががり、と原稿用紙を
「丹邨製薬の社長宅ね。ええ書いたわ。あんまりいやな目に遭ったから無理に忘れてたのに、あなたのせいで思い出してしまったじゃない」
それがどうかしたの、とようやく顔を向けてきた操の前に、苑子は手紙を差し出した。
「さっき言うた身上相談の手紙……差出人は丹邨孝太郎いうんや。社長一家の誰かやないかと思うて。あんたはん、訪ねたときに孝太郎っておひとがいはるって聞いた?」
興味を惹かれたのか操は手紙を受け取り、さっと目を走らせて
「身上相談にしては変なものね。でも私はそんな名前知らなくてよ。なにせ、奥様はご自分がいかに若々しいかってことしか話さなかったものだから」
「若々しい」という言葉に皮肉を込めた抑揚をつけ、操は不機嫌そうに
「そういえば、丹邨家から帰ってきたとき、あんたはんえらい腹立てとったなぁ」
操は少し意外そうな顔をした。
「よく覚えてるわね。そうなの、『あなたはお若くても、気を緩めているとすぐに老けてしまうわよ、私はそんなことはないけれど』なんて言われて、腹を立てない女がいるかしら。私よっぽどそれを書いてしまおうかと思ったわよ」
怒りのせいか、操の口調には普段より熱がこもっていた。思わず苦笑して、苑子がからかう。
「そんなことを書くんは訪問記やのうて化け込み記事やな。あんたはん、物売りにでも化けて、丹邨家を訪ねたほうがええ記事書けたんやないの」
「訪問記ってことで編集長に言われたんだからしょうがないじゃないの。あなたもそんな手紙、捨ててしまいなさいな。丹邨家なんかに気を取られてる暇なんてないでしょう」
操はぴしゃりと話を終えて、自分の仕事に戻った。
同僚にはああ言われたが、この手紙を捨てる気にはどうもなれなかった。奇妙な文面もそうだが、もし丹邨製薬の社長の家族から送られてきた身上相談だとしたら、後々何かの記事に使えるかもしれない。
苑子は机に置いてある辞書を開くと手紙を挟み、なんでもないような顔をして元に戻した。ここなら男性記者に見つかって戯れに
それから一週間が経ち、仕事に追われて辞書に挟んだ手紙を忘れかけていた頃、再び丹邨孝太郎からの投書が届いてきた。
がなり立てる
足をもがれ唇を縫われ
やはり仮名はなく、詩だけが書かれていた。文字が前より崩れ、墨の染みがぽつぽつと紙に散らばっている。
苑子はしばらく手紙を眺めたあと、辞書を開いて中に挟んだ。分厚い辞書を机の奥に戻したとき、なぜだかいつもより重く感じた。
はっきりした根拠はないが、苑子は三通目が来るのではないかという予感を抱いていた。普段ならばそんな当て推量など相手にしないのに、どこか胸騒ぎがする。それから手が空くたびに、ふと苑子の脳裏に丹邨孝太郎のことがよぎるようになった。
七日後、小倉袴の給仕が手紙を持って編集室に飛び込んで来、苑子の机に手紙の束をばさりと置いて、すぐに別の机に向かっていった。
白い封筒、小さい筆跡の表書が目に付き、苑子は素早く手に取った。丹邨孝太郎からの手紙だ。
表書も、差出人の名前も先の二通と比べて、明らかに文字が震えている。悪い予感がした。封を開けるのももどかしく、勢い余って封筒が斜めに破れた。
踏み絵を見ろ
踏み絵を見ろ
踏み絵を見ろ
歯のこまかな影だけは見るな
皺が寄った紙、ひどく乱れた筆跡で書かれた詩を凝視する。読んでいるうちに、呼吸が浅くなっているのに気付いた。息を吸い込み、編集室のあちこちから立ち上る煙草の煙が天井に流れていくのをしばらく見つめる。
苑子は顔をしかめて、背もたれに帯のお太鼓結びを押し付けた。操に相談しようにも、今はどこかの大学の博士に話を聞くという命令で出てしまっている。
机の上に並べた手紙と封筒を眺めていると、封筒の底に小さな皺が見えた。
封筒を手に取り、よくよく観察してみる。あらゆる角度から注視しているうちに、苑子は思わずあ、と声をあげた。
封筒の底が何か鋭利なもので開けられ、また閉じられた跡がある。
苑子は慌てて、一通目と二通目の封筒も確かめてみた。同じような跡が残されている。
これは丹邨孝太郎がやったことだろうかと疑い、軽く首を振った。自分の書いた手紙の封筒にこんなことをする意味がない。
誰かが封筒を底から開け、手紙を出し、読んで、手紙を戻したあとに悟られないよう封をし直した。
盗み読み、という言葉が脳裏をよぎる。あるいは、検閲。
こんなことをできるのは誰だろうか。孝太郎に
こめかみに指を当てて考え込んでいる苑子の隣で、椅子を引く音がした。操がいかにも大儀そうに座り、伸びをする。大学教授への取材を終えて帰ってきたらしい。
「ああくたびれた。京都までというのも楽じゃないわね。その上今日中に原稿を書けっていうんだから……」
操は言葉を切って、苑子をまじまじと見た。
「どないしたん」
「あなたの、こめかみに指をやる仕草」操が真似してみせ、眉根に深い皺を寄せた。自分はそんな顔をしていたのか、と苑子は初めて気付いた。
「考え込んでるときの癖。仕草はいいけど、その顔はやめたほうがいいわね。
憎まれ口を
「また身上相談の手紙で悩んでるの? 今度はどうしたっていうのよ」
手短に経緯を話す。検閲については推測も入っていたが、操は苑子の話を聞くと少し黙った。
「あなたに力を貸すようで
そういえば、丹邨製薬は薬だけではなく、化粧水やクリーム、
「化粧品の進歩について、という話だったから、丹邨製薬に勤めていらしたときのお話も伺ったのだけれど。……丹邨家には、孝太郎というご子息がいるそうよ」
苑子は思わず、操のほうへ身を乗り出していた。
「わざわざ
「話の流れよ。先生は丹邨家に直接出入りしたことはほとんどないけれど、一度食事に招かれたときに紹介された、って」
「そのときの、丹邨孝太郎の様子は」
操は顔をしかめて答えた。
「そんなに詳しく聞いてないわよ。私だって記事のほうが大事なんだもの。でも、前に手紙の差出人についてあなたが訊いてきたから、覚えてたってだけ」
唇を引き締めると、苑子は手紙を持って勢いよく立ち上がった。
「おおきに」
「ちょっと待ちなさいよ」
二、三歩、机から離れかけていた苑子を、操が呼び止めた。
「あなた、どうするつもりなの」
「どないする言うたかて……。丹邨家の息子からこんな手紙受け取ってもうて、
操はあからさまなため息をついた。
「そんなわけの分からない手紙を根拠に、丹邨家に乗り込むつもり?」
苑子は操の顔を真正面から見つめた。
「この手紙は何もかもがおかしい。文面だけやとわけが分からへんけども、丹邨家に入り込めば何か
「それで?」操が
苑子は三通の手紙に目を落とし、つぶやくように言った。
「……丹邨孝太郎が難儀しとるんか、神経が不安定なんか、わてには分からへん。そやけど、普通は手紙を出すとしたら、友人か、信頼でける誰かに出すはずなんや」三通目の乱れた筆跡を見つめ、ゆっくりと続ける。「そやのに、新聞社なんかに手紙を送ってきた。ひょっとしたら、ほかに助けを求める相手がおらへんのと
「だとしても……」
「わてにはこの手紙を見付けた責任がある。そんなら、
操はしばらく苑子を睨んでいたが、ふいと顔をそむけた。
「そう。なら好きにしたら」
机に頰杖をついた操の横顔は、不機嫌そうなままだった。
それきり操を振り返らず、足早に編集長の机へと向かう。男性記者からの原稿を読んでいた編集長に声をかけると、視線だけ寄越してきた。
「化け込み記事を書いて、よろしおますか」
いつも結論から言うのが苑子の癖だ。編集長は眉をひそめ、「なんぞ当てでもあるんかいな」と問いかけてくる。
三通の手紙を渡す。編集長はさっと目を通すと、放るようにして返した。
「こないにけったいな手紙で、わざわざ化け込むつもりかいな」
「丹邨製薬の社長令息から妙な手紙が届いて、しかも盗み見されたかもしれん跡があるんでっせ。ただごとやないと思わしまへんか」
ふぅむ、と編集長が
「丹邨孝太郎さん……丹邨家には、なんぞ良うないことが起こってる気がしますのやがな。こんな事情は、訪問記で正面から訊いて分かるもんやおまへん。化け込みで、家の中に入り込まんと……。丹邨製薬の社長一家の問題、記事にしたらおもしろいんと違いますやろか」
苑子の内心としては「おもしろい」という場合ではないのだが、こう言ったほうが編集長には通じやすい。
幸い、大阪実法新聞には丹邨製薬の広告は出されていない。丹邨家の問題を暴いたところで、社の不利益にはならないだろう。もしそれでも編集長が渋るようだったら、仮名にすると交渉するつもりだった。
編集長はしばらく黙ると、眼鏡の奥からじろりと苑子を見上げた。
「女優志願者やカフェーの女給やったら望みのとこに化け込めるけんど、家に女中奉公となったら口入屋に行かんとな……。丹邨家が口入屋で女中を探しとるか分からへんのに、どないして目当ての家に化け込むつもりやがな」
「前に丹邨家の近くに住んではる夫人の訪問記を書いたことがおますやろ。
編集長は少しの間考えていたが、やがて軽く
「どうせ行くんやったら、行田夫人の訪問記も書き。丹邨家のほうは……まぁ、期待せんでおくわ」
許可を出すなり、編集長は眼鏡を上げて、原稿を再び読み始めた。手紙を胸に押さえつけ、苑子は会釈した。
「そんなら、明日にでも行ってみますわ」
二
翌朝、
これは女学生のときから、苑子につきまとう持病だった。新聞社の、煙草の煙で視界さえ
親元から離れて三年、空気の悪いところからなるべく遠くに、と下宿を定めたつもりが、時が経つにつれ大阪全体が煙に覆われてきている気がする。三十年ほど前、苑子が生まれる前に大阪は「東洋のマンチェスター」と呼ばれていたはずだが、苑子にとってその二つ名はありがたくもなんともなかった。煙突の吐き出す煙のせいで肺を壊し、咳の発作に
午前中、新聞社でいくつか仕事を済ませたついでに、丹邨製薬について改めて調べてみた。丹邨製薬は、丹邨
その社長宅に乗り込んでいくとは、と思うと、我ながら無鉄砲な気がした。しかし一度決めた以上引き返すことなど、苑子の頭にはなかった。
操の訪問記も記憶をたどって古新聞の中から探し出した。だが操がぼやいていたように、夫人の若々しさに関する記述が記事のほとんどを占めており、付け足したように丹邨製薬の化粧品への賛辞が書かれているばかりだ。
昼食を済ませ、また市電に揺られていく。阪神電車前で降り、
婦人記者に任される仕事の中に、訪問記と化け込み記事がある。苑子が今からしようと試みているのは、編集長にかけあった通り後者だ。
訪問記は正式に記者だと名乗って政治家や実業家などの邸宅を訪れ、夫人や令嬢から生活ぶりや趣味などについて聞き出すもので、いわば名家の表の顔を描くものだ。
対して化け込み記事は身分を偽って富裕な家や様々な店に赴き、ときには内部に入り込んで、実情を暴き出すことに目的がある。訪問記では澄まして家庭の仲
丹邨家の内実を探り、記事にする。ここまでは化け込み記事として成り立つかもしれない。しかし、場合によっては孝太郎を助けるとなると、話は別になってくる。とんだお節介、という操の言葉も、分からないわけではない。
苑子は買い換えたばかりの手帳を
詩に目を走らせるたび、思わず胸元を押さえてしまう。自分が書き写した字と違い、日を追うごとに乱れていく孝太郎の筆跡が頭によみがえる。無視できない切迫したものが、あの手紙にはあった。
少なくとも、調べる価値はあるのではないか。孝太郎について。丹邨家について。
電車は
一歩駅に降り、苑子は思わず大きく息を吸った。工場の煙が届かない、清浄な空気を肺に入れるのはいつ以来だろうか。大阪で成功した商人たちが、家を店から切り離し、ここらに居を構えるのも頷ける。
行田夫人の家まで、車を使うほどの距離ではない。傘を差し、南に向かって歩き出しながら、苑子は辺りを見回した。行田家を訪れたのは一年前だったが、駅の近くにある鉄筋コンクリートの精道村役場は記憶のままに堂々としていて、精道村の発展を誇っているかのようだった。
松林と川に挟まれた道を進むうちに、目当ての行田邸が見えてきた。周りの家より一回りも大きな
戸を開けた女中に身分を告げると、ちょうど良く行田夫人は家にいるとの答えだった。この家の
しばらく待つと、行田夫人が姿を現わした。四十代半ばのはずだが表情は若々しく、上品な茶褐色の地に鶴を染め分けた
「お久しおますな、新波さん。雨の中こないなとこへ来てもろて、お
編集長からは、行田家の訪問記も書けるようにしておけと言われている。苑子は訪問記だと答え、当たり障りのない質問をいくつかした。
記事を書くのに充分な応答ができた頃、苑子はさりげなく切り出した。
「ところで、芦屋には丹邨製薬の社長もお住まいやと小耳に挟みまして。行田さん、丹邨家のご夫人とはお付き合いがおますやろか」
行田夫人は丹邨の名を聞くと、少し困ったような笑顔を浮かべて答えた。
「何度かお宅でお茶を頂いたことも、うちに招いたこともおます。それがどないしはったん」
「実は、丹邨家に化け込みすることになりましてん」
「社を辞めるから次の働き口を」などと適当な噓をついて、丹邨家で得られる職を探ることも考えたが、行田夫人の反応からして、丹邨家に良い印象を持っているふうには見えなかった。中途半端な噓をつくよりかは、「化け込むつもりだ」と言ってしまっても差し支えはあるまい。
行田夫人はさもおかしそうに、くすくすと笑った。
「そうでっか、丹邨家に化け込みを。あんさん、さては初めっからそのつもりで来はったんやな」
「いえ、訪問記は書かせてもらいます」苑子は慌てて答えた。「そやけど、丹邨家で何か入り用な人手があるか、知ってはったらと思うて。あの、化け込みのことは、丹邨家には……」
「言わしまへん、言わしまへん」行田夫人は繰り返して、笑みを浮かべたまま続けた。「白状しますとな、丹邨家とはお付き合いがおますけんど、わて丹邨家の奥様のことはあまり好かんのですわ。……これこそ言うたらあきまへんよ」
もちろん、と答えながら、苑子は内心やや驚いていた。訪問記や化け込み記事を多く書いていると、話している相手の人となりくらいは摑めてくる。行田夫人は滅多にひとを嫌わない、広い度量を持った人物だと苑子は感じていた。その行田夫人が「あまり好かん」と言うからには、よほど丹邨夫人に何か問題があるのだろう。
ひとつ、思い当たることがあった。
「もしかして、丹邨夫人がご自分の容姿を鼻にかけてはることでっか」
行田夫人はあら、と声をあげた。
「さよか、記者の間にも広がっとるんやな。そんなら隠すこともおまへんな。丹邨夫人はな、会うたんびにご自分の肌や髪の美しさをことさら自慢しはるんやがな。聞いとるほうはたまったもんやないで……。どの集まりでもそうしてはるもんやさかい、あまり評判は良うないんと違うかなぁ」
少し言い過ぎたと思ったのか、行田夫人は付け加えた。
「ああ、でも丹邨家にとっては悪いことばっかしやおまへん。ここいらのご婦人の間では、確かに丹邨夫人は若々しい、丹邨製薬の化粧品のおかげやないか、いうて、お使いになるおひともいはるよってに」
自慢されるのは癪だが、若さを保つ
考えている苑子をよそに、行田夫人が話を戻した。
「そや、丹邨家に化け込むいうことでしたな。女中奉公が手っ取り早い思いますけんど、あんさんは女中いう柄やおまへんな。見破られたら元も子もおまへんさかい」
苑子は自分の着ている、
「気付かれますやろか」
「お
行田夫人は少し考えると、ふと頭を上げた。
「あんさん、何かお嬢さんに
「お嬢さん?」苑子は思わず聞き返していた。「丹邨家には娘さんもいはるんでっか」
「正式に紹介されたわけやないんでっけど、ちらと見たことはおます。お嬢さんでっか、て夫人に訊いたら、そうです言うてはりました。女学校も卒業してはる年頃やろうなぁ。ああいうお嬢さんは趣味で何か習いはるよってに、ひとつ教ぇる仕事ならわてから紹介でけるんやないかと」
苑子は今までの経歴や得意なことを思い出してみた。
「裁縫はできます。日本
「多才やなぁ」行田夫人は
立ち上がった行田夫人に、「えろうおおきに」と、苑子は頭を下げた。
行田夫人から手紙と、丹邨邸への地図を渡され、苑子は行田家を辞した。丹邨邸は行田邸よりさらに南、海に近いところにある。芦屋駅付近で訪ねたことがあるのは行田夫人の家だけだ。見慣れぬ場所を、地図を頼りに歩いていると、やがて目当ての邸宅が見えてきた。どうやら裏手らしいが、クリーム色がかった白い壁とスレート屋根の洋風建築で、手前には家と対照をなす昔ながらの庭園らしいイロハモミジが植えられている。行田夫人の言った通りの外観だった。
玄関に回り込み、女中に丹邨夫人への取り次ぎを頼む。用件を告げると、玄関を入ってすぐ右手の客間に通され、待つように言われた。青い絨毯が一面に敷かれ、
五分ほどして、丹邨夫人が客間に入ってきた。黒地に黄色い
「こちらの家にお嬢様がいはるて聞きましたさかい、なんぞ教ぇて差し上げるものがあるんやないかと思いまして、お邪魔させていただきました。こないだまではある家のご令嬢に日本刺繡を教ぇてました。それが、一家が引っ越すことになってしもうたさかい、新しい勤め口を探しとるとこなんです」
「
苑子は内心首を傾げた。娘は礼以という名前らしいが、よほど人前に出ないのだろうか。
行田夫人からの手紙を渡す。文面に目を通して、ようやく丹邨夫人は得心がいったように声をあげた。
「ああ、行田夫人の紹介でっか。そういえば、あのおひとは一度礼以さんを見かけてはったな。よう覚えてはるこっちゃ」
「はい、行田夫人からお嬢様のことを伺いましたさかい……」
言いかけて、ひとつふたつ咳が出た。よりによってこんなときに、と急いでハンカチを口に当てる。
丹邨夫人は気分を害したようでもなく、心配そうに苑子の顔を覗き込んだ。咳の発作が治まるのを待って問いかける。
「肺が悪いんでっか」
「結核やおまへん。ただ生まれた頃から大阪に住んどったせいで、工場の煙にやられてしもうて……」
同情を込めた顔つきで、丹邨夫人は頷いた。
「わてらも昔は大阪に住んどったんやけども、空気が悪いわ道は
苑子は
丹邨夫人は行田夫人からの手紙を読み返すと、ふむ、と考える素振りを見せた。
「こればっかしは、わてひとりでは決められまへんわ。娘にも好き嫌いがおますよってに。あんたはん、ちょっと待っとくなはれ。話をしてきますわ」
そう言うと、丹邨夫人は手紙を持って、客間から出ていった。
再び待たされるのかと客間でじっとしていたが、今度は十五分ほど経っても帰ってこない。じりじりしながら待っていると、夫人だけが客間に戻ってきた。
「裁縫や刺繡はようやらん言うてますけど、あんたはん、絵も教えはるんやな。日本画? 西洋画?」
「日本画です。美人画をよう学んどりました」
丹邨夫人は頷いた。
「ほんなら、絵を教ぇてもろてよろしおますか。娘がやりたい言うとるさかいに」
丹邨夫人に導かれて、奥の階段を上がる。どうやら娘の部屋で引き合わされるらしい。廊下の突き当たりまでに扉が三つ、左手に並んでいるが、丹邨夫人は廊下の半ばほどで右に曲がった。右に
丹邨孝太郎について探るのはまだ早いだろうか、と考えあぐねているうちに、丹邨夫人が襖を開けた。広々とした畳敷きの部屋で、鏡台と
娘の礼以は鏡台の前で正座をしたまま、ゆっくりと顔をこちらに向けた。
礼以は苑子に向かい微笑みかけると、「その方ね」と丹邨夫人に話しかけた。夫人が苑子を手でさす。
「新波苑子さん。美人画も描けるさかいに、よう教ぇてもらい。新波さん、こちら娘の礼以。外には滅多に出んさかい、失礼があるかもしれまへんけど、よろしゅうお願いいたします」
苑子がはい、と答えたかと思うと、丹邨夫人はこれで紹介は済んだとばかりにひとつ会釈し、向かいの部屋に入っていった。どうしていいか分からず、礼以の部屋の外で動けずにいると、礼以が立ち上がって苑子に近付き、手を取った。柔らかな指だった。
「そんなところにいないで、入ってきてくださいまし。先生とお呼びしてよろしいかしら。それとも新波さん? 苑子さんかしら」
力は弱いが、部屋に引き入れられそうになる。苑子が慌てて、
「小雨が降ってましたさかいに、
と告げると、礼以は苑子の着物の裾をしげしげと眺めた。
「あら、乾いていたらなんてことないわ。遠慮なさらないで」
時機を図っていたかのように、後ろから若い女中が声をかけてきた。礼以の許しを得ると、女中は部屋の隅にあった
乾いているといっても、泥の跡や
女学校を卒業しているようだと行田夫人から聞いていたが、確かに礼以は
まだ気になったことがある。これなら尋ねても差し支えはないだろう。
「礼以さん……でっか。その
礼以はああ、と眉を下げた。
「女学生のときは、東京にいたの。お父様のお眼鏡にかなう学校が大阪にはなかったみたいで……。それで卒業と同時に、芦屋に越していたお父様たちのところへ戻ってきたのよ。震災の少し前だったかしら」
礼以の学友のことに思い至り、苑子は何も言えなくなった。しかし幸い親しい者にひどい被害はなかったのか、礼以は沈んだ顔を見せるでもなく苑子のほうへ身を傾けた。
「そんなことよりも、今日は絵のお道具は持ってきていないの。私の分はすぐお母様に頼むつもりだけれど」
「何を教ぇるか分からんかったもんで……。明日、大阪から持ってきますわ。そやけどしばらくは、画用紙を
苑子が絵を習ったのは実家にいた頃だったから、絵の道具は親に捨てられているだろう。帰ったら急いで用意しなくてはならない。
「じゃあ、私の集めたものをご覧になって。きっと教えるときの参考になるわ」
言うが早いか、礼以は手文庫の中を探って、紙の束を取り出した。乙女らしく少女雑誌の挿絵を切り抜いたものや、美人画の添えられた広告がほとんどだ。
「こういうものが描けたら素敵だと思うの。どうかしら」
「わてのやる日本画とは違いますけんど……美人画でしたら、教ぇて差し上げられます」
礼以は
「そうね、広告になるような絵がいいわ。丹邨製薬の広告って、少し味気ないと思うのよ。化粧品でさえ、瓶の絵と文だけだったりすることもあるし……。美しい絵を添えたら、きっと皆の目を惹くのではないかしらと思って。でも私、絵はからきしなものだから」
考えていたのとはかなり違う要望が来て、苑子は面食らうのと同時に感心した。資産家の娘であれば趣味で絵を
ただの箱入り娘ではない、と考えていると、礼以が出し抜けに訊いてきた。
「ねぇ、ところで、女学生は化粧をするの? もしするのなら、女学生向けの広告も考えたいのだけれど」
苑子は思わず
「そうでんな……女学生は薄化粧をしますけんど、学校によっては華美やいうて禁止してはるところもおます」
答えると、礼以は目を見開いた。
「あら、そうだったの。私の学校では化粧をしてはいけないと言われていたから、ほかの学校はどうなのかと思って」
それならば説明はつく。卒業後芦屋で父親の仕事を見ているうちに、化粧への関心が湧いてきたのだろう。
考えているうちに、礼以が苑子に向かい
「苑子さん。今日は絵の道具がないのなら、外のことを教えてくださらないかしら。私はこの家にこもりきりだけれど、苑子さんは働いていらっしゃるのだから、きっと世間のことを色々とご存じよね」
苑子が承知すると、礼以はいかにも嬉しそうな声をあげた。
礼以の質問は日々の行事や街を歩く人々の身なりといったちょっとしたことから、商業の動きまで多岐にわたった。婦人記者なりに世情には詳しいが、特に政治や商業に関して明るいと不自然だろうし、かといって何も知らないというのも格好がつかない。口に出す前に、いちいち答えを熟慮しなければならなかった。
問いかけは尽きるところを知らず、苑子が困りかけてきたとき、
袖で口を押さえるのと同時に、止めようもなく咳が出る。礼以から顔を背け、片手を畳につく。
礼以は悲鳴のような声を立てて、苑子の背をさすった。
「どうなさったの。何かお身体の具合でも」
「大事おまへん」また咳が出る。「持病のようなもんで。大阪の煙で、肺を悪うしとるさかいに」
礼以はそれを聞くと、「少し待っていて」と言い、部屋から飛び出していった。数分もしなかっただろう、足音が戻ってきて、脇に礼以が座る気配がした。硝子が触れ合い、水が注がれる音がする。薄目を開けると、盆の上に水の入ったコップと水差しが置かれていた。
うずくまったまま咳に耐えているうちに、礼以の手がふいに視界に入った。丸薬らしきものが一粒、掌に載っている。
不思議な見た目だった。真珠のように白く、
「丹邨製薬の咳止め薬なの。まだ試作なのだけれど、効き目は確かだから、お飲みになって」
試作の品というのに不安を覚えなくもなかったが、咳の苦しさに襲われている今、断ることはできなかった。それに丹邨製薬には日本中に知れ渡るほどの実績がある。苑子は丸薬を受け取り、コップの水で飲み下した。
しばらく軽い咳が出たが、数分後には咳が治まっていた。喉から胸元にかけて触ってみる。あの不快な感触が噓のように消えていた。
「どう?」
礼以の細い手には、丸薬の入った小瓶が握られている。苑子は信じられない気持ちで、小瓶の中身をまじまじと見つめた。
「喉から肺から、洗われたような心持ちですわ。こんな薬を丹邨製薬が作っとったやなんて……」
礼以は胸を撫で下ろして、
「よかった。ああ、ほかのひとには内緒よ。いずれ大いに売り出すつもりなのだもの」
「それはもちろん、秘密にしますわ」
ようやく事態が収まり、しばらく話していると、女中が声をかけてきた。夕食の用意ができたらしい。
「もうそんな時間なの。苑子さん、ご一緒してくださいな」
礼以が袖を引いてきて誘う。夕食の席ならば、丹邨孝太郎は来るだろうか。手紙通りの様子なら自室で食べるかもしれないが、一家の様子を
「そんなら、ご相伴にあずかります。えろうおおきに」
答えると礼以は嬉しそうに苑子の手を引いたまま、廊下を渡り、階段を下りた。
食堂は青い絨毯にテーブル、凝った透かし細工の施されたシャンデリアという、洋風のしつらえだった。南側に面しており、
訪問記で洋風建築の家を訪ねたことはあるが、食事にまで呼ばれたことは滅多にない。思わず見回しながら案内された席に着く。礼以と丹邨夫人も座ると、女中が料理を運んできた。
「主人は仕事で大阪に行っとるさかい、今日は遅うなるやろう。冷めへんうちに食べましょか」
「あら、孝太郎さんがまだよ」
孝太郎、という名前に、苑子の心臓が軽く跳ねた。丹邨夫人は礼以の言葉に一瞬固まると、困ったように眉を下げて、
「今日は熱を出しとるそうや。女中に食事を持っていかせるよって、安心しとくなはれ」
とやや早口で言った。
「そう、熱を。ちゃんと食べるか心配だわ。あの子は食が細いから」
礼以が独りごちるように返し、
「孝太郎さん……はここの息子さんでっか。熱を出してはるやなんて、心配でんな」と探りを入れてみた。
「弟なの。中学生なのだけれど、学校にも行かないで部屋に閉じこもっているのよ」スープの皿に目を落としたまま、礼以が答えた。「大きな病気はないから、苑子さんは心配しないで」
その口調にどこか冷たい壁のようなものを感じ、苑子は質問を重ねられなかった。それでも、全く何も分からないよりかはましだろう。
食事がてら話をしている間に、丹邨夫人は
「わてはこう見えて数えで四十五を過ぎとりますけんど」登世の口調に自慢げなものが混じる。「三十より
四十五、というのに苑子は驚きを覚えたが、おべっかを求められていることも分かる。
「ほんに、三十より手前に見えまっせ。肌も髪も、そんじょそこらのご婦人ではかないまへんわ」
登世は満足げに紅を塗った唇の端を上げ、小さな笑い声を漏らした。操や行田夫人の言っていたのはこういうことか、と考えていると、登世がこちらをじっと見ているのに気付いた。どこかじっとりとした、絡みつくような視線だった。
「新波さんは、おいくつなんでっか」
唐突に年齢を訊かれた戸惑いと、無礼ではないかという怒りが一瞬湧いたが、顔に出るのをすんでのところで抑える。「数えで二十三です」と素直に答えると、登世はますます粘ついた
「さよか、二十三……。大阪の女は二十でもう老けるいいますけんど、新波さんはおきれいでんな」
お世辞とも、素直な褒め言葉とも取りかねる、妙な口調だった。苑子はどうにか、
「はぁ、あの、それほどでも……」
と返すことしかできなかった。
登世の視線に耐えかね、助けを求めて礼以のほうを向くと、礼以は皿の上にある腸詰をしげしげと眺めていた。
「お母様。これは腸詰……よね」
我に返ったかのように、登世は苑子から目を離して答えた。
「さいでおます。牛や豚の腸に、
礼以は腸詰を切ってフォークで刺し、あらゆる方向から見つめ始めた。観察している、といっていいほどだった。苑子が怪訝に思っていると、やがて礼以の口から、途切れ途切れに言葉が聞こえてきた。
「肉……動物性
何かの分析をしている学者のような、乾いた口調だった。
ひとしきりつぶやきを終えると、礼以は腸詰を食べ、何度も
登世は慣れているのか、礼以の振る舞いに驚いた様子もない。ただ取り繕うように、苑子に向かって、
「腸詰が出たのは久しぶりやさかいなぁ」
とだけ言った。
食事が終わると、登世と礼以はわざわざ苑子を玄関まで見送りに来た。ふたりが食堂で見せた妙な素振りはもうどこにもない。ただ美しい親子が、広いホールを背にしてにこやかに立っているだけだ。
「ところで苑子さんは、週にどのくらい教えにいらっしゃるの。私は何日でも構わないのだけれど」
ふいに訊かれ、苑子はとっさに答えた。
「週に二日ほどやと、どないでっしゃろ。ほかに教ぇる家はおまへんけんど……」
「あら、じゃあ毎日でもよくってよ。私は暇を持て余しているんだもの」
新聞社での仕事も考えると、さすがに毎日は難しい。押し問答の末、週三日、午後に訪れることになった。これなら午前中や丹邨家への訪問がない日には会社に行ける。登世が礼以の背後で頷いた。
「ほんなら、明日から娘をよろしゅう」
はい、と登世に答え、すっかり雨の乾いた前庭に踏み出す。小雨を降らせていた雲は薄くなり、暗くなった空を覆っていた。
その日、芦屋から大阪に帰り、新聞社で行田夫人の訪問記を書いている間にも、退勤後に心斎橋で絵の道具や少女雑誌を買い、帰宅してからも、咳は一回も出なかった。
三
翌日、編集長に今回の化け込みは長くなりそうだ、と告げると、案の定眉をひそめられた。
「普通化け込みは一日、長うて三日ほどやというんに、どんくらいおるつもりや」
「まだはっきりとは言えしまへん。三日よりは長うなるんと違いますやろか。家庭の内情をようよう調べんとあきまへんさかいに」
渋い顔をしたままの編集長に、それでも化け込みがないときは社に来て仕事をする、と言って押し切った。
まだ記事にとりかかる段階ではない。苑子は自分の机に戻り、手帳と
紫がかった赤い革表紙の手帳は、入社当時、偶然店で見かけたときからの気に入りだった。ページが埋め尽くされるたびに、ずっと同じものを買っている。色合いや紙の書きやすさもさることながら、男性記者のよく使う黒い手帳と取り違えることがないのも、愛用している理由のひとつだった。
昨日の丹邨邸で見聞きしたことを手帳に書く。結局、孝太郎には会えなかった。とはいえ、学校に行かず部屋にこもっていること、大病を患ってはいないことを聞けたのは収穫だろう。
気にかかることを反故紙の裏に記し、机の引き出しに入れる。化け込みの期間は長くなりそうだ。
午後に丹邨邸を訪れ、礼以の部屋に通されると、待ちかねていたように礼以が駆け寄ってきた。
「ずいぶん待たせて、ひどい人ね。お入りになって。道具はこれで充分かしら」
文机の上を見てみると、昨日苑子が言った通りに、画用紙を綴じた写生帳と鉛筆が何本か置かれていた。
「そんなら、一度鉛筆で美人画か挿絵を模写してみなはれ。線を真似るだけで充分でおます。好きな絵でも構いまへんし、私も少女雑誌を
それなら、と礼以は手文庫から少女雑誌の切り抜きをいくつか取り出してきた。海を背景に、籐椅子に座る令嬢を描いた絵を手本と決めて、写生帳を広げる。
横で見ていると、手つきは
礼以が鉛筆を置くと、苑子はすかさず褒めてみせた。
「よう描けてはりますわ。からきしやなんて昨日は噓言わはって。女学校でも図画はようできてはったんと違いますのん」
描き上げた絵を厳しい目で見ていた礼以が、ふと苑子に視線を移し、「図画……」とつぶやいた。
「国語や裁縫に比べたら少ないですけんど、図画の授業はおましたやろ」
苑子に言われて、礼以はああ、と声を出した。
「そうね、良くもなし悪くもなし、だったかしら」
礼以はそれだけで女学校での図画の話は切り上げ、苑子に写生帳を渡した。
「悪いところは遠慮なくおっしゃって。褒めてくださったのは嬉しいけれど、まるでなっていないことは自分でも分かっているわ」
苑子も褒めてはみたものの、身体の部位や目鼻の均整はとれておらず、骨格のずれも目に付く。機嫌を損ねないようにと柔らかく指摘すると、礼以はすんなりと受け入れた。
「こうしてお手本を見るとできるように思えるものだけれど、案外難しいのね」
「慣れてきたら外へスケッチに行くのも気持ちのええもんでっせ。山やとか、海やとか。この家からやと海のほうが近いですけんど」
礼以は小首を傾げ、
「海は確かにすぐそこだけれど。家にずっと閉じこもっているから、ひどく遠く思えるわ」
踏み込んでいいのか一瞬迷ったが、ただ絵の先生のふりばかりしているわけにもいかない。思い切って尋ねてみる。
「礼以さんは、その……お身体に何か」
「そういうことじゃないの。ただ外に出るのが怖い気がするだけ。お母様がよくお客や婦人記者を家に入れるのだけれど、あれも苦手なの。だからそういうときは、私は部屋から出ないのよ」
人目を避けたい、という性格なのだろうか。行田夫人が礼以を見かけたのは、
「そんなら、なんでわてを雇ってくれはったんでっか」
「広告のために絵の勉強はしたかったし……」礼以ははにかんで、「お母様から若いご婦人だと聞いて。私には弟しかいないし、お姉様のような方だったら素敵だと思ったの」
どう答えていいか分からず、苑子は曖昧な声を出して礼以から視線を逸らした。女学生のとき、生徒同士で姉妹のような関係を築いたことはあるが、卒業してからもそのようなことを言われるとは思いもしなかった。
別の話題を探して部屋を見回しているうち、ふと床の間に飾られている藪椿が目に入った。昨日はそうとは気付かなかったが、花びらの端がやや茶色くなってめくれ、枯れかけている。
「礼以さん。あの藪椿……」おずおずと声をかける。「差し出がましいようですけんど、取り替えたほうがよろしいんやないかと……」
礼以は床の間に顔を向け、ああ、と声を出した。
「あれはいいのよ。そのままでいいの」
どういうことなのか、と訊く前に、礼以が続けた。
「枯れていくのを見たいの」
礼以は赤と茶色の入り混じる藪椿を眺め、口の端を上げた。
苑子が何と言っていいのか迷っているうちに、ふいに襖の外から女中が、
「
と声をかけてきた。礼以がぱっと立ち上がって襖を開ける。苑子は礼以に気取られないよう、静かに息を吐いた。なぜだか胸が早鐘を打っていた。
「今日はお早いのね。取引がうまくまとまったのかしら」
苑子をちらと振り返ると、礼以はまた女中に向き直った。
「ねぇ、夕食を少しばかり早くしてくれない。昨日の夕食ではお父様がいらっしゃらなかったから、苑子さんも一緒にお食事をしていただきたいの」
女中は戸惑い気味に眉を下げて、
「早くですか」
「そう。いけない?」
段取りが狂うことに女中は困惑を隠せなかったが、無理だとは言えないのだろう。「かしこまりました」と答えると、足早に廊下を歩いていった。
女中には気の毒だが、丹邨家の事情を知るためには主人である丹邨光将に顔を売る必要がある。苑子はあえて遠慮の言葉を口にしなかった。
礼以は当たり前のように苑子の手を取り、部屋の外に連れ出した。
「お父様が帰ってきたら、一家でお出迎えするのよ。孝太郎さんは出てこないだろうけれど……。苑子さんも先にご挨拶しましょう」
階段を下りると、長く広いホールの突き当たり、玄関の近くで、洋服を着た初老の男性が登世に出迎えられていた。
礼以は早歩きで両親のもとに近付き、ふたりに微笑みかけた。
「お父様、今日は早いお帰りで嬉しいわ。お待たせしてしまってごめんなさい」
「かまへん、わしこそいつも遅うてすまんな」
そう言って目尻に皺を寄せる初老の男性――光将は、苑子が写真で見るより良くいえば親しげ、悪くいえば大企業の社長とは思えないほど平凡な雰囲気だった。背もさほど高くなく、威厳を示す点といえば口髭と
礼以が苑子を自分の斜め前に立たせて、背中に手を添えた。
「お父様、この方は昨日から私に絵を教えてくださることになった新波苑子さん。苑子さん、こちらはお父様の丹邨光将。ご存じかもしれないけれど」
「ええ。お噂はかねがね伺っとります」
苑子が言うと、光将は気恥ずかしそうに笑った。
「さよか。一介の薬種商のつもりが、いつの間にか名が知れてもうて。化粧品も売っとるいうんに、社をまとめとるんがこんな髭面でえろうすんまへん。娘をよろしゅうお頼み申します」
気さくな口調に、登世と礼以が笑みをこぼす。仲の良い一家というふうだが、やはり孝太郎の姿はない。
光将の後ろには背の高い、洋装の男性が姿勢良く立っていた。西洋風の顔立ちとでもいおうか、彫りが深く鼻筋が通り、やや垂れた目は茶色みを帯びている。髪は軽く鏝を当てたように緩やかな曲線を描き、丁寧に撫でつけられていた。街を歩いていても振り返られそうな容姿だ。年は三十手前に見えるが、顔立ちのせいではっきりとしない。もっと若いかもしれなかった。
苑子の視線に気付いたのか、光将が一歩脇に退く。
「ああ、これはわしの秘書で、
苑子が挨拶をすると、白潟は一言、
「よろしくお願いします」
とだけ言った。
目を合わせたその一瞬、白潟の様子に、何か妙なものが感じられた。
わずかに眉をひそめ、目の奥まで覗き込むような視線で
動けもせず、言葉も発せられないでいる間に、礼以が急に苑子の袖にすがりついてきた。
「お父様、せっかく早くに帰ってこられたのだから、お食事の用意を急がせたのよ。苑子さんとご一緒しましょう。とても良い先生なのよ」
白潟がわずかに口角を上げた。先ほどまでの険しい様子は
「二日でずいぶん仲がよろしくなったようで。お嬢様にしてはめずらしい」
からかわれていると取ったのか、礼以はわざとらしくしかめっ面を作った。
「ひどいことをおっしゃるわね。私だって外の方と仲良くすることもあるわ」
光将が苦笑しながら頭を搔いた。
「娘がこれほど懐くいうんは、何にせよめずらしいこっちゃな。そやけど、わしは少し白潟との仕事が残っとるさかい……」
「だめなの?」
礼以が短く言う。光将は頭に指をやったまま、少しの間固まった。
「いや……あかんいうほどでは……」
「付き合ったらよろしいやないの」登世が口を挟んだ。「可愛い礼以の言うことやないの。仕事で忙しい分、たまには埋め合わせをしたらどない」
光将がちらりと白潟を見る。白潟は抑揚のない声で、
「仕事はこちらで引き受けます。夕食は僕の部屋に運ぶようにしてくだされば」
と言った。光将が申し訳なさと
「さよか、そんならすまんけど、頼むわ。分からへんことはあとで訊きに来たらええ」
頷くと白潟は光将の
白潟に向けられた眼差しが気になり、思わず苑子はその背中を見送った。長身が踊り場を抜け、二階へと消えていくまで、なぜだか目が離せなかった。
気のせいかもしれない、と強いて階段から視線を逸らしたとき、喉の奥にいつもの感覚が走った。止めるに止められず、咳が続けて出た。「すんまへん」と言う間もなく、また咳をする。
礼以が慌てた様子で苑子の背中を撫で始めた。立ちすくんでいる光将に説明する。
「大阪の煙害で肺を痛めていらっしゃるの。昨日、お薬を差し上げたのだけれど。ほら、あの試作の品よ。すぐ取りに行ってくるわ」
言うなり礼以は小走りでホールを駆けていった。女中に向かってか、「水を」という指示が聞こえてくる。
じき礼以が小瓶を持ってきて、丸薬を一粒苑子に渡した。飲んでみると、昨日と同じように数分経った頃には、咳が治まっていた。
「えろうすんまへん、貴重な試作の品を」
「いや……。そんなことはかまへん」光将は気の毒そうに苑子を見つめた。「そやけど難儀なこっちゃな。あの薬は一日しか効能がもたへんのや。それ以上はどないしても延ばされへん。大阪の煙害ばかりはなんともならへんさかいな、せめて薬で世の役に立とう思うたところが、肺ごと治す、いうわけにはどないしても……」
「いえ、一日治まるだけでも助かります」
光将はああ言ったが、苑子は薬の効き目に驚いてすらいた。市販の咳止め薬をいくつも試してきたが、これほど効くものはなかった。
「
「ええ」小瓶を手に、礼以が微笑んだ。「ほんとうに」
ふと、視界の端で何かが動くのが見えた。笑みを浮かべたままの礼以の背後、長いホールの端にある階段の踊り場から、十四、五歳ほどの少年がこちらを覗いている。
丹邨孝太郎に違いなかった。
真っ青な顔をしていることが、ホールからでも見てとれた。孝太郎は礼以の背中に、そして苑子に視線を寄越し、やがて静かに階段を下りて、手洗いのほうへ消えていった。
苑子を囲む丹邨家の誰ひとりとして、孝太郎に気付きはしなかった。
少し経って、食事の準備ができたと女中が告げてきた。食堂には登世と孝太郎がおらず、光将、礼以、苑子の三人で食事が始まった。
夕食は昨日と同じ洋食だった。前菜はサーディンが二尾とオリーヴが品良く盛り付けられたものだ。
五分ほど経った頃、登世も姿を現わして席に着いた。女中がすかさず登世の前菜を運んでくる。
「遅れてすんまへんな。友人への手紙を書くつもりが、つい筆が乗ってしもうて」
そう軽く
白潟の存在は気にかかったが、やはり自室で食事を
「あら、遅かったわね」
礼以の声色は優しかったが、孝太郎はびくりとして姉のほうも見ず、おずおずと苑子の向かいに座った。苑子たちにはコンソメが運ばれてき、孝太郎の前には前菜と、ほかの者と同じスープが並べられた。
何の変哲もない一家の食事だった。光将が取引の首尾について上機嫌に話し、登世は頷きつつも商売のことは分からないのか、やんわりと近所の夫人たちとの交流について話を運んでいく。今日は礼以も、出された料理の分析をする気配がない。
その中で、孝太郎だけがどうも気にかかった。食事の進みが遅く、コンソメすら無理に口にしているように見える。家族の会話に加わることもなく、誰かの話に反応すらしない。熱が出ていたと昨日登世が言っていたから、病み上がりで調子が悪いのだろうか。
牛肉の煮込み、トマトサラダと続き、デザートに
「孝太郎さん、食欲がないの?」
その言葉に孝太郎だけでなく、登世も、光将さえもびくりとしたのが、苑子にもはっきり分かった。孝太郎はまだ牛肉すら食べきっておらず、トマトサラダと苺には手がつけられていない。
「心配だわ。ちゃんと食べないとだめよ」
姉の気遣い、のはずだった。しかし何かが違う。声は硬く、冷たく、食堂の空気を凍らせていく。
突然、孝太郎の隣に座っていた登世が焦りを
「食べ。早う食べ。まだ肉もサラダもこんなに残っとるやないの」
それでもナイフとフォークを持ったまま縮こまっている孝太郎にしびれを切らしたのか、登世は孝太郎の手からフォークを奪い取り、薄切りの肉を孝太郎の口に突っ込んだ。うぐ、という声が孝太郎の喉から漏れ、ブラウンソースがテーブルに飛び散る。
「
孝太郎の
涙が孝太郎の目に浮かび、胸が
「孝太郎、早う食べ。わての、お母はんの言うことがきかれへんのか」
「礼以に心配させるんやない。わしの息子なんやさかい、このくらい食べられへんでどないするんや」
怒鳴りながら息子に食事を詰め込んでいる父母を、苑子はただ
ゆっくりと視線を横にずらすと、礼以は食堂の騒ぎなど起こっていないかのように、珈琲を飲んでいた。
この娘の言葉が発端だ。
思い返してみると、光将も登世も、表向きは普通だが、常に礼以の機嫌を窺っていた。ホールでも光将は仕事があると言っていたのに、礼以の一言で夕食に付き合うことにしたし、登世も礼以の味方をしていた。
珈琲を喉に流し込まれた孝太郎は、咳き込みながらテーブルに突っ伏しかけたが、どうにかこらえて席を立った。顔を
登世は額の脂汗をハンカチで拭うと、残ったサラダに手をつけ始めた。光将も席に戻り、ぬるくなった珈琲で口を湿す。礼以は苺をかじり、咀嚼しているが、その顔には何の感情も浮かんでいない。
誰もが一言も発さない食堂の中、食器の触れ合う音だけが、苑子の頭の中でいやに響く。
丹邨家は、
(気になる続きは本書でお楽しみください)
作品紹介
書 名:骨を喰む真珠
著 者:北沢 陶
発売日:2025年01月31日
横溝正史ミステリ&ホラー大賞三冠作家による、新たな恐怖と悲哀。
「僕はこの家から逃げられへん身にさせられてしもうた」
大正十四年、大阪。病弱だが勝ち気な女性記者・苑子は、担当する身上相談欄への奇妙な投書を受け取る。
大手製薬会社・丹邨製薬の社長令息からの手紙であり、不審を覚えた苑子は、身分を偽り丹邨家に潜入することに。
調査を進めるうち、その異様さが明らかになっていく。苑子を苦しめていた咳をただちに止める、真珠のような丸薬。
一家の不可解な振る舞い。丸薬を怪しんだ苑子は、薬の成分分析を漢方医に頼む。
返ってきた結果には、漢方医も知らない「骨」が含まれていた――。
もう逃げられない。気付いてからが、本当の地獄の始まりだった。
「丹邨家に巣くう災厄をあなたが払えることを祈ります」
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322404000862/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら