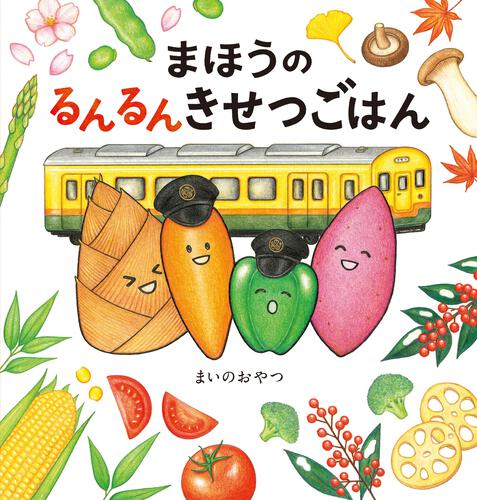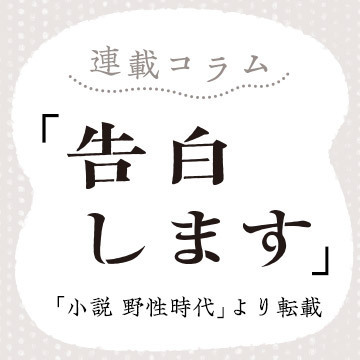4
家に帰ると、奈緒子は夕食の準備を始めた。
久しぶりの散歩で疲れたのか、郁子は帰り道の途中で寝てしまった。帰宅しても起きなかったので、そのままベッドに運んで横たわらせた。
夕食の準備をして、途中で居間の掃除を挟んで、また台所に戻る。唯奈はずっと居間のソファで、『セーラームーン』の漫画を読んでいた。プーさんがいなかったので尋ねると、「おばあちゃんにまだかしてあげてる」とのことだった。
あれ、と思った。引っ越してからずっとべったりだったのに。
「もしかして飽きてきた?」
奈緒子の声は、どこか嬉しそうだった。
「ちょっとこわいから。プーさん」
「え? 何で?」
「りゅうじくんが言ってた。プーさんはあくまだって。そういうお話があるって」
午後七時を過ぎた頃、唯奈に「おばあちゃん起こしてきて」とお願いした。
唯奈はすぐに戻ってきた。
「おばあちゃんいないよ。プーさんも」
は、と声が漏れた。
慌てて郁子の部屋に行くと、ベッドが空だった。枕元に、四つ折りにされた
なおこへ――
短いメッセージを読み終えると、縁側の窓が開いていることに気づいた。一気に血の気が引く。唯奈に留守番を命じると、奈緒子は家を飛び出した。まだ近くにいることを願う。けれど、いない。
あたりはもうすっかり暗くなっている。どうしよう。冠村は車通りはほとんどないけれど、道が暗いので川や田んぼに落ちるかもしれない。雪で滑って怪我をするかもしれない。凍えているかもしれない。もし命に
――そうなってくれたら。
一瞬浮かんだ考えを振り払うように
向かう先は決まっていた。
“窒息の家”は、村の北側の外れに建っていた。
柊家からは、車で二分ほどのところにある。
村で一番大きな家だ。敷地面積は約六百坪あるらしく、建物を囲む土塀はずっと向こうまで続いている。百年以上前から建っているらしいが、現在は誰も住んでいない。“御家”が何代か前に改築したらしいけれど、今ではすっかり朽ち果てていた。
土塀は一部が
表門をくぐって、敷地内に入る。すると、白い車が停まっているのが見えた。
ナンバーは「8888」。日中に会った男女のものだ。やはりここに来ていたのだ。
だけど、彼らと会ったのはもう五時間ほど前のことだ。あの後すぐに見つけたとして、いったいこんな古びた家で何をやっているのだろう。
ジャアア、とタイヤの下で砂利が鳴る。白い車の横に停めると、後部座席を振り返った。「ママはおばあちゃん捜してくるから、ここにいて。絶対外に出ないでね」
ぐずるかと思いきや、唯奈は素直に
懐中電灯を
引き戸が、中途半端に開いていた。
奈緒子は
懐中電灯の光を右に向けると、大きな池がある。夜闇を吸って黒く染まった水には波紋もない。しかし、見つめているとそこから何か出てきそうな気がして、奈緒子は慌てて正面を向いた。
玄関に着くと、首だけを入れて中の様子を
「お……お母さん?」
声を出すと、
「お母さん! いるの?」
返事はない。奈緒子は顔を歪ませると、意を決して進み始めた。
式台を踏むと、人が
玄関を抜けて隣接した部屋に入ってすぐ、足許に
恐る恐る食堂を抜けると、中庭に面した廊下が見えた。
通路の先に灯りを向けると、緑色に光る二つの目があった。奈緒子がひっと短い悲鳴をあげると、目の主はさっと身を翻してどこかに消えてしまう。ハクビシンか何かだろう。そう言えば、さっきから二階か天井裏で、何かが
廊下を真っ直ぐ抜けると、五畳の空間に出る。
五枚の襖が並んでいて、この先に広い空間があることを予想させた。
声は、襖の向こうから聞こえた。
「……しは……たがあかず……と……っていまし……」
郁子の声だ。間違いない。
しかし、いったい誰と話しているのだろう。
「はぁ……それであな……解……て……たんですねぇ」
あの男女二人組だろうか。いや、そんな感じではない。
誰かいるのだ。この向こうに。郁子以外の誰かが。
「あかず……が……人間をころ……めに」
けれども、声は郁子の分しか聞こえてこない。
「ははぁ……それ……っと……の
鳥肌が立った。足が勝手に後ろにさがる。
しかし、逃げ出すわけにはいかない。郁子を連れて帰らなければ。
奈緒子は、襖を開けた。
のっぺりとした闇がそこにあった。
懐中電灯で照らすと――そこはやはり、大広間のようだ。
その真ん中に、正座する郁子の背中があった。
周りには誰もいない。奈緒子は「お母さん」と叫ぶと、その背中に駆け寄った。
「悲しいお話ですねぇ。悲しくて、
そう言いながら、うんうんと頷いている。まるで、まだ誰かと話している最中かのように。
「お母さん!」
肩を揺すると、郁子は振り返った。不穏の後のような、
「何してるの? か、帰るよ!」
「う、ううう」
抱えるようにして連れて行く。入ってきた襖を懐中電灯で照らすと――そこに、鶴がいた。襖絵だ。
懐中電灯を振ると、襖絵は一枚だけではなく、床の間がある壁以外の襖十六面がそうであると気づいた。松が枝を広げる海辺に集まった丹頂が八羽、それぞれ飛んだり、松をつついたり、魚を捕ったりする様が描かれている。
はっと我に返った。
大広間から出ようとすると、襖の近くで郁子が抵抗した。
「ああ、帰るんやったら、あの子らも……」
そう言って、郁子は暗闇の一角を指さした。
「何? 誰もいないから! しっかりして!」
「いますよぉ……泣き疲れて寝てるんよ、かわいそうに……」
何を言ってるんだ。奈緒子はしかたなく、郁子の指さした方を照らした。何もいない。そう確認して、説得するために。
しかし、大広間の隅には――黒い何かが倒れていた。
まさか。これ以上何かあるのか。奈緒子は逃げ出そうとするが、郁子が言うことを聞かない。
仕方がないのでこわごわと、倒れている何かに近づいていく。
そこにいたのは、あの白い車の男だった。
大きく見開かれた目は、まともに射し込んでいるはずの懐中電灯の光に何の反応も示さなかった。暗い青紫色に変色した顔は、昼間に見たときよりもずっと老けて見える。わずかに開いた口の中に見える赤い舌は、上下の黄色い歯の隙間をこじ開けて出ようとして力尽きたようにも映った。
彼の隣には、茶髪の若い女性もいた。彼女は足を崩してへたり込んでいた。にやにやと
奈緒子の悲鳴が、静寂を切り裂いた。
試し読み
紹介した書籍
関連書籍

書籍週間ランキング
2025年10月27日 - 2025年11月2日 紀伊國屋書店調べ
アクセスランキング
新着コンテンツ
-
レビュー
-
文庫解説
-
レビュー
-
連載
-
特集
-
文庫解説
-
試し読み
-
文庫解説
-
試し読み
-
特集