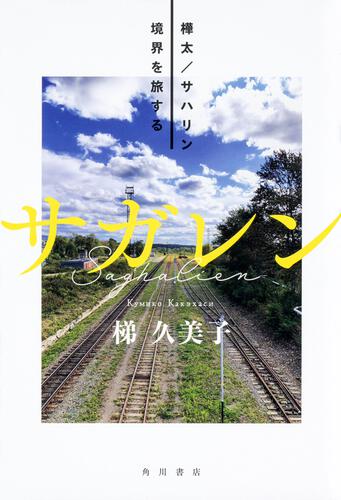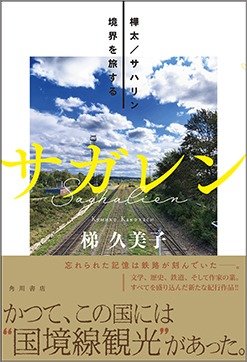サガレン 樺太/サハリン 境界を旅する
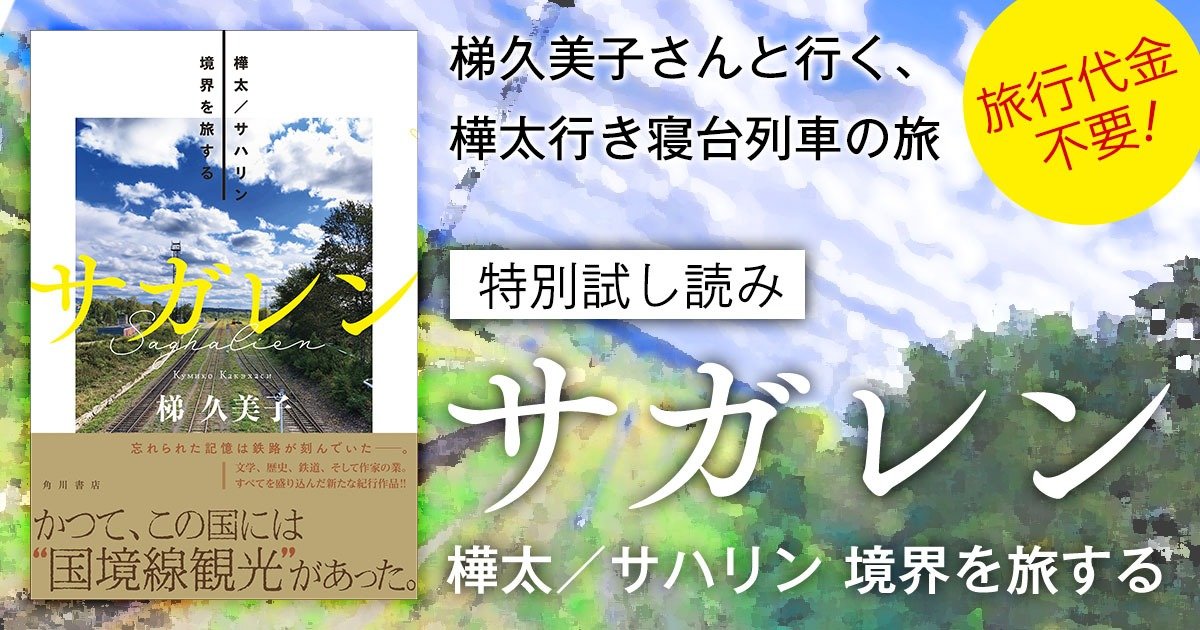
旅行代金不要! 梯久美子さんと行く、樺太行き寝台列車の旅 『サガレン 樺太/サハリン 境界を旅する』特別試し読み#3
かつて、この国には“国境線観光”があった。
樺太/サハリン、旧名サガレン。何度も国境線が引き直された境界の島をゆく。
『狂うひと「死の棘」の妻・島尾ミホ』、『原民喜 死と愛と孤独の肖像』、『廃線紀行』、『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道』など、常に話題作を送り出し続けてきたノンフィクション作家・梯久美子さんが待望の新作を4月24日(金)に刊行しました。
文学、歴史、鉄道、そして作家の業。今回は、梯作品に通底するものが一挙に盛り込まれた、新たな紀行作品になっています。
今回、梯さんが旅した土地は、サガレン。いまの樺太/サハリンです。
かつては、南半分が日本の領土だった島ですが、いまはロシア領となっており、多くの日本人には忘れられた島になっています。ところが、大日本帝国時代には陸の〝国境線“を観ようと、北原白秋や林芙美子ら、名だたる文士をはじめ、多くの人が観光に訪れていました。また、宮沢賢治は妹トシが死んだ翌年、その魂を求めてサガレンを訪れ、『春と修羅』に収録されることになる名詩を残しているのです。ロシア文学ではチェーホフもこの地を訪ねています。
いったい何が彼らを惹きつけたのでしょうか?
その記憶は、鉄路が刻んでいました。賢治の行程をたどりつつ、近現代史の縮図、歴史の地層の上を梯さんが訪ねます!
>>第2回はこちら
◆ ◆ ◆
サハリンの寝台車事情
われらが寝台急行は快調に進んだ。ユジノサハリンスク―ノグリキには中間駅が三十二あるが、この列車が停まるのはそのうち六駅のみである。
サハリンの東岸、つまりオホーツク海に面している側を南北につらぬいているのが、寝台急行の走るサハリン鉄道東部本線である。ユジノサハリンスク―ノグリキ間が六一三キロと最初のほうで書いたが、東部本線の起点はユジノサハリンスクより南にある港町コルサコフで、そこからノグリキまでの全長は六五四キロになる。
窓の外の景色は、北海道と同じエゾマツやトドマツの林から、タイガ(亜寒帯針葉樹林)に変わり、終点のノグリキに近づくにつれて、樹木は減り、ツンドラ(凍原)になっていく――はずなのだが、夜なので何も見えない。周囲が見えるようになるのは、終点のひとつ前の停車駅、ティモフスク(午前八時一分着)あたりだろうか。
この日の昼間は、ユジノサハリンスクと西海岸の町ホルムスクを車で往復したのでいささか疲れていた。ホルムスクは樺太時代の真岡である。一九四五年八月二〇日にソ連軍が上陸、港を見下ろす熊笹峠で日本軍と烈しい戦闘があったほか、民間人も巻き込まれて多くの悲劇があった。土地に刻まれた歴史の重さと、海から吹きつける風にさらされた段丘の町の寒さのせいで、私も柘植青年もぐったりしていた。時刻も十一時近いので、寝床の準備をすることにした。
コンパートメントは四人部屋で、二段ベッドが向きあう形になっている。この日はすいていて、ほかの乗客は乗ってこなかったので二人部屋として使うことができた。チケットの座席指定を見ると、二人とも下段のベッドになっていたが、私が最初にチェックしたのは上段の構造である。もし上段のベッドで寝ることになったときのために、私はあるものを用意していたのだ。
出発前に熟読した宮脇俊三氏の「樺太鉄道紀行」に気になる記述があった。寝台急行の上段のベッドには転落防止の柵もベルトもなく、寝ている間にころげ落ちそうで非常に危険だったというのである。ソ連の寝台車事情を知っていた宮脇氏および同行した編集者は、稚内でロープを買って車内に持ち込んでおり、編集者が壁のでっぱりなどを利用して器用にそれを張りめぐらせ、柵の代わりにしたという。
まさか現在の寝台急行がソ連時代と同じはずがないとは思ったが、出発前に念のため、旅行代理店のA氏にきいてみた。すると彼はあっさりと「あ、たしかにそうですね。ロープ、持って行った方がいいですよ」と言ったのだ。そこで私は、東京でしっかりしたナイロンロープを一巻き買い、着替えや洗面道具を入れたダッフルバッグに忍ばせてきていた。
心配なのは宮脇氏の担当編集者のようにうまくロープを張れるかどうかである。わが柘植青年はとても器用には見えず、ここは自分でやるしかない。出発前の心配のひとつがそれだった。
だが実際には、上段のベッドにはちゃんと転落防止用の柵があった。病院のベッドなどに、蒲団がずり落ちないよう幅一メートルくらいの柵がついているが、あんな感じである。
さすがにソ連時代からは進歩していることがわかったが、ではA氏の発言は何だったのか。もしかしたら氏もソ連時代にこの寝台急行に乗っていて、その記憶が根強く残っていたのだろうか。
A氏は謎の多い人物である。年齢はたぶん五〇歳前後、風貌はオタク風で、もちろんロシア語ができるのだが、どこで習ったのかときいたら、ほぼ錦糸町のロシアンパブのお姉さんからだという。まさかと思っていろいろ突っ込んで質問してみたが、インタビュアー歴三十年の私の経験からして、あながち冗談とも思えなかった(ユジノサハリンスクでおいしいレストランはありませんかときいたら、ユジノでは基本的にキャバクラしか行かないのでレストランのことはわかりませんと真面目な顔で言っていた)。
だがサハリンに関してはマニアックに詳しく、資料もたくさん持っている。打ち合わせに行ったとき、本棚に歴史の資料やロシア語の本と並んで、児童文学作家の神沢利子さんの『流れのほとり』があるのを見つけたときはちょっと感動した。『くまの子ウーフ』や『いたずらラッコのロッコ』などで知られる神沢さんは樺太で幼少時代を送っており、『流れのほとり』は当時のことを書いた美しい物語である。私がサハリンに行きたいと思ったきっかけのひとつがこの本だった。ああ見えてロシアンパブとキャバクラだけの人ではないのだと、ひそかに安心した瞬間だった。
私が地図マニアだというと、昭和十三年発行の豊原市(現在のユジノサハリンスク)の大型地図を出してきてくれたのもありがたかった。「大日本職業別明細圖」と書かれていて、企業や銀行、商店、料理屋、ホテルなどがびっしりと描き込まれている。幅が一メートル近くある大きな地図だが、わざわざA3サイズ八枚に分割してコピーしてくれた。出発前夜にそれを貼り合わせ、一枚にして持っていったのだが、これがあったおかげで、樺太時代の様子をイメージしながら街歩きができて実に助かった。かつての神社や学校、刑務所、墓地などの場所がわかるのも貴重である。
歴史のかけらを探す旅
この地図には、ユジノサハリンスク駅の西側にSLの転車台とおぼしきものが描き込まれている。転車台とは、機関車が方向を変えるための円形の装置である。
宮脇氏の紀行文には、この転車台がまだあったという記述があった。果たしていまはどうなっているのか。撤去するのに費用がかかるためか、転車台は日本国内でも撤去されずに残っていることがある。ユジノサハリンスクの繁華街は駅の東側で、西側はガランとしているので、もしかすると残っている可能性もある。この原稿のために地図を取り出して眺めていたら、確認してこなかったことが残念に思えてきた。もしもまだあるとすれば、それは日本の近現代史の貴重な遺構だ。
すでにおわかりかと思うが、私は鉄道ファンである。列車に乗って旅することをこよなく愛しているが、一方で、・歩く鉄道旅・も趣味としている。ほかならぬ宮脇氏によって広まった廃線探索である。
廃止になった鉄道路線をたどり、遺構を探す。レールは撤去されても枕木やバラストが残っていることがあるし、舗装道路に姿を変えていても、その道路が築堤や切通しを通っていれば、線路があったことが類推できたりする。橋やトンネルは高い確率で残っているし、半ば土に埋もれたホームを発見することもある。
廃線跡を訪ねるときは、なるべく地元の図書館に行くことにしている。郷土史関係の資料に必ず鉄道のことが出てくるからだ。そうやって、さまざまな土地で鉄道と歴史の関係を調べるうちに、台湾やサハリンに、かつて日本が敷設した鉄道が残っていることを知った。
現在も引き継がれて使われている路線もあれば、廃線となった路線もある。国内で六十数か所の廃線を巡ったあと、今度はそうした・外地・の鉄道を訪ねる旅をしたいと思うようになった。現存している路線があれば乗り、廃線となった路線はその跡を歩いて、それぞれの土地がたどった運命の、目に見えるかけらを探す旅をしてみたいと考えたのだ。
そんなときに、柘植青年から電話がかかってきた。当時の柘植青年は私の担当編集者というわけではなく、彼が担当した作品の書評を一度書いたことがあるという縁しかなかった。電話の用件は、『小説 野性時代』でノンフィクションの特集をするので、若手のいいライターがいたら紹介してほしい、というものだった。期待している二〇代の女性の書き手を推薦し、そのあと少し雑談をした。
「梯さんは最近、取材したいテーマはないんですか?」と柘植青年。私はダメもとで、台湾かサハリンで鉄道旅をしてみたいという話をした。
「おっ、台湾! いいですねー」と柘植青年。少し前に初めて台湾に行き、すっかり好きになったのだという。
電話の最後に「その企画、出してみます」と言っていたが、期待はしていなかった。それが数日後、「あの話、通りました! 『本の旅人』で連載しませんか」と連絡があったのだ。
数日後、柘植青年とその上司、それに『本の旅人』の編集長とで打ち合わせをした。柘植青年と会ったのはそのときが初めてである。
「台湾とサハリン、どちらにしますか」と編集長に訊かれた私は、サハリンと答えた。台湾に行きたくて、がんばって企画を通してくれたのかもしれない柘植青年には申し訳なかったが、北海道で育ち、樺太からの引き揚げの話を聞く機会があった私としては、まずはサハリンに行ってみたかった。九〇年代初めまで立ち入ることができなかったため情報が少なく、どんなところなのか行ってみないとわからない点にもひかれていた。
そのとき決まった計画はこうだ。取材は冬と夏の二回。初回は寝台急行に乗って島を縦断し、北部のノグリキまで行く。二回目は、一九二三(大正十二)年に樺太を旅した宮沢賢治の行程をたどる。賢治が鉄道ファンだったことはよく知られていて、樺太での鉄道旅は、『銀河鉄道の夜』のモチーフになったと言われているのだが、その話は本書の第二部ですることになる。
樺太時代に日本が敷設した鉄道は約七六〇キロ。これは一般鉄道のみの数字で、ほかに軽便鉄道(線路の幅が狭い小規模な鉄道)もあった。その中にはいまも使われている路線と、廃線になった路線がある。
寝台急行が走る東部本線のうち、北緯五〇度線以南の鉄道を敷いたのは日本で、樺太庁が敷設した部分もあれば、製紙会社が敷いた私鉄だった部分もある。五〇度線をはさんだ両側は、第二次大戦の末期に日本とソ連がそれぞれ突貫工事で建設した軍用線、それより北は戦後にソ連が敷設した部分である。まさに歴史の地層の上を走る路線なのだ。それにうまくいけば、ノグリキからさらに北に延びていたオハ鉄道の廃線跡にも行けるかもしれない。
はやる心を抑えて、二〇一七年一一月、私はサハリンで車上の人となった。鉄道にも廃線にもほぼ興味のない柘植青年を従えて。
(#4へつづく)※GW後半に公開予定です
▼梯久美子『サガレン 樺太/サハリン 境界を旅する』詳細はこちら
https://www.kadokawa.co.jp/product/321808000037/