この世の外ならどこへでも――杉江松恋の新鋭作家ハンティング『ペーパー・リリイ』
杉江松恋の新鋭作家ハンティング
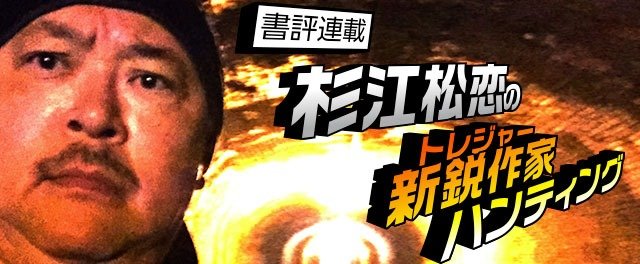
『ペーパー・リリイ』書評
書評家・杉江松恋が新鋭作家の注目作をピックアップ。
今回は、爽快なロード・ノヴェル。
人の心は孤立していて、決して誰とも交わらない。
佐原ひかり『ペーパー・リリイ』(河出書房新社)はそういうことを書いた小説だと思う。
誰かの気持ちがわかったと思うことはある。それは思い込みかもしれない。心の中を開けて覗くことはできないから、周囲の人々を理解しているつもりが、実は自分だけの虚像を見ているのかもしれない。
でも。
その虚像に囲まれている時間は不幸せなものだろうか。
誰かと一緒にいるというだけで幸せということもあるのではないだろうか。
物語は、十七歳の野中杏が三十八歳のキヨエと二人で自動車旅行をしている場面から始まる。杏とキヨエの関係は序盤にはわからず、少しずつ明らかにされていく。杏の保護者である野中京介は結婚詐欺師だ。キヨエはその京介に騙されたことに気づき、杏たちが暮らすアパートまでやってきたのである。だまし取られた金が三百万円だと聞いた杏は、咄嗟に部屋にあった五百万円の金を掴んで二人で飛び出した。目指す場所は、京介が昔住んでいたことがあるN郡T町だ。そこには夜になると発光する百合の群生があるという。その幻の百合をいつか一緒に見に行こうと、京介はキヨエと約束していたのである。果たせなかった、というか果たす気が初めからなかった約束を杏は代わりに遂行しようとする。
杏は身長百六十七センチで手足ももてあますほど長く、「今の日本の美的基準で考えるなら」「おそらく美人という生き物」だ。一方のキヨエは「あんたと違って、出せる体じゃない」と野暮ったい服装で身を覆っている。杏が口にする「エモい」などの若者言葉に怖気を振るうような態度を取る。杏から見るとキヨエの「年若の女に対するババアムーブ」は煩い一方だし、「自分でつくった殻を殻と認めてそれを破るなんてことはできない」「うじうじと理想の自分を夢想するだけ」の、自由に生きたい自分とは相容れない存在だ。卑屈さをなじられたキヨエはつぶやく。「怒ったってどうにもならないじゃない。それならきれいにしたほうがいいじゃない。いやな思い出にするんじゃなくて、よかったふうに捉えたほうが楽になるじゃない」と。京介に騙されたという事実も、美しいものに装えば消えると言いたげなキヨエの態度が杏には理解できない。いや、理解したくない。
要するにまったく気が合わない二人が旅をするという小説だ。これはロード・ノヴェル(ムービー)の基本形である。旅の途上でぶつかり合っていく中で、小さな化学反応が起きる。お互いの関係性が変わることもあるし、変わらないこともある。だが、同じ時間を共有したという事実は動かず、そのことによって心の中に何が芽生えたか、ということが話の核になっていくのだ。結婚詐欺師に騙された中年女と、詐欺師の娘の場合はどうなるか。
帯にも書かれているので、杏がなぜキヨエと旅をするのか、ということを作者は明らかにしてもいいと考えているのだろう。書かなくてもよかったのではないかな、と私は思う。杏という少女に寄り添い、彼女が今何を考えているのだろうか、と推し量りながら読むことが楽しい小説だからだ。杏の一人称〈あたし〉で書かれているのだが、物語の表面に出てくるのは条件反射的な感情の動きなので、内奥にある気持ちにまでいちいち分け入っていくわけではない。杏の心の動きがどうなのかを注視したくなる箇所がいくつかあり、それが物語としての重要な分岐点になっている。
たとえば前半における最大の山場は、杏が意外な相手に裏切られて傷つき、そのことに対して無神経な対応をキヨエがとった後に訪れる。そのあとで杏が文字通り暴走するのだが、ここの疾走感が素晴らしいのだ。「この世の外ならどこへでも」と言わんばかりに駆ける、跳ねる、飛ぶ。このとき杏の意識は嫌な現実を超越し、浮遊の感覚を味わう。少し長くなるが、引用したい。
――数日前まであたしは家で夏を怠惰に過ごしていた。狭苦しいアパートの一室で、架空の世界に生きる架空の人たちの人生ばかり観ていた。
あそことここは、すごく遠い。遠くて近い。あたしは何度も、あそこでこんなシーンを観てきた。よく知っている、なじみの光景。スクリーンの向こうの、近くて遠い光景。今、あたしたちはきっと、観られる側だ。誰かが、今、夜空の向こうから、あたしたちの人生を、象徴的なこの一瞬を、切り取って観ている。あたしがほんものだと思って生きている世界がうそものではない保証なんてどこにもない。
この場面を称してキヨエは後で「いつも綺麗だけど、きのうはとくに。ちょっと人間離れしてた。あんた、羽化したて、って感じだった」と言う。凄絶に美しかったのだ。
杏の述懐に、ほんもの/うそものという対比がさりげなく出てきていることに注目されたい。この後に、田舎の本物の星空を見た杏が、それをうそくさいと称する場面がある。杏にとっては京介と一緒に観たプラネタリウムに映し出されたうそものの星空のほうが心安らげるものだったのだ。真であること、あるいは偽であることと、それが心にしっくりと嵌まるものであるかという尺度とは必ずしも一致しない。うそものだから排除するわけではないのだ。こういった呟きにもつながっていく。
――なんか、いやだな、故郷って響き。ひとりにひとつ、大切にせよ、とねっとり迫ってくる感じ。しめった手で無理やり抱き寄せられたみたいで、思わず腕をゴシゴシする。
杏がキヨエと旅する目的は前述したように作中でも明言されるが、自分にとって真に必要なものは何なのかを探るということが深層にあるようにも見える。杏自身にも最初は意識されない目的だ。そのために、キヨエという見ず知らずの相手と旅をする。
キヨエが徹頭徹尾気の合わない赤の他人であるということが、融通の利かない反射板のような働きをして、杏の気持ちの中に少しずつ堆積するものを作っていく。ロード・ノヴェルの常道としてさまざまな出会いがある。出会いと別れによって、他人はしょせん他人にすぎないのだ、ということを思い知らされるのが旅の小説というものなのだ。他人だからいつかは別れがやってくる。この小説でもっとも印象的な別れの場面はやはり末尾に描かれるのだが、その小気味よさといったらない。爽快な印象を残して物語は幕を閉じるのである。
本作は佐原にとっては二番目の著書である。第一作は、父の再婚によってできた義弟がブラジャーをつけていることを主人公が発見することから始まる青春小説、第二回氷室冴子青春文学賞大賞を受賞した『ブラザーズ・ブラジャー』であった。本作もそうだが、佐原作品の主人公は、社会が押しつけてくる観念にとらわれず、自分の頭で物事を考えようとする。その姿勢が好ましいのである。これからどんどん書いていくであろうし、読みたい作者だ。
最後に一つだけ、間違ったらごめんなさい。本作の題名は直訳すれば「紙の百合」だが、これは映画「ペーパー・ムーン」とその主題歌It’s Only A Paper Moonに着想を得たものではないか。紙の月は偽物だがそれでも見る者にとって月は月。そのことが映画の詐欺師と彼を父親ではないかと疑う娘の関係性にも反映されている。偽物だけども、という一語を添木のように使うと、この小説はとても深い読み心地のものになると思うのだ。























