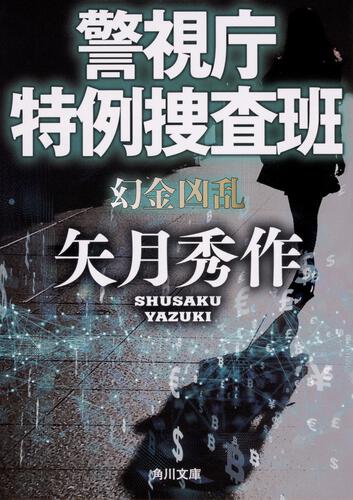【連載小説】新米刑事の意外な才能──。女性刑事二人が特殊犯罪に挑む! 矢月秀作「プラチナゴールド」#6-2
矢月秀作「プラチナゴールド」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
「わかった。わかったから」
小此木は両手のひらを前に押し出した。
座り直して一息つき、つばきを見やる。つばきは横を向いたままだった。
小此木はりおに向き直る。りおは椅子に浅く腰かけ、小此木の話を待っていた。
大きく息をついて、口を開く。
「近頃の大きな仕事は、必ず分業になってんだ。足がつかねえようにな。SNSなんて便利なもんもできちまったし。基地局なんてでけえもんを盗んで
「すごーい。勉強になります」
りおは目を見て
「どんな組織なのか、知りませんか、おじさま?」
「すまんな、お嬢ちゃん。聞いたことねえ」
小此木は優しい口調で返した。
「おじさまのような大物さんが知らないなんて。新しい組織ですかね?」
さらりと〝大物〟という言葉を入れる。小此木の表情がほころぶ。
「それはわかんねえなあ」
「そもそも、携帯基地局なんて盗んで、どうするつもりなんですかねー。自分ちにアンテナ立てようとしてるのかなあ」
りおがとぼけた意見を口にする。
はたで聞いていると、あまりにふざけた意見に思えるが、横目で小此木を見ると、いとおしそうに目を細めていた。
「そりゃねえよ、お嬢ちゃん」
小此木は笑顔を隠さない。
「鉄骨や配線は金属を売るんだろうな。基地局丸ごとってんなら、CPUなんかも売れるだろうなあ」
「部品も売れるんですか?」
「ああ。でも、基地局のCPUやメモリー、基板は、ただの部品でもねえ。その中には企業の秘密がいっぱい詰まってるから、解析すりゃあ、欲しい連中にはおもしれえデータも出てくる」
「なるほどー、そこは気づきませんでした。さすがです、おじさま!」
調子よく合わせて、小此木の気分を高揚させていく。
「そういうの欲しがってる人って、どんな人なんですかねー?」
「そうだなあ。外国の産業スパイなんかは欲しがるだろうな。日本は遅れてるなんて叫んで得意になってるヤツもいるけど、基幹技術の水準はまだまだ世界最高峰に位置していることに変わりはない。その技術は盗みたいだろうよ」
「産業スパイですか! 怖いなあ……」
「そうでもねえよ。昔は無茶苦茶な連中もいたけど、今はスパイったって、見た目も行動も普通のサラリーマンと変わらねえ。普通に入社して転職するふりをして、情報を持って行っちまう」
「そんなにすごいんですか! でも、そこまで優秀な人たちなら、日中堂々と窃盗事件なんか起こすわけないですよねー」
「そうとも限らねえ。基幹技術の情報を盗もうと潜り込んでも、設計図や概要などの資料が取れない場合、現物を盗んで解析しようと考える連中もいるだろう」
「そうですね。うんうん、わかります。おじさまの知り合いに、産業スパイの人、いませんか?」
「いねえよ」
小此木は苦笑した。
「俺たちとは毛色が違う。盗んでパッと捌くってのとはわけが違うんでな」
得意げに話しているうちに、自分が盗みに関係していることまでさらりと語っていた。
「あいつらは何重にも保険をかけてる。万が一の時は、足がつかねえよう、うまいこと立ち回ってる。バイヤーを
「わかりました。やってみます!」
「無理すんじゃねえぞ、お嬢ちゃん。あいつらは、国や企業が絡んでるから、潰しにかかってきたらえげつない」
「心配してくれるんですか?」
目を潤ませ、キラキラさせる。
「まあ……そりゃ、心配にはなるわな」
小此木は少し照れた。
「他に、どんな組織が考えられます?」
「そうだな。外国人と手を組んだ若いチンピラの疑いも拭えねえか。その手の連中は、少しでも金になりゃいいから、あまり後先考えずに行動する。計画も何もありゃしねえ。ただ、やっぱり、そういう連中じゃねえ気はするな。俺の勘だけどよ」
「大物さんの勘! きました!」
りおが興味津々の
「何も出ねえぞ。ほんとに勘なんだから」
小此木はりおの期待に
「勘、聞かせてください!」
「勘を聞かせろって……」
小此木は困惑した笑みを漏らす。
下を向いて大きく息をつき、ゆっくりと顔を上げ、おもむろに口を開いた。
「携帯基地局を丸ごととなれば、解体から部品選別まで、細かい作業が必要となる。捕まった若造、車ごと渡す契約をしていたと言ってたな? たぶん、その車ごと荷物をどっかに運んで解体しようとしていたんだろう。そうするには、ある程度広い場所がいる。また、きっちり解体できる技術者も雇わなきゃならねえ。チンピラはそんな細けえことしねえし、捌くルートを持ってなければ、足が出ちまう。そんな面倒で損をするかもしれねえような仕事、プロは受けねえ。だから、SNSでチンピラを雇ったんだろう。しかし、そこから先の捌きはプロでねえとできねえ。組織を束ねるには、全体をきっちり仕切るヤツが必要だからな。チンピラにそれはできねえ」
「Art3も、そうやって組織立てたのか?」
つばきがいきなり、横から訊いた。
「そりゃ、おまえ。俺はプロ中のプロ──」
口を開きかけて、あわてて閉じた。
「油断も隙もありゃしねえな」
つばきを睨む。つばきは横を向いたままだった。
「まあ、とにかくだ。産業スパイとはいかないまでも、それに近い連中が動いてると、俺は思う」
りおに向き直った。
「どこから手を付ければいいですか? それだけでも教えてください。お願いします、おじさま!」
りおはいきなり、小此木の右手を両手でつかんだ。
小此木はびっくりして手を引っ込めようとするが、りおが離さない。
「株価をあさってみろ」
「株価ですか?」
「ああ。ちょっと離してくれ」
小此木が右手を見やる。
「あ、ごめんなさい! つい」
「いいけどよ……。携帯や基地局に関連した株で急騰してるやつか暴落してるやつ。それも理由がよくわからねえ株がありゃあ、仕手が入ってることになる。仕手は勝手に情報つかんで入ってくることもあるが、会社とグルになって荒稼ぎしている時もある。企業が絡んでりゃ、間違いなく株は動くからな。手掛かりにしてみるといい」
「ありがとう、おじさま!」
もう一度、手を握ろうとする。
小此木は大げさに仰け反って、手を引いた。
「もういいか?」
つばきを見やる。
「いいぞ」
そっけなく言う。
小此木はつばきを睨んで立ち上がった。りおが立ち上がる。制服警官が歩み寄ってきた。手錠をかけられ、ドア口に向かう。
「あー、小此木」
「なんだよ」
つばきを見据える。
「助かった」
右手のひらを上げてみせる。
「おまえを助けたつもりはねえよ」
小此木はにやりとし、部屋から出て行った。
二人になる。とたん、りおはバッグからハンカチを取り出し、手を拭き始めた。
「あからさまだな……」
つばきが苦笑する。
「勢いでつい握っちゃったんですけど、なんだか脂っぽくて」
「そりゃそうだろ」
つばきが笑う。
「なんか、いろいろ訊いてみた感じでしたけど、役に立ちそうですか?」
「ばっちりだよ。小此木があれだけしゃべるということは、なんか心当たりがあるってことだ。よくやった」
つばきは立ち上がった。
「行くよ」
「どこへ行くんですか?」
「小此木の関係者で仕手をやってるヤツを知ってる」
「ひょっとして──」
りおは目を丸くした。
「
つばきはりおの二の腕を叩き、先に部屋を出た。
りおも急いで、つばきを追いかけた。
▶#6-3へつづく
◎第 6 回の全文は「カドブンノベル」2020年12月号でお楽しみいただけます!