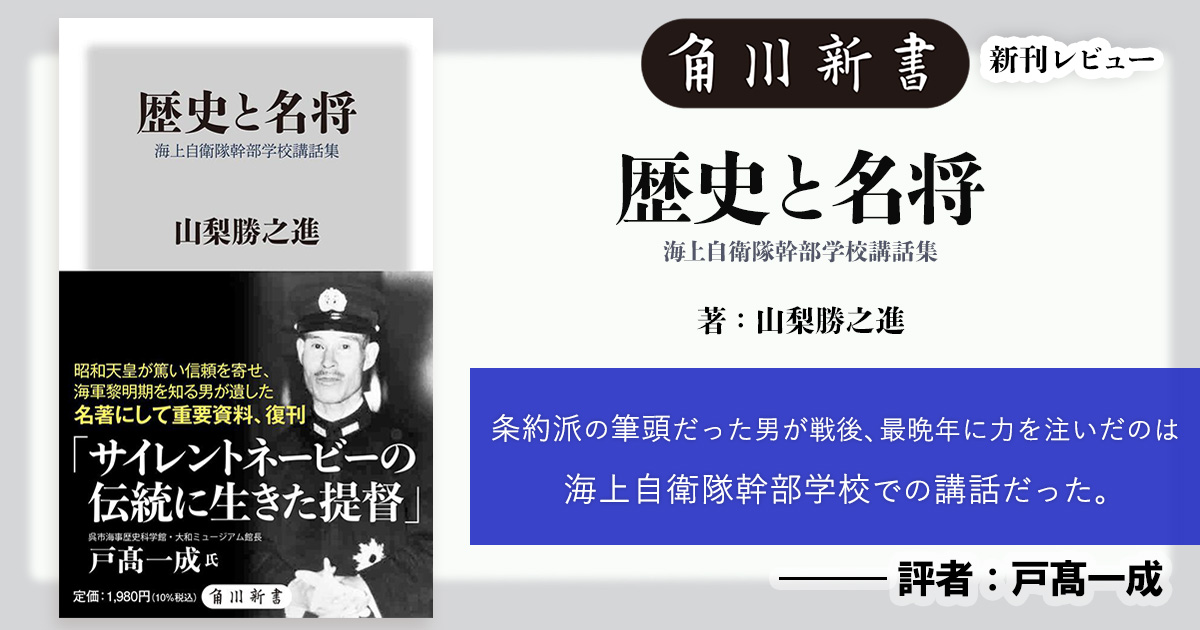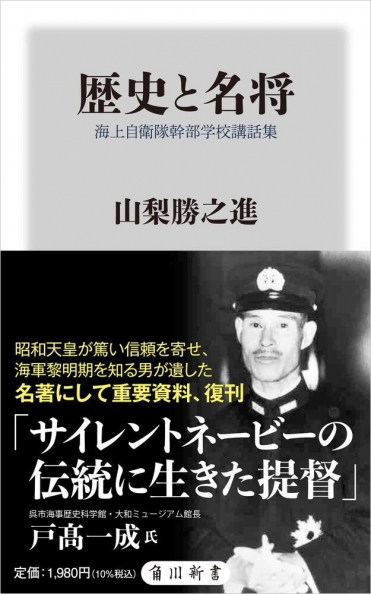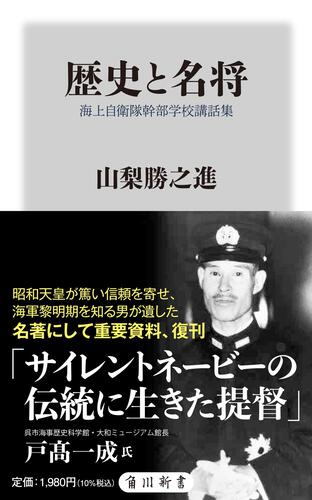条約派の筆頭として知られ、昭和天皇の「人間宣言」にも関与した元海軍大将の講話集!
巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
山梨勝之進『歴史と名将 海上自衛隊幹部学校講話集』角川新書巻末解説
【解説:戸髙一成(呉市海事歴史科学館・大和ミュージアム館長)】
「山梨大将講話集」と『歴史と名将』
山梨勝之進の名を想う時、まず浮かぶのは、サイレント ネービーという言葉である。山梨は、語るべきは大いに語ったが、秘すべきことを弁えていた、と私は考えている。
「まえがき」にもあるように、本書は山梨が海上自衛隊幹部学校で行った講話記録を纏めたものである。その講話は昭和三四(一九五九)年から四一年まで、八年間で一二回にわたって行われた。今回の底本となったのは、この『山梨大将講話集』(昭和四三年、海上自衛隊幹部学校)を更に整理編纂した『歴史と名将』(昭和五六年、毎日新聞社)に依っている。
この毎日新聞社版は、編集委員の判断で、本来の第一〇回昭和四〇(一九六五)年一二月六日の講話「ネルソンとナイルの海戦について」が削除されている。歴戦の優秀な海軍士官であった編集委員たちにとって、ネルソンはさほど名将ではなかったのかもしれない。もっとも、ネルソンに関しては、多数の文献が公刊されているので、改めて屋上屋を架する必要を感じなかったのかもしれない。
特異な経歴
さて、山梨勝之進はどのような人物であったのか。山梨の経歴を概観することにより、本書成立の背景を知ることは、本書の理解の上からも有用なことと思われる。
山梨勝之進は、明治一〇(一八七七)年七月二六日、仙台で生まれた。山梨の少年時代、海軍はあまり人気のある進路とは思われていなかったが、対清国海軍軍備を強化させるために急速に拡張して行く海軍の姿は、国民の注目を集めつつあった。このような中、同郷の斎藤七五郎が海軍兵学校に進んだことなどが切っ掛けで、明治二八年、山梨も海軍兵学校に進み、明治三〇年に卒業した。卒業成績は二番で、トップの松岡静雄は、民俗学者柳田國男の実弟である。当時の兵学校は、日本始まって以来の対外戦争とも言える日清戦争のさなかであり、兵学校教育も試行錯誤の途上だったと言える。
当時は、海軍士官としての教育は第一にマスト、ヤードの昇り降りで、軍人であるより先に船乗りであることを要求される時代であった。しかし、山梨が海軍兵学校を卒業して勤務を始めた日本海軍は、対露戦備の六六艦隊整備中であり、まさに帆走海軍から蒸気海軍に発展しつつある時期だったのである。
明治三三(一九〇〇)年、山梨は英国で建造中の新鋭戦艦「三笠」の回航員として渡英した。完成した「三笠」で回航の途中、ジブラルタルで英国の地中海艦隊と行き合った。英国の主力艦に引けを取らない戦艦である「三笠」艦上の山梨は、発展しつつある日本海軍を想い、感激をもって日英の軍艦を注目していた。
日露戦争中の山梨は「済遠」分隊長として参戦、戦後は海軍大学校に進み、戦略、戦術の研究に打ち込んだ。
当時の海軍大学校戦術教官は、秋山真之、佐藤鉄太郎など、日本海軍を代表する戦術家が揃っていた。ここでの研究は、山梨に大きな成果を齎したと言える。
山梨は「私は、戦略、戦術の研究は、やはり戦史が元だと思っている。過去の戦例を統計的に検討して、成敗因果の関係を明らかにすることである。しかし、統計だけでは駄目だ。当時の状況に自らを置き、事態に溶け込んで、決断、進退、処置等に指揮官の着眼を練り、歴史的課題、戦略、戦術を研究して、初めて価値があるのだと思う」と述べている。
これは、山梨が戦術上の進退について述べたものだが、この考えは、自身の生き方を表していたのである。
海軍大学校で数理的戦略観を身に着けた山梨は、以後、常に冷静な判断力の持ち主として部内で評価されるようになっていった。
大正三(一九一四)年、未曽有の海軍汚職事件となったシーメンス事件が起こった。海軍は、その健軍の功労者ともいえる山本権兵衛大将と、齋藤實大将を予備役にした。これら当事者たちは、当然ながら汚職に関わっていたわけではなく、責任者という立場での処分であったが、一言の弁明もせずに責任を負ったのである。山梨は、これを海軍の美風であると評価した。これこそ、山梨が海軍大学校で研究の結論とした、軍人の出処進退の姿であったからである。
第一次世界大戦開戦当時は海軍軍令部参謀であったが、大正五(一九一六)年には、海軍大学校教官としてヨーロッパ戦線の視察を行った。ロシア戦線では、日露戦争を戦った者同士と巡り合った。その帰国後、間もなくロシア革命がおこり、ロシアは崩壊に向かう。ロシア滞在中には、まったくそのような気配さえなかったことを思い、山梨は「外容は厳然としている国家組織も、わけなく崩れるものだ」との感慨に沈んだ。
第一次世界大戦は、敗戦国ばかりでなく戦勝国にも深刻な経済危機を齎した。日本においても、建造中の八八艦隊計画は国家財政を破綻に導くものと憂慮されていた。このような時、突如アメリカが海軍軍縮会議を提案してきた。加藤友三郎海軍大臣は、渡りに船と、これに応じる。会議の全権は加藤友三郎大臣、主席随員は加藤寛治中将、山梨は専門委員として随行した。
会議は、開会と同時に、英米日の主力艦比率を五・五・三とするアメリカの提案で始まった。世界の大海軍国と自認する英国はアメリカと同率に不満があり、一方日本はアメリカよりも比率が低いことに不満があった。山梨はこの調整に奔走したが、結局、各国共に財政的問題からこれを受け入れて妥結した。山梨は一行よりも早く帰国し、東郷平八郎元帥に報告した。東郷は「それでよろしい」と答えている。
このころ、山梨は海軍軍人として、はなはだ不自然な経歴の持ち主となっていた。山梨クラスの経歴では艦隊勤務が目立って少なくなっていたのだ。大正六(一九一七)年から七年に「香取」の艦長をしたのみで、ほとんど艦隊勤務を経験せずに大将になるという、特異な経歴であった。これは海軍部内でもやや目立っていたようである。
条約批准派対艦隊派の果てに
昭和三(一九二八)年、山梨は海軍次官となった。そして、山梨は昭和五年に軍令部出仕という立場から、ロンドン会議を日本国内で補佐することとなる。ロンドン会議では、無謀なことに日本側は出発前に国内へ対して、会議の妥結点を対米七割の確保と公表してしまった。これは手の内を晒して交渉に臨むようなものであり、日本側の外交センスの無さを露呈していた。結局、補助艦艇の総枠で対米六割九分というまずまずの提案が出されたので、山梨はこれに対して、大義名分を立てたうえで受け入れるべきと思った。
ところが、海軍軍令部の加藤寛治大将は七割絶対死守を求め、反対を表明していた。山梨は、だいたいこの七割という数字自体は厳密な根拠が有るわけではない、としていた。だれが考えても、七割ならば安全で六割九分では危険であるというような理屈はおかしいのだが、いつの間にか国民の間にも、この七割信仰は広まっていたのである。
山梨は加藤大将に対しても直接説明を行ったが、その態度は変わらなかった。しかし、日本側の結論を出すにあたり、浜口雄幸首相には、「いよいよ総理が妥協案を吞むことに決まれば、しかたがないから兵力量の欠陥に対する繕いだけはつけてください。それだけは承知してもらわなければ、海軍は納まらないし、私の立場も無くなる」と迫り、浜口首相から一筆を取り付けた。
これは、妥結反対派を抑えるためにはぜひとも必要であったが、山梨は上手く立ち回ろうとしている、と一部からは見る向きもあったようである。
このロンドン条約批准問題に関しては、以後、加藤大将を中心とした条約反対派は東郷元帥を巻き込んで猛烈な活動を始めた。当時の海軍では、東郷元帥のご意向は絶対的な重みをもち、大きな圧力だった。これを心配した山梨は、浜口首相に「一度東郷邸に行かれて、お話ししてはいただけませんか」と相談したが、浜口は「いや、東郷さんが首相の説明を聞きたいと言っておいで下されば、喜んでご説明するが、総理から膝を曲げて出向くことは、総理の地位から見て出来かねる」として、これを断っている。
山梨にすれば、そのようなことは十分承知の上であるが、浜口は、体面を捨てても実を取ることが出来なかったのである。当時の山梨はこの問題で心痛のあまり、気の毒なほど瘦せていたという。
こうして浜口、東郷会談は幻となり、海軍省―条約批准派と海軍軍令部―艦隊派の間には、遂に互いを理解しあう機会を持たないままに、海軍を二分する事態となってしまった。山梨は、堀悌吉軍務局長とともに、「もうこうなっては覚悟を決めよう」と話しあったほどで、艦隊派支持の右翼団体などのテロが現実的な危機となっていたのである。
この問題は、海軍省が天皇の大権である統帥権を犯した、とする政治問題となった。政友会の犬養毅総裁が総理を追及する様子を見て、山梨は「憲政の神様と称せられた犬養総裁が、まるで軍閥の代弁者でもあるかのような格好であったので、私は非常に失望した」と漏らしたほどであった。
結局、海軍は山梨を佐世保鎮守府長官に転出させることで事態の沈静化を図ることとなった。山梨は、ワシントン、ロンドンの二大軍縮条約に関わったが、軍の中で軍縮推進派が主流であれるはずもない。昭和七(一九三二)年に海軍大将となったが、翌八年には予備役とされ、山梨の海軍生活は終わりを告げた。
山梨は海軍を去るにあたり、「自分一身としては、既に最高の官位に到着し、従来分不相応の要職を歴任したので、今日目出度く退職したことは、むしろ幸運の至りで、心境安穏平静明朗である」と述べたと言うが、果たして本心であったかは知る由もない。だが、心中には、かつてシーメンス事件で予備役になった山本、齋藤の両大将の姿を思い浮かべていたことは確かであろう。
後に山梨は、ロンドン条約後の海軍人事について質問された時に、このように答えている。
「海軍の人事は、海軍大臣の専行事項で、海軍大臣が一度決意してしまえば、他のものがこれを動かすことは出来ない。それに、当時海軍大臣に対し、裏面から色々な強い示唆や圧迫があって、大臣も定めし苦慮されたことと思う。その全責任は大臣にあって、その当否は君たちの判断に任せる他なく、私からこれを批判することは出来ない。今日になって、私が語れば自己弁護と受け取られるし、また、関連の多くの方々は、既に故人となられているので、私は一切語らぬことにしている」
山梨は、サイレント ネービーという海軍の伝統を守り、一切の弁解をせずに東京郊外の自宅で花を作り、静かな暮らしに入った。
引退して足かけ六年半が過ぎた昭和一四(一九三九)年一一月、山梨は学習院長に任ぜられた。当時の学習院は、翌年皇太子が入学する予定で、その準備に忙しい時期であったが、山梨はその姿を黒の学習院長服に包み、静かに勤務していた。昭和一六(一九四一)年、日米の戦争がはじまり、戦時下の学習院の教育は、皇太子の疎開問題など困難なものとなった。
昭和二〇(一九四五)年、山梨にとっての敗戦はどのようなものであったか。山梨自身は多くを語っていないが、天皇と皇室の良好な行く末を最大の願いとし、全力を尽くす決意をしたことは間違いない。
人間宣言と天皇制
終戦の年、一二月に山梨は学習院の英語教師として、戦時中、神戸で外国人収容施設に居たレジナルド・ブライス博士を雇用した。ブライスは日本文化に造詣が深く、山梨はブライスの人間性に信頼を寄せ、GHQと宮中との仲介役としての立場も期待していたのである。ブライスも山梨の人柄と深い教養に敬意を払っていた。
ブライスはGHQとのかかわりから宮中とも連絡を持っていたが、一二月初旬にGHQ民間情報教育局のハロルド・ヘンダーソンを訪れて、宮内大臣から、天皇陛下は自分の神格化を否定したい意向が有るとの話を聞いたと伝えた。相談のうえでヘンダーソンは、天皇が自ら神格を否定する文書の草案を書き、ブライスが加筆修正した。これはすぐに山梨と幣原喜重郎総理に伝えられ、幣原の手で後の人間宣言の草案が纏められた。
一二月二三日には、これらの文書が詔書案として侍従次長木下道雄から天皇に示される。さらに手が加えられて、三〇日には閣議を経、直ちにGHQの承認をえて三一日正午に報道陣に発表され、翌二一(一九四六)年一月一日の公表となったのである。
山梨勝之進の、最大の願いはこうして満足のゆく結果を迎えた。山梨は以後、一切この件には触れなかったが、雑誌『サンデー毎日』に宮内庁詰めの記者による記事が発表された際に取材を受けることになった。
山梨は、「私は、自分は無関係とは言わないけれども、このことは私の口から決して言うべきではないという原則を守り、一四年たって、これが世間にわかったものだから……」としながら、簡単に経緯を述べている。
ロンドン条約の際の海軍人事についても、陛下の人間宣言についても、自身のことは殆ど語ることは無かった。だが、山梨ともブライスとも旧知であった、終戦時の海軍軍務局長保科善四郎は、筆者に「山梨さんが苦労なされたのだ」と話された。
山梨勝之進の名は、黙って任務に全力を尽くし、進退はこれを明らかにする、という海軍のサイレント ネービーの伝統に生きた提督の名として伝えられると思っている。
【作品紹介】
『歴史と名将 海上自衛隊幹部学校講話集』
『歴史と名将 海上自衛隊幹部学校講話集』
著者:山梨勝之進
発売日:2023年07月10日
条約派を代表し、昭和天皇が篤い信任を置いていた元海軍大将による講話録!
条約派を代表する海軍大将が残した名講話にして、日本海軍創設期を知る軍人による重要資料。
昭和天皇が篤い信頼を寄せた男の、戦後に海自で行われた講話録。
堀悌吉らと共に条約派の筆頭としてロンドン海軍軍縮条約締結に力を注ぐも、強硬派の艦隊派によって予備役に追いやられた海軍大将・山梨勝之進。
昭和天皇の「人間宣言」の文案作成にもかかわる程、信頼を天皇から寄せられていた。
海軍=薩閥の統領で、日露戦争時の海軍大臣も務めた山本権兵衛に仕え、海軍創設期の記憶も引き継ぐその男が最晩年に力を注いだのは、海上自衛隊幹部学校で行った講話だった。
昭和史研究者が名著と推してきた作品、復刊。
■東郷平八郎は、日本海海戦より黄海海戦を重視したいと言っていた。
■山梨「日本の取り組んだ軍縮(ワシントン・ロンドン海軍軍縮会議)は、相手がアメリカであり、軍人にとってはこの軍縮は弾丸を打たない戦争であった」
■秋山真之は「相手が弱いときは先制の方が得だが、相手が強いときは、先制は危ない」と言った。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322206000777/
amazonページはこちら