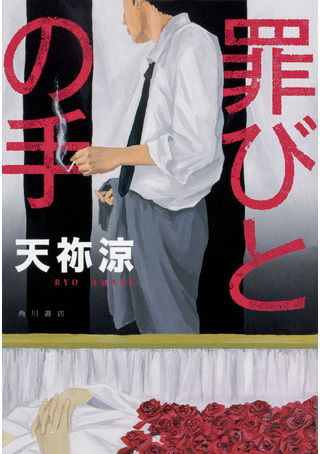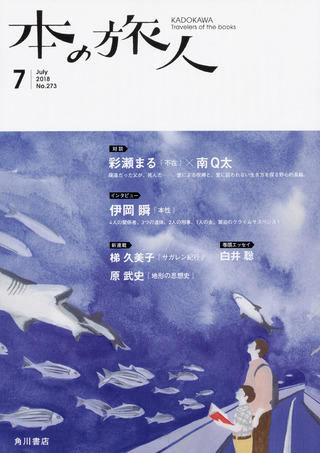印象的なタイトルである。
いや、一見しただけでは、おそらくそうは感じないだろう。けれど、物語を読み終えた後には深く胸に残る。その意味を考えずにはいられなくなる。
『罪びとの手』。こう書き記してみても、やはり秀逸なタイトルだ。
物語は、神奈川県川崎市の廃ビルで死んでいる男が発見されたことから動き出す。男は推定五十代後半から六十代前半。財布にカード類はなく、携帯電話も見つからなかった。争った形跡がなく、床にビールや酎ハイの缶が転がっていたことなどから、鑑識職員の指揮を執る検視官は早々に、酔って転んだ事故死、と判断を下した。
しかし、臨場した川崎警察署刑事一課強行犯係の滝沢圭は、その効率優先で手抜きとも思える判断に不満を抱く。自分には見えている不審な点を、検視官らは見ないふりをし、やり過ごそうとしていると憤る滝沢は、半ば強引に遺体を解剖に回すが、結果は「事件性なし」と出た。さらにほどなく、思いがけない偶然から遺体の身元も判明。
警察から引き取り手のない遺体の「お迎え」依頼を受けてかけつけた市内の葬儀屋が、「このご遺体は自分の父親だ」と申し出たのだ。
そんな偶然が起こり得るのか。すんなり受け容れられない滝沢は、いよいよ何かあるのではないかと疑念をつのらせていく。だが、葬儀屋の御木本悠司は、遺体は二ヶ月前まで自社の社長を務めていた自分の父親の幸大で間違いないと繰り返し、大々的に葬式を行う予定だと話す。積み重なっていく様々な違和感が拭いきれず納得できない滝沢は、何としてでも火葬されるまでに真相を突き止めてやる、と決意を固め、孤立無援の状態で動き出す——。
と、何やらきな臭いことこの上ないのだが、ここまでは、ほんの序章、物語の幕開けに過ぎない。
本章に入ると、仙台でウェディングプランナーをしている悠司の兄・昇一、かつて御木本葬儀社で幸大と共に働き独立した中守和哉、幸大の引退後、御木本葬儀社に転職してきた長岡姫乃らの視点から、葬儀までの出来事が語られていく。
当然、それぞれ「立場」が異なるゆえに、見えているものが違う。悠司が何かを企んでいるという気配は確かに感じるものの、それが何か一向に掴めない。滝沢は遺体発見から身元判明、悠司との面会、昇一たちへの聞き込みで抱いた疑問点をメモに整理していて、繰り返し提示されるたび、読み手もまた頭のなかで話を整理する機会を得られるにもかかわらず、真相に手が届かない。
そのミステリーとしての謎解きと、最後に明かされる真相の衝撃だけでも、読み応えは十分だが、胸を打つのはそう「せざるを得なかった」男たちが歯を食いしばってでも持ち続ける矜持だ。
検視官も法医学者も事件性はないと判断し、息子の悠司も納得している「問題はない」はずの事故死に、滝沢はなぜそうまで固執するのか。ある失敗から自分が死んでも葬儀は不要だと周囲に言っていた幸大の葬儀を、悠司はなぜ大々的に行おうとするのか。その背景にある連続少女殺人事件や「家族」と「仕事」の事情と問題を巧みに織り込み、一切のゆるみのない緊迫感に、読みながら心拍数が上昇していくのを感じた。
詰めるようにしていた息を吐く。ことの真相を予測し、謎解きに挑んでいたはずなのに、気が付けば自分がこれまで歩んできた道を振り返らずにはいられなくなった。手にしたはずのもの、こぼれ落ちたもの。今、自分の手の中にあるもの。じっと見つめたこの手は、人からどう見えているのか——。
本格ミステリ大賞候補にもなった傑作『葬式組曲』に続くこの葬儀屋ミステリーは、天祢氏の執念にも似た取材力がいかんなく発揮された、緻密なお仕事小説であり、不器用な父と息子の親子小説でもある。その関係性はちょっと羨ましくも感じるほどに。
けれど何よりも、読者の人生に寄り添う物語だ。ぜひ手に取ってじっくりと読み進めて欲しい。
紹介した書籍
関連書籍
-
特集
-
特集
-
特集
-
特集
-
特集