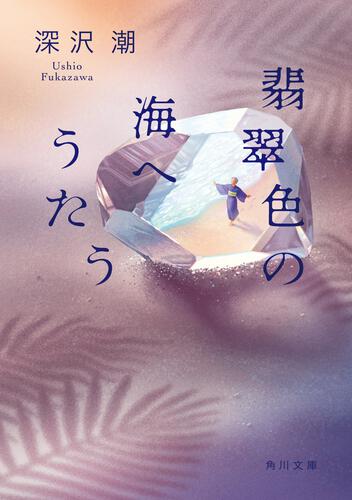深沢 潮『翡翠色の海へうたう』(角川文庫)の巻末に収録された「解説」を特別公開!
深沢 潮『翡翠色の海へうたう』文庫巻末解説
解説
痛い。
しかし、これは忘れてはいけない痛みだ。
本作は、第二次世界大戦中、日本で意に反して従軍慰安所で働かされ、国ぐるみの性暴力被害者となった女性たちの物語である。
視点人物は二人いて、現在は〈私〉、戦時中の過去は〈わたし〉が語り手を務める。
〈わたし〉が登場するのは第二章からだ。彼女は日本軍が司令部として設けた
「わたしは、ただただ、穴、に、される」という一文から始まる第二章は衝撃的だ。この小説では「穴」という言葉が複数の意味を背負って頻出する。〈わたし〉が幽閉されている壕は「穴」だし、男たちは彼女を「穴」と見なして性器で
──消毒する。
──また男が部屋に来る。切符を受け取る。脚を広げる。男はサックをつけて入れる。ことが済んで出ていく。
本書は『カドブンノベル』二〇二〇年一月号、四月号、九月~十二月号に掲載された後に単行本として刊行された。第一回にはこの第二章までが掲載されているのだが、読んだ人は心臓が
〈わたし〉が朝鮮半島の出身であることはここまで明記されていないが、移動のさなかにチマとチョゴリに関する記述が出てくるので、そうだとわかる。一行は新しい居場所の建物にたどり着き、「わたしは、ここでふたたび、穴、に、される」という一文で第二章は終わる。
慰安所で行われていたことが、健全な性産業というようなものからは程遠く、暴力を行使しての奴隷労働であったことが淡々と
人間の尊厳を傷つけられてしまった人の心情が平明な文章から
物語の中で〈わたし〉は一貫して、性に従事する女性の名乗り、いわゆる源氏名で呼ばれ続ける。本当の名前は故郷と〈わたし〉を結ぶものだから決して口にはしないのである。ある場面において親切にしてもらった下士官から本名を教えてくれと頼まれるが、応じない。「大事な本当の名前を明か」すことは「心まで差し出」すことだからだ。男たちは「すべてを搾り取」ろうというのか。男の暴力による収奪こそが本書の主題である。言語とそれにつながる思い出、自身が人間であることの証明である名前など、絶対に手放せないものまで男たちは奪おうとするということが描かれる。
〈わたし〉の痛みを描くために作者は小説構造にも仕掛けを施している。現在のパートだ。ここで視点人物となる〈私〉は「
「書こう。書くしかない。書くべき物語だ」と決断し、関連書籍を取り寄せて読むだけではなく、慰安所が設けられた沖縄まで足を運ぶ。第一章で現在の沖縄が描かれ、それが第二章の〈わたし〉の物語に重ね合わされていくのである。〈私〉と〈わたし〉の記述が交互に行われることにより、現代の読者が過去へ旅することが可能になる。
〈私〉は無邪気な同情者である。「女性たちの部屋」の存在を目の当たりにして〈私〉は「なんてかわいそうな境遇だったのだろうか」「こんな穴の中に、閉じ込められていたなんて」と考えるが、第二章を読めば〈わたし〉の境遇は〈私〉の想像を
〈私〉にとって慰安婦は希望でもある。「この島の痛みをなんとか伝えたい」と〈私〉は願うが、それは「そんな小説が書けたなら、私の人生も開けるはずだ」からである。身も
小説を書くという行為は誰かの人生に踏み込むということにつながる。当事者以外にそれが許されるのか、という問いが二〇一〇年代以降頻繁に議論されるようになってきた。無自覚のうちに〈私〉はその中に足を踏み入れてしまうことになる。物語の初めから〈私〉の
男が女の尊厳を奪うという罪の構造が第一にある。それを書くという行為を通じて、誰かの人生は他の者に利用されていいものではないという、もう一つの主題を深沢は浮かび上がらせた。二つの主題は別々の位相にあり、決して混同していいものではない。そのいずれを考えるにあたっても、まず第一に思いを
深沢潮のデビュー作は、二〇一二年に第十一回女による女のためのR‐18文学賞大賞を獲得した「金江のおばさん」である。お見合いのとりまとめをする女性を主人公とするこの物語は、結婚という制度に縛られる女性のありようを浮かび上がらせると同時に、南北に分断された民族出自を持つ、在日二世の現在と心性を粉飾のない言葉で描いた。同作を収録した『ハンサラン 愛する人びと』(二〇一三年、新潮社→『縁を結うひと』と改題し、現在、新潮文庫)が最初の著作である。
同作のみならず深沢は、折に触れて自身の民族的出自を直視した作品を著している。『ひとかどの父へ』(二〇一五年。現・朝日文庫)、『海を抱いて月に眠る』(二〇一八年。現・文春文庫)といった作品は、在日である父の人生を娘が知ることによって家族のたどってきた道筋が
同時に深沢は、女性に強制される不公平な状況や、
そうした作者が、国家によって性奉仕を強制された従軍慰安婦の問題を主題としたのは当然の帰結で、おそらくは作中の〈私〉こと
先に書いたように〈わたし〉は徹頭徹尾自分の名前を口にしようとせず、心の奥にしまい続ける。その思いに〈わたし〉が決着をつけるのが最後の第十章だ。『翡翠色の海へうたう』という物語はそこで見事に完結する。ページを閉じ、本を置くとき、読者の脳裏には静かな海の情景が浮かんでくるはずだ。ぜひ、記憶に留めてもらいたい。その海を思い出すとき、あなたの胸には〈わたし〉の痛みがさざなみのように広がっていくことだろう。
作品紹介
書 名: 翡翠色の海へうたう
著 者: 深沢 潮
発売日:2024年07月25日
国も、時代も、性別も、そのすべての境界を越えてゆけ――深沢潮、渾身作!
派遣社員、彼氏なし、家族とは不仲。冴えない日々を送る葉奈は作家になる夢を叶えるべく、次の投稿作のテーマを探していた。そんな中、推していたアイドルの投稿に「あなたがそんな人だったなんてがっかりした」というコメントがついていることに気付く。どうやらアイドルが慰安婦女性など性被害に遭った人たちを支援するブランドを着ていたことで炎上が起こったらしい。ファンの間でも賛否両論の意見が起こる中、葉菜はタブーとされるが故に女性たちの記録がきちんと伝わっていないことを知る。戦時中の沖縄を舞台に勝負作を書くことを決意した葉菜は取材のために沖縄へと飛ぶが、そこでイメージしていた女性たちの姿と、証言者たちが語る彼女たちの姿に乖離がある事に気付く。そして取材対象者の女性から、「当事者ではないあなたが、どうして書くのか」と覚悟を問われ――。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322403000802/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら