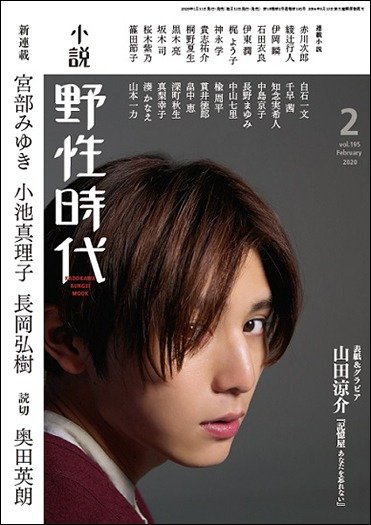文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(解説者:瀧井 朝世 / ライター)
その部屋で語られる内容が門外に出ることはない。なぜなら聞いて聞き捨て、語って語り捨てが決まり事だから。それでも人はそこを訪れ、語らずにはいられない――風変わりな百物語が繰り広げられる三島屋変調百物語シリーズ。第一作の『おそろし 三島屋変調百物語事始』の単行本刊行は二〇〇八年(連載開始は二〇〇六年)。その後も発表媒体を変えつつ物語は続き、本作は二〇一五年六月一日から翌年六月三十日まで日本経済新聞朝刊に掲載(連載時のタイトルは「迷いの旅篭」)、二〇一六年十二月に日本経済新聞出版社から単行本刊行。そしてこのたび文庫化された。収録されるのは四篇。これでようやく二十二話が語られた。百話まではまだまだ遠いが、読者にとってはそれだけ楽しみが続くわけだ。
三島屋の怪談語りの趣向については「序」で説明されているので省く。聞き手のおちかは十七歳の時に川崎にある実家の旅篭で残酷な事件に遭遇して心を閉ざし、叔父夫婦の元に身を寄せた。変わり百物語は、彼女の心を解かすための叔父のはからいだ。
シリーズものといえば、舞台設定に大きな変更はなく主要人物たちが年を取らないまま進んでいく手法もあるが、本作はゆるやかな時間経過のなかで、少しずつ人間関係やおちかの心模様が変わっていくのが特徴だ。彼女の心を開くための百物語なのだから、変化を描くのは当然のことだろう。
基本的に奇数話は深刻な話、偶数話はほのぼのした話を配置してめりはりが効いている。単行本ごとの色合いも少しずつ変わっており、第一巻『おそろし』は変わり百物語が始まるきっかけやおちかの過去など基本設定を読者に知らせるエピソードが中心。第二巻『あんじゅう』は子どもにまつわる話が多く(なんといってもあんじゅうの愛おしさよ)、第三巻『泣き童子』はバリエーション豊かだが、やきもち焼きの若い女性(「魂取の池」)や夫思いの妻(「くりから御殿」)など少々色艶のある話が加わってくる。本作『三鬼』も彩り豊かであるが、地方政治や地域社会の問題点といった要素も出てきて、それを理解するおちかの様子からは、彼女の知見が深まっているとも受け取れる。また、表題作での語り手である清左衛門の妹、志津の身に降りかかる出来事は痛ましく、若い女性であるおちかに聞かせるのは酷に感じるだけに、ついにこの類の話も出てくるようになったか、と思わされる。つまり彼女の精神的な成長に合わせて、持ち込まれる怪異を形成する要素も大人向け(少なくとも子ども向けとはいいにくい)の内容になっているのだ。
実際、彼女の変化は目覚ましい。怪奇譚に馴染むにつれ好奇心を見せ行動的になっていく面もそうだが、聞き手としての熟達ぶりも素晴らしい。最初のうちは元来の心根の良さと、心の傷による内向きな姿勢があいまって、他人の内面に土足で踏み込まない慎ましさがかえって相手の心を開かせていたが、本作ではすっかり巧みな聞き上手になっている。「迷いの旅篭」では緊張している子どもの心をほぐし、「食客ひだる神」ではいってみれば自らインタビューを申し込み、「三鬼」も打ち明けることを逡巡していた武士の心を開かせ、そして「おくらさま」では、自力では黒白の間に来られない人間まで彼女と話したがるという、信頼され具合。いやはや、実に名インタビュアーである。
ここで、各話の読みどころをざっと眺めてみよう。
●第一話「迷いの旅篭」
自ら語りたくて来たのではなく、予行演習としてやってきた子どもが語り手、という点がユニーク。語られる内容は、村、つまり地域社会の話だ。怪異は起きるが、それよりももう取り戻せないものに固執した人間の狂気にゾッとさせられる。しかし決して、その心理を糾弾する展開ではない。最後の最後で一人の男が村人たちを驚かせる行動をとるが、そこからは狂気よりも寂しさと哀しさが伝わってくる。そう感じさせる人物を配置させる点が、著者の実に巧みなところだ。
〇第二話「食客ひだる神」
「あんじゅう」に心ときめかせた読者なら、ひだる神にも悶絶したのではないだろうか。あやかしを受け入れる夫婦の人の良さも好ましい。一緒にいたいのにそれが難しい状況は切ないが、その理由がなんとも可笑しみに満ちていて、怖い要素は皆無の愛らしい一作。ひだる神の魅力だけでなく、食欲をそそる食べ物が続々登場する点や、商売においての成功物語としての読み心地も魅力だ(媒体が日本経済新聞だったからだろうか)。
●第三話「三鬼」
先にも触れたがなんとも痛ましい事件が語られ、そこから山奥の地域社会の話へと広がっていく。独自の決まり事がある村に余所者が足を踏み入れた時の不可解さ、不気味さがたっぷりと味わえる話。鬼も怖いが、しきたりを守り続ける村人の排他的な心理も怖い。そして後日談は、余韻を残すものである。ところで多くの読者が「三鬼の意味は何だろう?」と思ったのではないだろうか。町の鬼、山の鬼、人の中にいる鬼ととらえればいいのか……などと考えをめぐらせることも、読書の愉しみのひとつである。ただ、それではしっくりこないという方もいると思うので、著者が対談の中で語ったことを引いておく。
「三鬼」の「三」を「山」にするか迷っていたんです。山が舞台の話ですから「山鬼」でもいいんですが、私としては東西の村ではない、三番目のあの世に近いところからくるものの話なので「三鬼」でもいいな、と決めかねていたんです。 その話を刊行後の打ち上げのときにカバーの插画も描いてくださった北村さんに話したら、「絶対に『三』がいいに決まってる。山の鬼じゃないですよ」って
『宮部みゆきの江戸怪談散歩』(角川文庫)より
〇第四話「おくらさま」
黒白の間を訪れて過去を語るのは心は十四歳のままの老婦人。その正体に意外性のある話だ。彼女はおちかの背中を押す役割も果たしている。それに加え、袋物屋の次男でおちかの従兄、富次郎が戻ってきたり、貸本屋の若旦那、勘一が登場したり、そしてなんといっても、あの人が江戸から去るなど、物語が大きく変わっていく予感を抱かせる。その通り、第五巻『あやかし草紙』では大きな変化が訪れて……それは読んでのお楽しみ。百話を迎える頃、この物語はどのような様相となっているのかまったく分からなくなる。
本を閉じて振り返ると、しみじみと噛みしめるのは怪異の恐ろしさや不思議さだけではなく、それぞれの人の語られなかった思いである。一平はその後どのような気持ちで生きていくのか、房五郎夫婦の寂しさは相当なものだったのではないか、すべてを語った清左衛門の心中は澄んでいただろうか、お梅さんは何十年もどんな思いを抱いていたのだろうか……。そして、おちかの心が今後どう動いていくのかも気になるところだ。思いをめぐらせるうちに、いつのまにか、死者に対しても、これからを生きていく人たちに対しても、柔らかな気持ちになっている。各話の語り手だけでなく、我々読者もまた、黒白の間でおちかに慰められ、心洗われているのである。