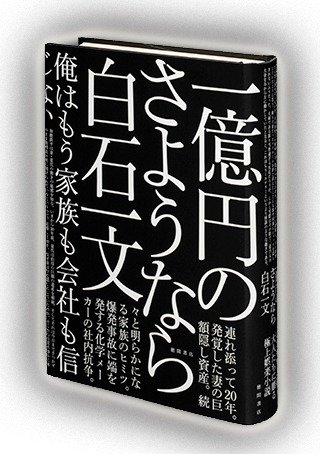小説はフィクション、つまりつくり話である。しかし、小説を読んでいる間、登場人物たちに愛着を感じたり、その反対に憎しみを覚えたりもする。架空の人物だとわかっていてもその運命に心穏やかではいられない。これはなんとも不思議なことだ。
どんなに夢中になったとしても、これが現実ではないということは百も承知だ。なのに意識が物語に浸ってしまうと、ウソとホントの境界はどうでもよくなる。というかその境界を問うという発想そのものがすでに存在しない。それはまるで現実に生きている私たちが、世界の存在を疑わないのと同じだ。文字を追い続けている限り、私たちはその世界の中で生きている。少なくとも脳内で起きている感情の動きはホントなのだから、主観的にはウソではないともいえる。本から顔を上げ、小説の世界から出て行かない限り、私たちは小説の中に生きている。
もちろん、すべての小説がそうした深い没入感を提供してくれるわけではない。だが、少なくとも『記憶の渚にて』を読んでいる間、私はこの小説の中にいたと断言できる。『記憶の渚にて』だけではない。白石一文の小説を読むたび、私は同じようなことを考え、戸惑いさえ覚えてきた。デビュー作の『一瞬の光』が発売された当時、作者のプロフィールが伏せられていたこともあり、ここに書かれていることはすべて本当にあったことなのではないかと感じるほどのリアリティを感じた。二〇〇〇年のことだからいまから十九年前だが、その衝撃はいまも記憶に鮮やかだ。
映像表現が飛躍的な発達を遂げ、3DからVRへとさらに仮想的な体験を可能にする現代にあっては、文字だけですべてを表現する小説はもはや古い表現形式といっていい。しかしそれでもなお読まれているのは、作者が言葉を使い、読者の意識にアクセスする方法がいまだに有効だからだ。ただ、そのためには言葉のみでつくられた広大な海原に起きる物語を構想し、語りうる優れた書き手と、能動的に言葉の海へと飛び込んでいく読者の存在が必要になる。小説の存立基盤にあるのは、作家と読者が互いに想像力を駆使するという暗黙の同盟である。この解説を読んでいるあなたは、意識するしないにかかわらず、その広大な海へ言葉を頼りに出て行く意思があるということになる。そして、白石一文はその海にただならぬ波乱を起こし、読者を新たな冒険へと誘う驚異的な書き手である。
『記憶の渚にて』は「私」の一人称で幕を開ける。私たち読者は「純一」という名のこの男性が兄について述べている言葉を手がかりに、二人の人物像をつくり始める。兄は「自分には記憶が見える。そしてその記憶こそが現実なのだ」と常日頃から豪語し、目の前の風景を頭にたたき込むことで目をつぶっても歩けたという。記憶、つまり、頭の中にある情報こそが現実であるというテーゼは強烈な印象を残し、読者はのちに何度もこの言葉を思い出すことになるだろう。純一は兄の言葉や考え方を次々に述べていく。しかし読者はそれらの文章が過去形であることに次第に気づく。そして、兄が五十四歳で亡くなったことが明かされる。純一は遺骨を抱いて帰る飛行機の中で兄についてのとりとめのない回想を行っていたのだ。どうやら純一の兄は「恐ろしく頭の切れる人」「天才」だったらしい。
文章で使われている言葉はすべてが明瞭で曖昧さはない。だが、小説世界をのぞき始めたばかりの読者にお節介な説明はなく、ひたすら純一の思考とその目を通した世界が描かれる。家に帰り着く前にスーパーに寄るくだりからは、さらに具体的に目に映ったものが言葉に変換されていく。そして読者は少しずつ純一と彼を取り巻く環境を理解し始めるのである。五十四歳で死んだ兄より五歳若い純一は、亡くなった父母が建てた家を改築し、㈲トモコの石鹸社の事務所兼自宅としている。トモコの石鹸はアトピーに効くという理由で高価ながら人気が殺到している。純一はトモコの石鹸の総販売代理店を経営し、少ないながら従業員も雇っている。そして、亡くなった兄が時代の寵児となったこともある有名な小説家だったことがわかってくる。兄の手塚迅(本名:古賀壮一)はノーベル賞をとるといわれたほどの作家だったにもかかわらず、晩年はほとんど作品を発表しなかった。だが、「文藝春秋」の巻頭随筆に「徹頭徹尾すべてがでたらめ」な文章を発表していた。なぜ兄はこんなことを書いたのか。そして、三カ月ごとに兄のもとに届いていた差出人不明の謎のメールと、兄自身が残した遺書のような文章には近い意味の文言が使われていたのはなぜか。その言葉「遥かなるいのちの海へ!」「限りなき生命の海へ!」が意味するものとは?
白石作品に共通する独特の没入感はその語り口の滑らかさと、読者への情報提供のタイミングの絶妙さにある。『記憶の渚にて』のような一人称の場合、読者はその人物の目を借りてその世界を見る。独白は思念に近く、説明的な要素は皆無ではないものの、それほど多くはないし、あったとしても謎が残る。トモコの石鹸社の説明はされているが、トモコが何者なのか、純一とどういう関係なのかはその場では明かされない。これは現実世界を「見る」ことに似ている。私たちが登場人物の一人なら、純一に尋ねればその情報は手に入る。しかし、私たちは小説世界に介入できない。できるのは限られた情報を手がかりに想像すること、推測することだけだ。そして、気がつけば物語にどっぷりと浸かっている。 物語全体を貫く究極的な謎として、純一と兄との関係に「ミチルさん」なる人物がかかわっていることが明らかになるが、むろん、その人物が何者かを読者が知るのはずっとあとのことになる。
物語全体を貫く究極的な謎として、純一と兄との関係に「ミチルさん」なる人物がかかわっていることが明らかになるが、むろん、その人物が何者かを読者が知るのはずっとあとのことになる。
天才作家の兄に対して弟の純一も凡庸な人間ではなく、透視能力や、予知できる能力を持っていることもこの物語の謎を深めている。白石作品にはこれまでも並外れた能力を持つ人間や、スーパー・ナチュラルな現象がしばしば登場してきた。その現象は空港で「皆々が真っ白な法被を羽織って飛行機の入口の中にスローモーションでも見ているようにゆっくりと吸い込まれていく情景がありありと眸に映った」(「夢の空」 『不自由な心』所収)という怪談の一節のようなものから、余命一年を宣告された男性が「病を癒す女」によってがんを消滅させる(『神秘』)奇跡までさまざまだが、どれも荒唐無稽とは言い切れない。友達の友達が聞いた話、あるいは都市伝説として語られる現象に近い。
実際、十階のビルの屋上から飛び降りた男性がかすり傷で助かるという場面から始まる『彼が通る不思議なコースを私も』について白石氏にインタビューした折り、もっとも印象的だったのが「千に一つもないことは書けない」という言葉だった。
たしかに『記憶の渚にて』で描かれている、純一の透視や予知の能力や、「神意天声之門」という新興宗教の信者が持つ手を当てることでの治療能力については、古今東西、数多くの証言がある。科学的な知見がそれを否定し、トリックやインチキが暴かれたとしても、私たちは直感的にそれを完全には否定しえない。いやむしろ、その能力を人間の生と結びつけ、非凡な力がもたらす悲喜劇や、ありえるかもしれない出来事を描くことこそフィクションの仕事だといえるだろう。なぜなら、フィクションには、ここではないどこかにあるかもしれない、オルタナティブな生を描くという大切な仕事があるからだ。
ところで、先ほど紹介したストーリーはこの小説のほんのとば口にすぎない。古賀兄弟を中心に登場人物とエピソードは枝葉を伸ばし、時間的にも空間的にも遠い場所まで読者を連れて行く。とくに第二部以降は、主な語り手を手塚迅の義理の甥にあたる小説家、白崎東也が語り手を務め、謎の探索に奔走し始める。手塚迅が残した数々の謎を解き、「ミチルさん」の正体へたどり着けるのかが物語を牽引する大きな力となっていく。
しかし、こうして物語を説明したところでこの小説について語った気がまるでしない。それもまた白石一文の小説を語るうえでつねについて回ることでもある。リアルな手触りのある世界を構築し、読者を引きつける謎を提示する、ストーリーの面白さが十二分にあることは間違いないが、その一方で、それらは小説の表層でしかなく、本質はそこにはないといいたくなる。むしろ本質はこの小説を「読む」という体験そのものにあるのではないか。ここまで見てきたように、小説家は文字だけでその世界をつくり、読者は文字を読むことで、それぞれの脳にある記憶のデータベースをもとに世界を再現する。そのとき、私たちは擬似的にもう一つの世界をのぞき込み、心を寄せる。言葉は記号にすぎないが、その記号を頼りに小説家と読者は世界を共有しているのだ。
白石一文の作品ではつねに「私」という存在の不思議さ、「生きる」ことへの力強い肯定が描かれてきた。『記憶の渚にて』でもその主題は変わらない。ただし、そのテーマを記憶というキーワードで時間的、空間的広がりを持ったスケールの大きなものにつくりあげたことが本作の読みどころだ。この物語が始まったときにはすでに亡くなっている手塚迅と、その背中を追うことになる白崎東也がともに小説家であることは意味深長だ。記憶とは? 小説とは? そんな問いを頭の片隅に置きながら、言葉の海へと漕ぎだしてほしい。