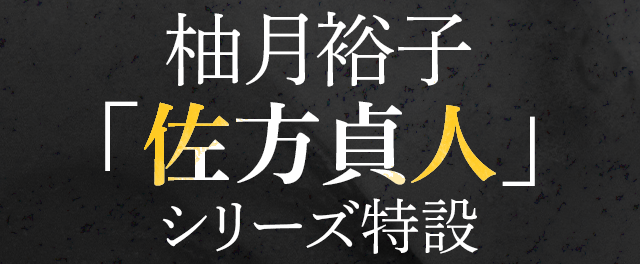この本を手にした時、あなたは「鹿の王」というタイトルにどのような印象を抱いただろうか。もしも鹿たちを統率し君臨するようなカリスマ的な存在を想像したのであるなら、この本を読み終えた時、そのイメージは完全に覆ったのではないだろうか。
本作は上橋菜穂子さんの二〇一四年の書き下ろし長篇『鹿の王』の文庫化の最終巻である。単行本刊行時は上下巻だったが、文庫版では四分冊となった。タイトルの意味はこの第四巻になってようやく明かされる。
二〇一五年の本屋大賞受賞作であり、同年日本医療小説大賞も受賞して話題を呼び、老若男女問わず幅広く読まれることとなったこの物語。一九八九年に『精霊の木』で作家デビューを果たした上橋さんにとって、作家生活二十五周年を迎えた後の最初の小説であり、二〇一四年の国際アンデルセン賞の作家賞受賞後の第一作でもある。国際アンデルセン賞作家賞というのは優れた児童文学を発表している作家に贈られる「小さなノーベル賞」とも呼ばれる賞である。それまでにも著者は国内外で児童文学のさまざまな賞を獲得しており著作は児童文学に分類されることが多いが、『精霊の守り人』に始まるシリーズや『獣の奏者』シリーズなどは子どもだけでなく大人の読者からも大変な人気だ。
さて本作に関しては、この最終巻でいよいよ、二人の主人公が邂逅を果たす。一人はかつて東乎瑠への抵抗を見せるため死を決して結成された戦士団〈独角〉の頭であり、その後奴隷となったものの生き延びたヴァン。もう一人は、かつて存在したオタワル王国の末裔である医術師、ホッサル。蔓延する黒狼熱について語らった二人は、やがてこの病を利用した陰謀に気づき、阻止しようと奔走する――。
ヴァンたちの物語について語る前に、他作品にも通じる上橋ファンタジーの魅力を三つ挙げておきたい。
一つ目。まったくもって子ども騙しではなく、むしろ大人こそ真摯に読みたいテーマが詰まった作品であること。国家の成り立ち、文明の在り方、政治的な状況、暮らしや風俗が細やかに設定されると同時に、非常に長い時間を盛り込みつつ描かれる。本作でいえば現在、東乎瑠帝国が支配しているアカファ王国の地域は、かつてオタワル王国があった場所である。そのオタワル人の末裔がホッサルということは、彼らは祖国喪失という過酷な状況のなかで生き抜き、医術という知識と技術を駆使して安泰の居場所を築いてきたと分かる。長い歴史が遠景に見えてくるからこそ、物語にも人物にも深みが出ているのだ。
二つ目。ファンタジーだといっても、魔法や超常現象などの超人的な力で根本的な解決がなされたりはしない点。人々も動物も、限られた力の中で懸命に生きていく。だからこそ、異世界の話であるのに、何か自分たちの現実の社会が投影されているような感覚を抱くことができる。そしてそれは時に警鐘となり、励ましとなるのだ。
三つ目。「個」と同時に「集団」が描かれる点。個性的な一個人(時に動物)が多数登場し、それぞれ掘り下げて描写されていくが、彼らの行動は、家族や所属する氏族、共同体、国家の意志に基づいていることが多い。多くの人は、自分一人だけの利益のために動くというよりも、自分の属する集団、あるいは大切な人が属する集団のために行動している。あるいは、時にそうした集団に対抗する。そうした描き方のため、集団というものが、謎めいた塊ではなく、個人個人が集まって成立していると感じさせる。「個」対「群れ」の描かれ方が秀逸なのである。
これらを踏まえつつ、この『鹿の王』の魅力も押さえてみたい。
まず特徴的なのは、これが医療小説であること。ウィルスの正体やその感染ルートを突き止めていく医学ミステリーという要素を持つ本作は、生物の生態系や体内のメカニズムまで丁寧に説き明かしていく。壮大なスケールの中でミクロの世界まで描き切ることをやってのけているのである。医療従事者でない著者がこれほどまでに分かりやすく生命の神秘を物語に溶かし込んでみせるとは、さすがの咀嚼力と解説力。さらに、動物の体内にさまざまな微生物が共存している様相と、人間社会、さらに動物をも含めた地上の生物世界の在り方を重ね合わせずにはいられない描き方は、私たち読み手にさまざまな示唆を与えてくれている。しかも、決して教訓臭くなることなしに。
生物が子孫を残そうとする生態系をテーマにしながらも、主要人物であるヴァンやユナを、血縁を持たない存在にした意味も大きい。家族や氏族といった集団が重要視されがちな世界で、赤の他人同士が家族のような絆を育んでいく。これは孤独だった男が再生し、幸福を得ていく物語とも読める。だが、だからこそ、この最終巻で私たち読者はタイトルの「鹿の王」の意味について、重く受け止めることになる。
飛鹿の群れの中には、群れが危機に陥ったとき、己の命を張って群れを逃がす鹿が現れる
とヴァンは語る。〈群れを支配する者、という意味ではなく、本当の意味で群れの存続を支える尊むべき者として〉、その盛りを過ぎた飛鹿のことを、敬意を込めて「鹿の王」と呼ぶという。
最後にヴァンのとった行動は、「鹿の王」と同じなのかもしれない。かつては絶望のあまり死を望んでいた男が、今は人々のために動く。同じような行為であっても、その動機は一八〇度異なるのだ。だが、本人がヒロイズムに酔っていないことは確かだが、周りの人間は、果たしてそれを英雄的行為とみなすべきなのか、尊ぶべきなのか。あるいは、昔ヴァンの父親が言ったように、それは「馬鹿がやること」なのか。
いや、最終章に描かれる、森の奥へ向かう人々の光景は、彼を孤独な英雄として崇めることをやんわりと退けているのではないか。もちろん犠牲を払おうとしたヴァンを貶めているわけではない。誰かのために己れの犠牲をいとわない人がいるのなら、その人のために行動を起こす人もいる、というわけだ。生物はそうやって生きているのだということを、象徴する光景なのだ。エピローグのホッサルの心の声を、私たちはしっかりと受けとめておきたい。
ときに、他者に手をさしのべ、そして、また、自分も他者の温かい手で救われて、命の糸を紡いでいくのだ
森の奥へと旅立つのが、異なる出自の者たちで、彼らが〈家族のように寄り添って〉いるのも象徴的だ。種や帰属する共同体を超えて、人と人は手を差し伸べあえる。個々の人間同士だけでなく、共同体も、国家同士も、きっと――。
こうした骨太な作品を生み出す上橋菜穂子さんは、作家であると同時に、文化人類学者でもある。オーストラリアの先住民アボリジニについて研究し、かつては現地に滞在してフィールドワークを実施してきた人だ。異文化の交流や衝突、個と集団というテーマを、現実味を持って掬い上げられるのも、こうした素養があることが大きいだろう。
以前、読書遍歴についてインタビューしたことがあるが、そのファンタジーから人文系の書籍まで幅広い読書量に圧倒された。きちんと作中の世界が作り込まれているものが好きだったことや、幼い頃から「時間」といった大きなものに想いを馳せていた、という話を聞いて、上橋作品がストーリーのうねりだけでも充分楽しめるが、遠景にちりばめられた世界観や時間の流れに想いを馳せるとさらに味わいが増す理由の一端を知った気がした。この『鹿の王』も、まさにそうして味わいたい作品である。著者の才能と思いが結実したこの物語。読めば必ず、心の中に何かが生じるはずだ。それはきっと、これからの自分の生き方や考え方に何かしらの影響を与えてくれる、不思議な微生物のような、何かである。
▽『鹿の王』シリーズ・[解説]一覧
「この本こそが、ファンタジーである」本屋大賞受賞作を書店員が熱く語る。『鹿の王 1』
https://kadobun.jp/reviews/32/cf3b36a2
「深い闇のかなたに小さな、けれども確かな灯火がある」医療小説の旗手が読み解く、生と死の豊穣なドラマ! 『鹿の王 2』
https://kadobun.jp/reviews/34/131f15a8
「この物語が世界に存在する奇跡」 『鹿の王 3』
https://kadobun.jp/reviews/66/10e5895c