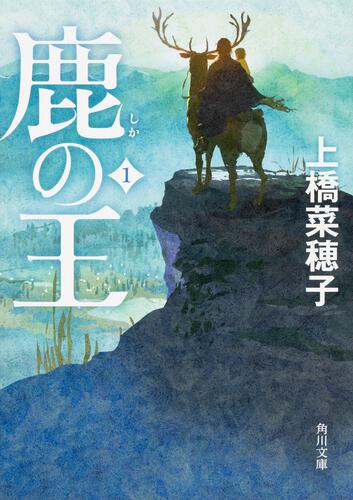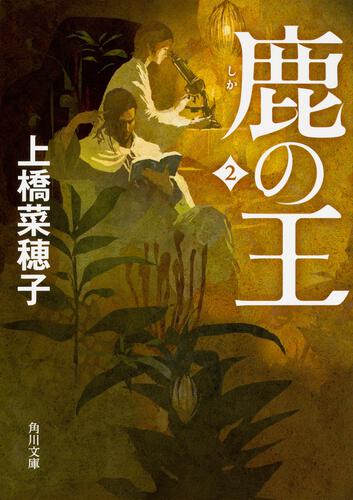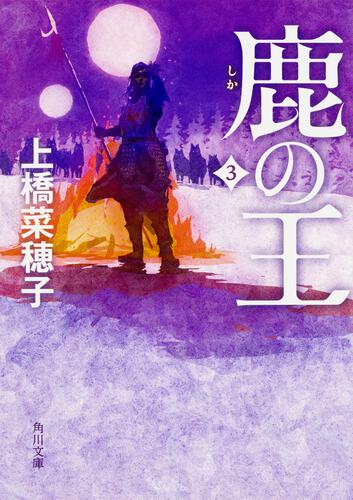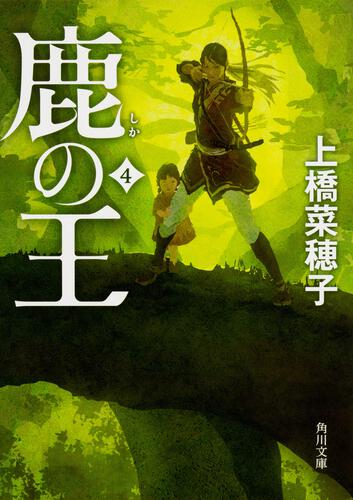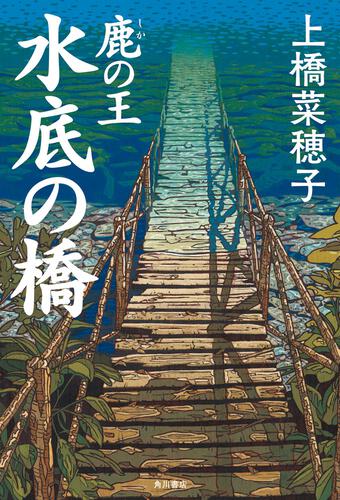2015年本屋大賞受賞作、上橋菜穂子さん『鹿の王』が角川文庫より文庫化されます。第1巻、第2巻が6月17日、第3巻、第4巻が7月25日に発売となります。
本作は、感染からふたりだけ生き残った父子と、若き天才医術師が未曾有の危機に挑む、綿密な医療サスペンスにして壮大なる冒険小説です。
著者・上橋菜穂子さんが『鹿の王』に込めた思いとは。
〈単行本刊行時に「本の旅人」2014年10月号に掲載されたインタビューを再録しました〉
“児童文学のノーベル賞”、国際アンデルセン賞を受賞。
2014年3月、上橋菜穂子は国際アンデルセン賞の作家賞を受賞した。トーベ・ヤンソン、リンドグレーン、そうそうたる顔ぶれが受賞したこの賞は、児童文学のノーベル賞と言われる。日本人では、まどみちおさん以来、20年ぶりの快挙だった。
「まさか自分が受賞するなんて、まるっきり考えていなかったんです。一週間前にショートリスト(最終候補)の6人に残ったと聞いた時も〝あ、そうっすか”ぐらいのノリで〝全世界の中から6人ってスゴくない?”って、みんなに言って回ったくらい。それでもう十分みたいなつもりでいたんですけど、さすがに〝今日の夜、発表です”と言われるとドキドキしてきて、全然眠れなくなっちゃって。家でアンドルー・ワイルの『癒す心、治る力』を読んでいたら、ちょうど〈不眠について〉という章があって、なんか今日の夜は不眠になりそうと思っていたところに、メールがきたんです」
おめでとうございます!——『獣の奏者』の担当編集者、長岡香織さんからだった。びっくりして、電話で折り返すと、ざわざわしている。ボローニャ国際児童書展に参加していた彼女は、国際アンデルセン賞の受賞者が発表される会場に駆けつけていたのである。
「えっ、私?」
「だと思います」
「だと思いますって……?」
受賞者は、ショートリストの6人が紹介された後、発表された。ナホコ・ウエハシと確かに言った気がするのだが、それは単なる紹介なのか、栄えある受賞者なのか。
Cultural anthropology 授賞理由に耳を澄ますと確かにそう聞こえた。文化人類学、これはもう、間違いがない。
「ボローニャには、去年の秋、まったくの観光で行ったことがあったんです。そうか、ここで国際児童書展をやるんだと思いながら、あの街のポルティコという有名なアーケードを歩いたりして。アンデルセン賞を受賞するとポルティコに大きな顔写真が飾られるんですけど、そこに自分の顔写真が飾られるなんてあの時は思いもしなかった(笑)。私の作品は長編なので、絵本みたいにパッと見て審査するというわけにはいかないし、あんなに分厚い本を読んでもらえるはずがない……だからきっと無理だろうと思っていたのに、ちゃんと読んでくれたんだなあと。そのことにまず感謝したくなりました。
授賞理由として、日本特有のというような評価ではなくて、多様な価値観がネットワークのように結びついた世界観、自然に対する畏敬の念に満ちていると言っていただけたのもすごく嬉しかったですね。今、世界中で気になっていること、評価される基準というのがそこにあるんだなということも、ひしひしと感じました。二十世紀は戦争の時代と言われた、二十一世紀は大きな戦争こそないけれども、紛争やテロがあちこちで起きている。これからは多様な価値観を持つ社会の中で、人々がどう共生していくかが問われているんだなと」
3年ぶりの待望の長編小説、 『鹿の王』はこうして生まれた。
3年ぶりの長編『鹿の王』の構想が生まれたのも、やはり1冊の本を読んでいる時だった。
「フランク・ライアンの『破壊する創造者』。ウィルスがいかに進化に深く関わっているかということを研究した本です。鳥インフルエンザ、ノロウィルス、エイズなど、ウィルスというと、やっかいな病原体というイメージがありますけど、考えてみれば、ウィルス自体が、ほかの生き物の中に入らないと生きていけない不思議な生き物なんですよね。よく乳酸菌の宣伝で善玉菌、悪玉菌ってやってるけど、自分の体の中をひとつの〈世界〉として生きて死ぬ生き物がいると思うと、不思議な気がしませんか。しかも自分の体の中で起こっていることなのに、私たちは今、何が起こっているのかを知らないでいる。その細菌に消化を助けてもらったり、免疫をつくってもらったり、守ってもらっている部分もたくさんあるのに、その顔を見ることもなく、その思いを知ることもなく、それに生かされ、あるいは害されながら、生きている。昔『ミクロの決死圏』という、医療チームをバクテリアくらいの大きさにミクロ化して人間の体の中に送り込むという映画があったけれど、人間の体の中というのは、まさにミクロコスモスなんですよね」
命というものは、生かし、生かされながら、まるで入れ子構造のように共存しあうものなのか。自分の体の中に、もうひとつの世界を発見したような気がした。
「『守り人』シリーズと『獣の奏者』という、ふたつの大きな物語を描き終えた時、自分では、もう描くべきことは描き尽くしてしまったような感じがしていました。ふと気がつくと、私自身、人生の折り返し地点を過ぎて、体力的にも、精神的にも疲れていたのでしょうね。何を見ても、何を読んでも、心が動かなかった。それでこの3年間、スランプだ、スランプだと言い続けていたら、ある作家さんから〝スランプって錯覚なんだって”と言われたりして。そう言われても、書けないものは書けない、ええっ、錯覚なんかじゃないよ! と思いながら、書きかけては捨て、書きかけては捨て……こんなふうに机に向かい続けていたところで、もう書けないんじゃないか、そう思ったことさえあった。ウィルスの本と出会ったのはそんな時だったんです。何を見ても、何を読んでも、心が動かなかったのに、面白くて面白くて一気に読んでしまった」
これなら、書けるかもしれない——。そう思うと、心が震えた。
「そんな気持ちになったのは、一体いつ以来だろう。それまでピクリとも動かなかった心が、あの時、初めて戻ってきたという感じがしたんです。私たちの体の中にもうひとつの世界がある、しかもそこでは、生かそうと思う存在と、いや、とって食ってやるという存在が、熾烈な陣地争いをしながら、せめぎあっているわけですよね。それって、まさに人間社会で起こっていることそのものだと気づいた時に、書ける! と思って」
なぜ人は戦うのか。なぜ共存しあうことがこんなにも難しいのか。上橋菜穂子という作家は、まさにそのことを描き続けてきた。そうした人間社会の在り様が、もし、命の摂理と二重写しになるのだとしたら。
「体の外側で起こっていることと、体の内側で起こっていることが、まさかこんなにもよく似ているなんてね。にもかかわらず、体の内側で起こっていることって、人間が何を思おうと関係ないですよね。これまで命について考える時は、人間の意識の問題、魂の問題として描いてきたけれど、それとは関係ないところで、命は勝手に生き死にを決めてしまう。生物としての体が勝手にやっていることなんですよね」
体の内側にもうひとつの世界がある。 そう気づいたとき、物語が走り出した。
「『破壊する創造者』を読んだその夜、犬に噛まれて、ウィルスが体の中に入ってしまった男の夢を見たんです。目が覚めた瞬間、ウィルスのせいで体が変わっていっちゃう男のイメージが浮かんで、それを同じように噛まれたチビの女の子が〝お父ちゃん、お父ちゃん”って引き留めようとしている光景が見えた」
物語が生まれる時は、いつも、ひとつの映像が浮かぶ。『精霊の守り人』を書いた時も『獣の奏者』を書いた時もそうだ。そこには、これから描かれる物語のすべてがすでに含まれているのだと上橋さんは言う。
死を求め、戦う戦士団︿独角〉の頭、かけ角のヴァンはこうして誕生した。3年ぶり、待望の長編『鹿の王』が、ついに舵を切ったのである。物語は深い深い地の底、岩塩鉱で始まる。そこでは勝ち目のない戦いを戦い抜いて敗れ、ひとり生き残ったヴァンが、奴隷として過酷な日々を送っていた。
「以前、ポーランドのヴィエリツィカという岩塩鉱に行ったことがあって、本当はエレベーターで降りていくんだけれど、エレベーターが壊れていたので、階段で降りていったんです。もう、寒いくらい、ひんやりした階段を延々降りていくんですよ。しょうがないから私は〝森へ、ゆきましょう、娘さん、ヤッホホ”と歌いながら降りていったんですが、歌い切っても、まだたどり着かない。そんなところに何本も坑道があって、一体、どこまで潜るんだろうと思いながら、その階段を降りていくと、なんと岩塩でつくったシャンデリアのある大広間があって。そんな深い坑道の中に、かつては馬がいたんですって。ものすごく美しく、そして、怖かった。作中に出てくる〝光る葉っぱ”も、エリシアクロロティカという実際にいる生き物からイメージしたものなんですよ。
エリシアクロロティカは、ウミウシなんですけど、成長の過程で植物になってしまう。そして卵を産むと、まるで自分が役割を終えたのを知っているかのように死んでしまうんです。卵を産むために遡上してきたサケが一斉に死んでしまうのは、よく知られていますよね。あれも、免疫力が落ちて、体内のウィルスが病を発症させるからだという説がある。この世の生き物がどういうふうに生きて死んでいくのか、命について、そこから問い直してみたいと思ったんです」
独角のヴァンは、言うなれば、死に場所を探してきた男だ。妻も、子も、仲間も皆、死んでしまったのに、なぜ自分だけが生き続けているのか。帰るべき故郷も失い、彷徨い続けてきた。
「生きたいのに体が生かしてくれないというのは恐ろしいことで、これが病ですよね。でも心は死にたいと思っているのに、体は生き続けているというのも、やはり、恐ろしいことだと思うんです」
命とは、幸福とは何か。もう一度、 根本から問い直してみたかった。
一方、謎の犬に噛まれた者に発症する死に至る病は、かつて一国を滅ぼしたと言われる黒狼病なのか。先進的な医術を使うオタワルの民の中でも「魔人の御稚児」と恐れられる若き名医、ホッサルが調査に乗り出す。
「宿主の体をひとつの世界として生きるウィルスが、人間社会の写し絵であるとするならば、ウィルスのような生き方をする人々がいてもおかしくないなというところから、オタワルの民の姿が浮かびました。国を持たず、己の才覚だけで生きている彼らは、権謀術数に長けた獅子身中の虫のようにも見えるけれど、覇権争いで戦いに明け暮れる人間社会においては、ひとつの希望になりえるのではないか。『守り人』シリーズのヒュウゴが、そうでしたよね。境界線を超えていこうとする者に、私は、やっぱり、希望を託したいと思ってしまう」
病の原因を突き止めようと奔走するホッサルは『鹿の王』のもうひとりの主人公だ。
「ウィルスによってもたらされる病とは、どういうものなのか……。そこのところをきちんと描かなければ、人間もまた一個の生き物であるという視点から命を問い直すこの物語が根本から崩れてしまう。顕微鏡の開発の話を読んだ時に、そうか、人は顕微鏡というものを知ったことで、肉眼では見えない世界がこの世にあることに気がついたのかと。つまりそこでエポックメイキングな思考のブレイクスルーが起きた。もちろん顕微鏡でウィルスを見ることは出来ないのだけれど、それまでは想像の世界に過ぎなかったのが、これより小さいものもあるのかもしれないと想定することができるようになった。体の内側で起こっていることと対峙するオタワルの医術を人々が魔法使いのように言うのも、肉眼では見えない世界を相手にしているから。ただ、医療とは何かを考えていくと、身体だけを診ているのでは、やはり不充分で。一方に、清心教という人間の心の在り方と向き合う医療を設定した時に、ようやく物語の全体像が見えたような気がしました」
上下巻、一〇〇〇ページを超える物語を書きながら、心の中にあり続けたのは「人間にとって、幸せのかたちとは何だろうという問いだった」と言う。
「感染症を描いた映画だと、いかに原因を突き止め、食い止めるかが主題になりがちですけど、私はそうじゃないものを書きたいと思ったんです。病が治れば、それで幸せなのか。治らなければ、それは不幸なのか。その時は治ったとしても、人は、いずれ死ぬわけですよね。だとしたら本当の恐怖は、死ぬことそのものよりも、自分が死ぬことで大切な人を悲しませてしまうことや、大切な人と別れ、守れなくなることなのかもしれない。どんな命も単体で成り立っているわけではないように、どんな人もひとりで生きているわけじゃない。これは、そのことに気づいていく物語でもあるのかも」
人が生きていくことと、命が生きたがることが体の内と外で響き合う。
小さき鹿よ、跳ねよ。
王になれない、凡庸な無数の命が、この物語の中で光を放つのはそのせいだ。
「人間って意識が肥大した悲しい生き物だから、意識じゃなくて体が主体になったら、どんな世界が見えるんだろうと。昔『ゲド戦記』を読んだ時に、イルカになった魔法使いが、イルカのまま、跳ねていっちゃう話があって、思えばその頃からそのことを考え続けていた気がするんです。人も山も獣もみんな、同じような、無数の光に見えてしまう獣の地平、命そのものの感覚の地平があるとしたら、そこからどんな景色が見えるのだろう。書きあげてみれば、これは、私の原点にあったそんな思いと向き合った物語になりました」