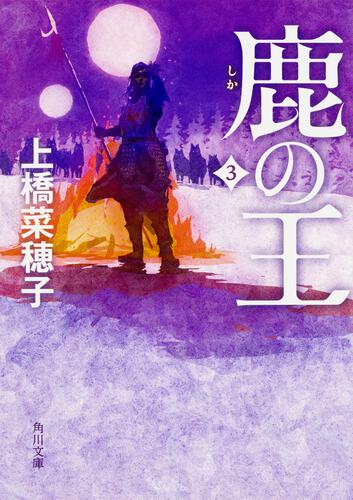本屋大賞を受賞した上橋菜穂子さんの超大作『鹿の王』は、強大な帝国が他民族への侵略を繰り返す世界で、突然よみがえった伝説の疫病に立ち向かうひとびとを描いた壮大なる冒険小説です。第四回日本医療小説大賞も受賞した本作では、主人公のひとりであるホッサルが学んだ「西洋医学」的なオタワルの医術と、強大な帝国・東乎瑠(ツオル)の祭司医(さいしい)たちが信仰する清心教に基づく「東洋医学」的な医術との対立が描かれています。現代日本において西洋医学・東洋医学の両方を取り入れた医療を行われている津田篤太郎さんと、『鹿の王』の世界における医学のリアリティとダイナミックさについて語り合っていただきました。
(2017年2月18日にジュンク堂書店池袋本店にて行われた上橋菜穂子さんの作家書店トークイベントの内容をレポートしたものです)
現実とシンクロする医療の歴史
上橋: 私と津田先生との出会いは、母の病がきっかけでした。母の病気が見つかったときに津田先生に漢方で支えていただきたいと思って、ある編集者に紹介していただいたんです。もともと津田先生のことはテレビ番組などで存じ上げていたので。津田先生に診ていただいたおかげで、母は抗がん剤治療をしながらもイギリス旅行に出かけるなど、最後の最後まで元気でした。母が逝くときも手を取って脈を診てくださっていて、母の状態を丁寧にお話ししてくださっていたことがとても印象に残っています。ぜひぜひ、津田先生と作家書店でトークイベントを行えたらと感じていました。
津田: 『鹿の王』は読んでいてファンタジーとは思えないほど、現実世界とリンクして読めてしまうようなところがいっぱいありました。
上橋: 私の作品はよくファンタジーと言われることが多いのですが、自分の意識としてはたぶん、異世界の民族誌を書いているんです。なぜ異世界が舞台なのかと言えば、物語を読んでいただくとき、現実世界での様々な固定概念から、いっぺん外に出ていただく、ということが大切だと思っているからです。これまでは当たり前だと思っていたことの向こう側にあるもの、それが伝わる物語を書きたいのです。人の生死やこの世のあり方に、魔法などの要素が入ってきてしまうと、私が一番書きたいと感じている「死がありながら生きることの様々」が書けなくなってしまう。なので、それはしたくないんです。
津田: なぜ生きるのかというテーマは、『鹿の王』でも強く感じました。作中では祭司医というお医者さんと、主人公のひとりであるホッサルが学んだオタワルの医療との対立が描かれていますよね。私は最初医療に対する立ち位置は逆だと思っていたんです。東洋医学に近い考え方をしているのがホッサルで、西洋医学に近い考え方をしているのが祭司医。よく読むと実は反対なんですけど……(笑)。
上橋: 祭司医たち……東乎瑠の体制側が、東洋医学ですね。でも津田先生、私「祭司医」の部分はほぼ書き終わってから書き足したんですよ。
津田: え、そうなんですか!?
上橋: 当初はホッサルという西洋医学の立場の人間だけの物語で書きあげていたんですけれど、どうしても気持ちが悪かったんです。これじゃない、という感じが消えなくて。いろいろと考えて、この気持ち悪さは私がたったひとつの視点から物語を書いているせいだと気づいたんです。実際の世界では病について様々な考え方があって、だからこそ、ひとつの病に対していろいろな葛藤を抱えていますよね。それに気づいて、慌てて頭から書き足しました。
津田: この東洋医学vs.西洋医学の構図は、私はてっきり監修をお願いしたという従兄さんにアドバイスを受けたのかと思っていました。そもそも『鹿の王』の医療の歴史は、幕末の医療体制と似ているんですよね。西洋医学のほうがチャレンジャーで、従来の日本に根付いていた東洋医学を打ち負かして、アイデンティティを確立していく。私は「『鹿の王』の医療は、幕末をモチーフにしているに違いない」と思っていました。
上橋: あ、いえいえ(笑)。従兄に教えていただいたことは、免疫や製薬や病の発祥の話が主でした。でも言われてみると幕末の医療体制と近い部分は多いですね。
津田: 物語で描かれる黒狼熱(ミッツァル)は架空の病気ではありますが、感染症ですよね。それが、とても良いと思いました。実は感染症というものは、日本においても西洋医学が最初に入ってきた領域ですからね。特に、治療という面に限って言うと、種痘以外はなにも入ってこなかった時代が百年くらい続くはずです。
上橋: えええ、そうなのですか?
津田: 幕末時期の西洋医学といえばターヘル・アナトミア(解体新書)が有名ですけれど、あれを見たからと言って病気は治らないですよね。臓器の場所が判明したので漢方の先生はびっくりしたみたいですけれど。「お腹の中はこうなっているのか」とわかり、それによって薬の使い方を工夫し始め、上手になっていく。そういう意味では医療を進めていますけど、西洋医学が本当の意味で病気を治せるようになるのは20世紀に入るか入らないかの時期ですね。抗菌剤ができてから。なので西洋医学は「いろいろと調べて解明することはできるけど、結局は治せない」と漢方から攻撃されていたみたいです。
上橋: 脚気のはなしなどは確かに有名ですね。
津田: 脚気は西洋医学では感染症だと言われ続けていましたけど、今はビタミン不足が原因だということが分かっています。けれど西洋医学は感染症だということに拘りつづけていた。顕微鏡で見て、それによって病の原因を解明したことは、西洋医学を学ぶ人間にとって強烈な成功モデルとして印象に残ってしまっていたんだと思います。
上橋: 先生にずっとお聞きしたいと思っていたんですが、免疫――つまり疫を免れるという発想はじつは抗菌剤などが見つかるもっと前から知られていましたよね。たとえば紀元前のギリシアでも、すでに、同じ病には二度罹らない、という認識があって、ローマ帝国期には、それを「免疫」という言葉で表現した詩がある、というような話がありますが。同じ病気なのに罹ったり、罹らなかったりする。それだけでなく、罹らなかった人間は何か特別なものを持っていて、それをもらえば良いという発想は、どのくらい昔からあったのでしょうか。
津田: 罹りやすい人間と罹りにくい人間がいるという考え方は昔からあったのだとは思います。あとは罹りやすい環境、という考え方もありますね。
上橋: 罹りやすい環境、というのはまさに鹿の王の発想のはじまりでした。最初は地衣類の森に暮らすトナカイと、彼らと共存している人間のイメージが漠然とありました。トナカイは地衣類を食べるので、トナカイ牧畜民が、弱毒化された病原体を日常的にトナカイの乳などから摂取していたとして、それによって病に罹ったときに身体が抗体をつくる可能性はありますかと従兄に聞いたんですね。そうしたら、可能性はある、と言われて、それで発想が広がったのです。ある地域を植民地化して入植した征服民たちだけが病に罹った場合、先住民たちは「この地に入る資格のない者だから、病に罹ったのだ」と考えるかもしれないと。人は「なぜ病んだのか」を知りたがり、そこに納得できる理由をみつけたがる生き物ですから、病を巡る様々な相を描けるかもしれないと思ったのです。
津田: 社会において病気がどういう影響を与えるかという視点は、上橋さんならではだと思います。医者の場合はどうしても目の前で向き合っている患者さん個人のことが中心になりがちです。けれど、ひとつの病が社会に影響を与え、差別に近い問題を引き起こしてしまうことも少なくはありません。『鹿の王』にも出てきますが、呪いであったり業病であったり血筋などに原因を求める考え方ですね。前世で悪いことをしたからこういう病になったのではないか。ですが意外にも科学はその考え方を否定し切るところまでいかない。たとえば、ハンセン氏病はライ菌による感染症で、決して「呪い」や「業病」ではないのですが、罹りやすい体質の人にしか感染しないと言われています。これが、隔離が無効であることの根拠なのですが、こんどは先天的な体質、すなわち「血筋」という話が残ってしまう……。
上橋: どんなに蔓延していても発症しない人もいますものね。実際に、結核などは、感染しても90%の人が発病しないと聞きました。なぜ、罹る人と罹らない人がいるのか、お医者様は説明できるかもしれませんが一般人の私達には、どうしても「わからない」ところが残るんです。
津田: たとえば医者であれば「白血球の数がどうである」とか「タンパク質の表面の形がちがう」といった説明をすることはできますが、科学的な考え方のフレームがない場合には、様々な解釈が出来てしまいますし、そういった解釈が呪いとか業病といった発想に繋がっていってしまうこともあります。果ては、大きな社会的な動き、政治的な動きに繋がることも。まさに『鹿の王』はそういう展開がありますよね。
上橋: そうですね。大切なテーマのひとつです。
病における謎解きのしっぽ
上橋: 今回『鹿の王』でホッサルという主人公を書いたら、養老孟司先生と対談をさせていただいた際に「若い医者をよく書けているね」と褒めていただいたんです。最初、その意味がわからなかったのですが、この「若い」というのは、ホッサルは医療に対して「いずれは必ず全てを解明できる」というベクトルで希望を持っているということだったんです。彼は自分がきちんと科学的な方法で原因を細密に探っていけば、「やがて誰かがこの世界のすべてを見通せる目を持てるのではないか」と思っている。けれど、21世紀の現在でも分かることの向こう側には新たに分からないものがどんどん出てくる。医学も科学も万能ではなく、どこかにブラックボックスがある。私も、今はそういう風に感じています。
津田: 医学におけるブラックボックスの最たるものは、人の命にかかわる部分でもありますね。
上橋: ええ。人間は絶対にみんな死ぬ。これは当たり前のことのはずですが、死に瀕した瞬間に、人は多分、本当の意味で死を自覚する。そうなったとき、人間が知りたいことはふたつだと思うんです。ひとつは、どうやったら治るのか。もうひとつは、なぜ罹ったのか。このふたつは実は近いものであって、なぜ罹ったのかがわかれば、そこから対策を立てられると人は考えるから知りたいんだと思います。謎解きの一番大切なしっぽを捕まえるイメージですね。この推論のかたちにおいて、西洋医学と東洋医学の違いはあるのでしょうか?
津田: おっしゃる通り「なぜ、病気に罹ったのか」「どうやったら治せるのか」は医療におけるふたつの極、ゴールだと思います。推論の方法は、西洋医学と東洋医学だと少しだけ異なりますね。西洋医学のほうは『鹿の王』で言えばホッサルの流れであり、「どうやったら治せるのか」を科学的に突き詰めていくわけです。けれど科学的な説明をしてもそれでは治らない人、救えない人も存在します。そういう人たちを助けるのが古いタイプの東洋医学であり、物語で言う祭司医たちですね。
上橋: はい。そう思って描きました。祭司医たちは死に逝く者の心を癒すのです。苦しい最期ではありましたが、神はあなたの辛さをきちんと見てくれていますよ。この苦労を乗り越えて最期まで頑張って生き遂げれば素晴らしい場所へ行くことができるし、やがてはあなたを見送った家族とも一緒になれますよ、と伝える。この祭司医に対して、西洋医学的な考えのホッサルは「病素を見せてあげようか」と言うんです。顕微鏡をのぞけば病の元になったものが見えるから、と。けれどその祭司医は「結構です」と返します。それはなぜか。彼は診るべきことはすべて、病んだ人間の身体に現れているから、元がなにかということは大切ではないと語るんですね。
津田: まさに東洋医学の考え方ですね。
上橋: 祭司医の世界観では、ユニバース全体を見守る神がいて、その下に「私」という人間がいて、いまある形が作られたことには既に何かの意味があると考えているわけです。なので、祭司医たちはそれ以上のことを解き明かす必要性を感じない。死というものも、彼らは受け入れているんです。こういう風に言われてしまうと、オタワル医術師はもう何も言えなくなってしまう。津田先生は東洋医学と西洋医学との二刀流――統合医療をされていらっしゃいますが、どのように使い分けをされているのでしょうか。
津田: 私は実は統合医療という言い方には反発しているんですが……(笑)。
上橋: え! なぜですか?
津田: 統合というとふたつを混ぜてしまうような考え方だと思うんですが、私はあまり簡単に混ぜずにきちんと対立点を残したほうが良いと考えています。違う視点から見ることで客観視することができる。それこそが二つの医療をまたぐ意味だと思っているんです。その点、『鹿の王』はきちんと対立点を描いていますよね。
上橋: そう言っていただけると嬉しいです。
津田: 治せる医学の方が上とか、治せない医学に未来はないと考えられることもありますが、けっしてそんなことはないんです。両方が大切ですし、実際に人々は両方を求めているのだと思います。治せない病気の場合、最後に人が到達するのは「なぜ、私が病に罹ったのか」ということの追求だと思います。「どうして私はこの瞬間にこの病気を得たのか」「それが人生にとってどういう意味があるのか」「周囲の人にとってはどういう意味があるのか」と、広く考える視点が東洋医学にはあるように思います。死ぬということを避けられるものとは考えておらず、どういう風に人生を全うするかということに大きな文脈を求めているんですね。
上橋: 病になったことをただ忌むべきものとは見ないことで、病が人生のひとつの大切な出来事に変わり、命の姿を見せる瞬間があるわけですね。西洋医学的な考え方だけで、すべてを解きほぐそうとすることは難しいでしょう。ただ、人間の物語機能というのはすさまじいものなので、東洋医学的に「なぜ」を追求し続けた結果、自分にとって都合の良いストーリーを導き出してしまう可能性もあると思うのです。それは呪術的な考えにもつながってしまうので、東洋医学だけがあればいいというわけでもないと感じています。
津田: おっしゃる通り、両方があることが大切で、片方に偏ってしまうことが駄目なのだと思います。ふたつの考え方があって、お互いに反証し合うことが大切です。『鹿の王』で言えば、祭司医が「病素を見なくて結構」と言ってしまうのは、助ける術がある人を救えなくなってしまう可能性もある。逆に今度は病素にばかりこだわっていると手だてが失くなった場合、死に逝く人に本当に何もできなくなってしまいます。ポジティブな物語を語ることで寿命が延びるという例もありますから、両方が出来てこそ治療者であると私は考えています。長所と欠点をわきまえて使い分けすることが大事ですね。
上橋: 安易に統合してはいけない、ということですね。面白いです。おっしゃる通り、統合は一見よいことに思えますが、一方で、自らを批判的に見る目をなくすことにもつながる。気になるというか、どこか引っかかる対立点を残すことは大事ですね。
津田: 自分と相手の矛盾点を消さないと不安という人もいると思うんですけれど、私はそれ以上に対立点をつぶすことによって手詰まりになってしまうことの恐怖のほうが強いですね。もちろん間違いを否定されたくない、という気持ちもわかるんですが。
上橋: 目の前にいる患者さんに対して、手詰まりになることのほうがよっぽど怖いということですか。お医者さんならではの感覚ですね。人間は完全ではなくて、つねに間違える可能性を含んでいる生き物ですが、お医者さんほど間違いが許されない職業というのはないと思いますので本当に大変ですね。