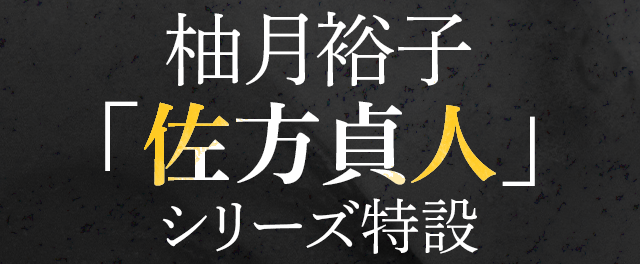解説 生と死の境界へ
――この世界を、私はよく知っている。
『鹿の王』を読みとく中で、そして読み終えたあとも、なんとなく私を捕らえていた淡い感慨を言葉にすると、そんな一文になる。
ずいぶん乱暴な意見であるが、そんな思いがなければ、なかなかこの巨大な作品の解説を引き受ける覚悟を持ちえなかったことは間違いない。
『鹿の王』の世界はあまりに深く、あまりに広い。
壮大なファンタジー小説といえば、名のある作品はいくらでもあるだろうが、本書は、このファンタジー小説という既存の枠組みそのものを、軽々と乗り越えてしまうスケールを有している。読者は作中で多くの驚きと発見と感動に出会う。しかし出会うと同時に、そのひとつひとつが実に多面的な要素をはらんでいることに気づかされて、当惑も覚えるに違いない。
そんな類例のない世界観を持った作品であるにもかかわらず、私は冒頭のごとく不思議な感慨を覚えたのである。
――この世界をよく知っている。
それは、私が過去に『鹿の王』のような物語を読んだことがあるという意味ではないし、私が医師であるために、医療を主題のひとつに据えている本作を身近に感じるという意味でもない。おそらくそれは、僭越を承知で言えば、上橋さんの死生観、もしくは生命観というものが、私と非常によく似ているということなのではないかと思う。
児童文学やファンタジーの語り部として多くの読者を魅了してきた著者と、片田舎の病院で働く内科医の価値観がこんな形で交錯するということは、不思議であると同時に、なにかとても大切なことを意味しているように感じられる。
話が話であるだけに、明快な論旨にはなるまい。
けれども、上橋作品の愛読者であると同時に、ひとりの医師として、そんな文脈の中で本書を語ってみようと思う。
『鹿の王』は、周知のごとく2015年の「本屋大賞」を受賞した作品である。
折しも上橋さんが、児童文学の世界では最高の栄誉のひとつとされる「国際アンデルセン賞」の作家賞を受賞し、受賞後の第一作として刊行され、本屋大賞受賞後には「医療小説大賞」も受賞して出版界をおおいににぎわしたことは、今ここで細かく述べるまでもない。いずれにしても本書を取りまく、一見するとほとんど脈絡がないようにさえ見えるこの多面的な話題性こそ、『鹿の王』の特異な存在感の証左と言えるだろう。
元来が上橋作品の大きな魅力のひとつは、自身で立ち上げた新しい物語世界を丹念に描き出していくその細やかな筆致にある。上橋さんは『精霊の守り人』を始めとする多くの著作の中で、主人公やその周辺の登場人物だけでなく、名もない人々の姿まで生き生きと描写してきた。料理や食卓の風景に始まり、狩りに向かう男たちの緊張感や天候のふとした移りかわり、森の木漏れ日から獣道の静けさに至るまで、描き出されたものは市井の人々の生活そのものであり、そのことが作品に圧倒的な深まりを持たせ、多くの読者を魅了してきたことは疑いない。異国のさりげない日常の景色の中でゆっくりと物語が活動を始めるときの胸の高鳴りは、多くのファンが味わってきたことであろう。
本書において、上橋さんはそのスタイルを微塵も変えぬまま、医療というまったく新しい世界観を投入してみせる。それも生半可な世界観ではない。膨大な医学の知識に裏打ちされた現代免疫学の体系をほとんどそのままの形で、しかし巧妙に衣替えをさせながら、アカファ王国の、東乎瑠帝国の世界に描き込んでいく。
トナカイの蹄について語るときの静かな口調で、また、兄弟送りの儀式を描き出すときの冷静な筆致で、徐々に全貌が描き出されていく黒狼熱の存在は、それを支える知識が現実のものであるだけに独特の切迫感をもって読み手を圧倒するのである。
しかし、とここでにわかに話頭を転じたい。
さんざんに熱弁をふるっておきながら乱暴な話だが、私が本書に強く惹きつけられた一番の理由はここにはない。そこに多くの魅力があることは否定しないが、それでも私にとっての本作の核心はさらに一歩踏み込んだところにある。『鹿の王』は、単純にファンタジー小説に医療小説としての要素をブレンドした作品ではない。ファンタジーはもとより、一般的な医療小説の枠組みにも収まりきらない深度を感じるのである。
この物語では、たしかに病と人が対峙する。
多くの人が病と闘い、これを克服しようと奮闘する。ホッサルやミラルは、黒狼熱を打倒すべくこの世界を駆け回り、そして実際に多くの人々の命を救う。
この一見当たり前の、そして胸を打つ景色が、しかし『鹿の王』ではごく自然に相対化されているということに驚かされるのである。
ホッサルはたしかに病と闘う。けれどもそれがこの作品世界の絶対的な価値とはされていない。むしろ逆に、病と闘うことそのものを拒否する者たちも、ごく自然な姿で描かれている。
呂那師に代表される清心教の在り方は、その意味で衝撃的である。「私共が救いたいと願っておりますのは、(命ではなく)魂でござりまする」と告げる老祭祀医の言葉は容易ならざる真理を含んで見える。一方で、黒狼熱の拡大を政治的な駆け引きの道具として利用しようとする者もあれば、神の差配と受け止める者もあり、ヴァンのようにまったく異なる道を行く者もある。
上橋さんは、人が努力によって難病を克服するという、ある種の典型的な世界解釈を静かに逸脱し、病を取り巻く人々の多様な考え方、受け止め方を提示し、その結果として、命の在り方そのものを根底から問い直しているように見える。
むろん無邪気に生を肯定することが間違っているわけではない。けれども、命の意味を極限まで考え抜こうとするとき、それではどうしても辿り着けない場所がある。その見極めがたい生と死の境界へ、本書はゆっくりと足を進めていく。
本稿の冒頭に私は、「この世界をよく知っている」と述べた。まさにこの態度に共感を覚えたのである。
私は医師であり、医師である以上は、患者を治療することが至上の責務であることは言うまでもない。そして臨床における熱意と努力については相応の自負を持っているつもりだが、一方で私の本質的な哲理は、意外なほど呂那師に近い。ホッサルの黒狼熱に立ち向かう情熱に打たれつつも、彼のように病について「いずれ必ず隅々まで明らかになる日がくる」とは感じないし、リムエッルのように医学に対する万能感もない。医師が努力した分だけ患者が助かるのであれば、そんな気楽な世界もないという、ある種の暗い諦観が常に胸の奥底に沈滞している。
こういう思考の運び方は、臨床医としてはけして健康なあり方ではないだろうが、日常的に人が死んでいく景色を見つめていれば、命の多様な解釈の先に虚無を見てしまうこともまた臨床医の宿命のように感じている。おそらく医師にとっての最大の敵は、眼前に立ちはだかる難病ではなく、自身のうちに沈滞する諦観なのであろう。
その意味で、生命に対する絶対的な価値観を提示せず、ゆるやかに多様性を描き出す『鹿の王』の生命観に強く惹きつけられるのである。
ただし、誤解をしてはいけない。
『鹿の王』は、たくさんの生と死を描きながら、その先に虚無を見てはいない。ともすれば立ちこめる暗い諦観さえも相対化し、明確に距離を取ることに成功している
そのことは本書を読み終えたときに心の内を満たす、ほのかな安堵感が示してくれるだろう。ここでは、たくさんの死が描かれ、たくさんの絶望が描かれながらも、作品そのものはけして虚無感に飲み込まれていない。
深い闇のかなたに小さな、けれども確かな灯火がある。
その温かさを感じたとき、本当に上橋さんはとんでもない作品を書いたのだと痛感するのである。
もう十年近くも昔のこと、私は自分の作家としてのデビュー作の解説を上橋さんにお願いしたことがある。
もとより縁もゆかりもありはしない。ただ私が愛読者であってぜひお願いしたいという一方的な熱意だけが理由であったのだが、そんな乱暴な依頼を、上橋さんは快諾してくださった。
その解説にこんな言葉がある。
「現実」に深く思いの針をおろした人でなければ、心地よい物語は書けません
冬をよく知っているからこそ描ける春なのですから
本当に、そうだと思う。
『鹿の王』には様々な人々の生き方が描かれている。そのことはすなわち、上橋さんがどれほど死について深く〝思いの針〟をおろしたのかということでもあるのだろう。そうして描かれた物語であるからこそ、無数の死の背後に、我々は確かな命の鼓動を感じることができるのである。
この物語は、繰り返し私たちに語ってくれる。
生命とは、これほどに儚く、力強く、哀れで、不可思議に満ちているのだと。
そしてすべての生が、結局は死につながっていたとしても、恐れることはないのだと。
ヴァンの背にいつも笑顔のユナがいたように、絶望の淵には必ず温かな希望の光が灯っているのだから。
▽『鹿の王』シリーズ・[解説]一覧
「この本こそが、ファンタジーである」本屋大賞受賞作を書店員が熱く語る。『鹿の王 1』
https://kadobun.jp/reviews/32/cf3b36a2
「この物語が世界に存在する奇跡」 『鹿の王 3』
https://kadobun.jp/reviews/66/10e5895c
本屋大賞作品、そのタイトルに隠された謎とは――読み手の人生を動かす、唯一無二のファンタジーを読み解く 『鹿の王 4』
https://kadobun.jp/reviews/70/2c718aa9