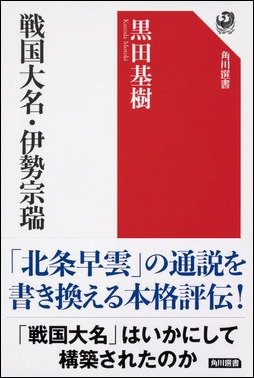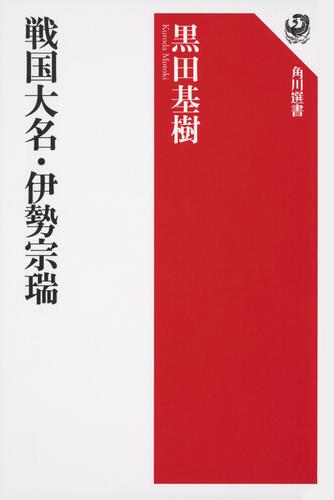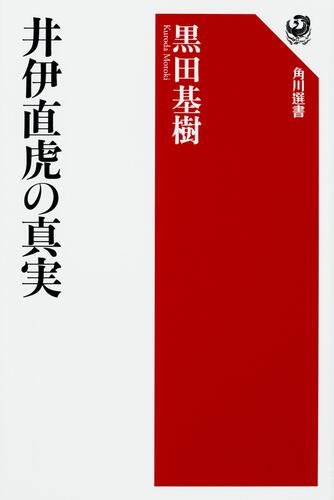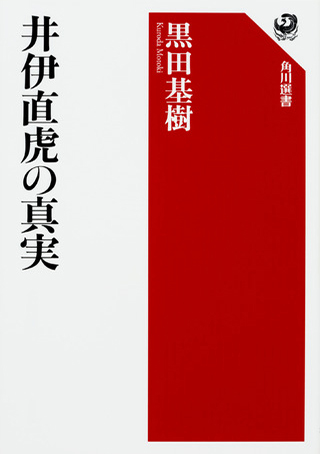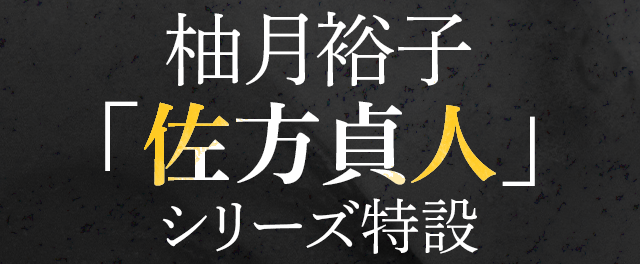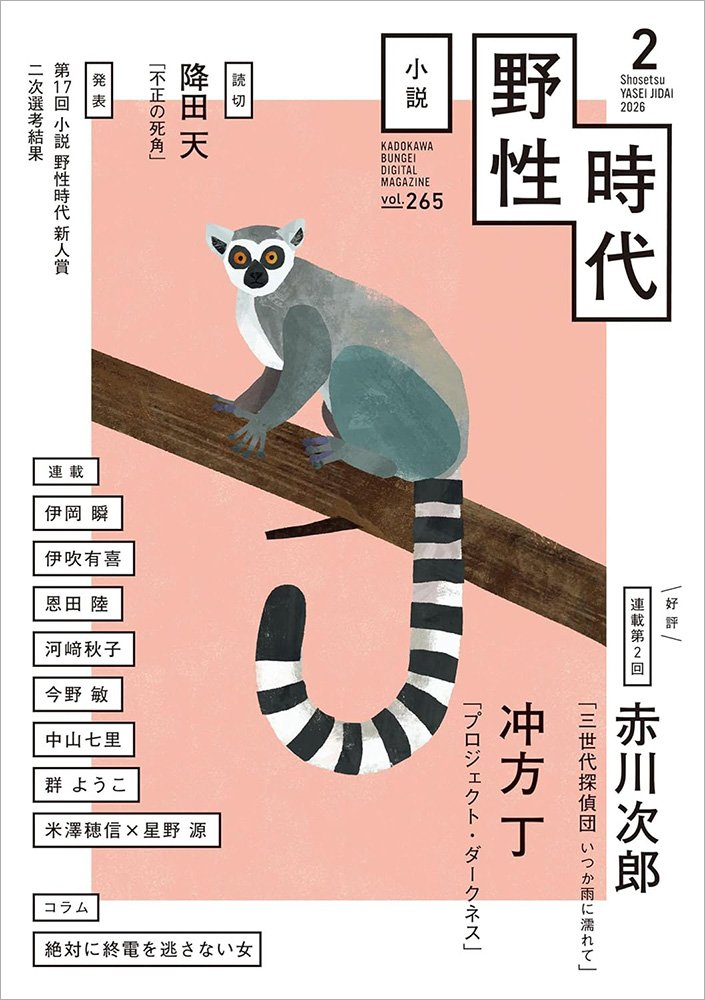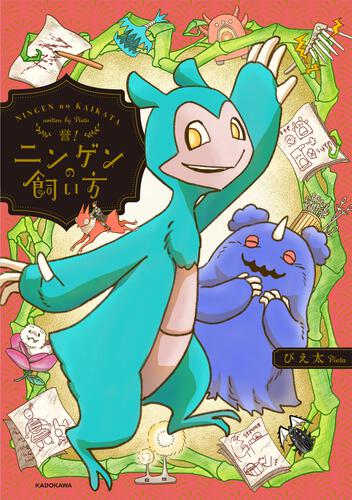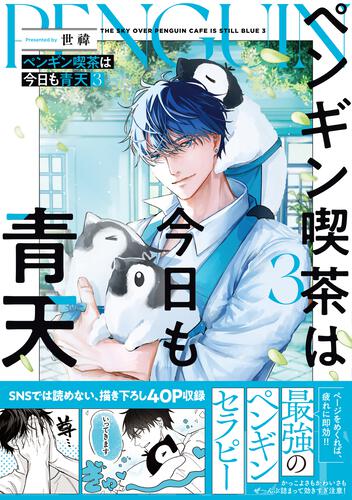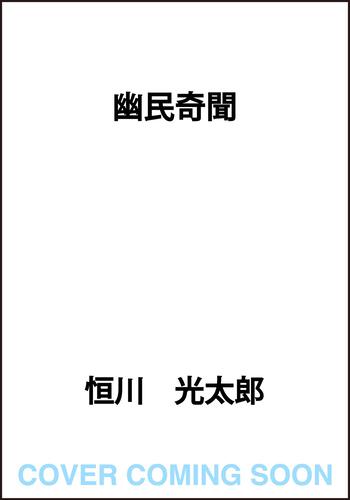書評家・作家・専門家が《今月の新刊》をご紹介!
本選びにお役立てください。
(評者:丸島和洋 / 東京都市大学共通教育部准教授)
いわゆる「北条早雲」こと伊勢宗瑞は、戦国大名の先駆け、あるいは「下剋上」の代名詞として語られることが多い。そこでは、次のような経歴が語られる。
―――「北条早雲」は、伊勢の「素浪人」であったが、妹が駿河守護今川義忠に見初められて側室となった縁で出世を果たし、伊豆を占領して一代で戦国大名に上り詰めた。時に「早雲」は五九歳、老境からの大躍進である。その後、謀略で小田原城を攻略し、関東最大の戦国大名小田原北条氏の礎を築いた。
長年信じられてきた彼の生涯である。日本史関連の書籍や番組(映画・ドラマからドキュメンタリーに至るまで)は、しばしば人生訓やビジネスを進める上での手掛かりとして扱われる。そうした時、「低い身分から」「老境になってから」という「北条早雲」の生涯は、非常に魅力的に映る。
しかしながら、こうした「北条早雲」像は、日本史学界では三〇年以上も前から見直しが続き、伊勢新九郎入道宗瑞の実像は、まったく異なることが明らかにされてきた。実際の伊勢宗瑞(盛時)は、室町幕府の重臣の家に生まれ、幕府官僚となり、将軍直属軍に所属した存在であった。生年も二回りも下であり、関東で活躍を始めたのは青年期のことである。
新しい伊勢宗瑞像は、一部の歴史愛好家の中では知られているが、一般化しているとは言いがたい。私も講座や講演で、伊勢宗瑞をとりあげることがある。そこに来ている人は、言うまでもなく歴史好きで、勉強熱心な皆さんだ。しかしやはり伊勢宗瑞の姿は、「素浪人上がりの北条早雲」と理解されている。通説を改める、というのは非常に難しい。
本書は、最新の研究成果に基づいた、伊勢宗瑞の初めての本格的伝記である。ではなぜ三〇年以上前から再検討されてきたのに、それをまとめた伝記がなかったのだろう。この本を読めばわかるという羅針盤は、今まで歴史愛好家に提示されてこなかった。
その理由は、宗瑞の活動範囲の広さにつきる。室町幕府政所執事伊勢氏の最有力分家の子息として京都で生まれ、幕府の若手官僚として育った上、禅宗寺院にも出入りした(政所執事は財務大臣兼首相補佐官のようなポスト)。本領は、備中荏原荘(現岡山県井原市)にある。
そのような名家だから、「姉」(妹ではない)が駿河守護今川氏に嫁ぎ、嫡男龍王丸(氏親)を生んだ。この龍王丸を今川氏の家督につけるために、伊勢宗瑞は駿河に向かう。今川氏親の勢力拡大に協力をしつつ、関東の動乱に巻き込まれていく。相次ぐ動乱は、「坂東の天地は複雑怪奇」としか表現しようがない。
いっぽうで、将軍に仕えているのに、勝手に駿河や関東に行ってよいのか、という疑問も湧くだろう。よいわけはない。宗瑞の行動は、将軍の許可の許に行われていると見なければならない。彼の動向は、京都政界の動きとも結びつけて考える必要がある。なお小田原北条氏は、戦国大名でもっとも緻密な内政を行った大名である。その理由としても、幕府官僚という出自を無視はできないだろう。
つまり彼の生涯を逐うには、京都・関東、双方の視点をリンクさせ、複雑に絡んだ糸を解きほぐしていかなければならない。それを成し遂げることができるのは、長年小田原北条氏だけでなく、幅広く関東の研究を蓄積させ、京都政界の動向もマークし続けた著者でなくては不可能であったろう。
今年(令和元年、二〇一九)は、伊勢宗瑞没後五〇〇年にあたり、小田原城でも様々な発掘成果が得られている。ゆうきまさみ氏が「月刊!スピリッツ」で連載している漫画『新九郎、奔る!』(小学館)は、少年期の伊勢宗瑞が応仁の乱に接するところから始まる。最新の歴史学の成果に基づいた、伊勢宗瑞像を理解してもらうにはいい折だろう。ヴェールに包まれた「北条早雲」ではなく、歴史上の伊勢宗瑞の実像を楽しんではみませんか。
ご購入&試し読みはこちら▶黒田 基樹『戦国大名・伊勢宗瑞』| KADOKAWA